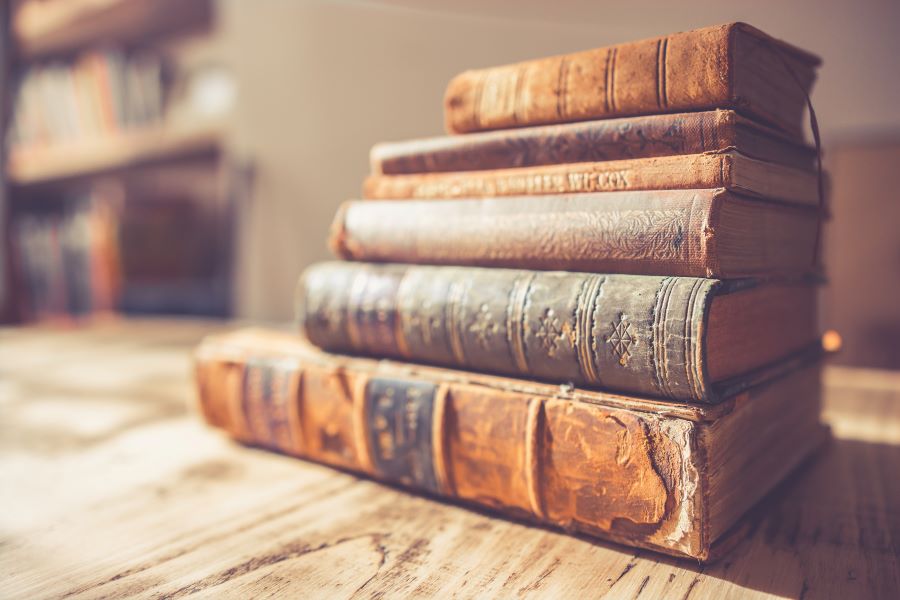若者を中心に広く名前が知られているMBTI。韓国のポップカルチャーから若者に広まり、今では星座占いや血液型占いと同じような使われ方をしています。流行りに乗じてMBTIの性格タイプをイメージした無料でできる簡易アンケートがネット上に散見されます。心理テストが普及していくことは歓迎すべきことですが、心理テストは薬と同じような効用を持つため低品質なテストや不適切な利用が様々な問題を生じさせることがあり、懸念すべきこととも考えています。
ここで改めてMBTIの普及に尽力された大沢武志氏(元人事測定研究所社長)の名著「心理学的経営」からMBTIとは何か、どのように活用すべきものかをご紹介します。
目次をみる 目次を閉じる
MBTIとは
MBTIの正式名称はマイヤーズ・ブリッグス・タイプ・インディケーター(Myers- Briggs Type Indicator)です。イザベル・マイヤーズとキャサリン・ブリッグスという親子によって開発されたパーソナリティテストです。心理学者カール・グスタフ・ユングの性格類型論に基づいて測定モデルが作られました。
1962年米国のテスト専門機関ETSから研究用ツールとしてリリースされ、日本には1964年にはじめて紹介され、日本語版の翻訳研究がはじまりました。1968年に大沢氏がマイヤーズ氏から日本での正式な利用許可を受けたことで日本での利用がはじまり、このことが後押しとなりマイヤーズ氏は1975年に第一回全米MBTI学会を開催しました。この学会をきっかけに米国のみならず、ヨーロッパ、アジアなど世界70か国以上の利用がはじまりました。この学会がプロフェッショナルユーザー組織の結成につながり、資格認定などの仕組み作りが整備され、1988年に倫理憲章が制定されました。

MBTIの16タイプ
MBTIはユングの性格類型論に基づいて、性格を16タイプに分けています。
まずは、知覚と判断という心理的な機能で人の行動をとらえます。知覚機能は物事をどうとらえてどう意識するかを決めるものであり、判断機能とは知覚したことをどう結論付けるかを決めるものです。知覚と判断にはそれぞれ異なる二つの方法があります。知覚の二つの方法は感覚と直観です。感覚による知覚は五感を使って対象をあるがままにとらえ、直観による知覚は自分の内面にある想念を対象に付加して間接的に対象をとらえます。知覚型は目に見える現実に関心が向き、直観型は可能性や想像に関心が向きます。判断の二つの方法は思考と感情です。思考による判断は論理的な方法で客観的な結論を導き、感情による判断は好き嫌いによって主観的な結論を導きます。思考型は客観的な分析で結論を出す冷静なタイプであり、感情型は人の気持ちを配慮した結論を出すタイプです。ここまでで述べた4つの心理的機能(感覚、直観、思考、感情)がユングの性格類型論の基本概念です。
この4つの機能に基本的態度と呼ばれる外向型と内向型が加わります。この二つのタイプはエネルギーの方向を示しており、外向型は外の世界との関わりを求め、内向型は内なる世界にこもろうとします。最後に外的世界の処理に使われる心理的機能の判断と知覚が加わります。
エネルギーの方向が外向型(E)か内向型(I)か、知覚の方法が感覚型(S)か直観型(N)か、判断の方法が思考型(T)か感情型(F)か、外界を処理するプロセスが判断型(J)か知覚型(P)の4つのタイプの組み合わせから16タイプに分類する仕組みが作られています。
ちなみに私は内向、直観、思考、知覚のINTPタイプです。たしかに新しい仕事を作り出すことに目が行きがちで、目の前のタスクがおざなりになることがよくあります。
| 外向(E) | 内向(I) |
|---|---|
|
|
| 感覚(S) | 直観(N) |
|
|
| 思考(T) | 感情(F) |
|
|
| 判断(J) | 知覚(P) |
|
|
※大沢武志「心理学的経営 個をあるがままに生かす」(PHP研究所 1993年)より引用
活用方法
MBTIは自己理解のための質問紙です。専門教育をうけたプロフェッショナルユーザーからのフィードバックにより受検者が自分のタイプを探索し、ベストフィットタイプをみつけます。人はベストフィットタイプ以外の行動を一切取らないというわけではありません。何かを行う上では、ベストフィットタイプと反対のタイプの行動をバランスよくとる必要があります。ベストフィットタイプに関連する行動が現在の社会生活でどのように発揮されているか、反対のタイプの行動をあまりとらないことがどのような影響を及ぼしているかをよく考え、行動を強化したり改善したりすることに役立てるのが適切なMBTIの活用法です。

管理職と経営者のMBTI
MBTIを選抜目的で使うことは推奨されていませんが、大沢氏は管理職に共通のタイプがあることを著書で述べています。日本とアメリカの調査データから管理職で最も多いタイプは思考・判断(TJ)タイプでした。また、経営者は管理職に比べ個性のばらつきは大きくなるものの、独創と信念で組織に君臨する孤高の経営者に内向・思考(IT)タイプが多いと述べています。その代表的な方は以下の通りです。
井深大氏(当時ソニー社長)INTP
堤清二氏(当時セゾングループ相談役)INTP
伊藤雅俊氏(当時イトーヨーカ堂相談役)INTP
佐治敬三氏(当時サントリー会長)INTJ
このような伝説の経営者からMBTIデータを収集していた大沢氏のMBTIに対する情熱と行動力に敬服いたします。
おわりに
大沢氏は1993年に出版された「心理学的経営」で社員の自己実現を経営のゴールに位置付ける企業経営者が増えてきた状況を伝え、社員一人ひとりの個性を生かす経営の必要性とその方法を提示しました。そこで個性をとらえるツールとして紹介されたのがMBTIです。このツールは自分の個性を正しくとらえ、組織においてその個性を最大限に活用するために使われるべきものなのです。自分のタイプを見つけるだけでなく、自分にとって未発達な特徴を把握し、問題の発生を未然に防いだり、周囲の人との協力によって問題を解決したりするために使われます。
MBTIというバズワードをきっかけとして、正しいMBTIの理解とその適切な活用が普及していくことを同じアセスメントを取り扱う者として切に願います。
参考文献
大沢武志「心理学的経営 個をあるがままに生かす」(PHP研究所 1993年)

このコラムの担当者
清田 茂
執行役員
入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。