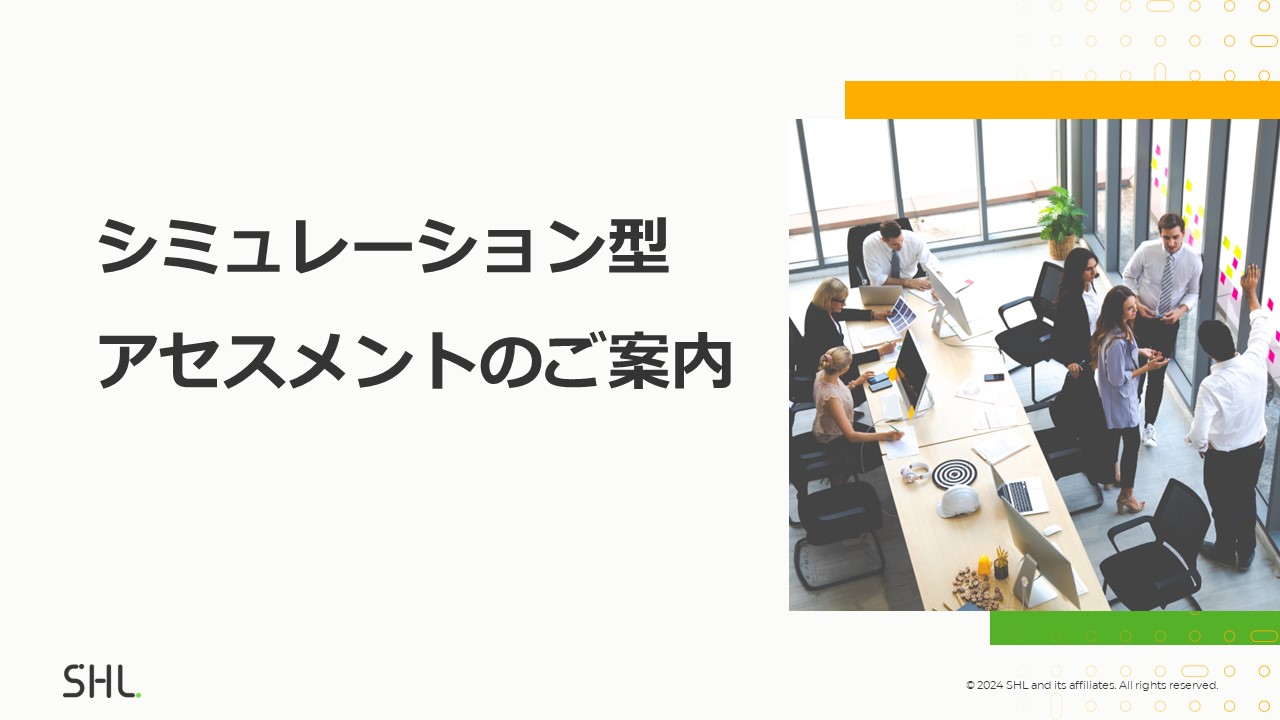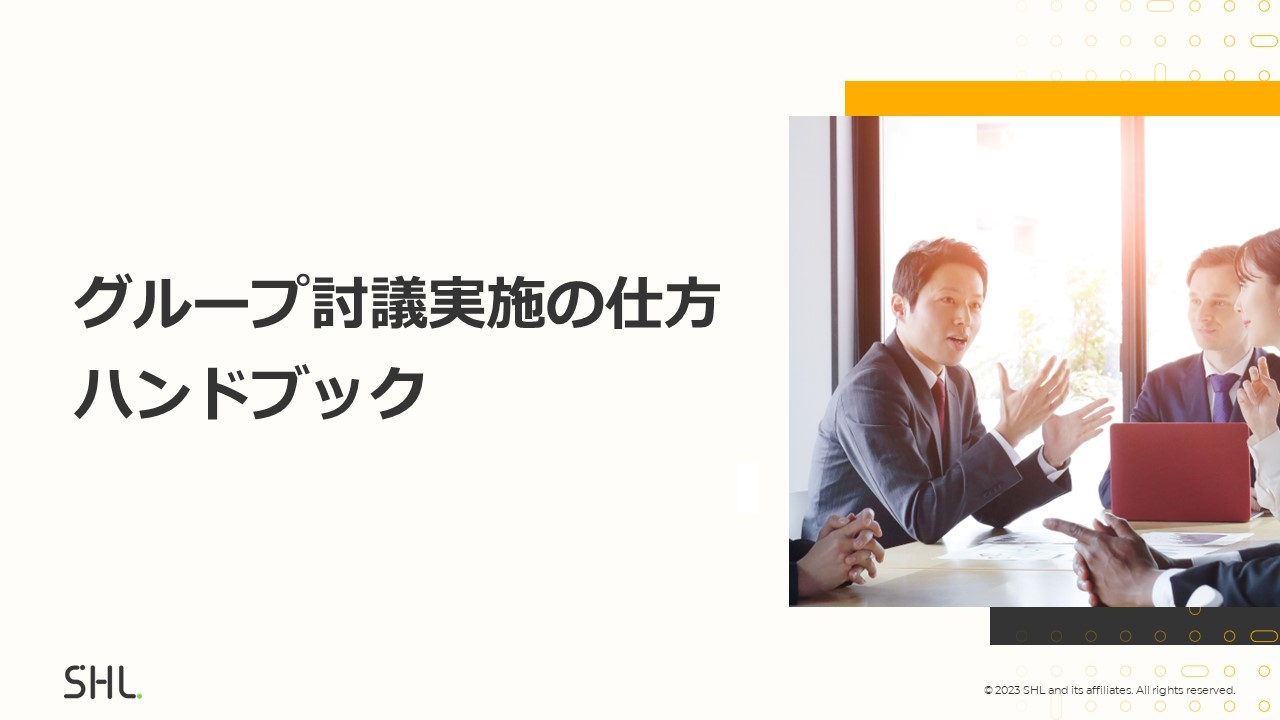目次をみる 目次を閉じる
個人の視点では、キャリア自律やリスキリングというキーワードに代表されるように、キャリア形成は従来の企業主導から、個人が積極的に開発していくものへと変わっています。この傾向により、人材の流動化が一段と高まるでしょう。
一方、企業側も副業・兼業を奨励し、多様な経験から得た知恵を活用しようとする取り組みや社内労働市場(タレントマーケットプレイス)の構築などのように、人事戦略の柔軟性を増しています。同時に、人材の獲得方法についても多様化しており、新卒者だけでなく既卒者の採用にも力を入れる企業や、コア業務を外部人材に委託することで専門知識を活用する企業が増えています。こうした取り組みが、企業と従業員の関係性に大きな変化をもたらしています。
今後は、企業と従業員の結びつきが以前よりも柔軟なものになると考えられます。さらには、プロジェクトごとにチームが形成され、その後解散するような柔軟な組織スタイルも生まれる可能性があります。
採用選考への影響
こうした変化は、採用選考にどのような影響を及ぼすのでしょうか。従来、長期雇用・長期育成を前提とした新卒採用では、カルチャーフィットが重要でした。企業の文化に合致し、長期的に貢献できる人材を見極めるために、面接中心の選考手法が用いられてきました。組織の柔軟性が増し、人材の流動性が高まった場合においても、企業は独自性のあるパーパスによって人材を惹きつける必要があります。「パーパスを共有できるのか」という観点における適合度については、これからも重要で在り続けるでしょう。
より重要になってくるのは能力の見極めです。プロジェクト単位でプロを雇って、完了したら解散するような組織の採用選考では、能力がより一層重要になります。ジョブ型雇用の進展により、成果を評価しやすく、求められる能力も明確になっています。ただし、経験がある人材は競争が激しいため、新たな方法で能力を評価する必要があります。未経験でも適性があり、成果を出せる人材を見つけることが求められます。
その一つの方法が「ワークサンプルテスト」です。業務を模した状況を設定し、実際の振る舞いを評価する手法です。この方法を新卒採用に取り入れる企業事例をご紹介します。

ワークサンプルテストの導入事例
この会社の採用選考の特色は次の3点です。・5つの選考ステップの中で、通常の面接(面接官が質問し、応募者が回答する)は、最終選考の最後の5分のみ。
・その他の選考手法は全てワークサンプルテスト。
・随所に選考のフィードバックが行われる。
具体的な選考ステップと実施内容は、次の通りです。
1次選考:Webテスト
エントリーした後に、知的能力3科目(言語、計数、英語)とパーソナリティの計4科目のWebテストが行われます。約1時間弱の時間で実施され、知識を問うような問題ではなく、短い時間で多くの問題に取り組む能力が試されます。
合格通知と共に、知的能力テストの結果に関するフィードバックも提供されます。例えば計数テストでは、次のようなコメントがあります。
「計数理解テストでは、基本的な計算能力はもちろんのこと、求められている解答を得るために最も効率的な作業手順を案出する能力が求められています。あなたは、短い時間で多くの数的処理を行う力がありますが、ケアレスミスや思い違いで回答してしまう傾向があります。冷静に問題の意味を読み取り、計画を立ててから必要な作業を行うように心掛けるとよいでしょう。」
応募者は選考を通じて自分の能力に関する理解が深まる仕掛けとなっている点が、応募者の惹きつけも意識していることが伺えます。
2次選考:インバスケット演習
インバスケット演習とは、デスクワーカーの情報把握や業務計画、分析・意思決定に関する能力を測定するために開発されたワークサンプルテストの一種です。通常、管理職の登用試験などで使用されることが多いアセスメント手法です。
この演習では、入社直後や異動直後のように、大量の情報に埋もれる中で、素早く情報把握をし、優先順位を付けながら業務計画を立てて、妥当な意思決定をできるかどうかをシミュレートする内容であり、実践的な業務環境での対応力を効果的な測定する手法となっています。
3次選考:模擬会議(グループディスカッション)
一般的に、グループディスカッションと聞くと、1つのテーマに基づいてグループで議論する手法を想像されることが多いですが、この選考ではまったく異なるアプローチが取られています。
具体的には、実際の会議と同じように10数ページに及ぶ会議資料が準備されます。約1時間後の会議終了時までに、事業上重要な意思決定を行うことを目標として、利害関係が対立する他の参加者と議論する場面が再現され、その中でどのような言動を取るかを評価されます。
この選考についても、合格通知と共にフィードバックが提供されます。例えば、次のようなコメントです。「根拠を述べながら自分の意見をはっきり主張し、グループとしての合意形成を図る行動が多く見られた。一方で、他者の発言機会を奪うような場面が見られた。」
こうしたアプローチによって、参加者は自身のコミュニケーションスキルやリーダーシップ能力を客観的に評価する機会を得ることができます。これによって、選考の透明性が高まり、応募者の成長につながるようなプロセスとなっています。

ファクトファインディング演習とは、情報収集能力を評価するための演習です。この演習は、顧客からのクレーム対応を行うなどの状況を想定し、アセッサーが演じる情報提供者に対して様々な角度で質問を投げかけ、情報を収集し、妥当な解決策を考えることが求められます。情報がまったく提供されていない状態から、何が起きているのか、どのような手段が取れるのか、それらの解決策がもたらす影響や効果などについて、包括的に情報を収集する能力を試されます。
最終選考:逆面接+通常面接
逆面接とは、特定の設定の中で応募者が面接官に向けて質問を行う面接手法を指します。この企業では、「自分が就職する先として妥当かどうかを判断するために取材を行う」という設定を与えていました。4次選考と同じような情報収集の能力把握も行いますが、質問に対して厳しい切り返しを行うことで、プレッシャーがかかる状況に置き、対応力も評価します。
選考全般を概観すると、1次選考のWebテストを除き、次のような業務場面を切り出して選考している様子が見てとれます。
2次選考:新しい環境での情報把握の素早さ及び段取り能力
3次選考:集団で議論し、プロジェクトをリードしていく時のコミュニケーション能力
4次選考:曖昧な環境における情報収集と解決能力
5次選考:上位者からの厳しい対応を受けた時の対処能力
おわりに
実は、ご紹介した事例は約20年前に筆者自身が経験した日本エス・エイチ・エルの新卒採用選考です。当時はベンチャーブームであり、奇をてらった様々な選考手法が取り入れられていましたが、当社の採用選考はひときわはっきりと記憶に残っています。選考プロセスを通じて、コンサルタントの職務に対する理解が深まり、自身の能力発揮方法や個性の活かし方を実感する貴重な機会でした。今後の人手不足の社会の中では、選び・選ばれる採用活動が求められます。相互理解が深まるような選考プロセスを実現する企業の採用ブランドが上がり、求職者からの人気を集めるのではないでしょうか。皆さまの組織ならではの採用活動を検討するヒントになれば幸いです。

このコラムの担当者
杉浦 征瑛
日本エス・エイチ・エル株式会社 副部長