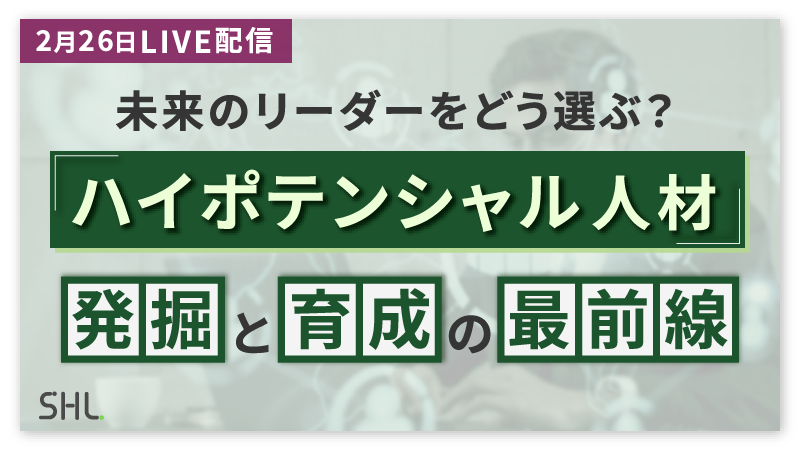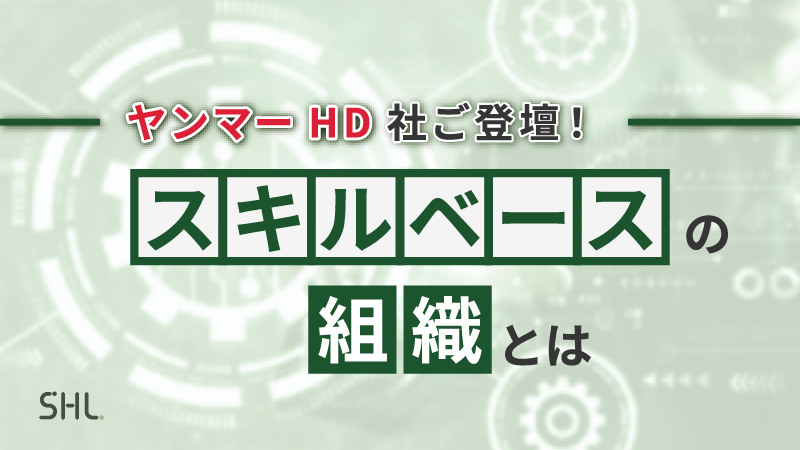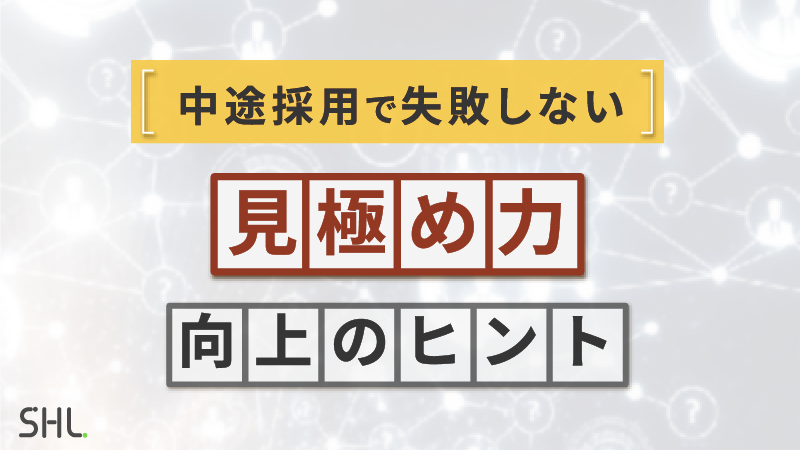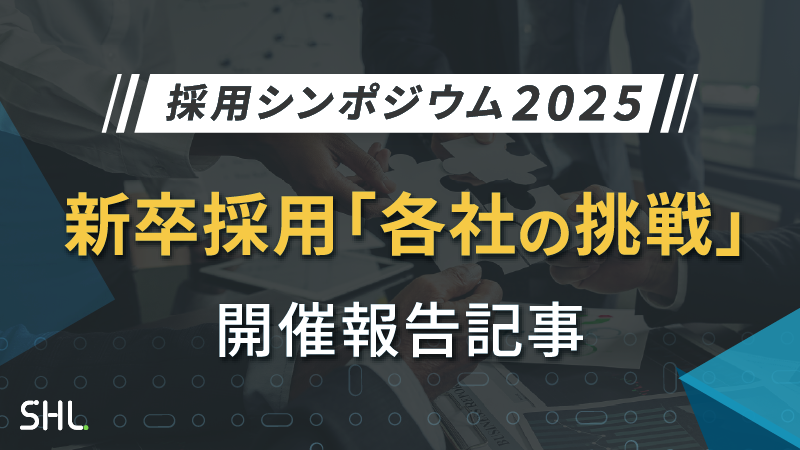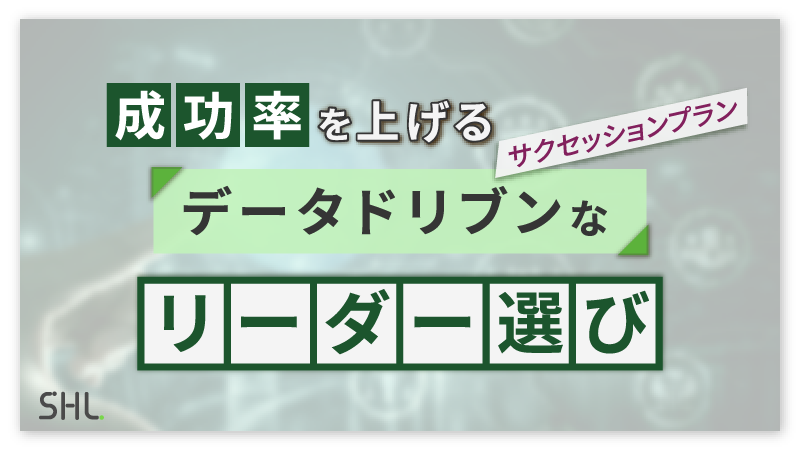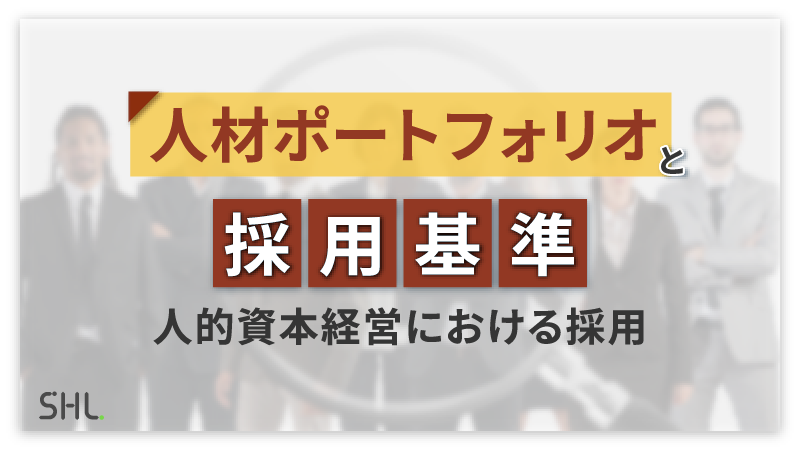部署内のコミュニケーション改善のため、チーム長制度を導入した愛知製鋼。
コミュニケーションの要を担うチーム長の育成に、アセスメントをどのように活用したのかをご紹介します。
※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
愛知製鋼株式会社
鋼材、鍛造品、電磁品の製造と販売
鉄鋼業
2,687名(2020年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方
杉浦裕樹 様
愛知製鋼株式会社
人事部 人材開発室
インタビューの要約
上司部下間のコミュニケーション不足の解消と、若手にマネジメント経験を積ませることを目的に、チーム長制度(4~7名の小集団をチーム長が束ねるという制度)が発足した。
チーム長の研修として、コミュニケーションの基礎となる自己理解を促進するために、OPQを導入した。
OPQを部下とのコミュニケーションの改善に役立ててくれる人もいた。チーム長制度の導入から、マネジメントアンケートの評価は向上してきている。若手をチーム長に登用して研修を受けさせるというサイクルが定着してきた。
当社はかつて少人数によるチーム体制をとっていたのですが、2003年に組織のフラット化をしまして、室長がすべての部下をマネジメントするという組織体制になりました。しかし十数年たつと、上司と部下のコミュニケーションが不十分で、若手の育成や指導が行き届かないという問題が出てきました。そのため、もう一度4~7名の小集団の体制に戻して、細かな指導やコミュニケーションを行っていきましょうということで、2016年頃にチーム制を再導入しました。
「チーム長」というポジションは基幹職の登竜門になっており、チーム長制度は二つの目的を持っていました。その二つというのは、チーム長が小集団を束ねてチーム内のコミュニケーションの活性化を図っていくこと、管理職になったときに円滑に業務を遂行させるためチーム長となった若手に小規模のマネジメントを経験させることです。
チーム長に任命された人の反応は様々でした。もともと役職についてなくても後輩育成を行っていた人からは、きちんとチーム長に任命され指導がやりやすくなった、という声がある一方でプレイヤーとしての業務が忙しい中で責任が重くなったと感じる人もいました。
コミュニケーションの基礎は、自己理解から。
新任チーム長のための研修に、チーム長自身の自己理解のためのアセスメントとして、OPQを活用したコミュニケーション改善のプログラムを取り入れました。きっかけは、数年前に新卒採用で日本エス・エイチ・エルの適性検査を導入した際に、「めっちゃ当たってる」と僕がベタ惚れしたこともあったのですが、コミュニケーションのスタイルを的確に分析できる指標を探した結果として行き着いたのがOPQでした。そもそもチーム長を強化しようとした背景は、チームのコミュニケーションの活性化を図っていこうということなんですが、まずは相手のことを知る以前に、自分のことを理解して、「僕ってこういう人間なんだな」「こういう傾向があるんだ」ということをわかったうえで、「じゃあどうやって相手と接しよう」「僕はこういうところに気を付けないと地雷を踏むな」とか、そういうことを考えるべきではないかなと思っていたんです。そのために、とにかく自分を理解するのに最適なツールを探していました。就職活動中の学生にも自己分析をさせますが、それと同じですね。その際に、「僕ってこういう人間かなあ」と一人で考えても納得感がないので、だったら定量的に見えるものを使って自己理解をしようということで、日本エス・エイチ・エルにお願いしました。

日本エス・エイチ・エルのアセスメントを選んだ理由は、僕が自分の結果を見たときに、新たな自分を発見できたというのもあります。たとえば勝気なところは認識が一緒だなと思ったんですけど、違う部分で意外な傾向が表れた部分もあって。「俺ってこういう傾向ある?」と人に聞いたら「うーん、あります」と。自分が無意識にとっている行動も結果に表してくれるアセスメントだったら自分の新たな側面を発見できるなと思いました。
実際に、研修を設計運営して思ったことは、コミュニケーションにおける自己理解の大切さを伝えるのは難しいということです。自己理解の重要性をいかに人事として伝えていくかというのは今でも課題ですし、当時は思うようにいかないなと思うこともありました。
逆に良い点は、自分と部下の結果を照らして、「自分と部下はこういう相性なんだ」、「こういう喋り方をすると伝わりにくいのか、だからコミュニケーションがうまくいかないのか」といったことを数字で見ると、特に技術系の人は良く理解してくれます。なんとなく、で言われても彼らは納得しづらいので、その点を定量的に見せて、「だからこういうふうにしたほうがいいですよ」という説明を加えることで、活用してくれる人はいました。チーム長たちが率先して行動を変えてくれれば、いずれ会社がいい方向に向かうと思うので、これは嬉しかったですね。
チーム長だけが対象ではないのですが、職場マネジメントアンケートを2年に1回とっていて、いわゆるマネジャーのマネジメントに対する評価を調査しているのですが、アンケートの結果は年々向上しています。コメントを見ても、小集団規模でうまく組織が回っているという声はあります。
あと、チーム長に若手を積極的に登用して、この研修を受けさせて自己理解させる、という流れが出来てきたと思います。基幹職の意識もチーム長は若手にやらせるものだと変わってきました。
今後は、チーム長が評価者となる仕組みを導入することを検討しています。現在、チーム長の上の室長が評価していますが、メンバーを一番近いところで見ているチーム長に評価とフィードバックをやってもらい、適切にPDCAをまわせるようにしていきます。今はチーム長に対してコミュニケーションや指導を軸にした研修を行っていますが、今後は評価を研修に含める必要があると思っています。
個人的には、チーム長のアセスメントデータが蓄積されてきたので、チーム長適性モデルを開発し、次期チーム長候補の選抜や採用選考の基準として使うことも検討したいと思っています。単一のチーム長適性モデルを作ると、同じような人がチーム長になってしまうので、複数のチーム長タイプを想定して分析したいです。当社は保守的な会社ですので、人を数値化することに慎重ですが、定量的なアプローチで人事からの提案の納得性を高めたいです。
日本エス・エイチ・エルとは長い付き合いで信頼しています。人の特徴を正確に表すアセスメントツールとアセスメントツールを活用したタレントマネジメントのノウハウを持っているので、当社のタレントマネジメント施策を一緒に進めてもらえる会社だと思っています。めちゃくちゃ融通利かせて、当社に寄り添ってアレンジしてくれるので助かっています。今後も先進的なアセスメント活用手法について情報提供してもらいたいと思っています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 名古屋オフィス長
杉浦 征瑛
偶然同じ苗字であった杉浦さんとはHR以外の分野についても同じテーマに関心を持っていることが多く、初めてお会いした時から幅広い意見交換をさせていただきました。マネジメントは「人を動かして、組織目標をなんとか達成する」ことですので、人を動かすためのコミュニケーションが欠かせません。コミュニケーションは相手が動くことを目的としており、自分の言動を相手がどのように知覚するのかを知るために、自己理解と他者理解が重要になります。マネジメント力強化のために「自己理解」を取り入れるのは、一見突飛に見えますが実は本質的な取り組みです。研修設計のための行った杉浦さんとの議論は私にとって有意義な経験となりました。今回の研修でのメッセージは、繰り返し形を変えて伝えていく必要があるものです。引き続きお力になれればと考えています。