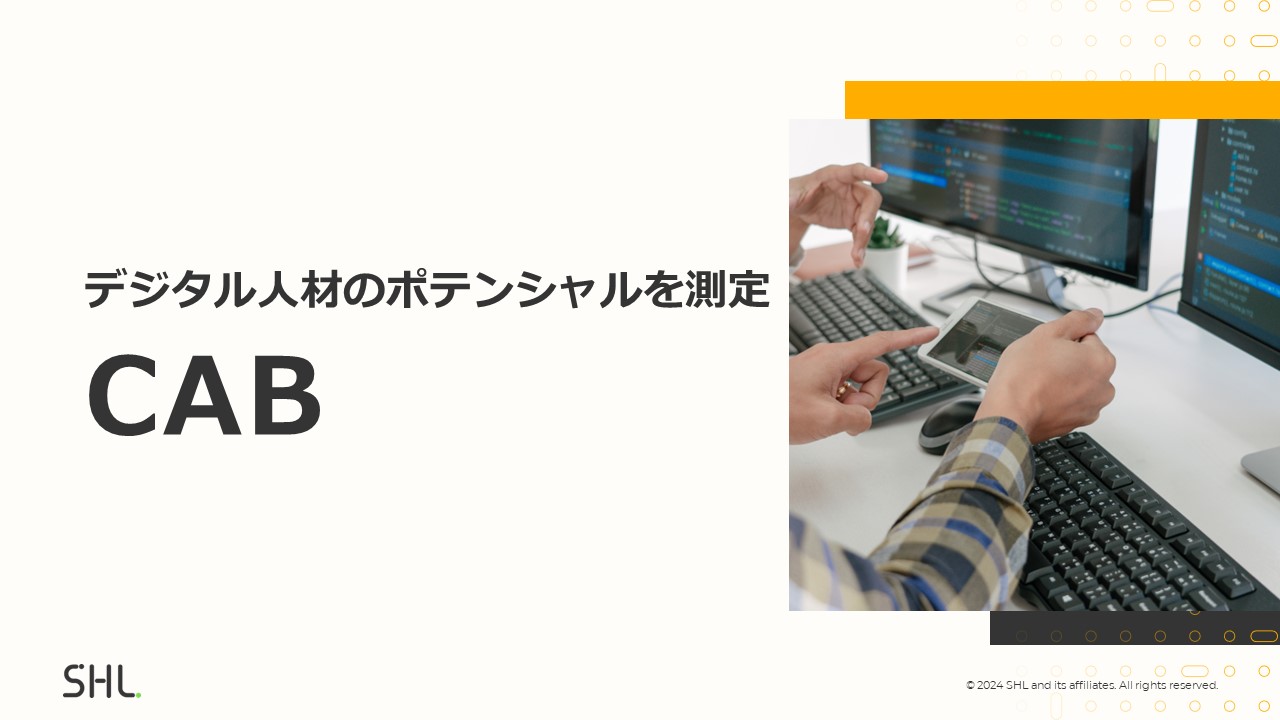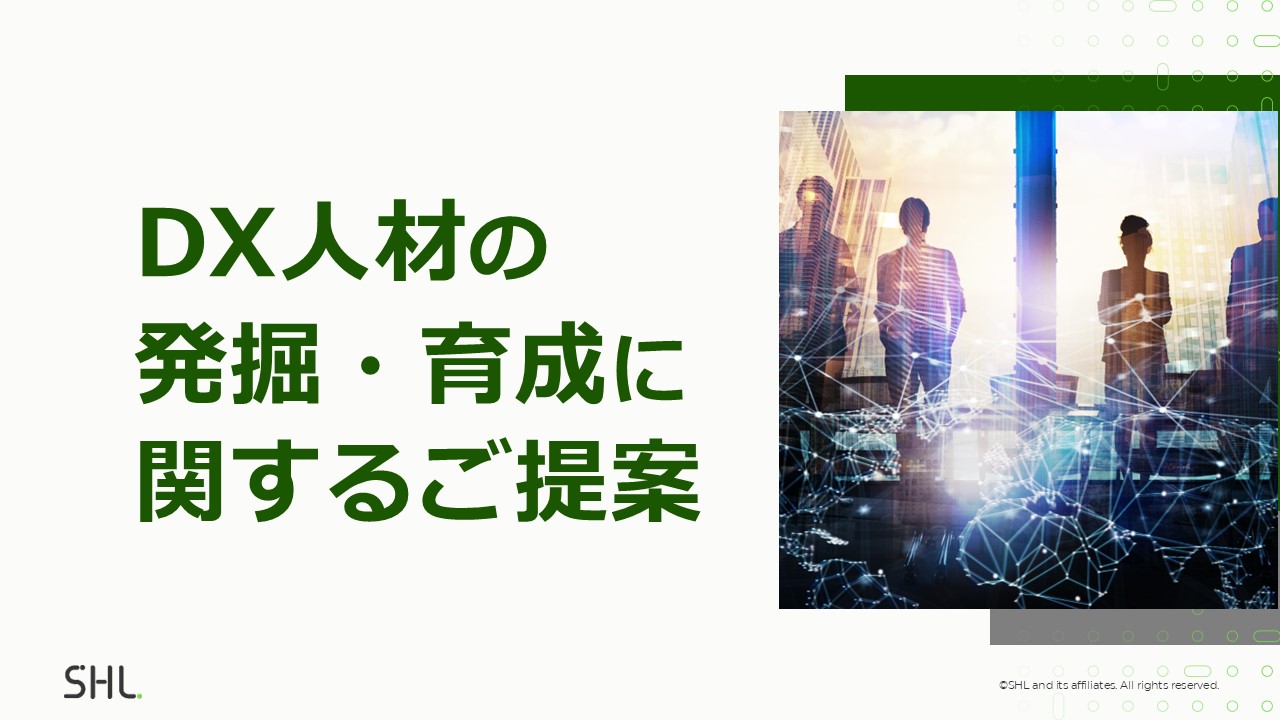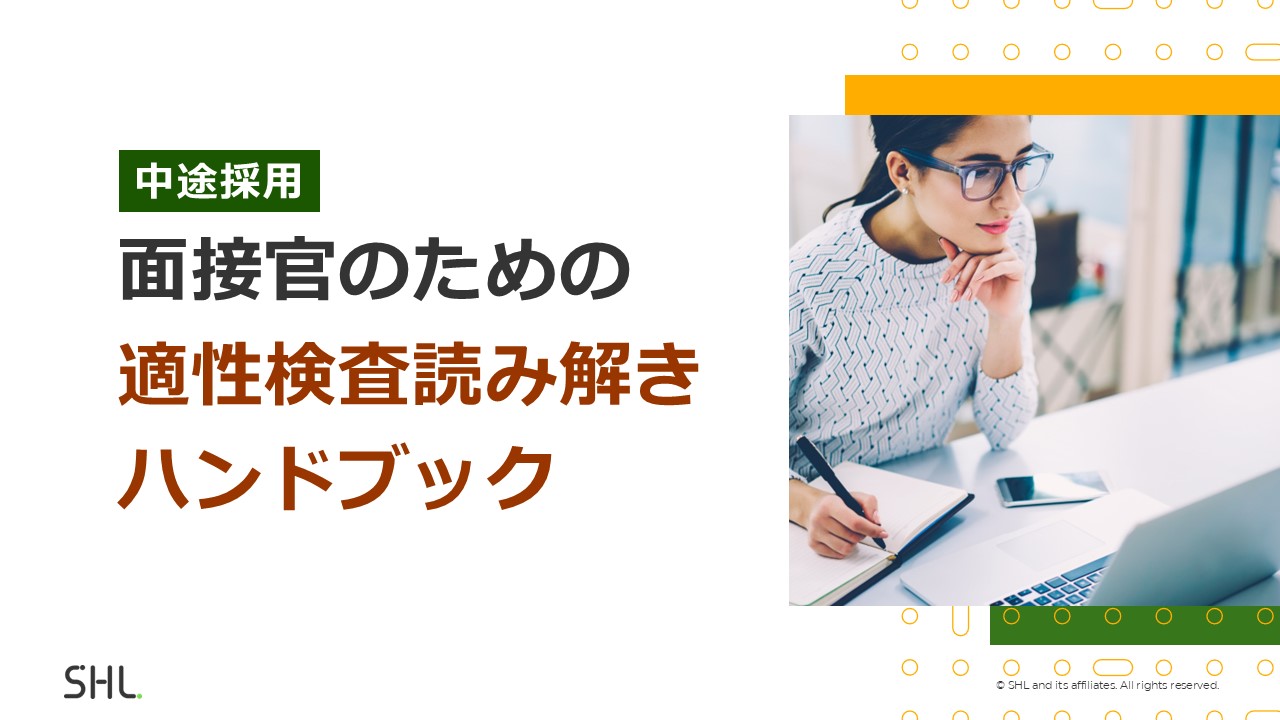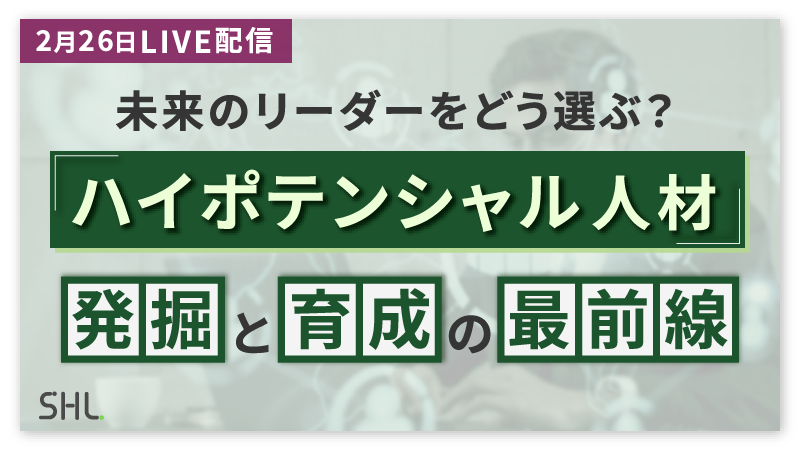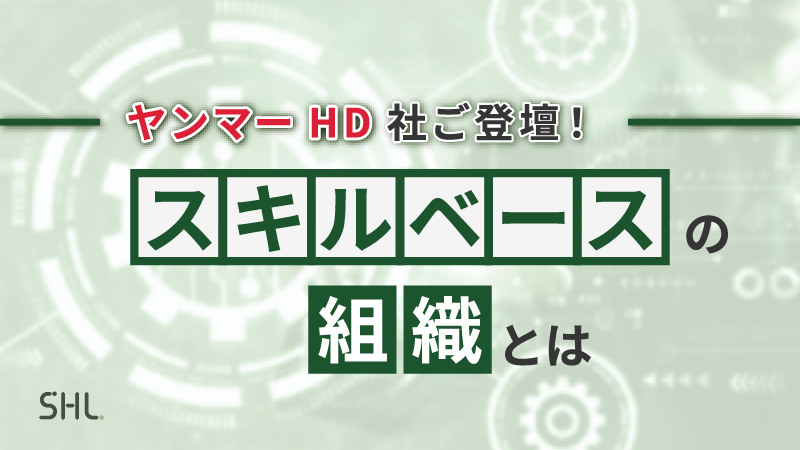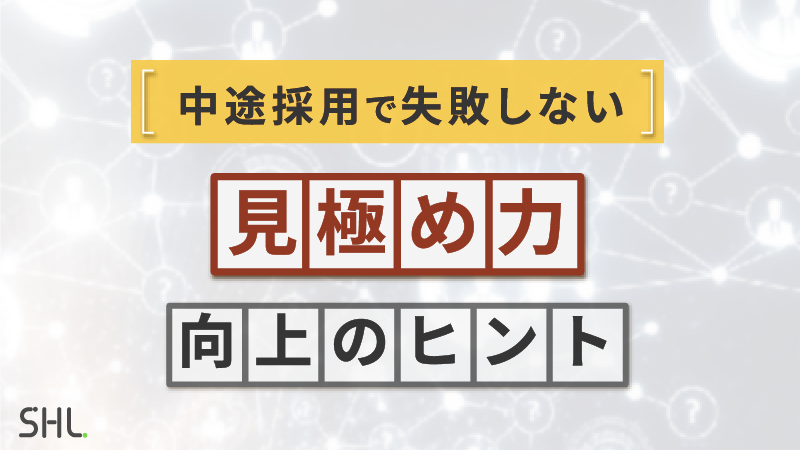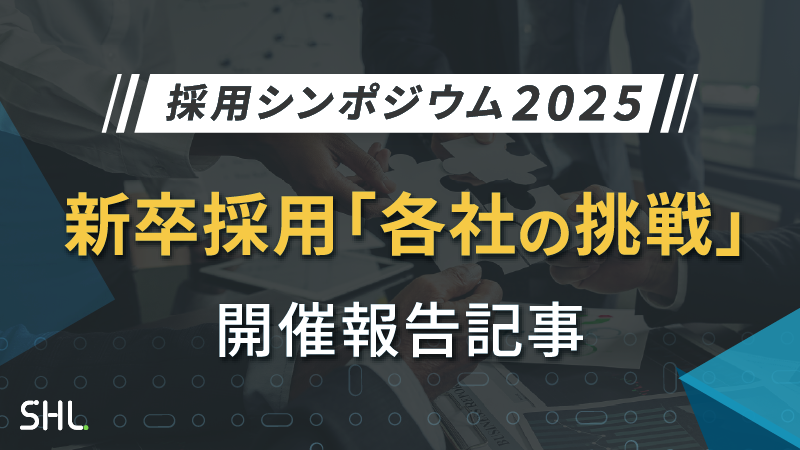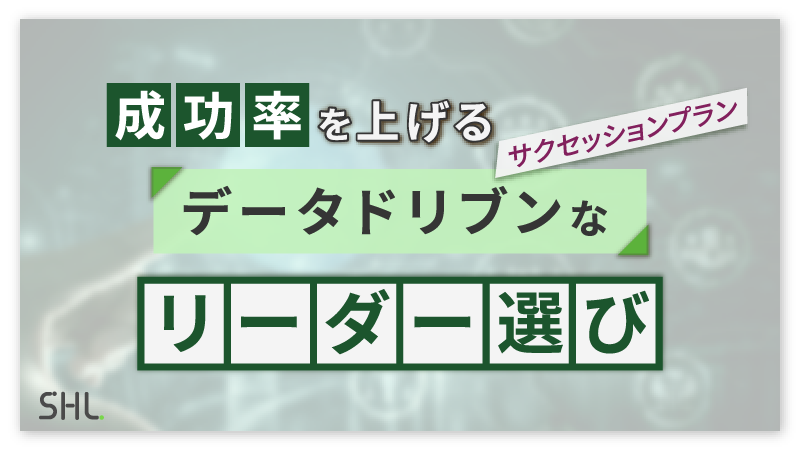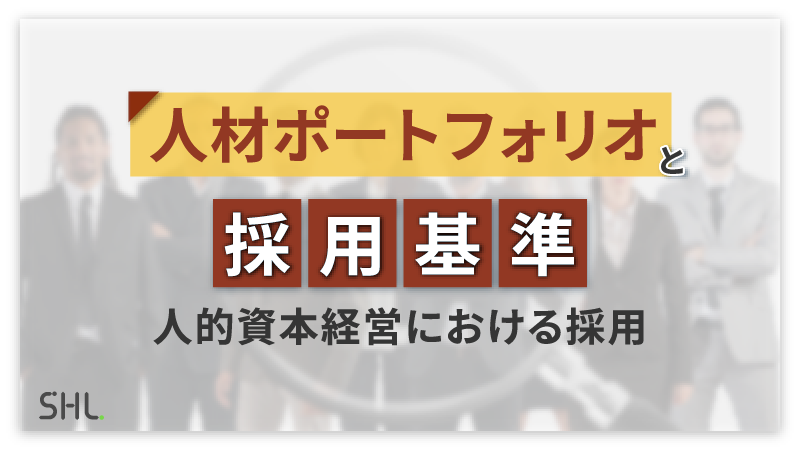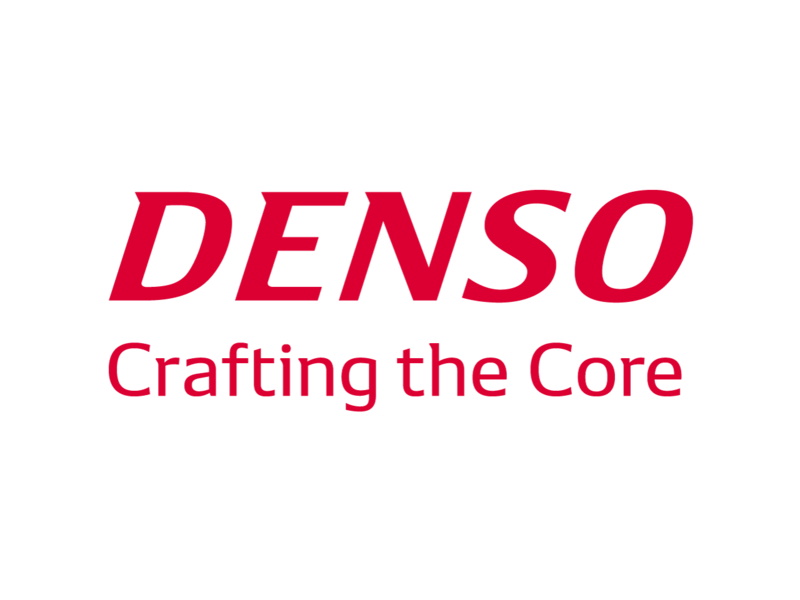DX支援を中心に展開する情報戦略テクノロジーでは、ソフトスキルにも注目した中途エンジニア採用改革を推進。CABテストを活用して行った自社独自の分析で、事業に貢献する新たな人材の定義と見極めの取り組みをご紹介します。
※本取材は2025年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社情報戦略テクノロジー
大手優良企業特化型システム内製支援事業
IT
358名(2025年4月1日時点)

インタビューを受けていただいた方
川上 貴之 様
株式会社情報戦略テクノロジー
人材採用部
部長
レッドオーシャンのエンジニア採用でソフトスキルに注目
私は大手総合人材会社に法人営業として新卒で入社し、その後フリーランス人事として2年間活動していました。情報戦略テクノロジーには人事マネージャーとして入社し、2024年に現場の感覚を掴むべく、勉強のため1年間営業部門で兼務をしたのち、現職に着任しました。現在は年間約400件の面接を精力的に担当している傍ら、エンジニアのバックグラウンドがないながらも、AWSやデータ活用に関する資格を取得し、日々研鑽に務めています。
情報戦略テクノロジーは内製支援に強みを持つ大手企業向けのDX支援の企業です。創業17年目で、昨年東証グロース市場に上場を果たしました。当社では中途採用で年間30-40名のエンジニアを採用しています。単なるシステム開発だけでなく、IT企画・上流支援・PMOなどのポジションでの価値発揮が求められる中、どのターゲット層を狙っても他社と競合する状況になっています。

その中で少しでも活躍するエンジニアの属性分析・多くの試行錯誤をしていた中で、いわゆる専門的なハードスキルだけでは測れないその人自身の「ソフトスキル」が重要であることが分かってきました。
創業当時から活用しているCABにより、エンジニア採用の精度向上を実現
情報戦略テクノロジーでは創業以来、中途エンジニア採用においてCABを活用しています。選考プロセスは、書類選考と1次面接を人事の私が行い、CABの受験後、最終面接に進みます。最終面接はエンジニア部門の役員・部長クラスが行います。
以前は1次面接前にCABをご案内する選考フローも試していましたが、候補者への負担からか選考の離脱率が高かったため、現在はこのフローで落ち着いています。
CABは長く利用している歴史もあるため、社内でテスト項目も共通言語化されており、人物面を定量的に論じられるのが良い点だと感じています。新任の面接官にはCABのレポートの見方ガイドも配布し、人事から説明する機会を設けるなどして浸透を図っています。
エンジニアの素養を見極める知的能力の観点はもちろん、パーソナリティ診断結果の部分も深く活用しています。

例えば、知的能力項目の得点が同じで、「①ヴァイタリティ・創造的思考力・問題解決力・状況適応力が高く、人あたり・チームワークが低い方」と「②問題解決力・状況適応力が高く、人あたり・チームワークが中得点だった方」がいたとします。前者は人とのコミュニケーションは苦手だが、思考力は高く優秀なパフォーマンスを発揮する方であり、スペシャリストとしての期待を持ちます。後者はパーソナリティ面のバランスが良く、顧客やビジネスサイドとの対応・折衝も期待ができる、ソフトスキルに優れているSEと評価します。
もちろん、面接でお会いした所感と突き合わせながら人物評価をしますが、CABの結果と大きく外れるケースは少なく、これらの情報も最終面接官に引き継いで判断しています。
CAB結果に基づいた分析により新たな採用ターゲットを発見
これまで当社の採用は、知的能力の点数が高い人材をコアターゲットとしており、具体的に適性検査の知的能力総合の得点で一定の基準以上であれば有望視する、という採用活動を行っていました。しかし、5年ほど前からDXという言葉がトレンドとなり、単純なシステム開発だけでなく、顧客のDX支援、特に「何から始めればいいかわからない」という顧客からの相談も増えてきたタイミングがありました。その際、知的能力の高さだけでなく、他の要素もエンジニアのパフォーマンスに大きく影響していそうだ、という話題が挙がりました。
人事の視点から、活躍している人材の定性的なパフォーマンスやデータを収集し分析を行ってみた結果、CABテストの能力特性を振り返りながら分析を進めると、ソフトスキルに優れたエンジニアが活躍しているという新しいターゲット像を発見できたのです。これまでの知的能力総合得点の基準はやや下回るものの、人あたり・チームワークの合計得点が一定以上であれば、持っているエンジニアリングスキル以上に活躍している層が居ることを発見できたのです。

このターゲットに該当する社員を分析すると、同程度の業務経験があるエンジニアよりも、顧客からの単価評価が数十%高いという結果が得られました。この結果を発見してからは、同様の傾向を持つ人材をターゲットとして、積極的に採用しています。現在もこの傾向は変わっておらず、役員や部長との間で共通言語化も進みました。この出来事は事業視点で見ても大きな影響があったと感じており、ソフトスキルに優れた人材という新しい枠組みで採用を行うことができるようになったのです。
AI時代にフィットした人材活躍の模索へ
今後の展望ですが、近年、AIの活用が急速に進んでおり、当社も注力しているテーマの一つですが、CABの結果はAI人材の発掘、登用、育成にも活用できると考えています。
現在、私自身が社内でAI活用の推進をリーダーとして進めています。営業部門など他部署に対して業務整理から入り、AIを前提とした業務プロセスの再設計・業務支援などを行っています。
その中で感じるのは、AI導入のフェーズによって求められる人材の要素が異なるということです。立ち上げフェーズでは、ヴァイタリティ・プレッシャーへの耐性・状況適応力など、精神力が高い人材が活躍するように見受けられ、逆に運用フェーズでは、人あたりやチームワークが高い、ホスピタリティに優れた人材がより活躍しているように見受けられます。
こういった仮説も基にしながら、AI時代にフィットした人材の活躍について、多くの物事にチャレンジしながら模索を続けていきたいと考えています。
日本エス・エイチ・エル、ならびにCABは当社の人事業務・事業拡大にとって欠かせない重要な要素になっています。特に当社のビジネスモデル上、人材の採用・育成・配置は事業の肝であり、CABという1つの基準があることで人材戦略を効果的に決めて実行できていると感じます。今後、どんな環境変化があったとしても引き続き活用させていただきたいと考えています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
横山 武史
情報戦略テクノロジー様では、中途採用においてハードスキルだけでなくソフトスキルにも注目され、ソフトスキルに優れたエンジニアほど高い単価評価を得ていることを発見されました。CABは当初、知的能力の測定を目的に導入されましたが、現在はソフトスキルの評価にも活用されています。
評価手法と職務成果の関連性を説明できる状態にすることは、すべての企業が取り組むべき課題であり、情報戦略テクノロジー様の事例は、中途採用を拡大する企業にとって貴重な参考になると感じました。川上様はエンジニアのバックグラウンドがない中でも、関連資格を取得されるなど日々研鑽を重ねておられます。私も現状に甘んじることなく、新たなアセスメント活用の方法をご提案し、より良い採用支援に努めてまいります。