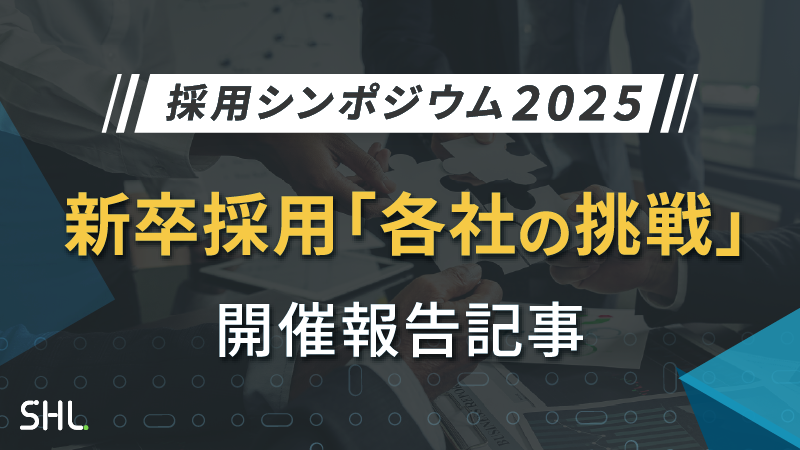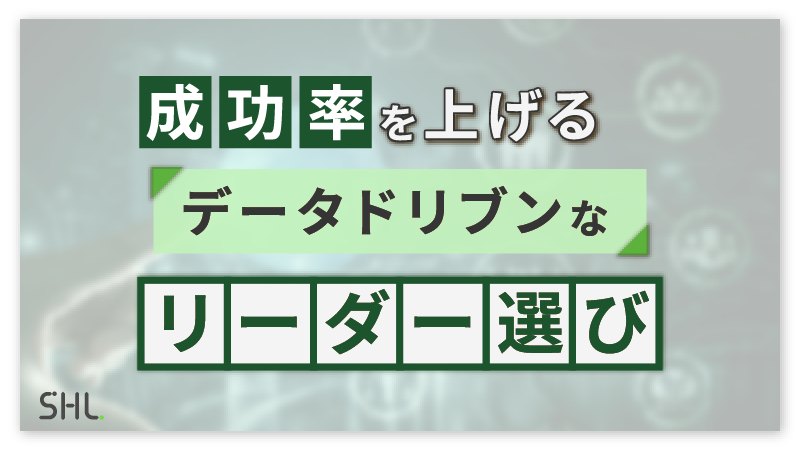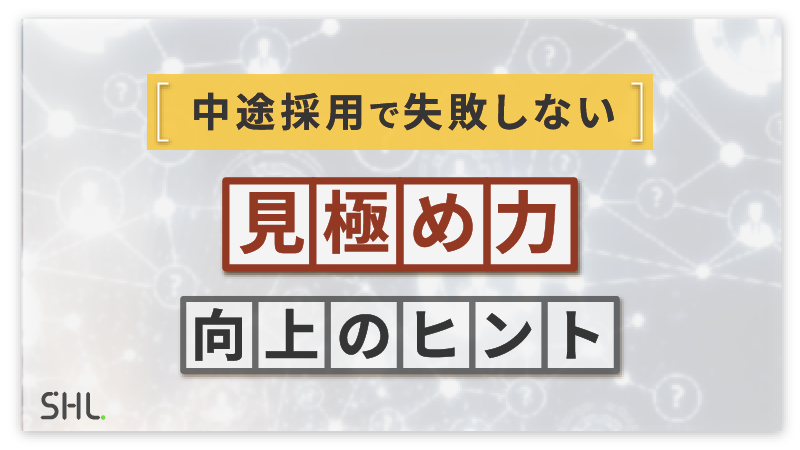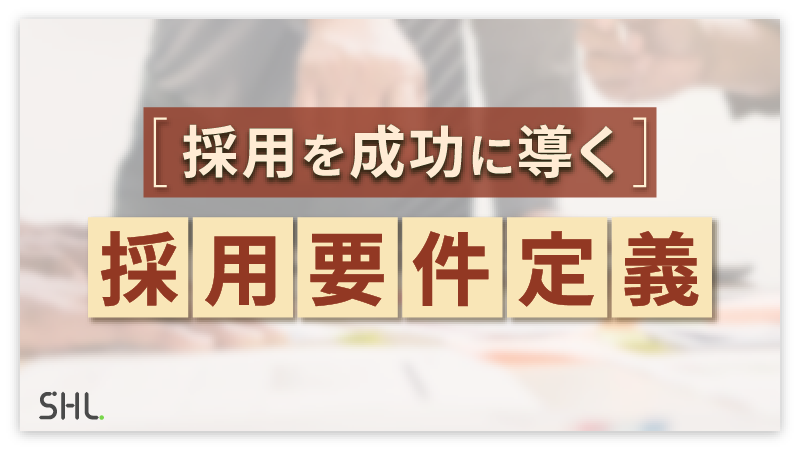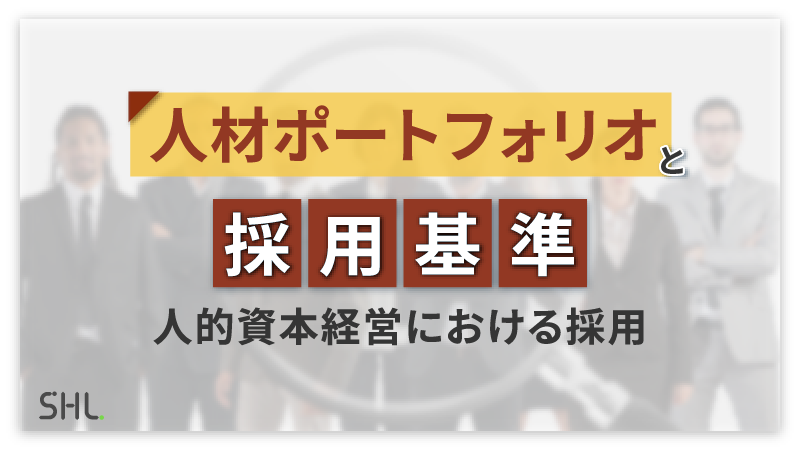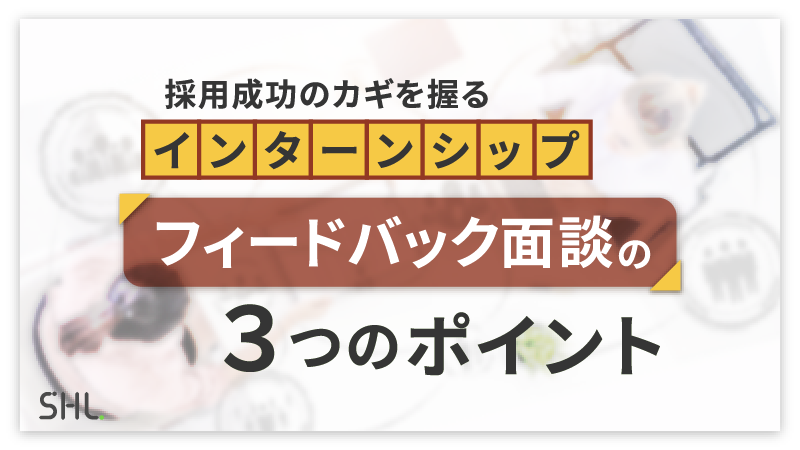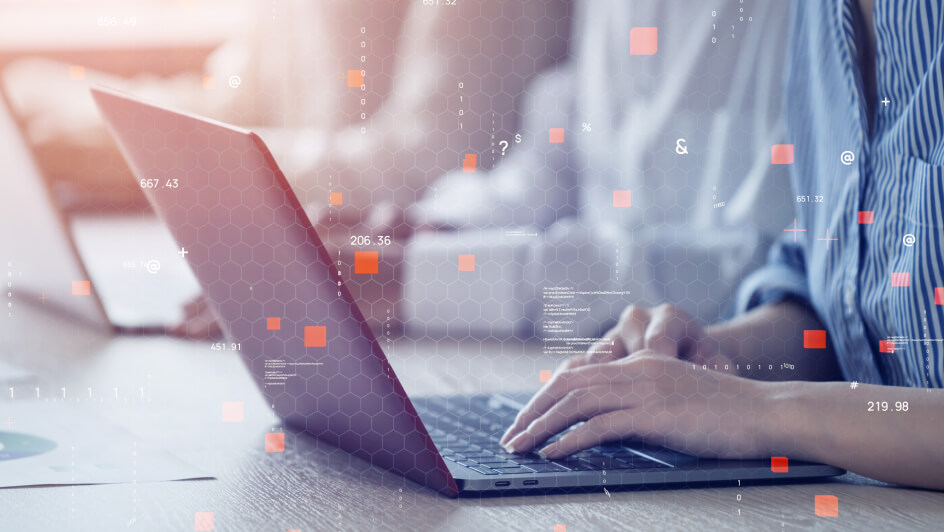日本市場で急速な成長をとげた、ホットヨガスタジオ事業のLAVA International。
組織の急拡大に伴う人事課題にどのように取り組んだのか、そのタレントマネジメント事例を紹介します。
※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社LAVA International
ヨガスタジオの運営、ヨガインストラクター養成スクール等の運営、ヨガウェアブランドの展開、ヨガイベントの運営
サービス業
グループ全体 5,877人(正社員4,256名、アルバイト1,621名)※2019年8月末現在
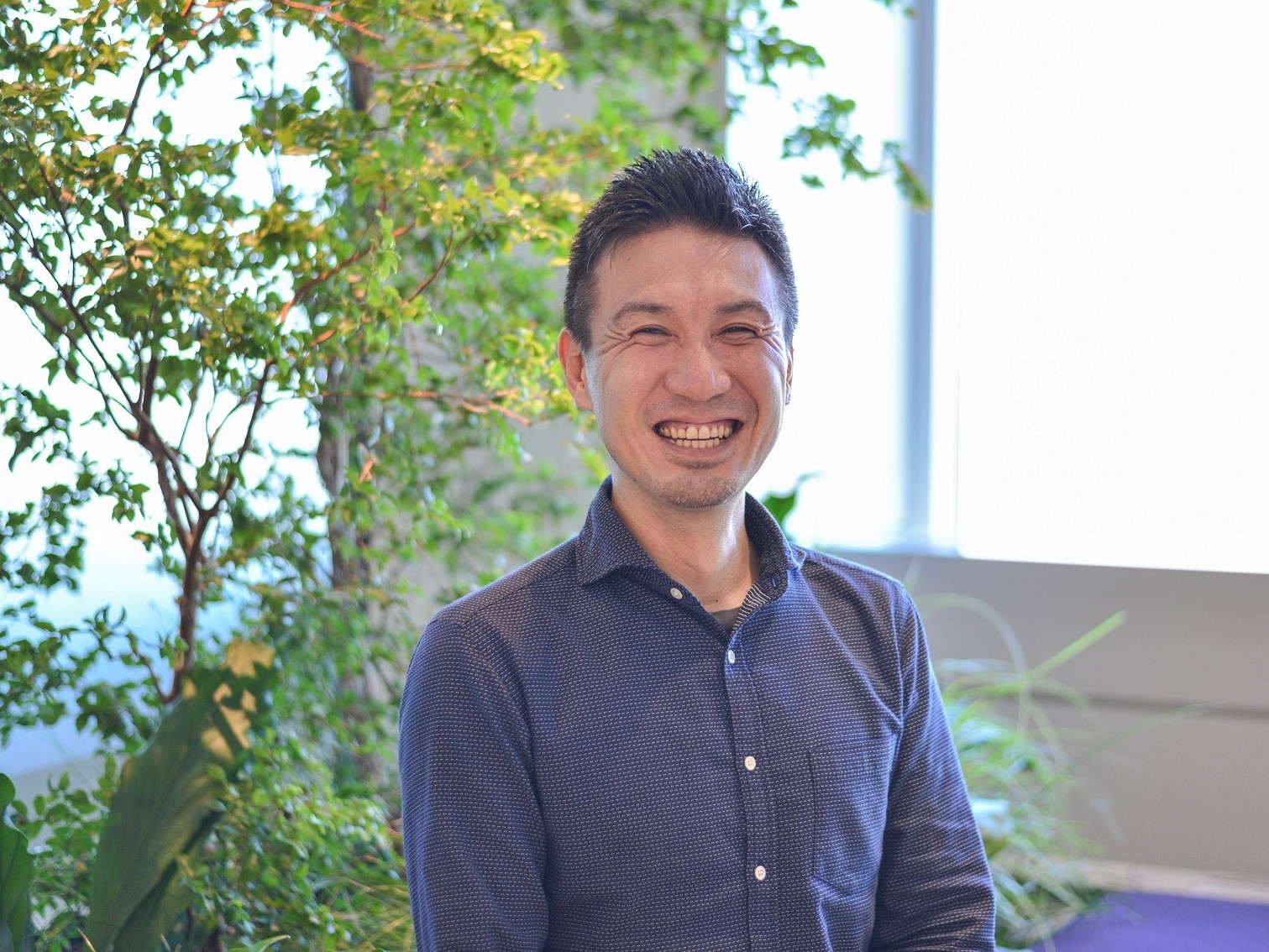
インタビューを受けていただいた方
的場 勝己 様
株式会社LAVA International
運営部 部長
インタビューの要約
急拡大に伴う大量採用が求められる中、採用数よりも採用の質を担保する必要性を感じ、入社後のパフォーマンスを予測できるアセスメントを探し始めた。
部長以下の全社員に日本エス・エイチ・エルの適性検査を実施し、データ分析を行った。インストラクター、店長職、SV職、本部系企画職の適性がそれぞれ明らかになった。
採用のフローにアセスメントを組み込み、質の高い採用活動が可能となった。また、インストラクターから本部系企画職へのキャリアチェンジにもアセスメントを導入し、適性に沿った異動が可能となった。また、社内にアセスメントの用語が徐々に浸透し、人材の能力や特徴を表現するための共通言語ができた。
ギリギリ合格した人材の中に、光る逸材がいる。 それがパフォーマンス分析に目を付けたきっかけ。
今の立場は、店舗運営の責任者ですが、日本エス・エイチ・エルのアセスメントを導入した当時は、人材開発部の採用グループのグループ長でした。大量採用のさなか、私の問題意識は、採用数を確保することも大事なのですが、今の採用は成功しているのか否かを、入社後のパフォーマンスで示すべきではないか、ということでした。
このような問題意識を持ったきっかけは、いくつかあります。私自身のキャリアは営業畑が多く、結果がすべて数字でわかる世界です。採用の結果は採用数はもちろんわかりますが、もっと違う形で採用の成果を表したかったというのがまず一つ。もう一つは、採用と教育、現場の立場の相違です。採用と育成は、育成がうまくいかないケースに対し、「なぜこの学生を採用したんですか」と葛藤が起こります。教育と現場は、現場でスムーズに業務が行えなかった場合に、「なぜこの状態で送り出したんですか」と、また葛藤が起こります。このような構造を解消するために、現場でのパフォーマンスをベースとして、こういう理由で採用したのだという根拠を出発点に持ちたかったのです。そのために、採用の視点と現場でのパフォーマンスに相関があることを示す必要がありました。

もう一つ加えて言うと、大量採用で採用数を確保する必要があったので、ギリギリで受からせた人たちがその後どうなったのかを知りたくて、最終面接評価C-で合格した人材を、自分で追跡調査してみました。その結果、C-で合格した人材は、早期離職はたしかに多かった。でも、入社後パフォーマンスが高い人材の出現率も、C-が多かったのです。このような興味深い結果が表れたことも、パフォーマンス分析に踏み出したきっかけになりました。
選んだポイントはわかりやすさと汎用性、そして「当たっている」ということ。
「採用時のアセスメント結果と入社後のパフォーマンスとの相関をはっきりさせて、より質の高い採用をしたいので、そのための提案をください」と、6,7社くらいにお声がけしました。日本エス・エイチ・エルを選んだのは、最終アウトプットを自分たちがどう使っていくのかイメージしたときに、一番わかりやすかったから。あとは、「今回は入社後のパフォーマンスとの相関を分析するつもりだが、いずれは役職への登用や、本部系の企画職へのキャリアチェンジなどにも使っていきたい。その分析も可能か?」と聞いたら、ことごとくできると言っていただいたので。社員のアセスメントは何かを知りたいというたびに実施するものではないと思うので、一度の実施で色々な活用ができることは大きなメリットでした。
最後の理由は、導入前にモニターとして社員が受検した結果が、本人の特徴を正しく説明していて、役員が感動したからです。「本当だね、この子そうだよね」と。最初はインストラクター採用のためとしか考えていなかったのが、この最終決定に至る過程で上層部に見てもらった時に、これは面白いねとなって、部長以下全員に受検してもらう流れとなりました。
見えてきた各職種への適性をもとに、効率的な採用・異動を実現。
社員のアセスメントデータを分析した結果、インストラクターに必要な特徴に加え、店長職やSV職に求められる特徴、そして本部企画職に求められる特徴がわかりました。店長職やSV職には、インストラクターの資質に加えて求められる資質があり、また本部企画職の適性は、インストラクターの適性とは一部相反することなどがわかりました。
その結果を受けて、採用ではかならずアセスメントを実施して、面接官と見方を共有して評価に使いました。また、インストラクターから本部系職種へのキャリアチェンジの際も、実施して見極めに使うようにしました。インストラクターと本部系職種は、業務内容がまったく異なりますので、アセスメントをして面接してみると、現場よりも本部に適性のある方もいたりします。そういう方を発見できる喜びもあります。

さらに、社内で実施している360度評価の結果を、さらに詳細に解釈する際にも、このアセスメントを組み合わせて使っています。360度評価は、あくまである人の視点なので、時期やペアリングの影響も受けますし、完全に鵜呑みにすべきではないと思っています。本人のアセスメントの結果も併せて参照し、なぜこのような360度評価の結果になったのか、というのを深く理解しようとしています。人には多かれ少なかれ多面性があって、何かきっかけがあれば誰でも異なる側面が出てくるものなので、なるべく客観的な視点をもつよう努力しています。
社内の人材を表す共通言語ができた。
採用や異動を効率的に行えるようになったということのほかに、アセスメントを入れてよかったことは、社員の特徴を的確に表す共通言語ができたことです。実際にアセスメントの結果を目の前にするのは人事系の役職者だけですが、彼らが各部門に対してもアセスメントに使われている用語を使って、採用や育成について話します。アセスメントに使われている表現が社内に浸透すると、他の社員のことを評価するときにその表現で話すので、社内にいる人のコンピテンシーを表すのに共通言語ができます。たとえば、プレッシャーへの耐力がある、というのが正確な表現だとして、それを単に「メンタルが強い」などと表現してしまうと、少し意味があいまいになってしまう。そういう共通言語ができることも、いい人材マネジメントにつながるのかなと思います。
今後の人事施策については二つあります。まず新しく着任した人材開発部長の言葉を借りると、「採用に際して、インストラクターを採るのではなく、全体を対象に利益創出ができる人材をとる」。インストラクターがゴールと見えないような入社後の広がりを感じる採用活動をすることで、良い店長が排出されるようにしたいです。女性が多い会社ですので、妊娠・出産・復帰のサイクルがあることを考えると、もっと役職者を輩出するペースを上げるべきですし、入社当時から自然とキャリアアップを目指したくなる採用をしたいというのは、まさにその通りだなと思います。
もう一つ、私の現在の役割である運営部の目線で言うと、採用を担当していたときから実施したかった、アセスメントを用いた配置や昇進は、まだまだ活用できる余地があると思いますので、今後は運営部でさらに力を入れていきたいと思います。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
下越 千尋
社員の方々のアセスメントデータ分析結果を報告した際、その結果を裏付ける具体的なエピソードや意見が的場さんや役員の方から出てきて、活発なディスカッションとなったのが印象的でした。お客様の持つ仮説がデータによって検証され、それが具体的な言葉や数字となって共通認識された瞬間でした。分析結果を深く理解されようと、実際の現場で起きていることや既存の情報などを組み合わせて多角的に判断しようとされている点は、私自身勉強をさせていただいたことも多かったです。また、私どもが提供するアセスメントツールが現在も社内のコミュニケーションの道具となって活用されていることも、お客様の組織の発展に寄与できているという私たちの自信と誇りにつながっています。お客様がこのツールから得られる知見がより価値の高いものになるよう、引き続き支援させていただきたいと思っています。