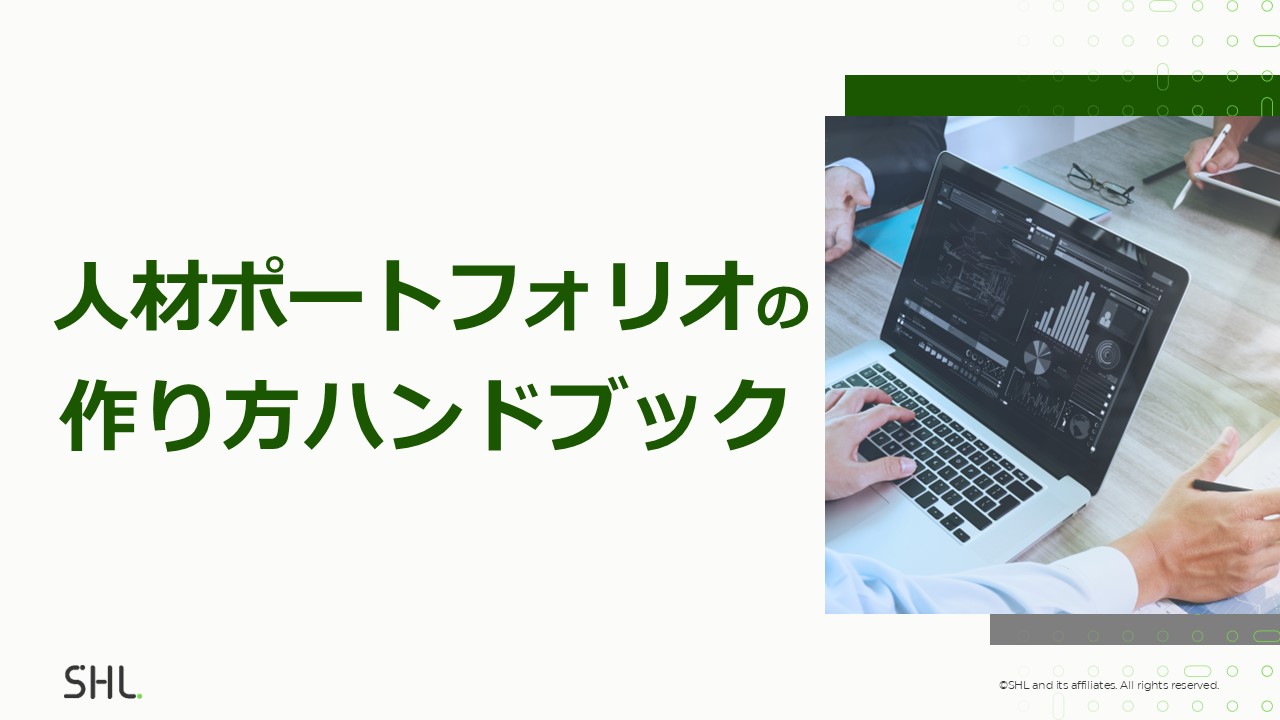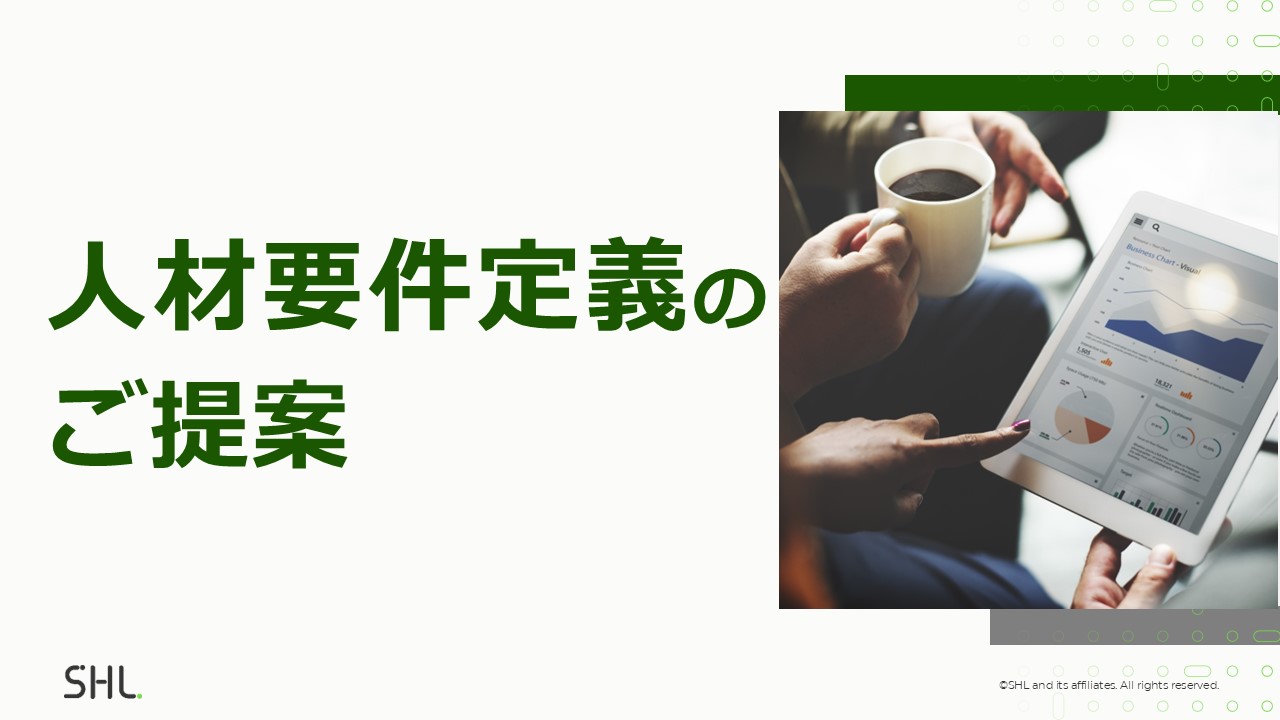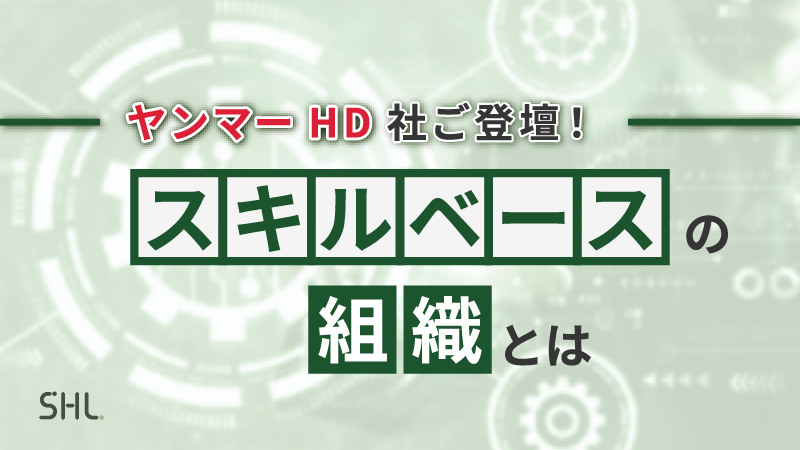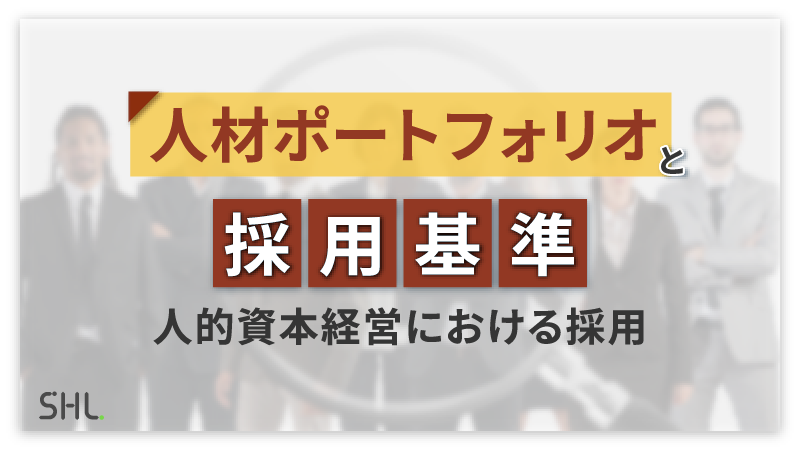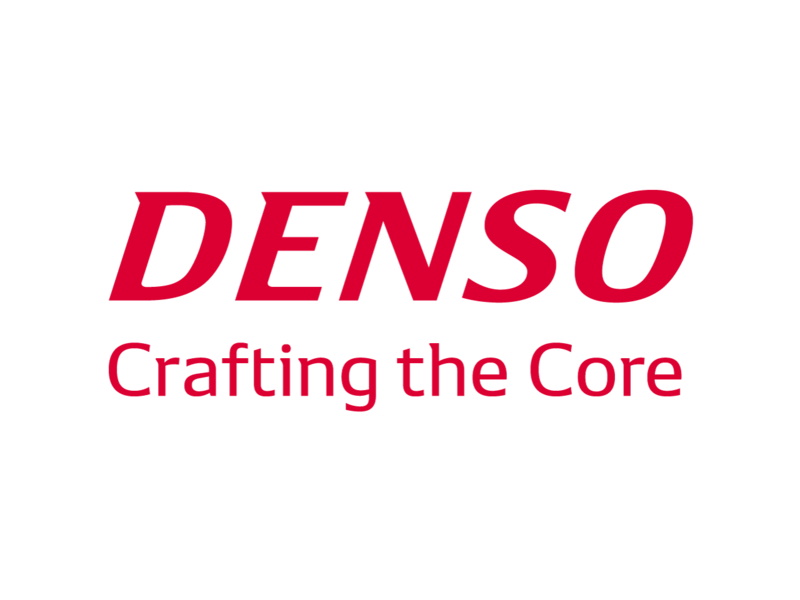「顧客価値創造企業」への変革を目指すヤンマーでは、スキルベースの人材マネジメントを全社的に推進。人材ポートフォリオを軸にした育成体系の再構築と、社員一人ひとりのスキルアップとキャリア実現を支える仕組みづくりの取り組みをご紹介します。
※本取材は2025年10月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
ヤンマーホールディングス株式会社
農業機械・農業施設、建設機械、エネルギーシステム、小形エンジン、大形エンジン、マリン、コンポーネントなどの研究・開発、製造、販売
メーカー(産業関連)
26,671名(連結、2025年3月31日時点)

インタビューを受けていただいた方
司尾 龍彦 様
エンプロイーサクセス本部
人事部
人材開発グループ
課長
インタビューの要約
「顧客価値創造企業」への変革を目指し、人材育成体系の再構築に着手。20年近く整理されていなかった教育制度を見直し、グループ全体での育成強化を推進した。
人材ポートフォリオを活用し、現状とあるべき姿のギャップを可視化。スキルベースの人材育成を軸に、社員のキャリア形成支援、教育研修体系の再構築、プロフェッショナル人材の育成を3本柱として取り組みを展開した。
技術系で30年以上運用されていたスキルベースの人材マネジメント「CDP(Career Development Program)」を全職種に展開。スキル設定・教育マップ整備・専門職認定の3ステップで社員の成長を支える仕組みを構築。
国内外でのスキル設定と専門職制度の導入を進め、今後はグローバル展開を完了予定。社員の成長実感とエンプロイーサクセスの実現を目指す。
「顧客価値創造企業」への変革に向けた人材育成の課題
ヤンマーは、1912年に創業し100年以上の歴史を持つ老舗企業です。世界で初めて小型ディーゼルエンジンの実用化に成功した企業であり、事業のコアは動力源、つまりエンジンを中心とした技術です。この動力源を活用して、農業機械、船舶、建設機械、空調機器などの製造・開発・販売を行っています。現在、グループ会社は115社、世界中で約28,000名が活躍しています。
私自身は1999年に新卒でヤンマーに入社し、最初は営業を経験しましたが、ほぼ一貫して人事領域に携わってまいりました。昨年7月に人材育成体系の再構築を任され、現在その取り組みを進めているところです。
どの企業もそうだと思いますが、環境が激しく変化し複雑さが増す現在、ヤンマーはグローバルでの顧客価値創造企業を目指しています。人事領域では「マインドセットの変革」「機動的な組織体制の構築」「専門スキル人材の育成、次世代経営人材の選抜・育成」、「グローバル人材情報の一元化・見える化」の4つをキーテーマとして掲げて中期的に改革を進めています。

私のミッションの背景には、人材育成を取り巻く内部環境の課題がありました。過去20年近く体系的な整理がないまま教育・研修が積み上げ式で行われており、必要な育成の仕組みが不足している状況でした。例えば、A社では実施しているがB社では未実施、あるいは重複して実施しているなど、さまざまな課題が存在しています。
人材ポートフォリオを軸に人材育成の新たな挑戦に着手
これらの課題に対し、ヤンマーグループでは①自律的を後押しする仕組み作り、②グループ全体の教育研修体系の再構築、③プロフェッショナル人材の育成強化 の3つのアクションを掲げて取り組みに着手しました。
①は、キャリア形成支援の強化を進め、社員同士が自発的に学び合う場の創出、公募制度の活性化にも取り組んでいます。具体的には、海外や異業種への公募、育成・異動の幅を広げるためのFA制度の導入などを推進しています。②は、「誰もが、どこでも、いつでも最新の教育・研修を受けられる仕組みの構築」です。オンライン学習プラットフォームを導入し、現在その整理を進めている段階です。教育体系については、ほぼ見直しが完了しており、今後はスキルを中心に据えた教育・研修をグループ会社も巻き込みながら展開していく方針です。③は、今回のメインテーマとなるスキルベースの人材育成組織の構築に関する取り組みです。

スキルベースを考える上で、最も重要な要素は「人材ポートフォリオ」です。どのエリアに、どれだけの人材を、どのようなスキルを持って配置するかを、戦略的に設計していくことが基本となります。現在、現状(As-Is)とあるべき姿(To-Be)を分析し、必要なスキルの整備を進めています。財務グループを例にとると、職種(会計、資金管理、財務)別・習熟レベル(スキルレベル)ごとに人材の分布を可視化します。例えば、会計分野では「エキスパート」レベルの方が1名おり、あるべき姿としても1名であれば、十分と判断できます。一方、資金管理の分野では、現状「エキスパート」が1名ですが、あるべき姿としては3名必要と予測される場合、2名分のスキルギャップが発生していることになります。
このギャップを埋める方法としては、例えば「エクスペリエンス」レベルの方を育成してスキルアップを図る方法がありますが、時間がかかる可能性があります。そのため、内部の他部署、例えば財務戦略部門に同等のスキルを持つ方がいれば、そこから配置転換する方法も考えられます。それが難しい場合は、外部から同等のスキルを持つ人材を採用するという選択肢もあります。
このように、スキルをベースにした人員配置を展開していきたいと考えています。さらに、このデータがタレントマネジメントシステムと連動することで、どのエリアにどれだけのスキルを持った社員がいるかを可視化できるようになります。これは非常に重要なリソースになると考えています。
スキルベースで社員の成長を支え、一人ひとりのキャリアを実現する
社員側の視点でも、どのようにキャリアを実現していくか、スキルベースで成長を支える仕組みを描きました。これは私が着任した際に、まさに取り組みたかったことで、試行錯誤しながら描きました。
現在、キャリアモデルの構築に取り組んでおり、これまで年間約100名の社員にインタビューを実施しました。夢や目標を持って入社した社員のキャリア実現を後押しできるよう、目指すポジションに必要なスキルや、実際にそのポジションに就いている人が入社後にどのような経験を積んできたかを示しています。
また、社員は自身の目標に対して現在のスキルを測定し、ギャップを把握することができます。そのギャップを埋める手段として、経験、研修、アドバイス(薫陶)などが組み合わせて、スキルを高めていきます。スキルアップによって目指すポジションへの準備が整ったら、社内公募などを利用して関連するポジションへの異動に挑戦できます。この「目標設定→スキルアップ →挑戦・異動」のサイクルを繰り返すことで、社員の能力とスキルは継続的に向上し、個人のキャリア目標の実現につながります。

これが、社員側の視点から見たスキルベースの考え方です。
スキルベース人材マネジメントを全職種へ展開
- 私たちが「スキルベースの人材マネジメント」と呼んでいる取り組みのコアは、以下の3つのプロセスです。
- 1. スキルを設定・評価
- 2. 教育マップ(スキルレベル別研修体系の可視化)の整備
- 3. 高スキル人材の認定(報酬・役職への反映) ヤンマーでは、技術職で30年以上にわたり運用してきた仕組みをベースに、今回その他の職種へも展開しました。社内ではこの取り組みを「CDP(Career Development Program)」と呼んでいます。
1. スキルを設定・評価
まずは定義されたスキルを個人が自己評価し、上司との面談を通じて中長期的・単年度の目標をそれぞれ設定します。その後、教育マップを参照し、必要な研修を選定して育成計画を立てます。スキルレベルが4以上(社内トップレベル以上)になる場合は、職種ごとに行われる社内のCDP委員会での審議を経て「専門職」として認定されます。このプロセスは、常に最新スキルへのアップデートを目的として継続的に回されます。技術系では、研究開発・品質保証・品種・生産の4つの機能を設定し、それに対して31の職種を定義しています。これらの職種に対して、合計65の専門スキルが設定されています。
一方、管理系・営業サービス系では、16の機能に対して79の職種を設定しています。例えば人事部門では、12の職種があり、人事リーダーシップ(部門長)、人事ジェネラリスト、HRBP、人事業務オペレーション、採用、育成などが含まれます。将来的には、これらの職種において専門家として認定される仕組みを構築していく予定です。各職種に対して設定されたスキルは、例えば人事ジェネラリストであれば17のスキルが求められます。全体では400以上のスキルがあり、これを整備する作業は非常に大変でした。振り返ってみても、最も苦労した部分だったと感じています。
スキルランクは0〜5の6段階で設定しています。ブランクは「育成対象外」、0〜5は育成対象で、4は社内トップレベル、5は社内外の第一人者と定義しています。スキル4以上の専門職に認定された方には、社内で「先生」としてゼミ形式の指導を行っていただくことも検討しています。
また、全職種に共通するスキルとして17項目を設定しました。これはヤンマーの評価項目に紐づけたものや、ハーバード・ビジネス・レビューなどの文献を参考に、今後必要とされる世界共通のビジネススキルを抽出したものです。なお、これらの共通スキルは人材育成を目的としており、専門職の認定には使用していません。
2. 教育マップ(スキルレベル別研修体系の可視化)の整備
教育マップには、スキルとそのランク、対応する研修コンテンツが一覧で表示されており、社員は自分が何を受けるべきかを把握し、必要な研修を選びます。社員は自律的に学習を進めています。将来的にはAIを活用し、「このスキルを高めたいならこの研修」といったレコメンド機能も導入していきたいと考えています。この教育マップの整備は非常に大変で、まだ完成には至っていません。5年〜10年かけて完成させたいという思いで、現在も作り込みを進めています。この取り組みに、部門の協力は不可欠です。人事だけでは専門的な教育内容を把握できないため、各部門の事務局の方々に協力を仰ぎながら進めている状況です。新しい取り組みであり、非常に手間もかかるため、時間をかけて部門側との対話を行いました。直接現場に赴き、熱意を込めて私たちの思いやビジョンを伝え、部門のトップやHRの役員なども巻き込みながら全社的に進めていきました。
3. 高スキル人材の認定(報酬・役職への反映)
専門職としての役割ですが、社内の人事制度から引用しているもので、上から「エグゼクティブ・プリンシパル(技監)」「プリンシパル(主席)」「プロフェッショナル(主幹)」といった職位があります。これまでは技術系のみが認定対象でしたが、今回初めて営業、サービス、そして私たちのような管理系の職種にも専門職としての認定がなされる形になります。この分野へのニーズが非常に高かったため、現在急ピッチで導入を進めているところです。新たな育成体系とスキルベース人材マネジメントのグローバル拡大を目指す
今後の取り組みとしては、来春には国内の全社員に対してスキルを設定する予定です。また、海外拠点においても同様の取り組みを開始しており、最終的には2027年度末までにグローバル展開を完了させ、専門職制度も導入することを目標としています。この3年間で、なんとかこの取り組みを完成させたいと考えています。
私たちが目指すのは「顧客価値創造企業」であり、グローバルでの「エンプロイーサクセス」の実現です。これは私たちの部門名にもなっている重要なテーマです。特に、社員が成長を実感できる育成体系の再構築と、スキルベースの人材マネジメントが鍵になると考えています。現在、チーム一丸となって情熱を持って取り組んでいるところです。まだ走りながらの状態で、つまずいたり失敗することも多々ありますが、他企業の皆様とも情報交換をさせていただきながら、私たち自身も学びを深めていきたいと考えています。

ヤンマーでは、約20年前に採用適性検査を日本エス・エイチ・エル社のアセスメントに切り替えて以来、信頼できるパートナーとして長年活用させていただいております。時代や採用環境が変化する中でも、一貫して“人の可能性を見極める”という原点を大切に、公正で納得感のある選考を支えていただいていることに深く感謝しています。今後も採用・育成の両面で、アセスメントデータを活かした新たな価値創造をご一緒できることを期待しています。

担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
小迫 拓実
チーム一丸となって情熱を持って取り組んでいることをお聞きし、大変感銘を受けました。人事部門から会社を大きくしたいという司尾様の強い想いがメンバーにも伝播し、この人材育成の取り組みに繋がっているのだと感じております。今後は弊社が提供するアセスメントサービスを通じて、ヤンマーホールディングス様の更なる発展に貢献できますと幸いです。