はじめに
多くの日本企業がメンバーシップ型の雇用モデルからジョブ型の雇用モデルへの変革を進めています。新卒一括採用と長期雇用を前提とする年功序列型の人事から職務別採用とキャリア自律を軸とした人事への転換です。しかしながら、環境は我々よりもさらに早く変化しており、世界中が人手不足、急速な技術革新、そして多様性の拡大といった急激な環境変化で今までのやり方の限界を感じています。
こうした状況下、世界ではスキルベース組織への移行を模索する企業が増えてきました。役割や職務を組織の最小単位ととらえ人材を当てはめていくジョブ型の組織では適した人材を採用・任用することが困難になってしまったのです。一つの職務(ジョブ)を構成しているタスク単位に分解し、各タスクを遂行するためのスキルを特定し、各人の保有するスキルにあわせてタスクを集めジョブを再構成する、このスキルベースの考え方に期待が寄せられています。これは採用だけでなく、異動や配置、能力開発やキャリア開発に影響を与える大きな人事戦略の転換です。

スキルベースの採用
スキルベース採用とは、スキル、コンピテンシーおよびこれらのポテンシャルを基準とする採用手法です。スキルには専門技術や知識、資格などのハードスキルだけでなく、問題解決力、柔軟性、コミュニケーション力、推進力といったソフトスキルを含みます。採用ポジションに求められるスキルを定義し、それらのスキルを採用基準とします。スキルベース採用の特徴を明確にするため従来のやり方と比較してみましょう。
日本の新卒採用で一般的な総合職採用(職務を限定しない採用)では、様々な職務や環境に適応するための能力、行動特性、価値観などをコンピテンシーとして定義し、採用基準とします。入社後、職務や職場環境が変わることを前提とするため、具体的なジョブやタスクに直結するスキルよりも抽象的なコンピテンシーのほうが使いやすいのです。
職務別採用が一般的な中途採用では、今までの職務経験と職務成果が最優先され、併せて成果創出に際して発揮したスキルやコンピテンシーが基準となります。職務に求められるスキルを評価する点では、職務別採用とスキルベース採用は共通しています。最大の相違点は職務経験を重視するかどうかです。スキルベース採用では募集職種の職務経験は問われません。求められるスキルがあるかどうかを判断するために職務経験を確認するのであり、全く異なる職務を経験していてもスキルさえ確認できれば問題はないのです。スキルベース採用であれば、ジョブチェンジやキャリアチェンジ、また未経験者の候補者を採用できる可能性があります。
スキルベースの人材モビリティ
人材モビリティとは組織の内外に人を動かすこと。具体的には人事異動、昇進昇格、プロジェクトへの参加、出向などを指します。スキルベースの人材モビリティでは人材のスキルを中心に据え、人と職務のマッチングをはかります。まず社内の人材が保有するスキルとそのレベルを可視化し、その人材のスキルセットを最大限に活かすように職務や役割を再構成するのです。
従来の人事異動は異動先および異動元のニーズと候補者の属性を念頭に置き、人事部門が経験と勘で人材を当てはめるという多分に主観的なものでした。近年は人材データ活用やジョブ型人事の普及により、職務分析により定義されたポスト要件と客観的に収集された本人の人材情報およびキャリア志向を考慮し、客観的な意思決定がなされるようになりました。この変化は人事異動の成功率と従業員満足度の向上に貢献したものの、一つの職務に一人の人を当てはめるという点において何ら変わってはいません。スキルベースの人材配置は次のように行います。
営業部門に「顧客折衝が得意で関係構築に強みを持つAさん」と「データ分析や提案資料の作成に優れたBさん」がいたとします。今までは両者とも営業職として全ての業務を担うことが求められていました。スキルベースの配置では営業の業務を、Aさんのスキル(顧客対応、関係構築)に合ったタスクの集合であるフロント業務とBさんのスキル(提案資料の作成、データ分析)に合ったタスクの集合であるバック業務に再設計し、各人に得意な業務を割り当てます。これにより、Aさんは顧客との信頼関係を深めることに集中でき、Bさんは分析力を活かして営業部門全体の提案の質を高めることができるようになります。
このようにスキルを基準として人に職務を合わせる発想へと転換することで、社員は自らの強みを発揮しやすくなり、組織全体としても生産性とエンゲージメントを高めることが可能となります。また、現在の職務に対応できる人材が社内にいない場合であっても、複数の人の持つスキルを組み合わせることで職務遂行が可能となり、さらにはAIの活用などにより職務に求められるスキルが変化しても、今いる社員のスキルに最適化した職務を設計することが可能です。
スキルベースの人材モビリティは、単なる異動の効率化ではなく、人材の可能性を最大化し、組織の柔軟性と競争力を高めるための新しい配置戦略です。

個人のスキルを把握する3つの方法
個人のスキルを正しく把握するためには、複数のアプローチを組み合わせることが重要です。代表的な方法は以下の3つです。
- 推定(Inferred)
- 履歴書や職務経歴、学歴、資格などの情報からスキルを推定する方法です。例えば、システムエンジニアとして5年間の職務経験があれば、一定のプログラミングスキルを持っているであろうと推定できます。この方法のメリットは、一般的な情報を活用でき簡便であること。デメリットはあくまでも推定のため実際のスキルレベルを正確にとらえられないことです。近年はAIを活用してスキル推定を行うケースも出てきたようです。
- アセスメント(Assessed)
- テストやシミュレーション、ケーススタディなどのアセスメントを通じて、スキルを客観的に測定する方法です。認知能力テスト、状況判断テスト、コーディングテストなどが用いられます。科学的に裏付けられた手法で客観的なデータの取得が可能ですが、導入コストや受検者の負担を考慮する必要があります。
- 自己申告(Self-Report)
- 本人が保有するスキルとそのレベルを申告する方法です。タレントデータプラットフォームなどへの簡便な入力で迅速にデータを収集できますが、評価の信頼性については慎重な検討が必要です。
パワースキルの重要性
スキルベースの議論において注目されるのがパワースキル(Power Skills)です。パワースキルは、ジョシュ・バーシン氏が人事分野のリーダーに対して行ったグローバルな調査によって得られたスキルフレームワークです。未来のスキルは技術的なものではなく、行動的なものであることを示しています。AI時代においてソフトスキルとしてパワースキルの重要性は今後さらに高まっていきます。

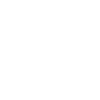
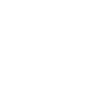
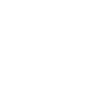

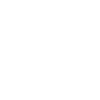
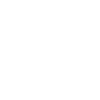


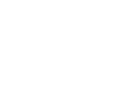


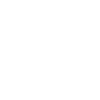

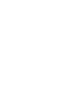
スキルベースの導入
スキルベースもタレントマネジメント施策の一つです。あらゆるタレントマネジメント施策を進めるうえで共通に行わなければならないのは、経営事業戦略と組織人事戦略の明確化です。次に組織人事戦略に立脚するスキルベースの導入によって何を成し遂げたいのか、どのような問題を解決したいのか、目的の明確化です。
ここからはスキルベース特有の取り組みとなります。まずは、職務側のスキル定義です。自社の職務に求められるスキルを自社独自に定義していくことは極めて困難であり、一般的なスキルフレームワークを活用することが現実的です。厚生労働省が運営する「就職情報提供サイトjob tag」は職務のタスクとスキルの整理に活用できます。
次は社員側のスキル評価です。既に述べた通り、自己申告の導入、職務経歴等の収集、アセスメント導入により客観的なスキル評価の仕組みを整えることが重要です。
まとめ
スキルベースの採用と人材モビリティについて述べました。世界的に注目されているスキルベースですが、AIによる環境変化や人材不足の対策としてスキルベースを導入する日本企業はいまだ少なく、能力開発やキャリア自律支援を進める枠組みとしてスキルを活用する企業が徐々に増えてきたと感じます。今後、スキルベースは日本の労働力不足を軽減し、生産性を高める手法として日本で定着していくでしょう。
参考
eBook How to Build a Skills-Based Organization
White Paper Discover the Skills of the Future and Where to Find Them

このコラムの担当者
清田 茂
執行役員
入社以来30年、HRコンサルタントとして日本の人事アセスメント界を牽引。大手を中心にコンピテンシーモデリングから選抜設計、サクセッションプラン構築まで広範なプロジェクトを完遂。特に経営層との対話を通じた次世代リーダー育成に高い実績を持つ。 2002年取締役、2020年より執行役員として直販部門を統括。最前線で「人と仕事と組織の最適化」を追求する傍ら、SHLグループのグローバル知見の国内導入も推進。




















