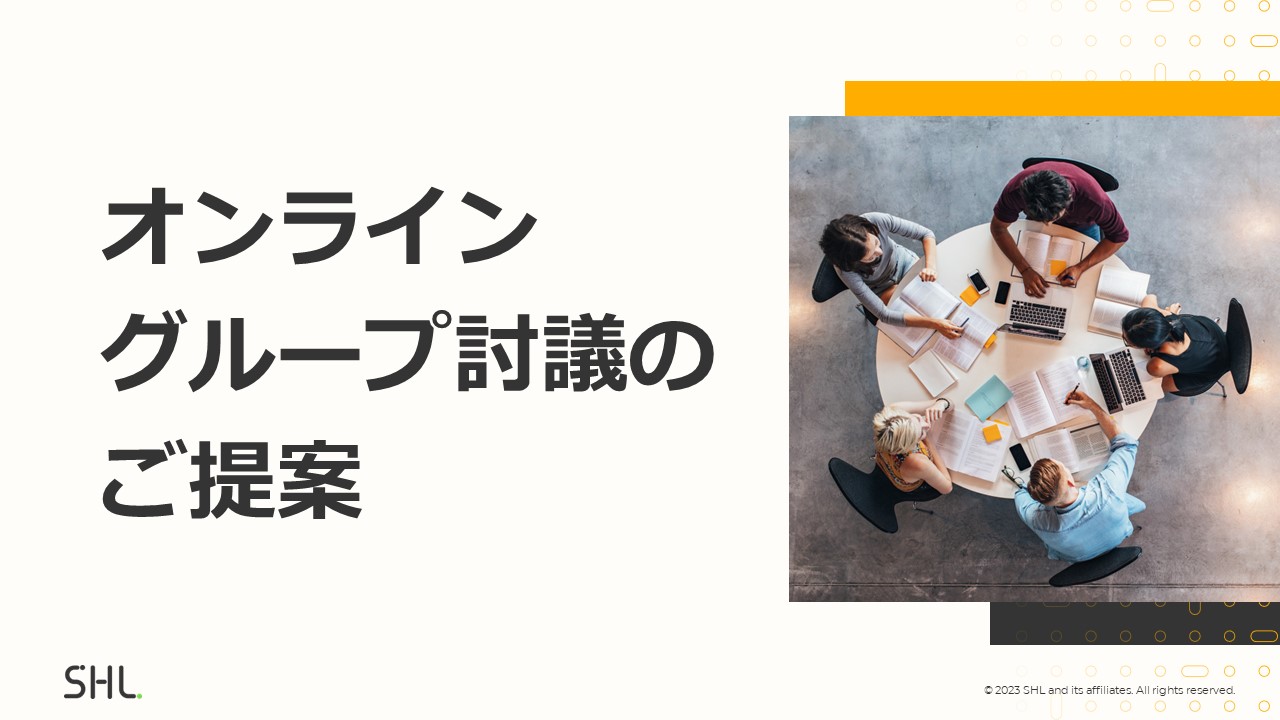更新日:2021/06/25
目次をみる 目次を閉じる
シミュレーション演習では、まず参加者に場面設定や課題に関する資料が配布され、参加者はそれらを読み込んだ上で、参加者同士、または評価者(アセッサー)との議論や質疑応答に臨みます。オンラインで実施する場合、参加者は従来「紙」で配布されていた資料をPCやタブレットといった「デジタル端末」で読み込むことになります。これが対面とオンラインとの主要な違いのひとつです。では「紙」と「デジタル端末」で内容の理解度にどのような差が生まれるのでしょうか。

紙とモニターの視認性の違い
ノルウェーのStavanger大学の研究者Mangen氏が15~16歳72人に行った実験では、液晶モニターで文章を読んだ人は「紙」で読んだ人に比べて、その後の読解力テスト(被験者は、適宜文章を見返しながら制限時間内に解答する)の点数が低くなる傾向が見られました(Mangen et al. 2013)。我々は「紙」で文章を読むとき、無意識に残りのページの厚さを指で確認したり紙面を俯瞰したりして、「どの辺りにあったか」という情報も一緒に記憶しています。この触覚的・空間的記憶が「前半のほうに出てきた話だ」「びっしりと字が書かれていたページにあった気がする」と後から内容を思い出したり探し出したりする際の手がかりとして役立ちます。しかし、モニターで文章を読んだ被験者はこの手がかりを得ることができず、内容の想起や検索に時間がかかったため、点数が低くなったと考えられます。他の研究でも同じような傾向が見られており、モニターの場合は「情報全体に素早くアクセスしにくい(ページを瞬時に行ったり来たりして確認することが難しい)」「画面を拡大・縮小したりスクロールしたりすることで文章が ”移動” し、位置関係を記憶しにくい」「モニターの発光によって視覚疲労が起こる」など、紙と比べて「情報の認知や理解を妨げる要素」が多いという可能性が指摘されています。これらの事例を踏まえると、紙で配布していた演習資料を単にデータ化してオンラインで提示するだけでは、紙と同じレベルで内容を理解することは難しく、また、閲覧するデジタル端末の画面サイズによっても視認性に差が生まれるため、オンラインで実施する場合には運用方法や資料の内容を再検討する必要があります。
オンラインで演習資料を提示する際の工夫
<方法①:演習資料を事前に配布する>「そもそも、資料をオンラインで提示しない」という方法です。あらかじめ資料を候補者にデータで送付し、印刷しておくように伝えることで、従来と同じ閲覧環境を作ることができます。しかし、候補者が事前に資料を読み込んで準備をしたり、資料が第三者に流出したりする可能性があるため、「事前に資料を読み込むことを前提として演習を設計する」「外部流出しても差し支えない情報のみ資料に盛り込む」といった対応が必要になります。
<方法②:オンライン上での閲覧環境を統一する>
例えば、PCとスマートフォンでは画面サイズや操作性が異なるため、演習当日、資料の内容を理解する速さや精度に差が生まれる可能性があります。そのため、「演習には(デジタル端末の中では最も画面サイズが大きく、視認性に優れているであろう)PCで参加するように」とあらかじめ候補者に伝え、閲覧環境を極力統一しておく必要があります。また、従来よりも読み込み時間や演習時間を長く取るべきかどうか、事前に検証する必要もあるでしょう。なお、この方法はPCを持っていない、または(多くのシミュレーション演習では発言・発表を求められるため)人の出入りが無い静かな場所にPCを持ち出せない候補者がいた場合、参加機会や応募意欲が損なわれる可能性があります。
<方法③:資料を必要最小限に絞る>
スマートフォンは持ち運びが容易で、「PCは用意できないがスマートフォンなら持っている」という候補者は多いため、小さな画面でも容易に読める程度に資料の分量を減らす、というのも有効な方法です(当社が今春開発した新卒採用向けオンライングループディスカッションも、この方法を採用しています)。この方法であれば、より多くの候補者に参加機会を提供することができ、資料の視認性の違いによる不公平も無くすことができます。ただし、資料を減らすことで参加者の分析的な能力を評価することは難しくなるため、この能力を重視する場合は、必要に応じて知的能力テストなどを実施して評価を補完する必要があります。
シミュレーション演習は「できるかどうか、実際にやってもらう」という「行動」を評価できる点で、妥当性の高い評価手法です。しかし、これまで紙で配布していた演習資料をそのままデータ化するだけでは、従来と同じような品質は確保できません。オンライン固有のリスクや特徴を踏まえた上で、運用方法を変更したり演習を再設計したりする必要があります。

このコラムの担当者
清野 剛史
アセッサーグループ 課長
HR業界で20年のキャリアを持ち、1,000社以上の採用改革やタレントマネジメントを支援。現在はアセスメント専門部署の課長として、面接やグループ討議等のヒューマンアセスメント技術の体系化とアセッサー・講師育成を統括する。科学的根拠に基づいた多角評価技術の普及を牽引し、2023年には産業・組織心理学会で「効果的な能力開発面談」に関する論文を発表。国家資格キャリアコンサルタント。