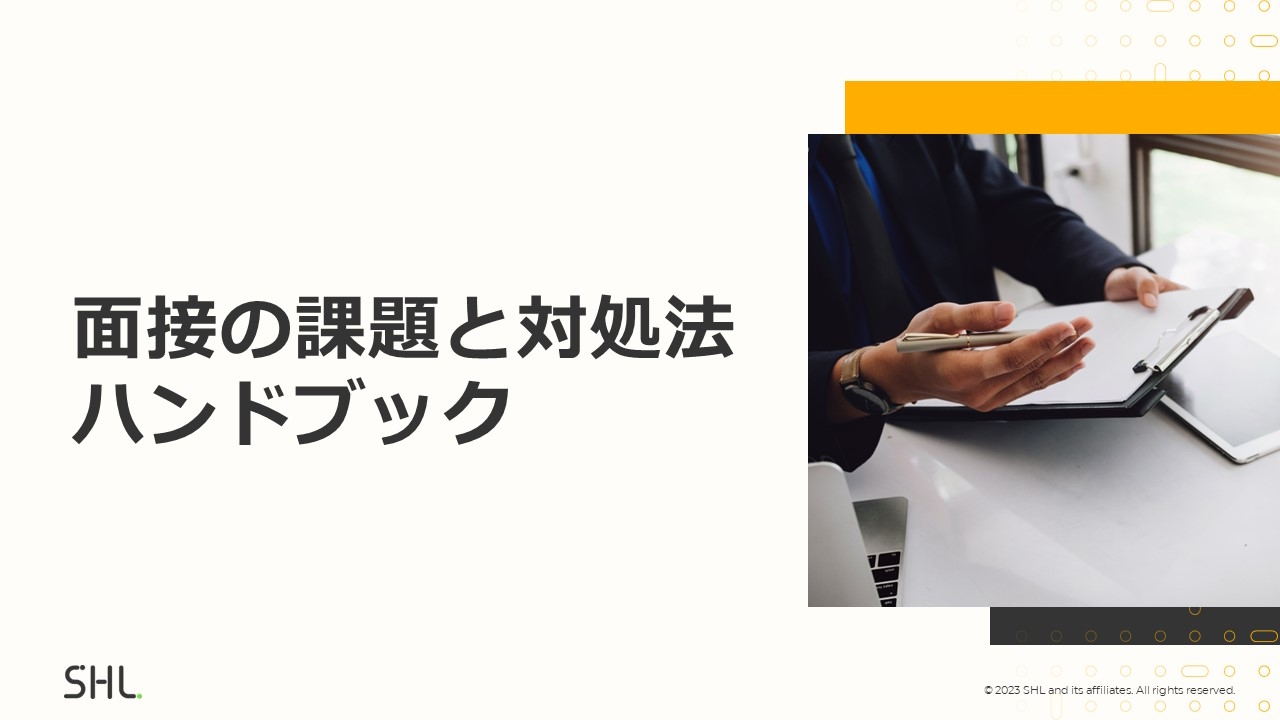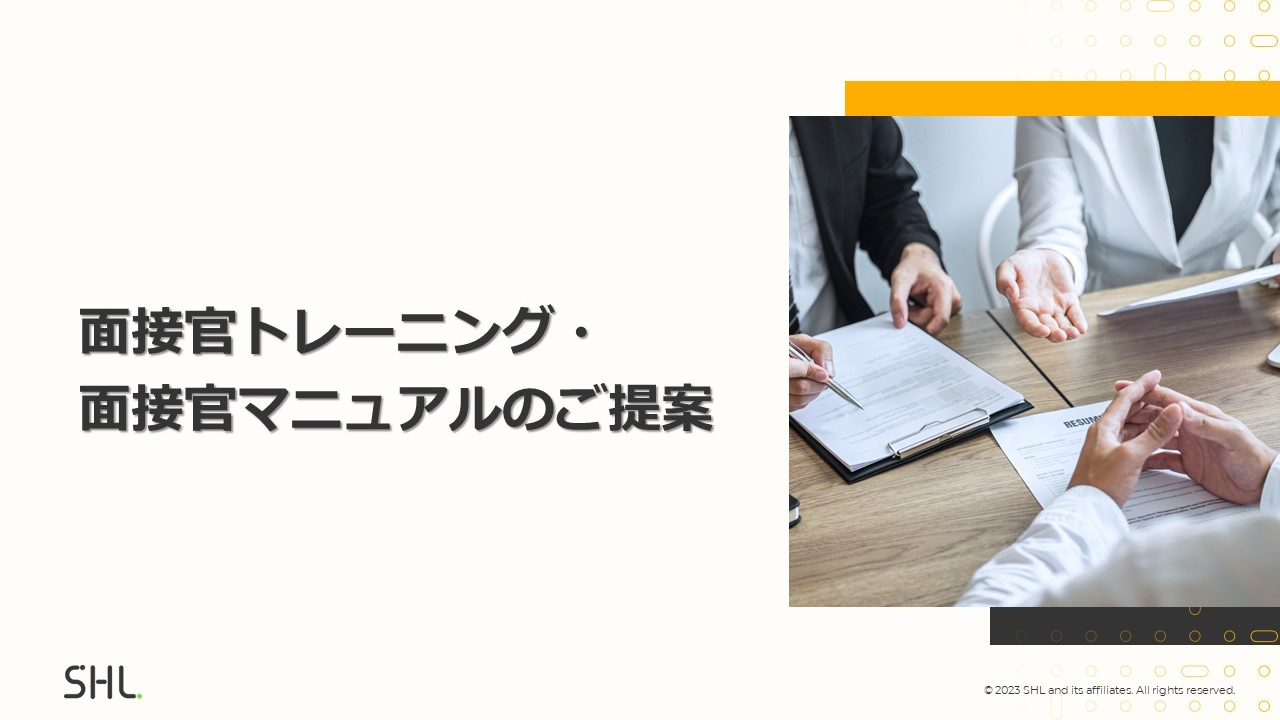面接は採用選考において最も一般的な評価手法です。採用面接は、面接官に質問内容や評価基準を委ねて候補者と自由に対話する「非構造化面接」と、あらかじめ決められた質問内容や評価基準、面接の手順に沿って構造的に対話と評価を行う「構造化面接」に大きく分かれます。一般的に構造化面接のほうが妥当性(面接時の評価と将来の職務業績との関連性)が高いため、構造化面接、その中でも特に「コンピテンシー面接」が多くの企業で実施されています。
コンピテンシーとは、職務で成果を上げるために必要な行動特性を指します。営業職なら高い売上予算を達成するための「ヴァイタリティ」、研究職であれば、事象や問題を構造的に分析して論理的な結論を導く「問題解決力」などが該当します。コンピテンシー面接とは、確認するコンピテンシー、質問、判別指標をあらかじめ決めておき、それらに沿って評価を行う面接手法です。しかし、コンピテンシーによっては面接で評価しにくいものもあるため、別の選考手法で補完、または代替したほうが望ましい場合もあります。
そこで本コラムでは、当社が定義する「様々な職務の遂行において一般的に必要とされる9つのコンピテンシー」を例にとり、面接での評価のしやすさ・しにくさを紹介します。
目次をみる 目次を閉じる
評価しやすいコンピテンシー
- ヴァイタリティ(困難な目標をやり遂げるのに必要な体力・気力がある)
- 人あたり(人に対してよい印象を与え、思いやりと節度を持った態度がとれる)
- チームワーク(チーム全体の目標に向かって、協力・協調ができる)
- 状況適応力(状況に合わせて行動する。自分の行動を客観的に眺められる)
面接で評価しやすいコンピテンシーは以下の4項目です。
「人あたり」と「チームワーク」はいずれもメンバーの一員としてチームに貢献した経験を詳しく掘り下げることで確認していきます。「人あたり」は相手を思いやる行動を指し、話し方や言葉の使い方から評価します。「チームワーク」は自分よりチームの成功を優先し、メンバーと協調して課題解決にあたる行動を指し、他者と協力して何かを成し遂げた経験から評価します。どちらも面接で評価しやすいコンピテンシーですが、グループ討議などのグループ型演習を実施すると、より明確に評価することができます。
「状況適応力」は相手や状況に応じて、自分の考えや行動を柔軟に変化させることができるかを示すコンピテンシーです。これまで経験した最も大きな変化や、海外生活や留学など今までと全く違う環境に身を置いた経験などを尋ね、その時の対応を詳しく確認していきます。面接以外の手法では、その場で候補者に特定の役割や設定を与えて課題に取り組んでもらうシミュレーション演習によっても評価することができます。

評価できるが注意が必要なコンピテンシー
- 創造的思考力(斬新で創造力豊かなアイデアを思いつく)
- 問題解決力(問題を構造的に捉え、合理的な手順で適切な推論を行う)
- プレッシャーへの耐力(緊張の強い場面でも冷静で、自分を見失わない)
- 統率力(周囲の動きに注意を払い、先頭に立ってチームをまとめる)
面接で評価できるが注意が必要なコンピテンシーは以下の4項目です。
「問題解決力」は様々な観点から情報を収集し、問題を分析して適切な結論を導くためのコンピテンシーです。過去の実績以外に話し方からもある程度評価できますが、中程度以上のレベルの候補者は「中程度」か「高い」かの判別が難しいので評価者間のばらつきが大きくなります。また、事前に想定問答で練習してから面接に臨んでいる候補者の場合、受け答えがスムーズで納得感のある回答が多くなるため、候補者本来の問題解決力を評価しにくくなります。そのため、知的能力テストや、多くの資料を読み込んだ上で課題に対する結論や理由を記述、あるいは発表させるイントレイ演習やプレゼンテーション演習といった選考手法も実施できると、より評価精度を高めることができます。
「プレッシャーへの耐力」はプレッシャーを過度に強く受け止めず、冷静に対処するためのコンピテンシーです。強いプレッシャーがかかった経験を尋ねてその時の対応を詳しく確認する、あるいは意表をついた質問を投げかけて想定外の場面での行動を観察するなどして確認していきます。ただ、面接では「プレッシャーへの耐力」が低い人は分かるものの、高い(強い)人の見極めは困難です。過去の経験の確認では、当時をある程度冷静に振り返れるようになっていることと、意表を突いた質問1つ2つの反応を見るだけでは「高い(強い)」とまで判断することは難しいためです。そのため、たとえば候補者の質問に対して面接官が様々な反応を示す「逆面接」演習のように、先の展開が予想しにくく、その場で相手との当意即妙なやり取りが一定時間求められる演習のほうが適しています。
「統率力」はリーダーシップに関わる項目であり面接で評価できますが、学生を対象とする新卒採用の場合は注意が必要なコンピテンシーです。企業における「統率力」とは、様々な年齢、立場、価値観の人々をまとめることを指しますが、学生からはゼミやサークルなど「自分自身に近い存在の集団」をまとめたエピソードが挙がりやすく、その中で発揮した「統率力」が社内でも発揮できるとは限りません。そのため、できるだけ幅広い年齢、経験、考え、文化を持った人たちをまとめた経験を確認してください。

評価しにくいコンピテンシー
- オーガナイズ能力(緻密で慎重で計画的である)です。
面接で評価しにくいコンピテンシーは以下の通りです。
ここまで、面接で評価しやすい・しにくいコンピテンシーについて紹介してきました。面接は、質問の仕方や内容を変えることで候補者の様々な能力を評価できる汎用性の高い選考手法です。また、よく構造化された面接は高い妥当性を持つことが研究でも明らかになっています(Smith & Robertson, 2001)。しかし、面接は万能ではありません。面接選考の特徴や限界を理解した上で、場合によっては別の選考手法に切り替えることで、より適切に候補者を評価することができるようになるでしょう。


このコラムの担当者
清野 剛史
アセッサーグループ 課長
HR業界で20年のキャリアを持ち、1,000社以上の採用改革やタレントマネジメントを支援。現在はアセスメント専門部署の課長として、面接やグループ討議等のヒューマンアセスメント技術の体系化とアセッサー・講師育成を統括する。科学的根拠に基づいた多角評価技術の普及を牽引し、2023年には産業・組織心理学会で「効果的な能力開発面談」に関する論文を発表。国家資格キャリアコンサルタント。