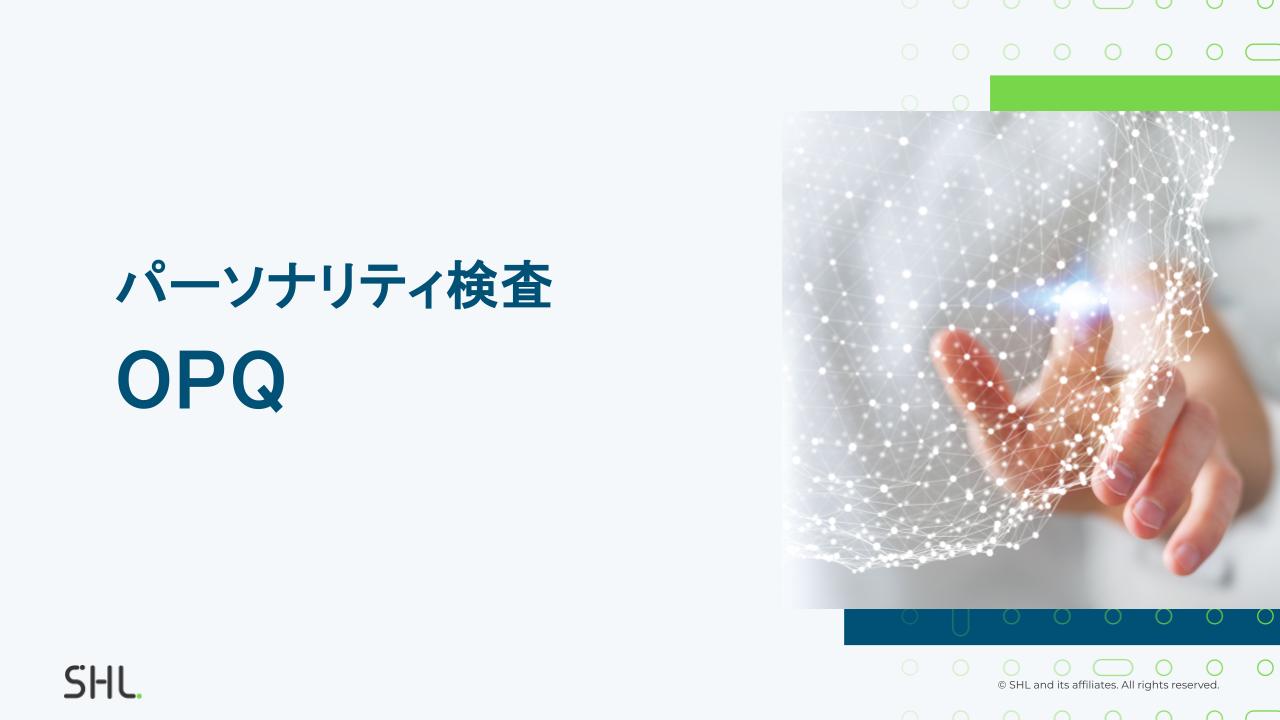クライアント からよくいただく質問の一つに以下のようなものがあります。
「OPQの受検結果は変化するのか」。または、「同じ人が数年後にOPQを受検したら、その結果はどのように変化するのか」。
この質問へ端的に回答すると、【変わるものもあれば変わらないものもある】です。
目次をみる 目次を閉じる
パーソナリティは変わるのか
パーソナリティは「ある程度変化することがあるが、ある永続的な特徴は安定している」とされています。故に、当社のパーソナリティ検査「OPQ」の結果も、変化する側面がある一方で比較的安定性を持っています。OPQは、一度受検した結果は12ヶ月から18ヶ月は有効です。
ただし、受検者本人を取り巻く環境が大きく変化した場合は、その期間内であってもOPQの結果は変化すると考えられます。「大きな環境の変化」には、異動や昇進、業務内容の変化等が挙げられます。
OPQはあくまで「自己認識」の結果です。異動や昇進によって業務内容が変わり、求められる能力や行動が変化したことによって、自身の自己認識に変化が起こると、その変化は受検結果にも表れます。

パーソナリティはどう変わるか
例えば、今まで営業部門にいた人が経理部門に異動になったとします。営業部門では必要だった「大胆さ」や「勢い」は求められなくなり、それまで気にしていなかった「緻密さ」や「正確さ」が求められるようになりました。すると、関連するOPQ30因子の「決断力」・「行動力」、また「計画性」「緻密」の得点に変化が出てくることがあります。異動後に求められる行動に関連する得点が高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。
理由は、OPQがあくまでも「自己認識による自己理解像」だからです。周りの人が「計画性」「緻密」に関して優秀で、自分は「緻密さ」や「正確さ」が低いと痛感すると、実際の出来に関わらず、それらの得点は低く出ます。業務内容が変わってもその変化に関連しないパーソナリティは、自己認識に変化が起こらず受検結果に変化は生じにくいと考えられます。つまり、大きく環境が変化したとしても、全ての因子が大きく変化して別人のような受検結果になるということは考えにくく、特定の因子は変化したが、その他ほとんどの因子は変化していないという結果になることが大半であると考えられます。
従って、冒頭の「OPQの受検結果は変化しますか?」という質問には、【変わるものもあれば変わらないものもある】という回答になります。

採用時にパーソナリティを測定する意味
大きな環境の変化でパーソナリティが変化するのであれば、「学生」から「社会人」はとても大きな環境の変化といえます。採用時のパーソナリティ受検結果が入社後に変化しうるのであれば、新卒採用時にパーソナリティを測定する意味はあるのか?
答えは、【あります】。
パーソナリティは仕事の成否に大きく影響を与えることが過去の様々な研究から明らかにされています。そのため、新卒・中途関わらず採用時にパーソナリティを見極める(測定する)ことは合理性があると言えます。
その上で、パーソナリティ検査を採用時に行う一番の目的は「効率化」です。パーソナリティを測定する手法は質問紙法の他に面接やシミュレーション演習(グループ討議など)等多々ありますが、それらは質問紙法に比べて時間とコストがかかるというデメリットがあります。
採用時のパーソナリティ検査で明らかに不向きな人をスクリーニングして、面接やシミュレーション演習に呼び込む人を絞り込む。面接では事前に受検者の特徴を大まかに把握して効率的に情報収集(入社後懸念点になりそうなことについての質問)を行うなど、パーソナリティ検査結果を活用することで、短期間に効率的かつ合理的な人材選抜を行うことができます。(パーソナリティ検査の活用方法については、過去のコラムも参照してください。)
スクリーニングされた人の中には、入社後にパーソナリティが変化して活躍できた人が含まれていたかもしれません。しかし、前述の通りパーソナリティはある程度安定しています。「効率化」を考えると、入社後の変化を期待して現状不向きな人を採用するよりも、現時点で向いている人を採用する方が、入社後の不適応などに繋がりにくくなります。
パーソナリティは環境の影響を受けて変化をすることは事実ですが、ある程度安定していることも事実です。そのため、採用時のパーソナリティから入社後の活躍を予測することは合理的であると言えるでしょう。

このコラムの担当者
柳島 真理子
テスト開発・分析センター
2010年入社。5年間のHRコンサルタント経験を経て、現在はテスト開発・分析部門にて10年以上にわたりアセスメントの品質管理と新商品開発に従事。コンサルタント時代の採用・育成支援で培った知見を活かし、のべ300社以上のデータ分析支援実績を持つ。営業職の要件定義やストレス要因予測、モチベーションの性差に関する論文を発表。現場感覚を活かしつつ、R&D部門の技術的知見から顧客の組織課題解決に貢献している。