ICT人材を増やしていきたく、新卒や中途でその点に注力しています。しかし既存の社員に学ばせICT人材化をすすめるのには時間的にも本人の意欲的にも苦戦しています。何か良い方法はあるのでしょうか。
ICT人材という定義が曖昧でよく分かりませんが現代的なシステムエンジニアです。
クラウドサービス、ビッグデータ、AI、データベース、通信、組み込み、ネットワークと範囲は多岐にわたり全網羅的なエンジニアを採用するのも育成するのも非常に困難です。
COBOLで巨大な銀行の業務システムを組んでいた人がたかだか4bitCPUの単純制御すらできなかった、毎月数百億円扱うシステムのセキュリティが穴だらけだったなど自分も見たことがあります。
これはエンジニアが一つのカテゴリーに見えても実際は得手不得手が多くあるため本来専門家として複数の専門職として採用しなくてはならないのにまとめて採用してその後どうにかなると勘違いしているから起こる問題です(専門性を見極めて採用している企業は今伸びている企業です)。
自分の考えるシステムエンジニアには大きく4つのカテゴリーがあると考えます。
- 全体の知識の幅が広く浅い技術は持っており、計画性、柔軟性、コミュニケーション能力すべてを持っているプロジェクトマネージャタイプ。
- データベースやサーバ設定、アプリケーションプログラミング、Webサービスなどこなすソフトウェア専門タイプ。
- ネットワーク、組み込み、センサー、制御などハードウェアに近いところに力を発揮するハードウェアよりのタイプ。
- 実際に何も構築できないがEUCの促進や研修、サポートや営業に特化した対人専門のタイプ。
これら4カテゴリーをさらに専門性を分けていくのが理想的だと思います。
カテゴリー内であれば育成や人の異動は可能です。カテゴリーを外れる場合、適性が無いと難しい場合があるので慎重に見極め無ければ成りません。
また社会のニーズに合わせて専門性の高い人ほど採用コストは跳ね上がります。総合職の給与テーブルで高度なITエンジニアを雇うことは今後できないと考えてください。
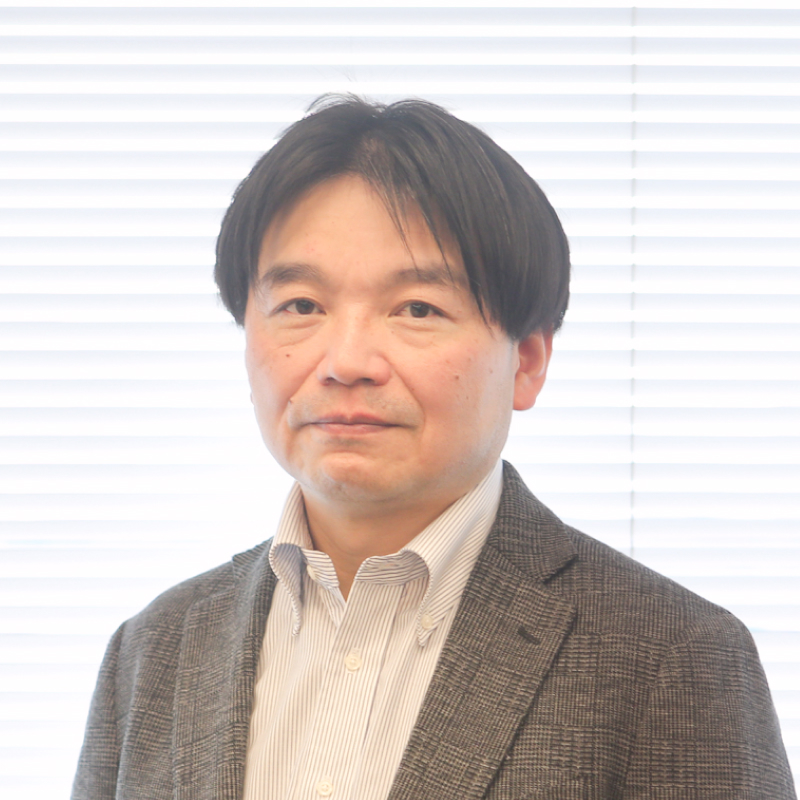
このコラムの担当者
三條 正樹
取締役



