マネジメント層への処遇の見直しが進むと思いますか?個人的には見直しが進まないと、誰もやりたがらないと思ってしまうのですが。
処遇に対してはなんとも言えませんが、ジョブ型やテレワークが進むと中間のマネジメントの負担は減ります。
Google社が大半の中間管理職を廃しているのも成果に対する会社と個人の契約であり、中間層はここのマネジメントをする必要がなくなるためです(むしろ意思決定のマイナスに働くという考えの方が主流)。
ではどこの層に負担がかかるかと言えば、日本で言えばかなり上位のマネジメント層になります。
かれらは個人との契約を予算の範疇行い、常に優れた人間のリクルーティングに力を注ぎ、文化や宗教上の理由などから来るような組織の衝突を押さえ組織のパフォーマンスを支えて成果をださなくてはなりません。
日本ももしジョブ型やテレワークが主流になれば中間層管理職は不要となるでしょう。そんな人間が何百人居ても企業にとっては負債であり、優秀な個人に対して高い報酬を与える制度に変わるからです。現状の体制のままジョブ型に移行しても役に立たない中間層が溢れ失敗に終わると思います。
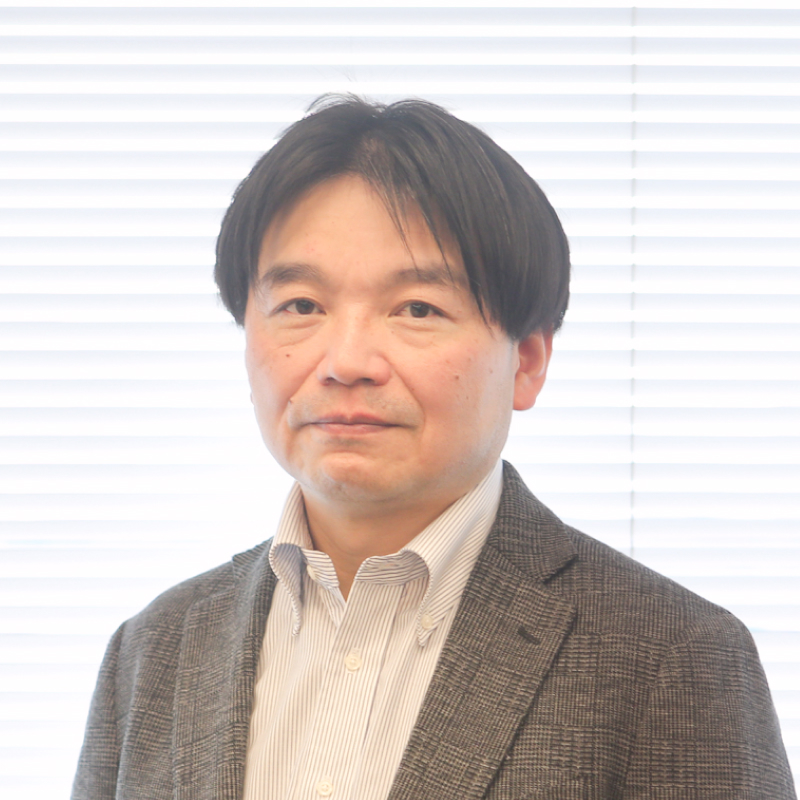
このコラムの担当者
三條 正樹
取締役
前の記事へ
採用選考を完全にオンライン化したため、1度も来社せず入社する人が出てきました。オンラインでは相互理解に限界があり、イメージと違う、馴染めないなどの理由で早期離職が増えないか心配しています。入社後のギャップを埋めるために何に気を付ければ良いでしょうか。
2020/11/27
次の記事へ
人員配置の適材適所というのはよく分かるのですが、適性が偏っており適性通りに配置するとどうしても手薄なところと余ってしまうところに分かれます(新規開拓営業8 ルートセールスに2の割合にしたいのに適性はその逆)。
世の中には何でもできる人いればほとんど何もできない人もおり現実は悩ましいです。上手な適材適所の配属をするための指針があれば教えてください。
2020/12/01



