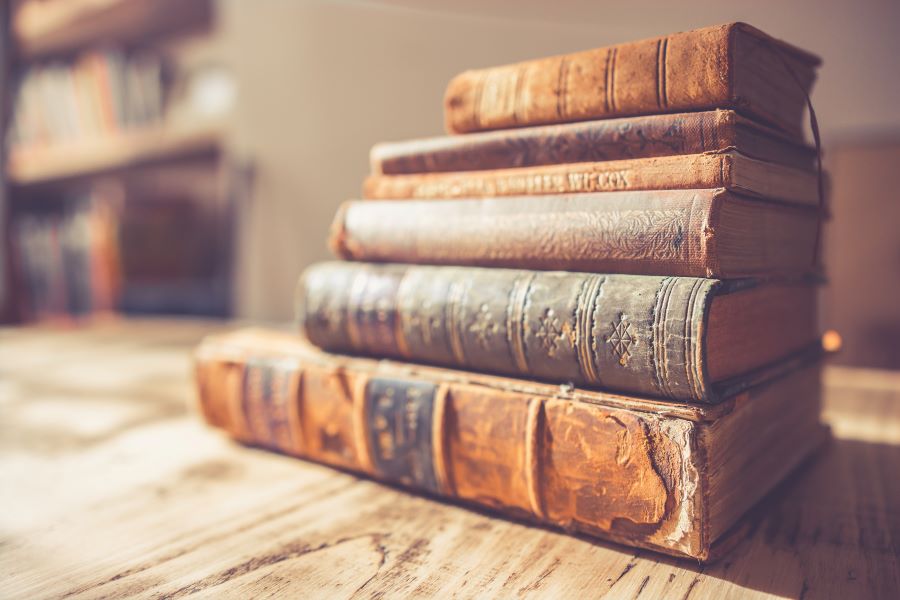「あなたは○○タイプです」
もしこのように言われたら、あなたは納得するでしょうか?それとも違和感を覚えるでしょうか?
パーソナリティ検査(あるいは日常でよく目にするような「性格診断」)の結果として、「あなたは外交型です」「慎重タイプです」というように、タイプに分けて示されることがよくあります。このように、パーソナリティのいくつかの典型(タイプ)を設定し、どれに近いかによって分類する考え方を、性格類型論(以下、類型論)と呼びます。
一方で、パーソナリティをいくつかの構成要素(因子)に分け、それぞれをどの程度持っているかによって捉えようとする考え方を性格特性論(以下、特性論)と呼びます。当社のパーソナリティ検査OPQは特性論に基づいています。

パーソナリティとは
「人格(パーソナリティ;personality)」とは、人の行動や思考における個人差を説明する概念です。語源は「仮面(ペルソナ;persona)」に由来し、状況によって人はいろいろな振る舞いをするという意味が内包されているとも考えられます。状況によって行動が変化するならば、本当の「パーソナリティ」とは何なのか?という疑問が浮かぶかもしれません。しかし、行動には状況や時間を越えて、ある程度の一貫性があることもまた、数々の研究によって示唆されています。
当社では、パーソナリティを「ある人の典型的なまたは好む行動のスタイル」と定義しています。この定義は、行動が環境や状況によって左右される一方で、個人の違いを決める比較的安定した特徴に重きを置いています。つまり、行動は状況によって変化するものの、人それぞれに比較的安定した傾向があるという見方です。
パーソナリティ理論の歴史
パーソナリティ理論がどのように発展してきたのか、その歴史をたどってみましょう。
類型論
- 人の性格の違いに対する関心は、心理学という学問が生まれるよりもはるか昔から存在していました。その起源をたどると、古代ギリシャ・ローマ時代にまでさかのぼります。紀元前4世紀頃、古代ギリシャの医学者ヒポクラテスは、人間の体には血液・黒胆汁・黄胆汁・粘液という4種類の体液があると考えました。そして後に古代ローマ時代の医師ガレノスは、これらの体液のバランスによって人の気質が決まるとし、4つの性格タイプに分類しました。これを体液説と言います。
- 多血質(陽気で活動的)
- 黒胆汁質(憂鬱で内省的)
- 胆汁質(短気で情熱的)
- 粘液質(穏やかで冷静)
その後、20世紀前半に、ヨーロッパを中心に類型論はさらに発展しました。体型と気質の関係に着目したドイツの精神科医クレッチマーは、やせ型・肥満型・筋肉質といった身体的特徴と、分裂気質や躁うつ気質などの性格傾向とを対応させる理論を提唱しました。また、アメリカのシェルドンもこれに似た枠組みで、体格と気質の関係を探ろうとしました。これらは、性格を生物学的・体質的な特徴から分類しようとする立場と言えます。
一方で、心理的側面に注目した理論も登場します。スイスの心理学者ユングは「内向型/外向型」といった概念を提唱し、人の性格傾向を大きな二分軸で捉えました。後に、親子であるブリッグスとマイヤーズがこの理論を基に発展させたのがMBTI(Myers-Briggs Type Indicator)であり、現在でもビジネスや自己理解の場面で広く使われています。
類型論には、「シンプルでわかりやすい」「診断結果がキャッチー」「対話のきっかけになる」といった利点があります。実際に、採用や配属の場面でも「このタイプは営業向き」「あのタイプは慎重だから事務向き」といった語られ方を耳にすることがあります。しかし、人をいくつかのタイプに断定的に分けることには限界もあります。たとえば、「○○タイプ」と診断された人でも、場面によって、別の一面を見せることはごく自然で普通のことです。また、中間的な特徴を持っている、複数のタイプに該当する、あるいはどれにも該当しない、という場合もあります。
特性論
- 特性論は1930年代後半、心理学者オールポートによって体系化が進みました。オールポートは、性格に関する語彙の大規模な整理を通じて、性格特性は共通特性と個人特性の両面を持つことを示しました。これを受けたキャッテルは、因子分析を活用して性格の根源的な構成要素を抽出し、16の主要因子からなるモデルを構築しました。さらにアイゼンクは、性格を外向性・神経症傾向・精神病傾向の3次元で捉える理論を打ち立て、性格研究に実験的・統計的な基盤を築きました。
- 神経症傾向(Neuroticism)
- 外向性(Extraversion)
- 開放性(Openness to Experience)
- 調和性(Agreeableness)
- 誠実性(Conscientiousness)
このように、統計的な手法(とくに因子分析)を導入して、人の性格傾向を測定可能な構成要素として捉える研究が進み、現在では「ビッグファイブ理論(Big Five personality traits)」が心理学のスタンダードとなっています。ビッグファイブでは、以下の5つの主要特性に基づいて個人の性格傾向を把握します。

タイプで区切らず、特性で読み解く人材理解
当社のパーソナリティ検査は、特性論に基づいています。
「◯◯タイプだから営業向き」「このタイプはマネジメント不向き」など、タイプ分けによる早合点や断定が先行してしまうと、その人の可能性を狭めるリスクがあります。しかし、特性論ベースの検査は、あくまで「その人の傾向を知り、柔軟に対応する」ための材料として活用することが可能です。たとえば、個人の人物像把握(面接での人物イメージ形成など)に活用可能です。
性格や能力は、「測る」ことだけが目的ではありません。測った後にどう「理解」し、どう「活用」するかが重要です。
特性論に基づいた検査では、
- 「この人はどんな傾向を持っているのか」
- 「どんな場面で強みになり、逆にどんなときに弱みに転じる可能性があるのか」
- 参考文献
- 神村栄一(1999). パーソナリティ 中島義明・安藤清志・子安増生・坂野雄二・繁枡算男・立花政夫・箱田裕司(編) 心理学辞典 (pp. 686-687) 有斐閣
- 杉若弘子(1999). 性格特性論 性格類型論 中島義明・安藤清志・子安増生・坂野雄二・繁枡算男・立花政夫・箱田裕司(編) 心理学辞典 (pp.480-481) 有斐閣
- 詫摩武俊(1973). 性格・知能心理学 東洋・大山正・詫摩武俊・藤永保(編)(1973). 心理学用語の基礎知識 (p.170-214) 有斐閣

このコラムの担当者
中川 優奈
テスト開発・分析センターグループ