公開日:2010/08/24
このコーナーは、イギリスのSHLグループがお客様に向けて発信している様々な情報を日本語に翻訳してご紹介するものです。主にグループのネット配信「SHL Newsletter」や広報誌「Newsline」、HPから記事をピックアップしています。海外の人事の現場でどんなことが話題になっているのか、人材マネジメントに関して海外企業はどんな取り組みをしているのかをお伝えすることで、皆さまのお役に立てればと願っております。
今回は、「アセスメントツールの活用」に関する調査結果です。この調査は第三者調査機関(アバディーン・グループ)によるものですが、特にSHLツールを活用している企業とそうでない企業に分けて分析・考察を進めている部分を中心に、SHLグループのHPで公開されています。
アバディーン・グループ独自調査によれば、採用前後のアセスメントにSHLツールを使用している企業は、他のツールを使用している企業と比べて、以下のメリットを享受しています
- 社員一人当たり売上が増加-12%、利益が増加-11%
- 配属先管理職の満足度が向上-47%増
- 1年目定着率が向上-15%増
- 新規採用者の業績が向上-18%増
2010年3月、アバディーン・グループが、現在アセスメントを使用している250社強に調査を実施しました。その中にはSHLツールを使用している74社が含まれています。調査の目的は、採用や能力開発などにおける意思決定を改善するために、企業が社員のライフサイクルの各段階でアセスメントをどのように導入・活用しているかを明らかにすることです。
結果は、各業界の一流企業がSHLアセスメントを使って企業業績を推進していることを示しています。以下、結果の要約をご報告します。(報告書全体を見るにはここをクリックしてください。)
社員のライフサイクルを通じてのアセスメント
ここ数年、企業は新しいやり方でアセスメントを使い始めるようになりました。すなわち、人材に関するよりよい意思決定を下すために、人材マネジメントシステム全体でアセスメントデータを組み込むようになったのです。アセスメントは長い間、採用前の意思決定のためのツールと見られてきましたが、キャリアの複数地点におけるガイダンスとしてアセスメントを使用する会社が増えています。
図1:アセスメントの使用目的
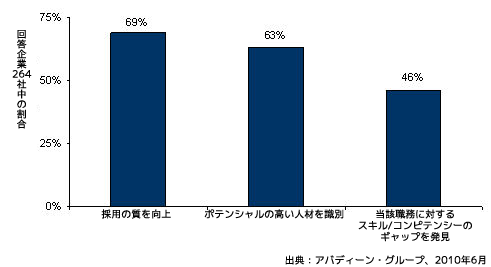
採用の前と後にアセスメントを一貫して使うことのメリット
採用前と採用後の両方でテストを使用するという戦略をとっている企業の業績が向上しています。そして、人材ライフサイクルを通してSHLアセスメントを導入している企業の結果はさらによいものです。採用前後でSHLアセスメントを使用している企業は、他ツールを使用している企業と比べて、「1年目定着率が向上した」と回答した割合が15%、「新規採用者の業績向上」が18%、「配属先管理職の満足度向上」が33%多くなっています。
図2:重要指標における成果
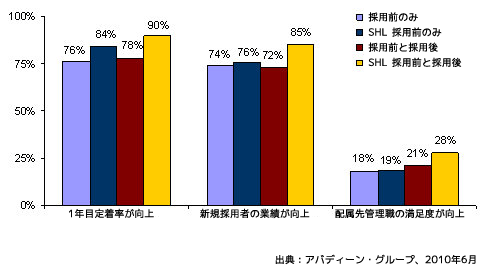
これらの結果は、採用前にのみアセスメントを使用している企業に対して、重要なメッセージを発信しています。
売上と利益へのプラス影響
- 社員一人当たり売上が増加-12%
- 社員一人当たり利益が増加-11%
管理職やリーダーにとってさらに重要な点は、社員のライフサイクルを通じてSHLアセスメントを使用することが売上や利益に与える影響です。採用前のみのSHLアセスメント使用でも財務面の業績にプラスの影響を与えていますが、採用前と採用後の両方で使用された場合の改善度は劇的です。
図3:売上・利益における成果
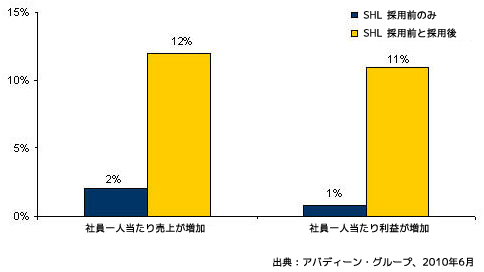
新卒者アセスメントの成果
- 1年目定着率が向上した企業は86%
キャリアのスタート時点でアセスメントを使うことは重要です。なぜならば、ほとんど経験を持たない人が入社する際、彼らの能力を立証し、さらには職務要件とのギャップを埋めるために必要なステップについての情報を与えることができるのは、彼らのアセスメント結果だからです。新卒者の採用でSHLツールを使用している会社は、プラスの結果を得ています。
- SHLアセスメントを使用した企業で「配属先管理職の満足度が向上した」と回答した割合は、他社のアセスメントを使用した企業に比べて、47%多い
さらに、新卒採用でSHLアセスメントを使用した企業は、他社アセスメントを使用した企業に比べ、「配属先管理職の満足度が向上」で47%多くなっています。実際、採用、能力開発、職務遂行度を、それぞれ孤立した状態で見ることはできません。相互に緊密に関連しており、その連続線に沿って個人を評価するために使用されるアセスメントも、同様に相互に緊密に関連していなければなりません。
図4:新卒者アセスメントの成果
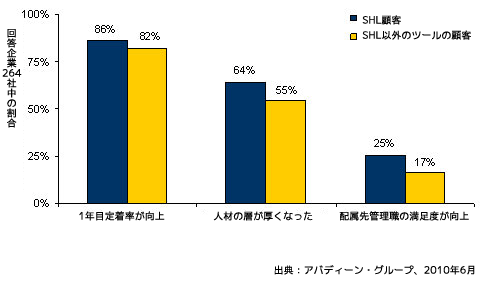
既存の人事施策にアセスメントを組み込む
アセスメントツールやプロバイダーを吟味する際、業界最高の一流企業は、それらのツールや提案内容がどれくらいうまく既存システムに組み込めるか、に最も関心を持っているようです。そうではない企業は値段を最も重視しますが、一流企業にとって値段は4位です。
意思決定のプロセスにおいては、ユーザー企業と協力して活用手法を作り出し、測定方法や要点を確立できるようなプロバイダーの能力も鍵であることがわかりました。
図5:ツールや提案を選択する基準
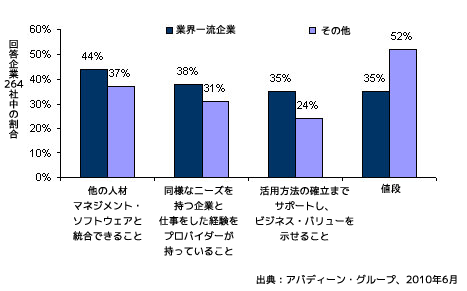
この記事のはじめに示されたURLでダウンロードできる報告書では、この記事で取り上げられたテーマ以外にもいくつかの結果が掲載されています。英語ですが、グラフが豊富なので、ご興味のある方はぜひぱらぱらとご覧いただければ参考になる箇所を見つけられると思います。
各業界を代表するような一流企業ほど、採用時だけでなく、入社後のいくつかの時点でアセスメントツールを使用しているという報告でした。
報告書のほうには「実施場面別導入率」のグラフがあります。「一流企業」と「その他」で分けられており、それぞれ、「採用」(85%、92%)、「導入」(61%、38%)、「業績管理」(74%、64%)、「人員計画」(72%、56%)、「学習」(79%、69%)となっており、(対象企業が「現在アセスメントを活用している企業」であることを加味しても)かなり高い導入率です。
これまで、日本でも適性検査などアセスメントツールの活用場面は主に採用選考でした。適性把握、能力開発、昇進・昇格などの目的で在職社員に使用することは、その必要性は認めても、さて実施となると二の足を踏むお客様がやはり多かったようです。しかし、ここ十年くらいの間、徐々にですが確実に増えてきた、と感じています。

このコラムの担当者
堀 博美
日本エス・エイチ・エル株式会社



