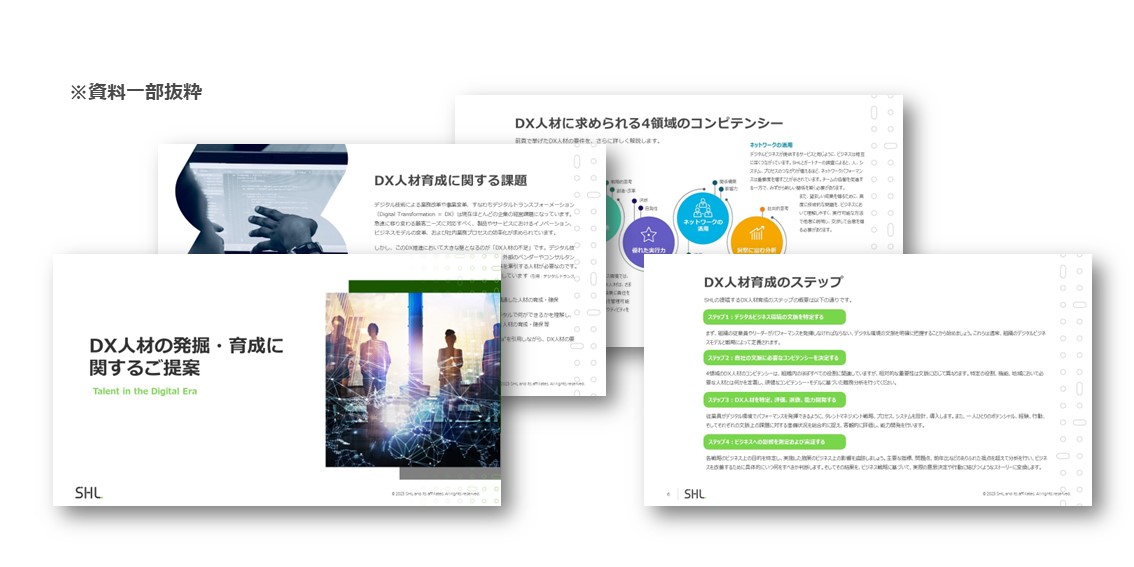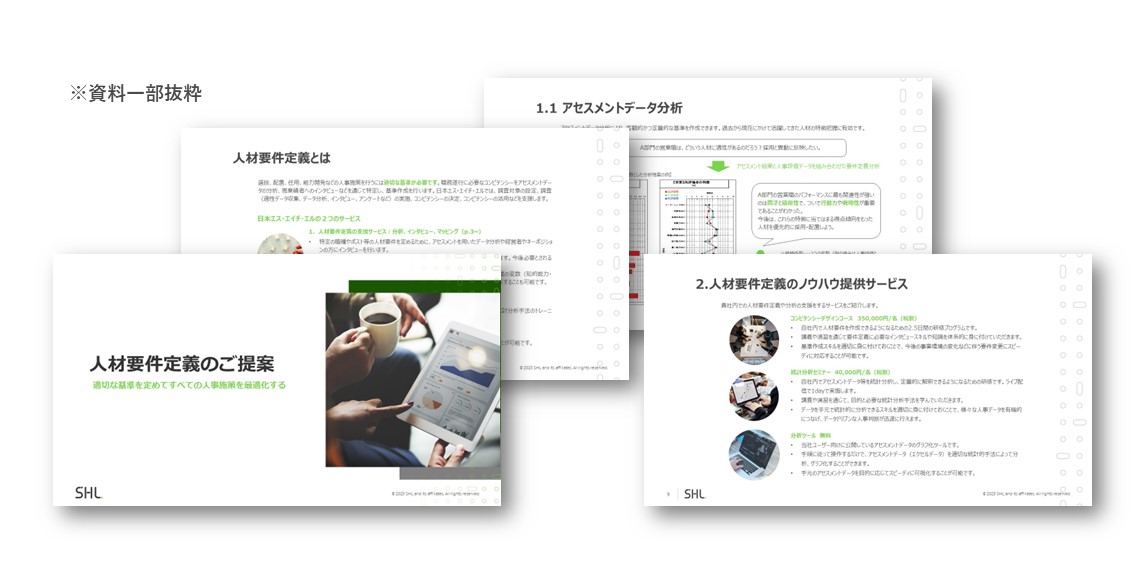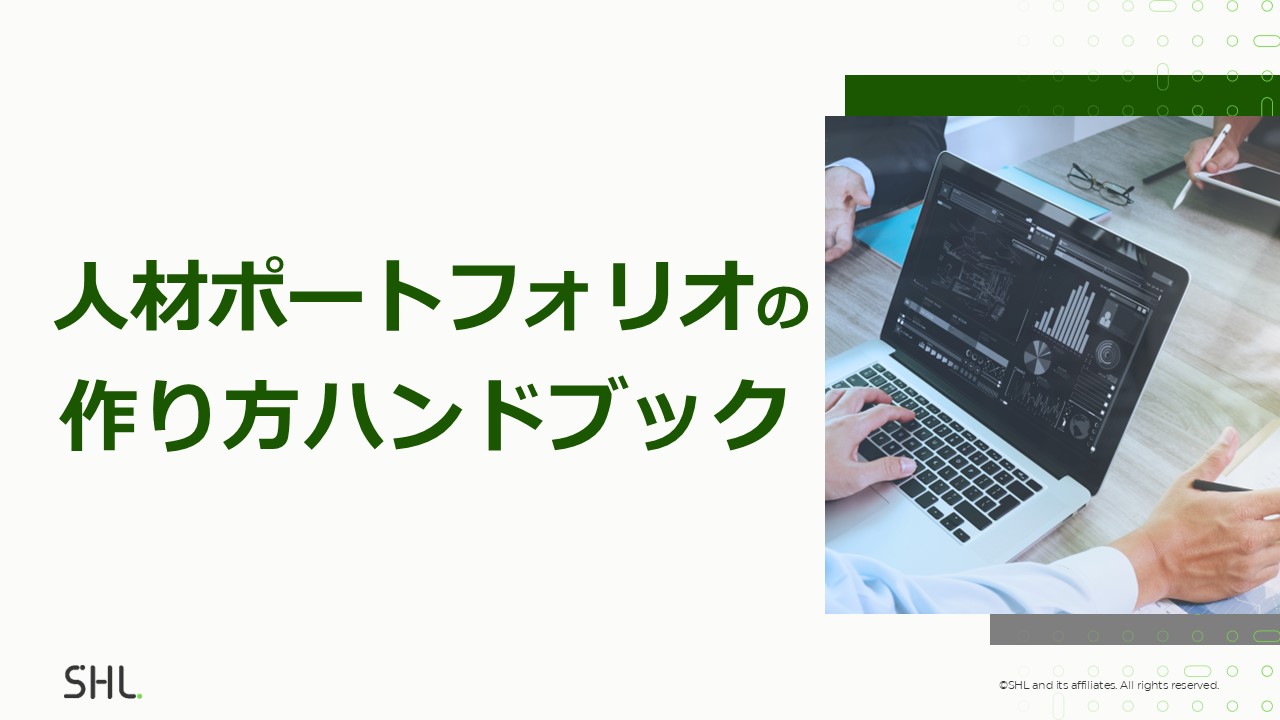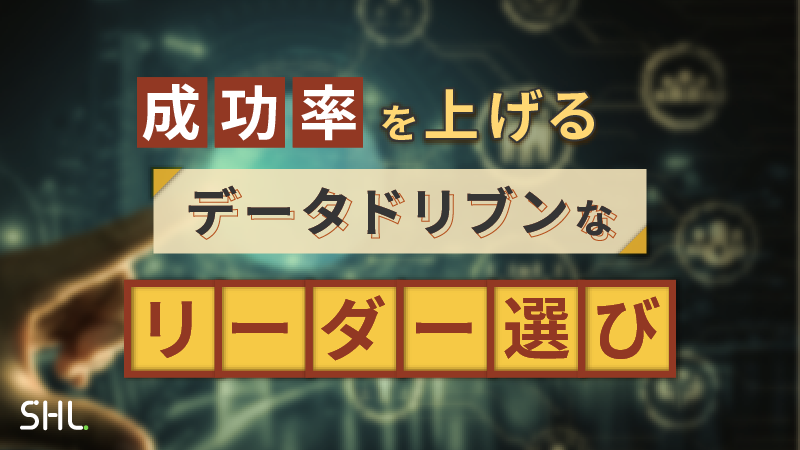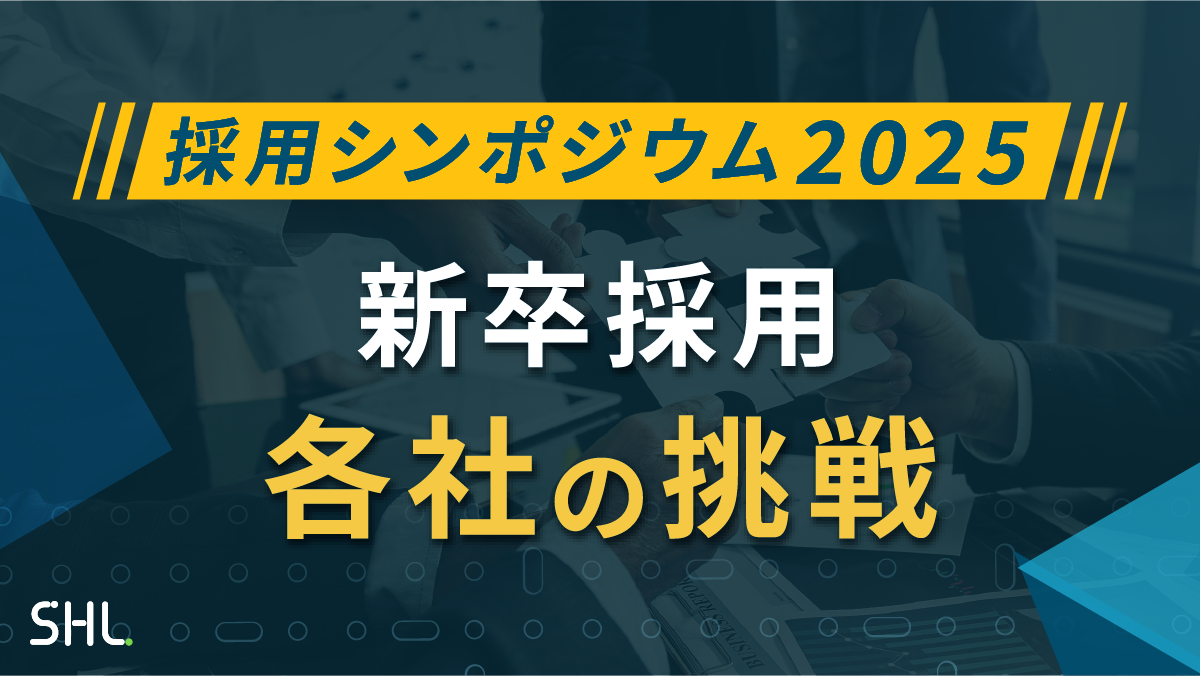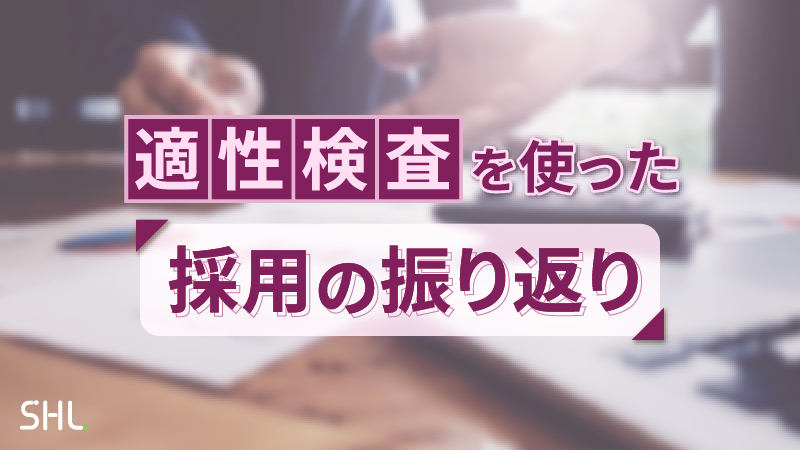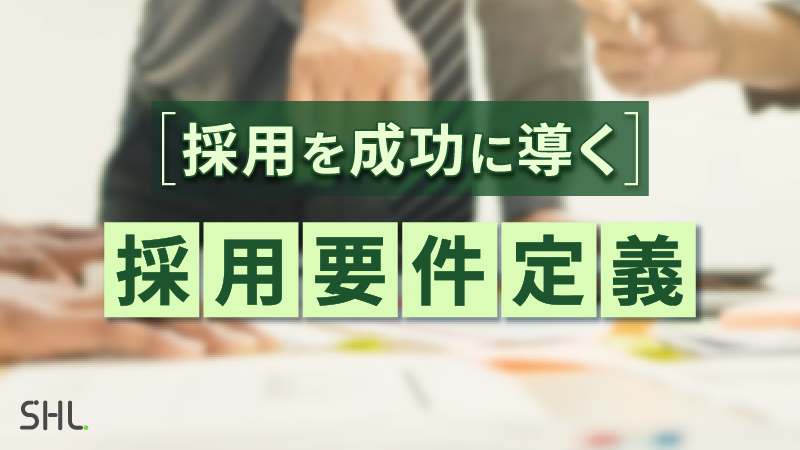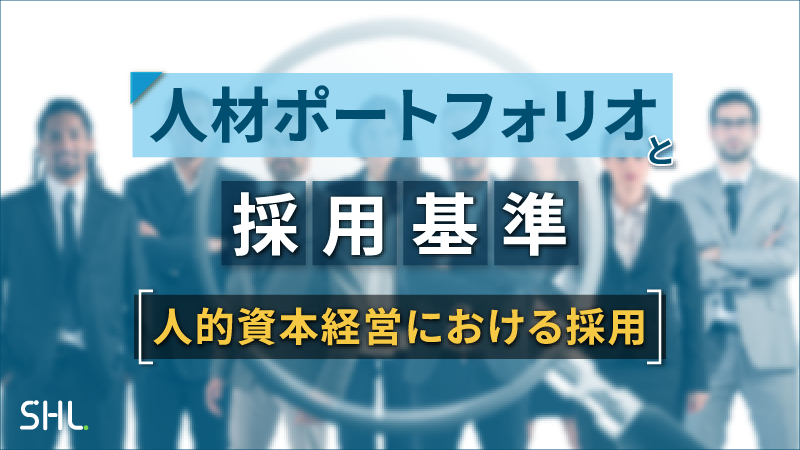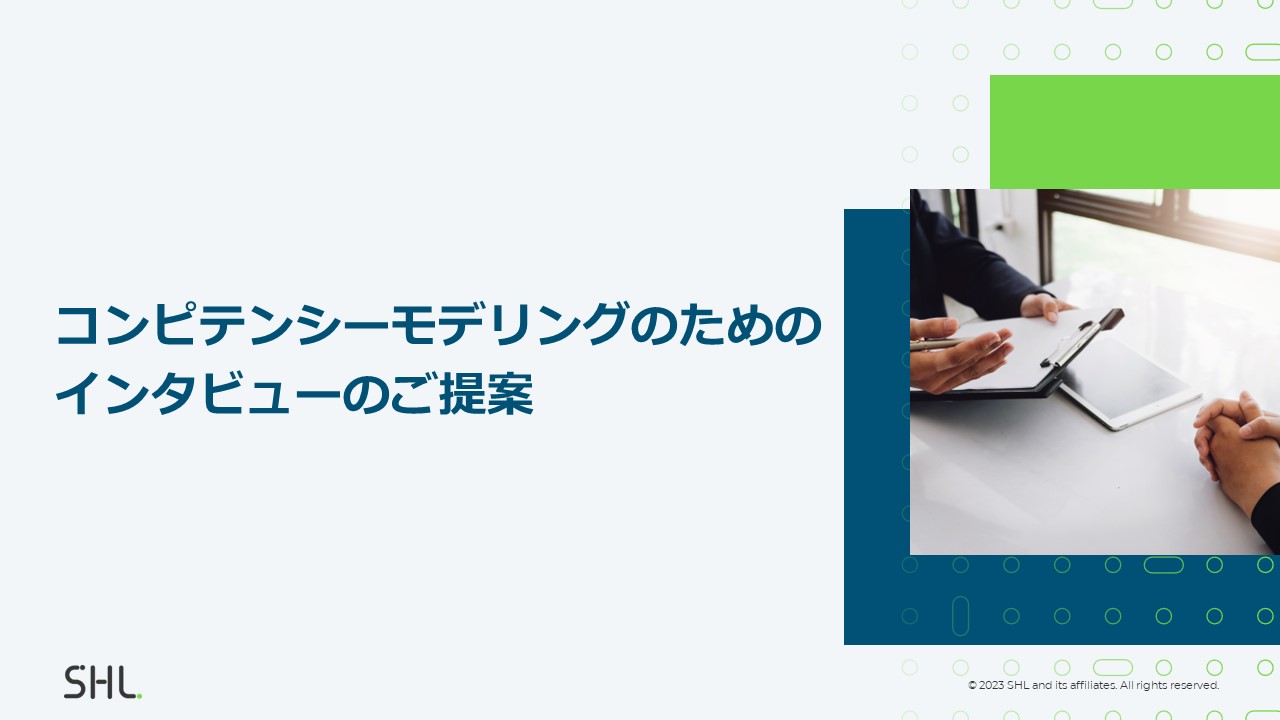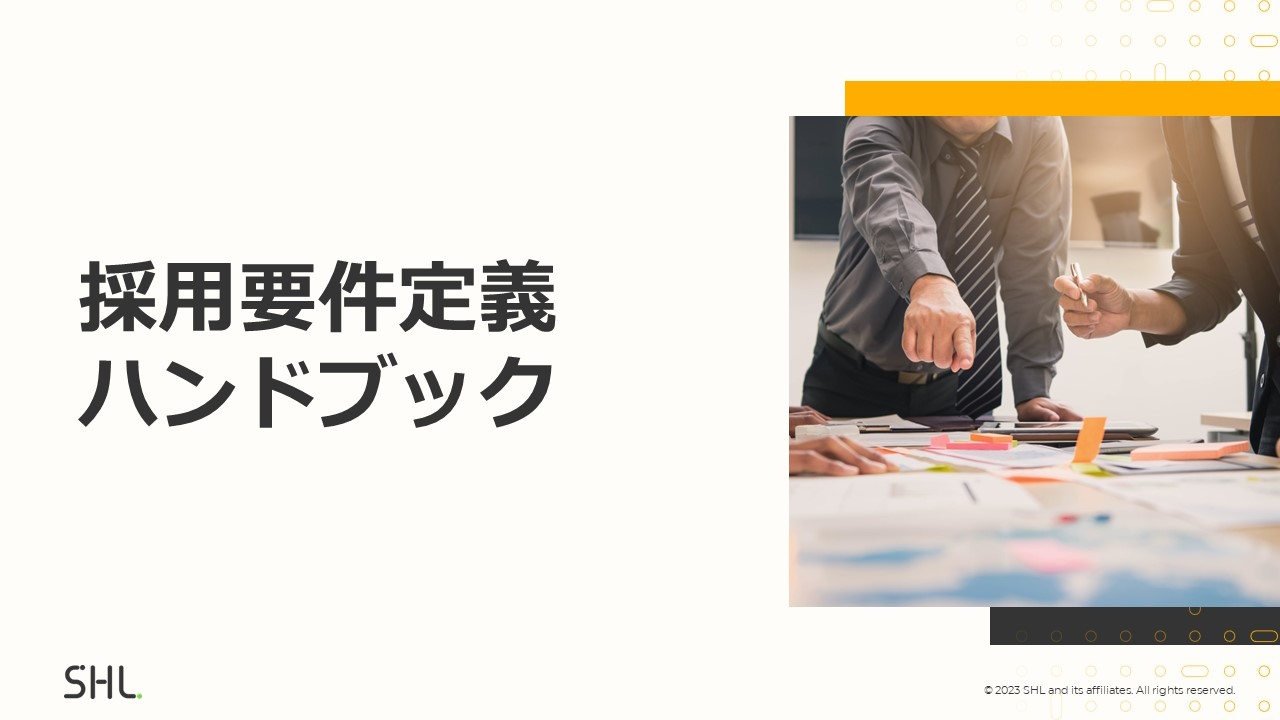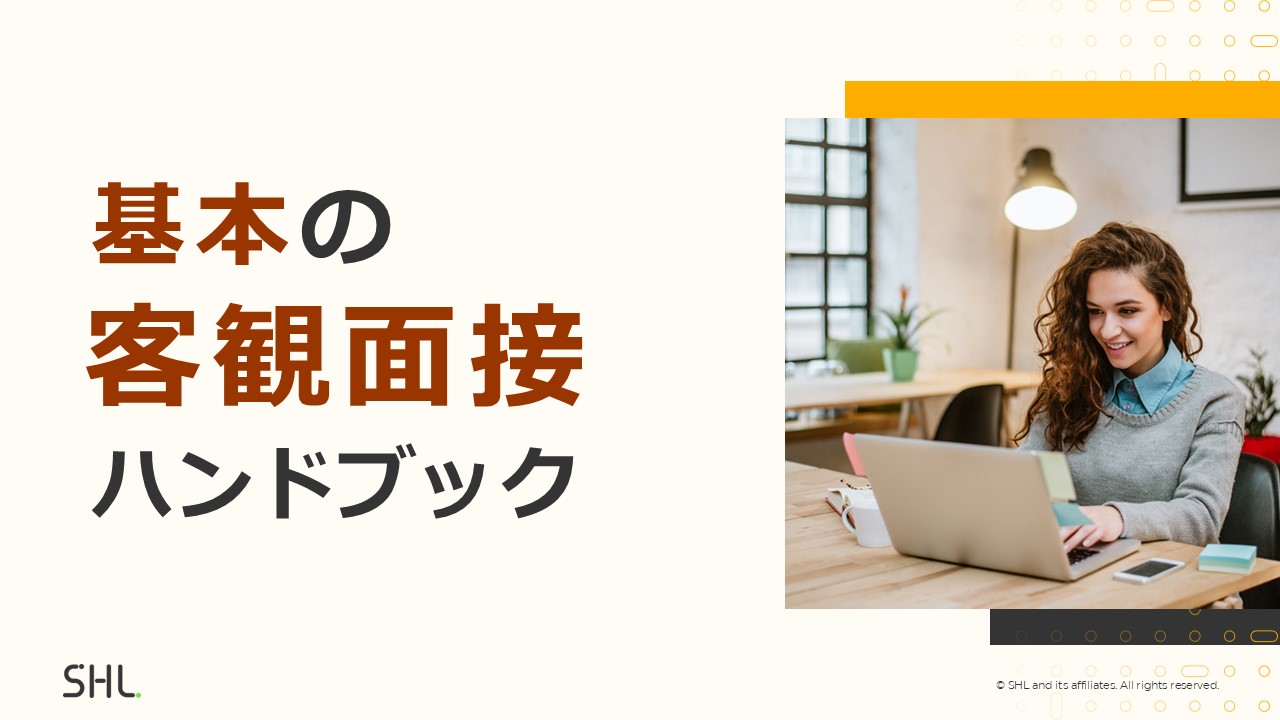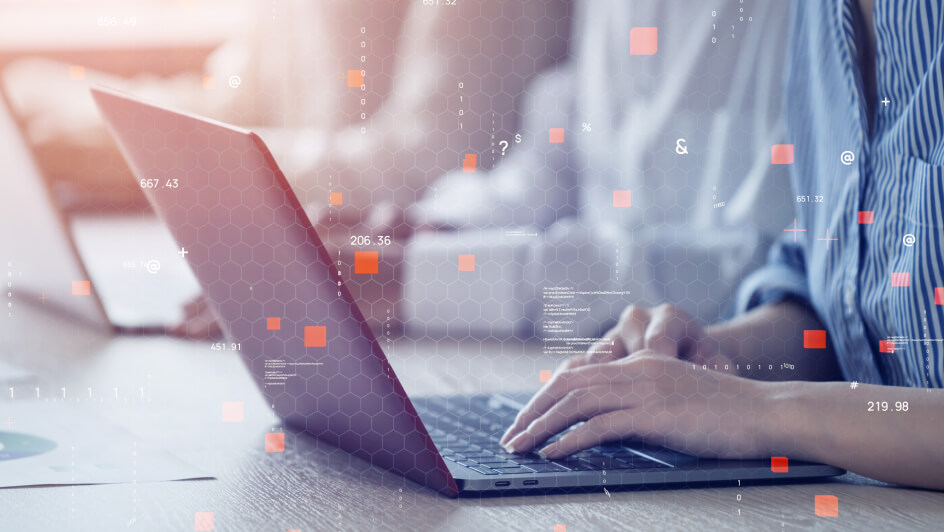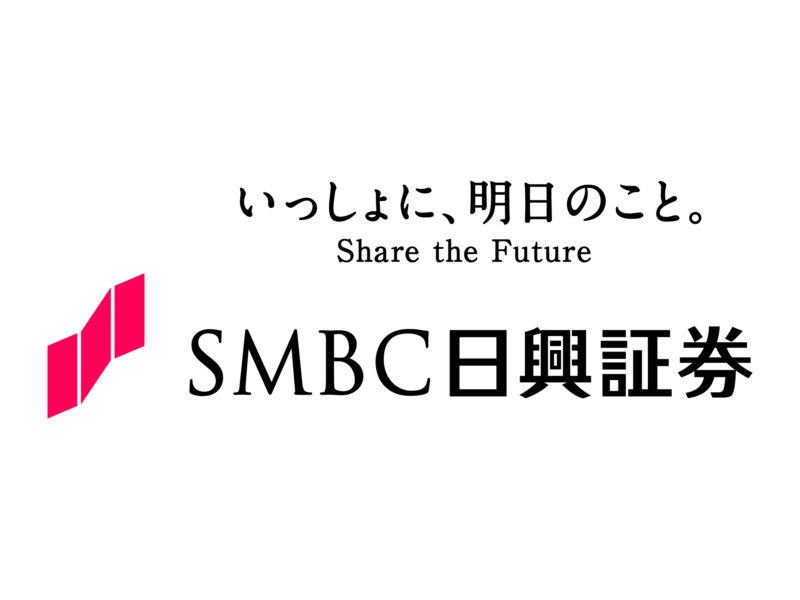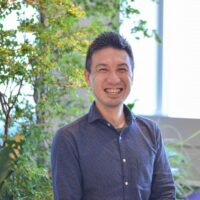客観データの活用を組織の人事プロセスに埋め込んでいく
今後は、この取り組みを継続していく仕組みが必要です。全員に受検してもらったのはよいですが、各人が結果を十分に理解して目標を持つところまでできているかというと、まだそこまでは到達していません。既存の年次別の研修などの機会に組み込んでいくことを検討しています。従来、このような研修では役割期待と自分とのギャップを検討し、今後の目標を立てていましたが、自分に関する情報は自分の思い込みだけでした。しかし、客観データが活用できるようになったので、パーソナリティの特徴と役割期待とをすり合わせて、目標や行動計画の立案に活かしていきたいと考えています。
私がシステム部門に在籍していた頃、電子メールの導入に携わったことありましたが、導入することでコストがどのくらい削減できるのかと問われることがありました。しかし、今となれば電子メールはインフラのようなものになり、コスト削減の効果という質問は意味を成さなくなりました。価値観が変わったのです。パーソナリティデータの活用も同様で、まだ社内で定着したとは言えませんが、一人一人の社員が能力を発揮する上で、こういう情報があって当たり前の世界になっていくと考えています。
具体的に育成に活かす仕組みをさらにブラッシュアップして、データを活用する文化を作っていければと思っています。そうすることで、当社において自分が腹落ちできる目標を持ち、その実現を目指して意欲を持って働くことができるようになるのではないかと考えているからです。そして、それが人財の流出を防ぐことにも繋がっていくのが目指す姿です。
日本エス・エイチ・エル様には、私たちが明確な答えを持っていない状態でご相談させていただくことになりましたが、よくここまでお付き合いいただけたな、丁寧に対応していただけたな、という印象を持っています。契約につながらなければ申し訳ないと思うほどに、非常にいろいろなことを対応していただきました。日本エス・エイチ・エルのアセスメントのデータはいかようにも活用できるという点も魅力です。半面、得体のしれないという側面もあるかもしれませんが、将来的に人事領域での新しい知見や枠組みが登場しても、それらに合わせてデータを利活用する方法を検討することができます。今後もデータの活用に関して、当社の文脈に即したご提案を期待したいと思います。