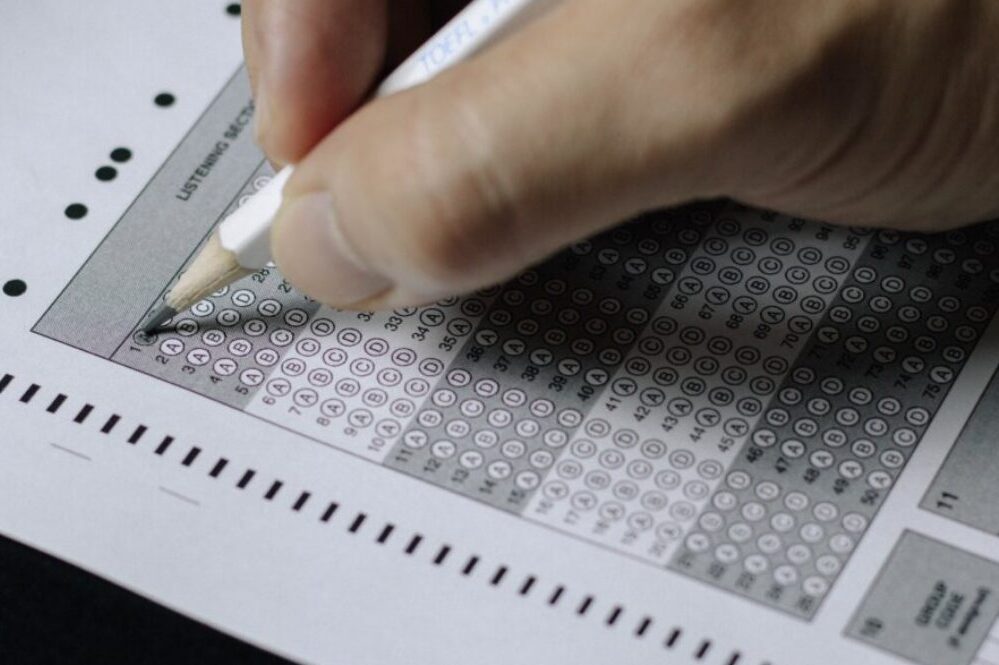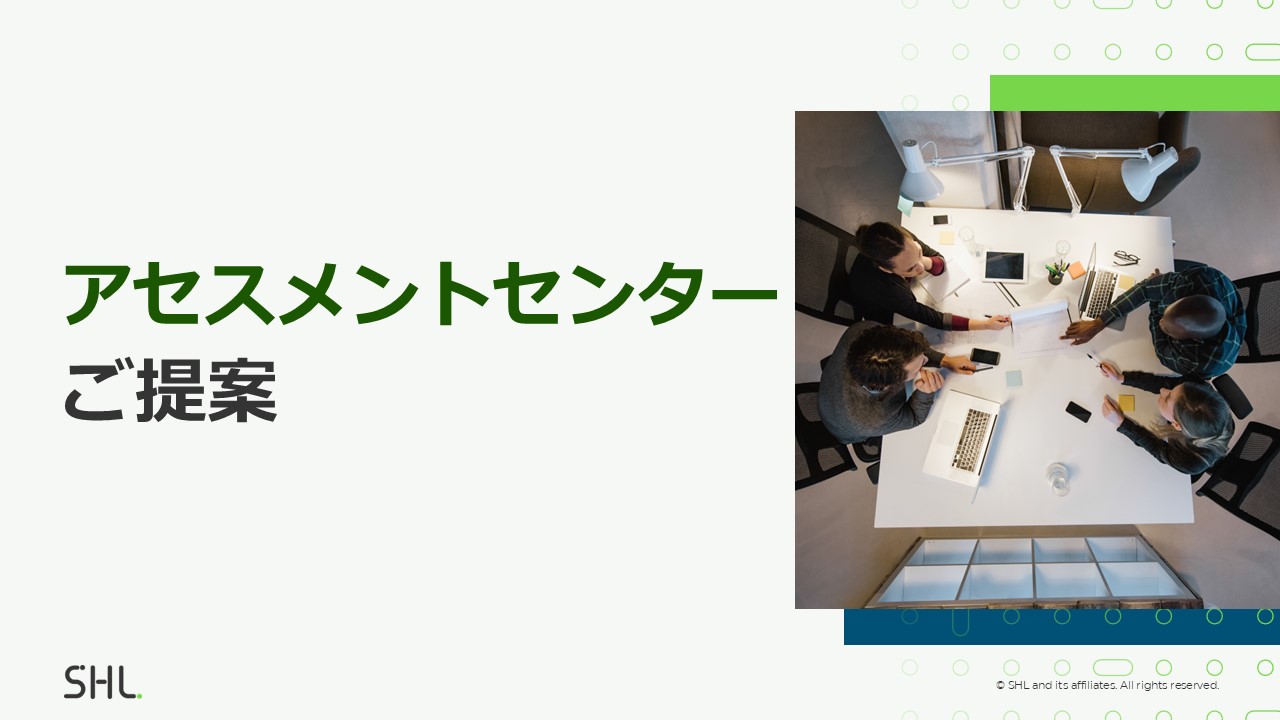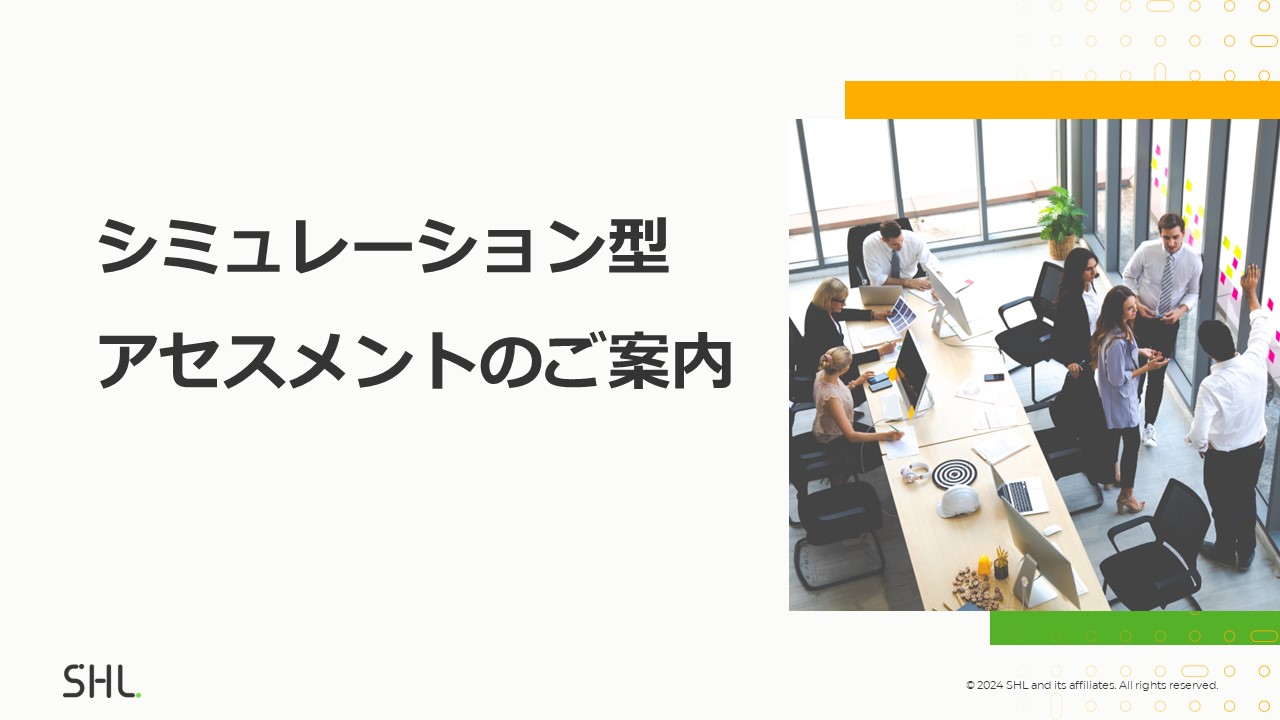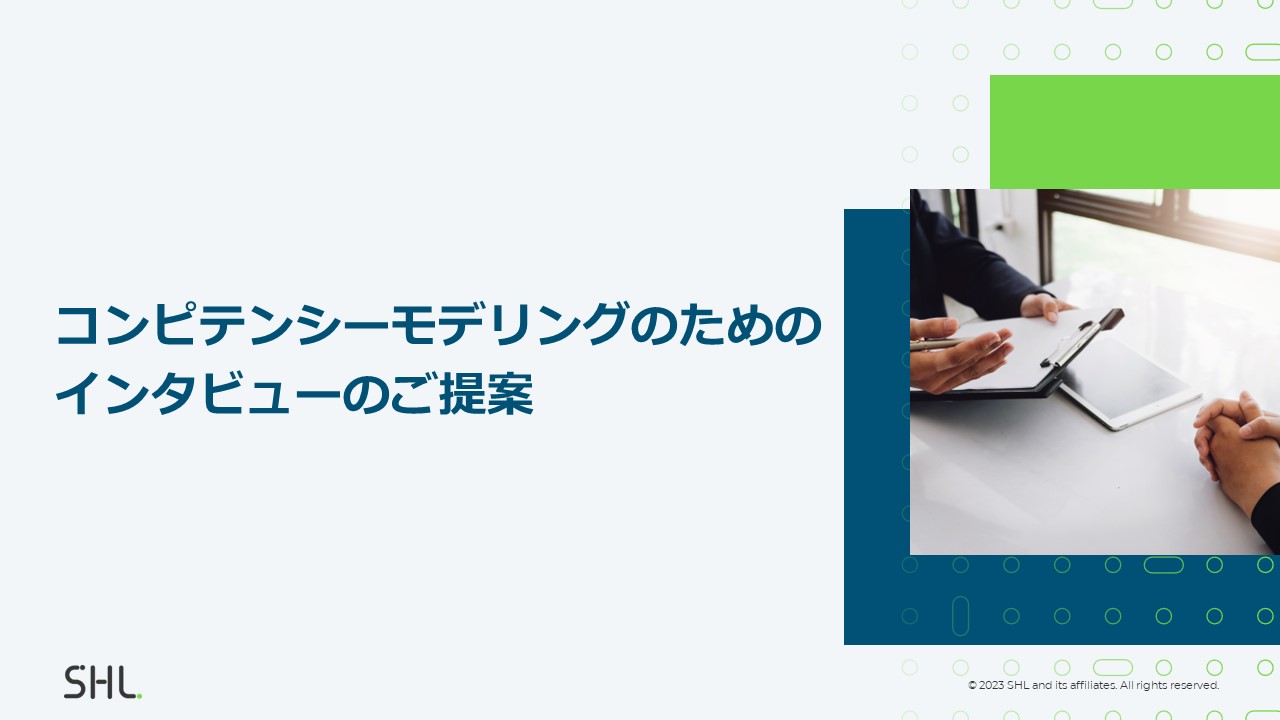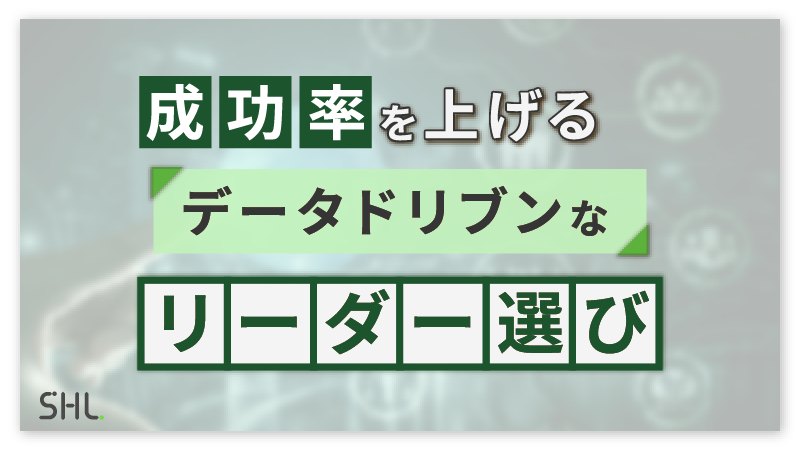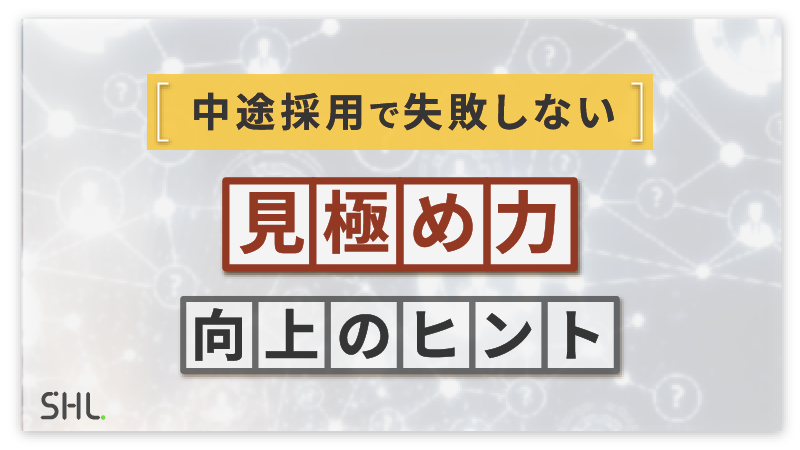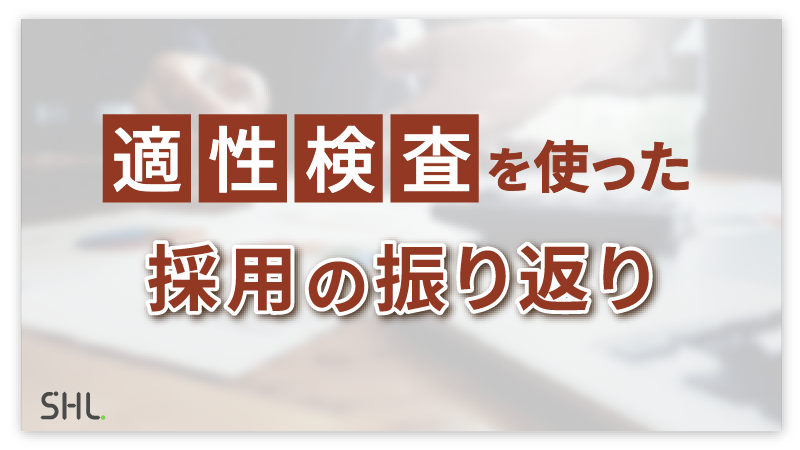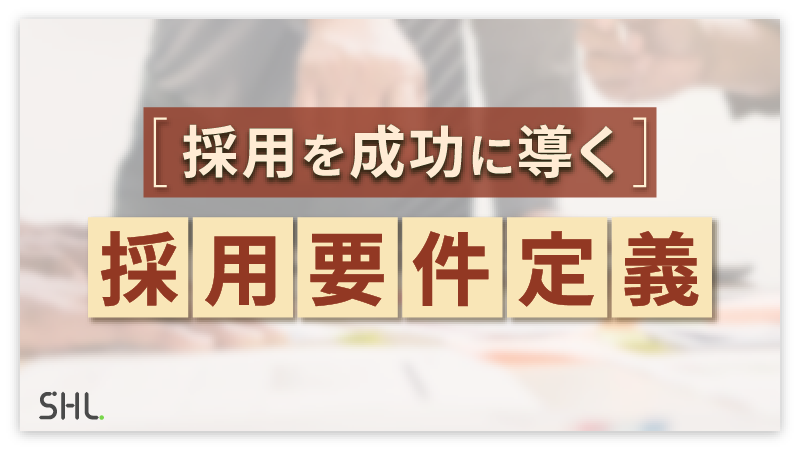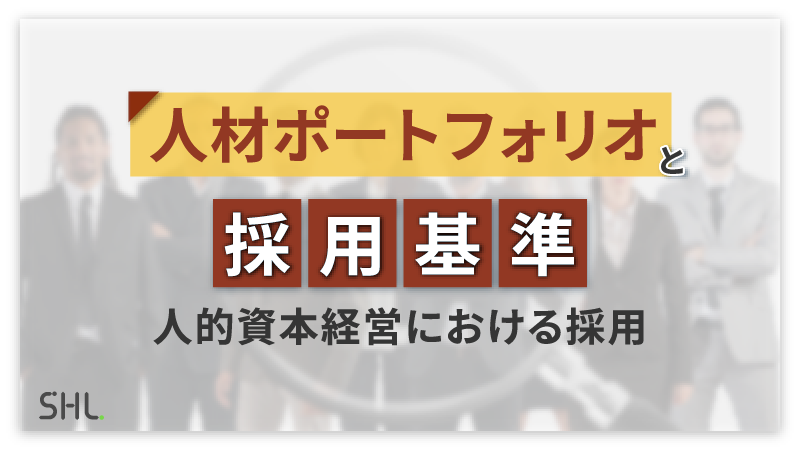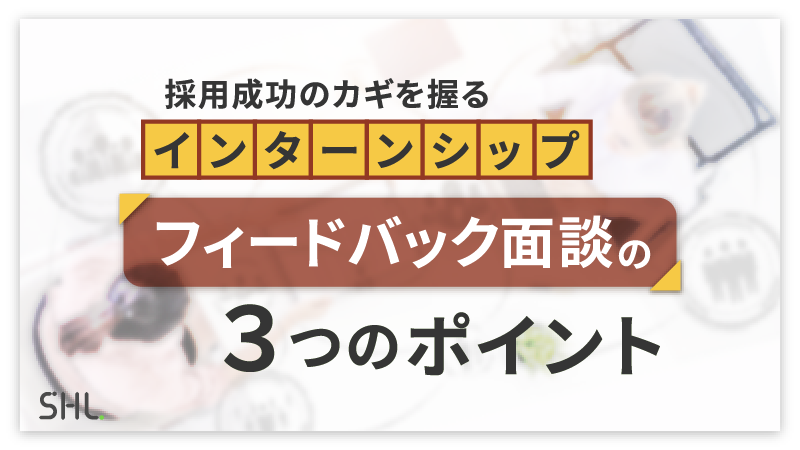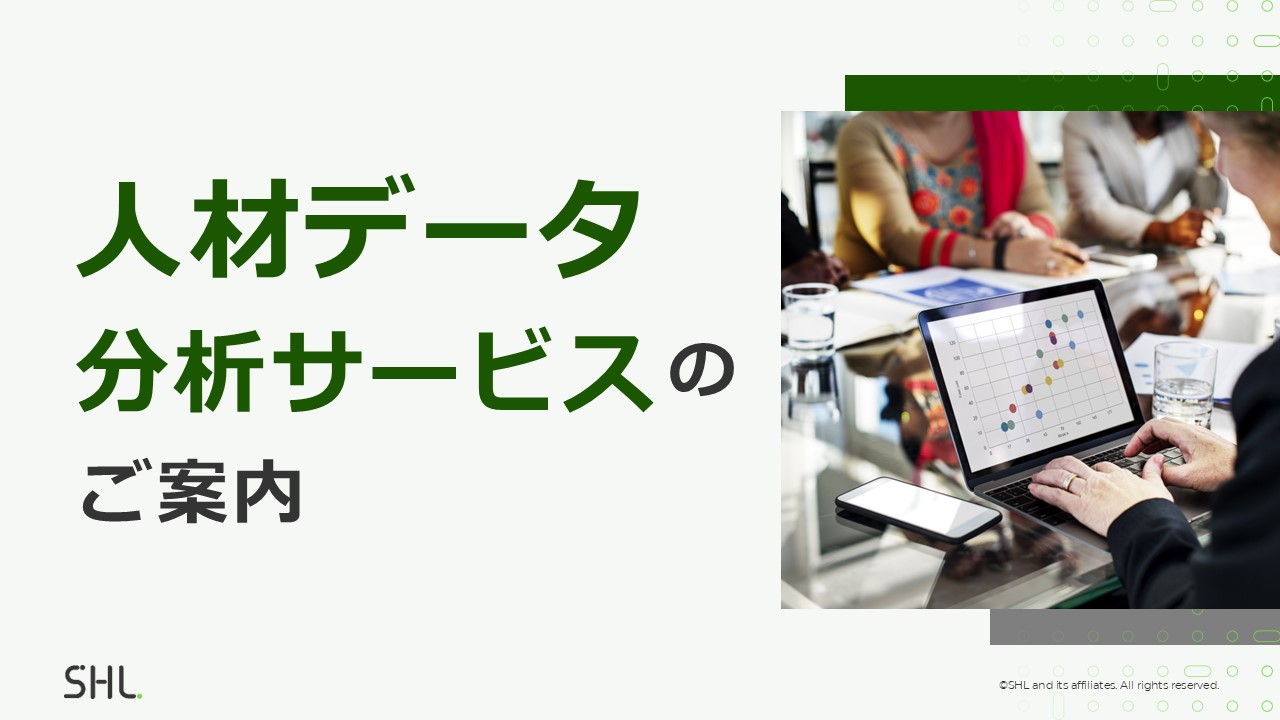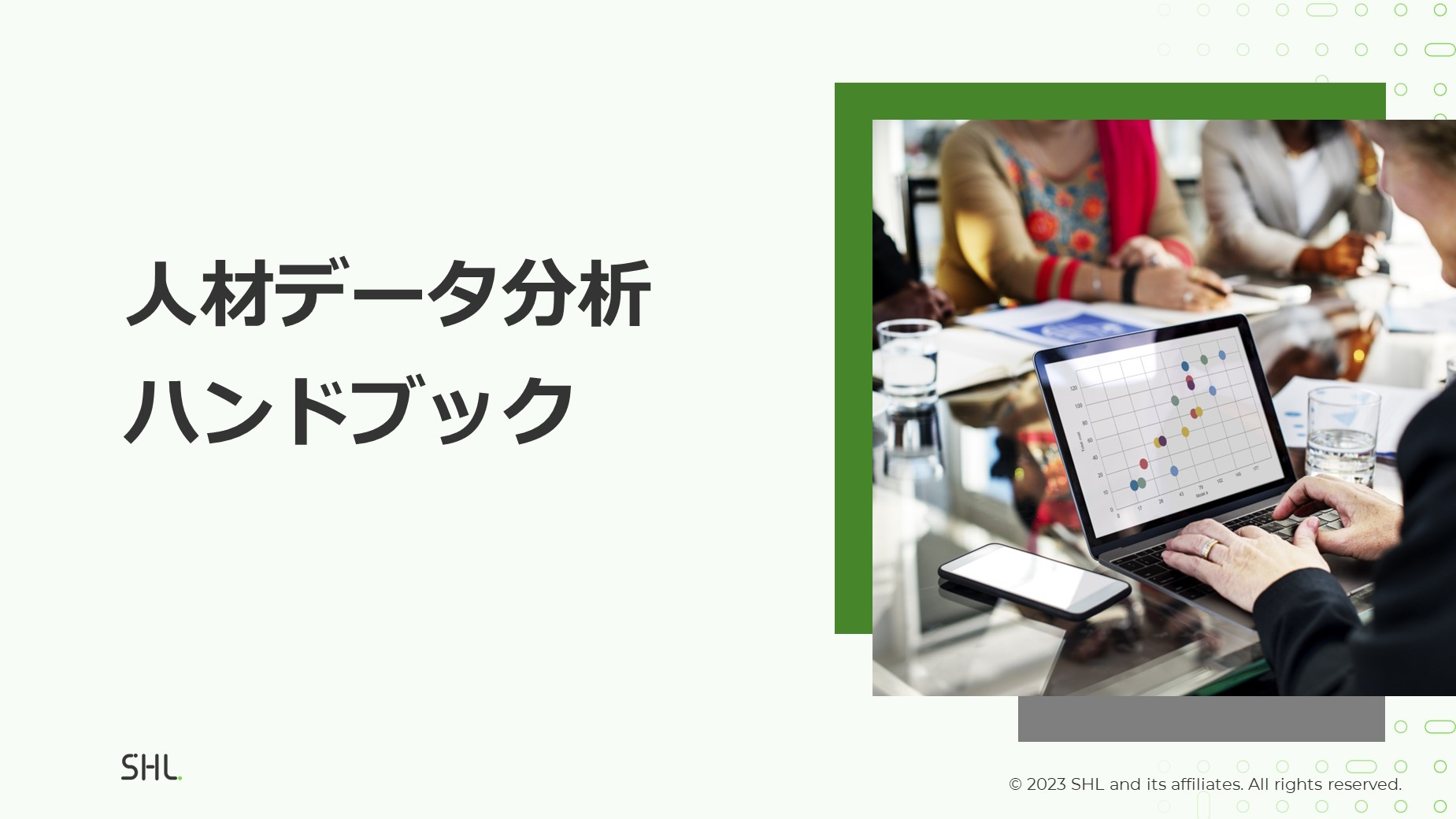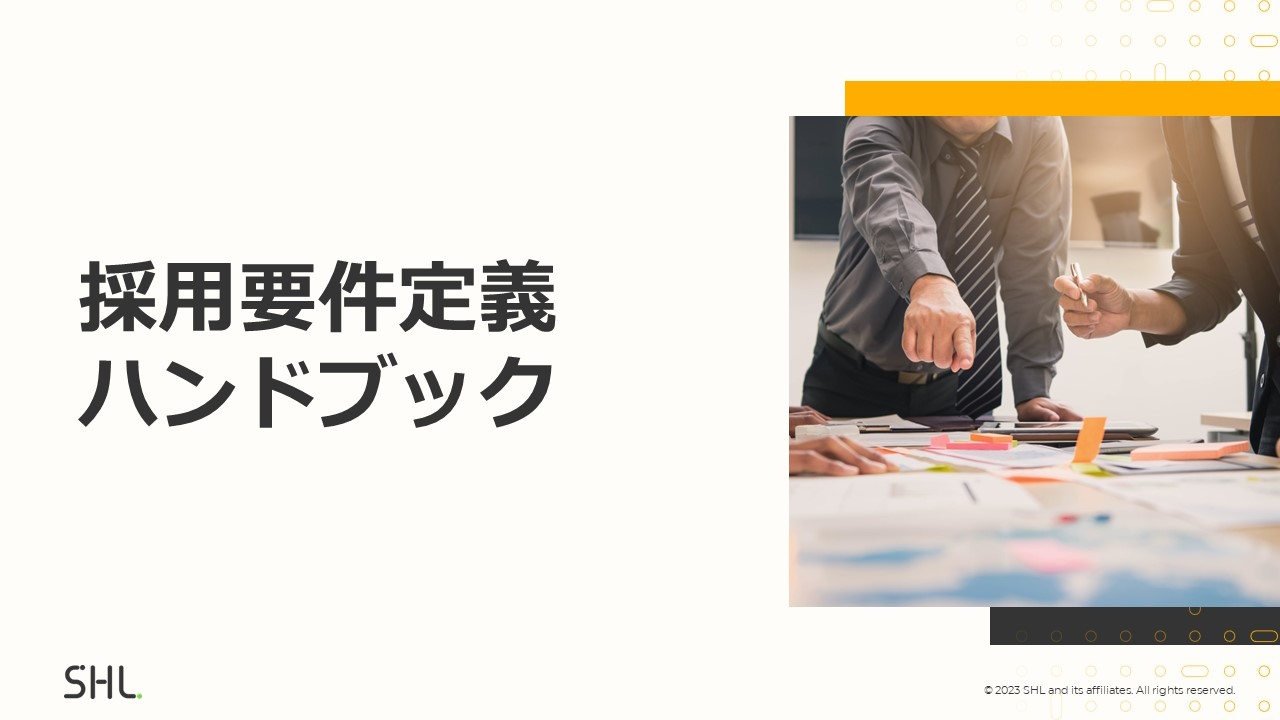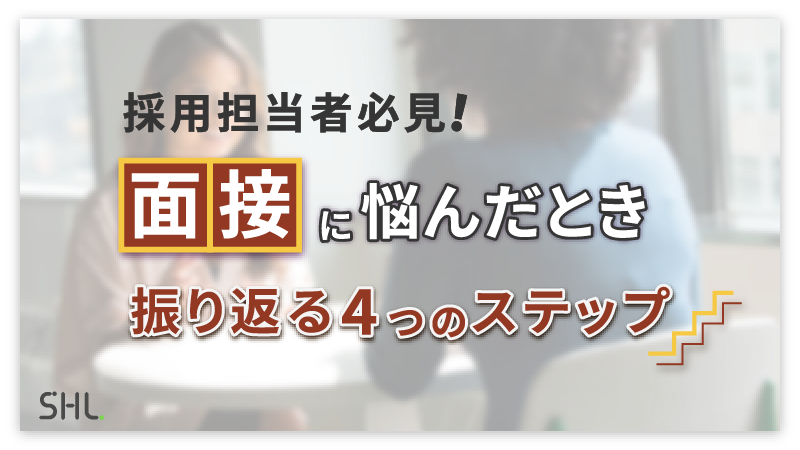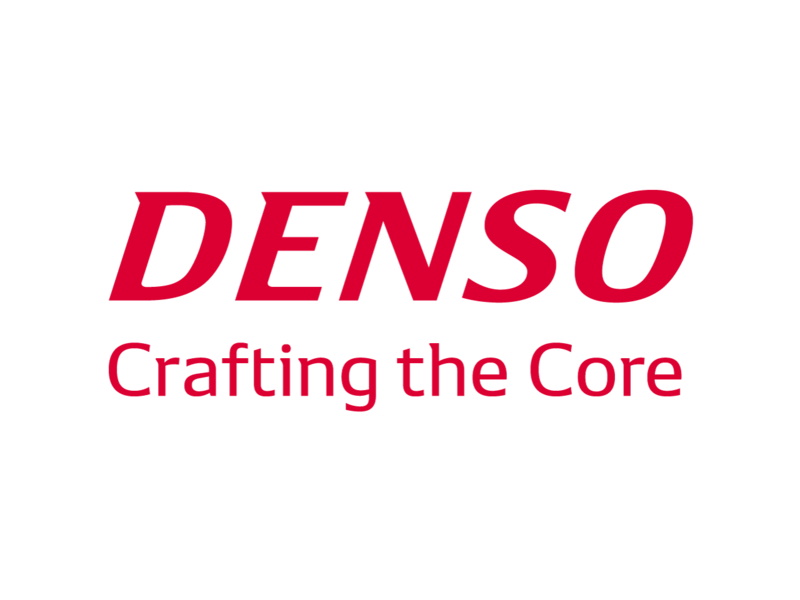変化の激しい時代、新たな価値創造に向けて組織は変化を加速させています。同時に、そこで働く一人ひとりは、自分のライフスタイルやライフステージに応じて柔軟にキャリアを選択する傾向が強まっており、これまでの組織が主導する一律のキャリアパスが機能しない現実があります。こうした背景から、従業員が主体的にキャリアを形成していく「キャリア自律」は組織の人材育成のスタンダードになりつつあります。本コラムでは、キャリア自律を実現するヒントと組織としてのキャリア自律支援策をご紹介します。
キャリア自律への7つのヒント
具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。
内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。組織として、人事としてできること
これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。
まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、
パーソナリティ 、
価値観 、
モチベーションリソース など、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は
1on1のフィードバック ですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。
部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。
また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。
おわりに
日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。
タレントマネジメントという言葉は、今や日本でも広く浸透しています。単に人材を管理する仕組みや、同様のシステムを想起される方もいるかもしれませんが、真の意味は異なります。タレントマネジメントとは、組織の戦略を実行して維持発展していくために行うあらゆる人事戦略と実行を意味します。広範な意味を包括していますが、本コラムではこの言葉を、「組織内の人員の育成・配置・昇格に関わる施策」として取り扱います。
SHLはグローバルで1600名以上のHRプロフェッショナルに調査を行い、採用・タレントマネジメントの最新トレンドをまとめました。
調査 のテーマは、アセスメントツールやアナリティクス、DEIやニューロダイバーシティ、AIの影響まで多岐にわたります。
今回はこの調査の中から、タレントマネジメントにフォーカスし、その現在地を探ります。
グローバル企業が実践できている良い点と改善点はなにか。自社のタレントマネジメントの点検も兼ねて、ぜひご一読ください。
重要性が増すタレントマネジメント分野
平均で人事予算の36%がタレントマネジメントに割り当てられており、その割合は増加傾向にあります。これは、戦略的優先事項として人材開発・タレントマネジメントに全社を挙げて取り組んでいることを示しています。この意図的な投資は、重要なスキルギャップを埋めるための迅速な解決策であると同時に、将来のリーダーを生む強固な
サクセッションプラン を確立し、組織の成功と発展を守ることができます。一方で、財政的なプレッシャーは組織内のどの部署も感じている中、予算を割いて実行しているタレントマネジメントのどの施策がうまくいっており、どの領域は改善が必要なのでしょうか?
タレントマネジメントでうまくいっていること
タレントマネジメントにアセスメントが広く使われている
回答者の80%以上がタレントマネジメントで積極的にアセスメントを利用していると回答しました。正確かつ客観的なデータを用いた意思決定の重要性を強調しています。
リーダーやハイポテンシャル人材が優先事項となっている
組織で最も影響力のある役割に注力しており、
リーダシップ開発 がタレントマネジメントの最優先事項となっています。次いで、
ハイポテンシャル人材の特定 とキャリア開発が続きます。
タレントマネジメントに投資している
ほとんどの組織(83%)が人材育成への投資を計画しており、将来の成功や重要な従業員の確保において、人材育成が戦略的に重要であることを強調しています。
グローバル企業の問題意識とは
社内での異動・昇進の機会
社内での異動や昇進の機会は様々な階層で存在していますが、最も多いのは一般社員レベル(27%)と初級管理職レベル(27%)です。優秀な人材が社内に留まり、モチベーションを維持するためには、より上級の職務への道筋が見えることが重要です。
客観性に欠ける人材発掘
社内選抜や昇進の意思決定が主観的な情報(87%)や過去の実績(78%)に大きく依存しており、アセスメントのような、より客観的な情報の活用に価値があることを示唆しています。
ハイポテンシャル人材の特定が依然として課題
55%がハイポテンシャル人材の特定にアセスメントを利用しているにも関わらず、ハイポテンシャル人材の定義やその特定方法の満足度は50%を切っています。科学的な裏付けを持ったデータに基づき効果的なハイポ人材プログラムを実施することは大きなメリットがあります。
タレントデータの効果的な活用にはいまだ様々な障壁
データ活用における障壁 を認識し、統合された人材システムを利用するなどの解決策を講じる必要があります。
おわりに
自社のタレントマネジメント施策と照らし合わせて、いかがでしたか?
まずは調査で「うまくいっている点」として挙げられた①アセスメントの積極活用、②サクセッションプランやハイポ人材プログラムの優先課題の着手、③タレントマネジメント分野への投資 を出発点として、自社の施策の実行・評価・改善を行ってみましょう。課題として挙がった4点は多くの企業が苦慮している点です。当社が持つ科学的なアセスメントとグローバルな人材に関する知見を活用する余地がありますので、ぜひ当サイトでの情報収集やコンサルタントに
ご相談 いただければ幸いです。
参照:https://www.shl.com/resources/by-type/blog/2024/talent-management-today-what-works-and-what-needs-to-improve/
変化の激しいビジネス環境で新たなリーダーを作り出すために、多くの企業がハイポテンシャル人材の発掘と育成に力を入れています。ハイポテンシャル人材の育成には、能力をストレッチさせるための職務と経験が必要です。どのポジションでどんな経験をさせるか。この重要な判断には、必ず対象者のディベロップメントニーズの把握がセットになります。
今回は360度評価を用いた能力開発についてご紹介します。
360度評価とは
360度評価とは、評価対象者(本人)の周囲の上司、部下、同僚などが評価を行う仕組みを指します。複数の立場から評価を行うことで、対象者の能力やコンピテンシーを様々な角度から確認することができます。周囲の他者からのフィードバックは対象者に様々な気づきを与えるため、特に能力開発に有効です。
実施の流れ
360度評価の実施から結果フィードバックまでの計画を立てます。まずは目的(何のために誰を評価し、どのような効果を期待するか)を明確にします。その上で、目的に合致する評価項目と評価対象者を設定します。評価項目は、他者から観察可能な行動であり、業績に関係するものでなくてはなりません。続いて評価者を選定します。最後にフィードバックについて検討します。能力開発ではこのフェーズがとても重要です。誰がどのような形式で評価者にフィードバックするのか。適切な結果の返却が自己理解を促進し、行動変容の後押しをします。その後、実際に能力開発がなされているかを確認しながら、一連のプロジェクトの実効性を判断します。
能力開発を促すための着目ポイント
前述の通り、360度評価はフィードバックが重要です。機密性と専門性を担保した上で適切な人がしっかり結果を返却します。外部の専門家に支援を仰ぐ場合もあります。
定められた要件に従い、必要となるコンピテンシーの結果を見ます。結果の着目ポイントは次の2点です。当社の360度評価ツール「無尽蔵」では本人・周囲の評価以外に、仕事における能力の重要度を上司が評価する機能があり、これらも活用します。
自分が高く評価し、周囲が低く評価した項目
自分と他者との間で、強み、弱みの判断が食い違っている項目です。どうしてその食い違いが生まれたかを追跡する必要があります。特に、自分ではできていると判断しているが、他者からはそうみえない項目については振り返った上で、場合によって行動変容が必要です。
上司が重要と評価し、周囲が低いと評価した項目
上司は仕事の成功上不可欠なものと考えているのに対し、他者は本人のその能力は不十分であるとみなしています。現状では、業務遂行で苦戦する可能性があるため、これらの能力を身につけていくことは必要不可欠です。
おわりに
ハイポテンシャル人材の能力開発は、個人の成長だけでなく組織開発にも直結します。個々の強みと弱みをしっかり把握した上で、次を見据えた人材配置を行っていくことが組織の力を強くします。
当社では
無尽蔵 という360度評価ツールを提供しています。詳細にご興味がある方は、下記の関連リンクにある資料をご一読ください。また導入のハンドブックもご用意していますのでご参照ください。