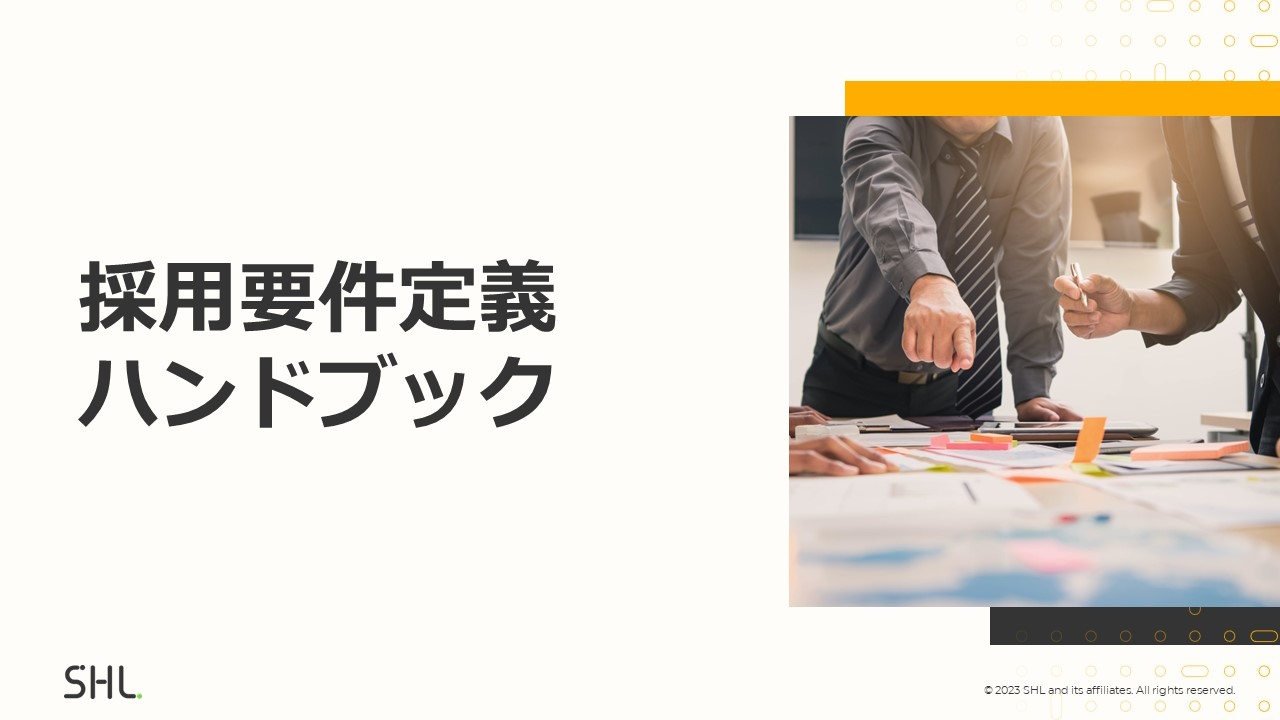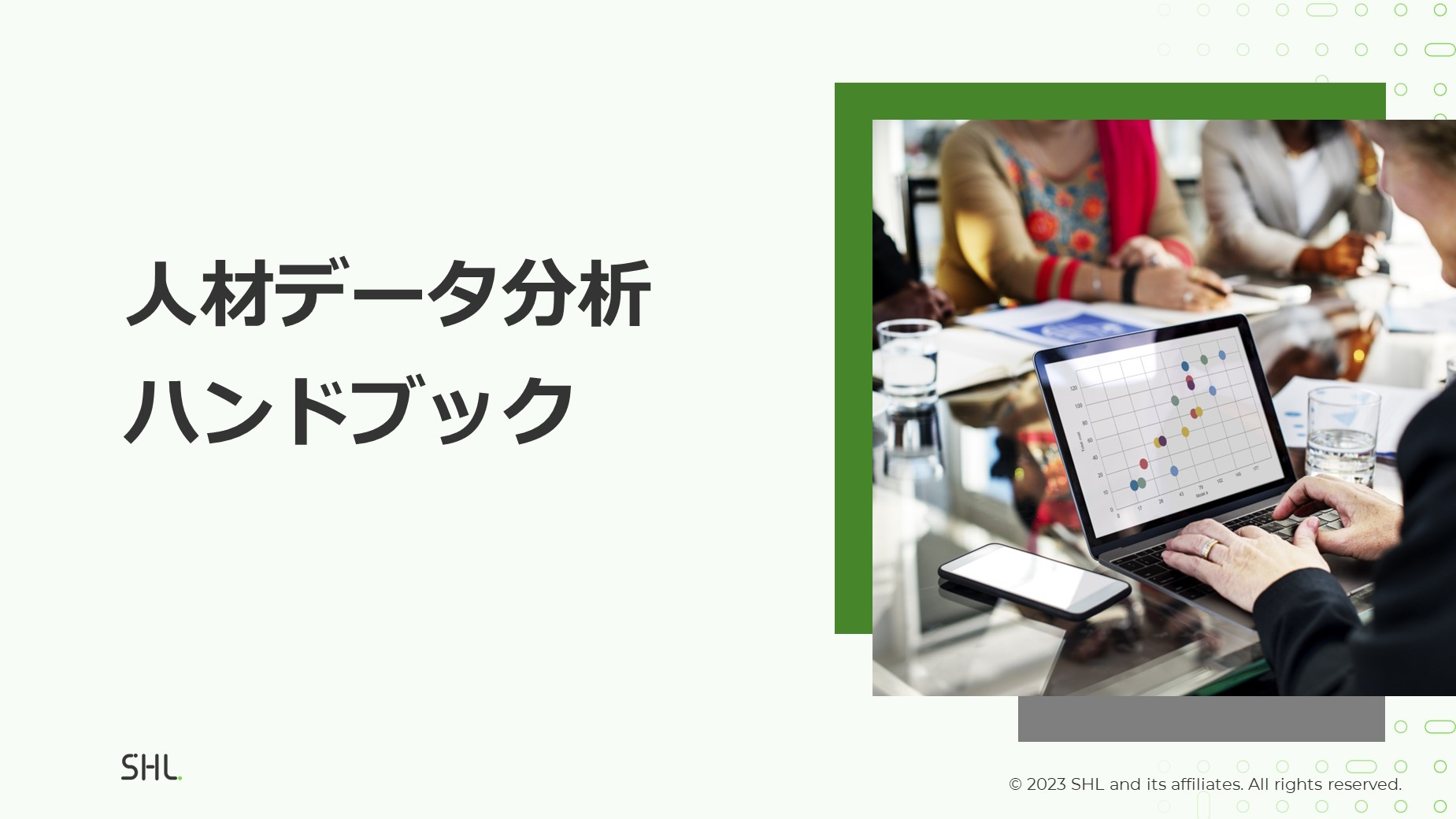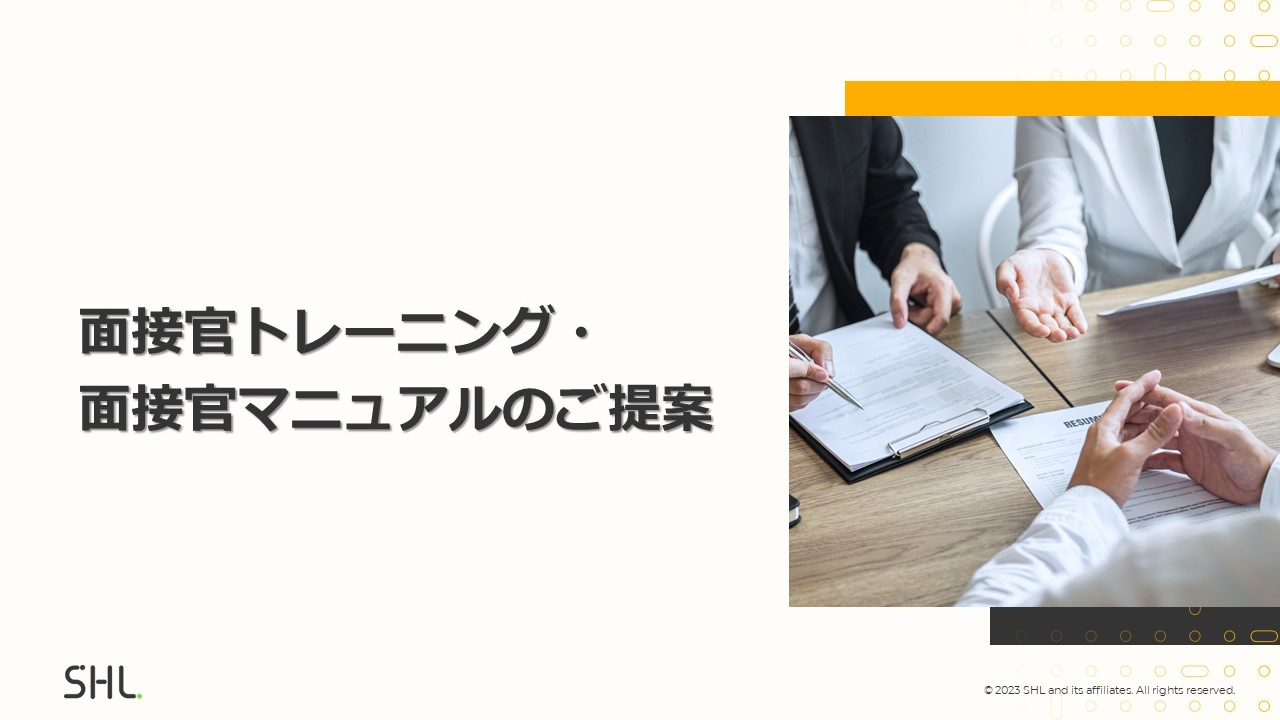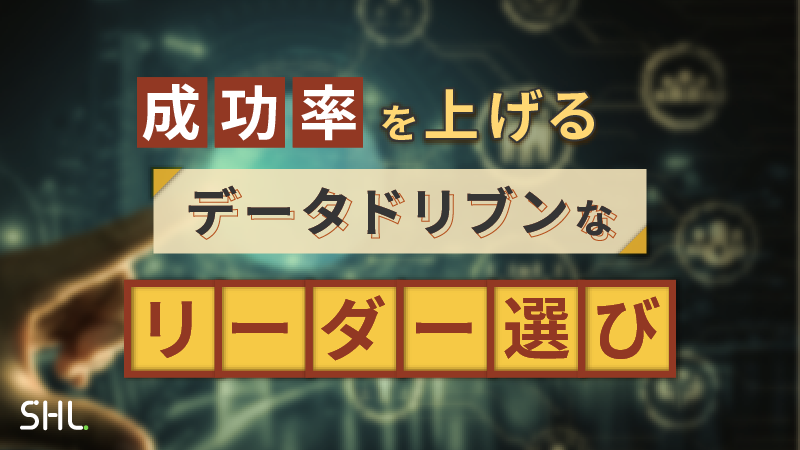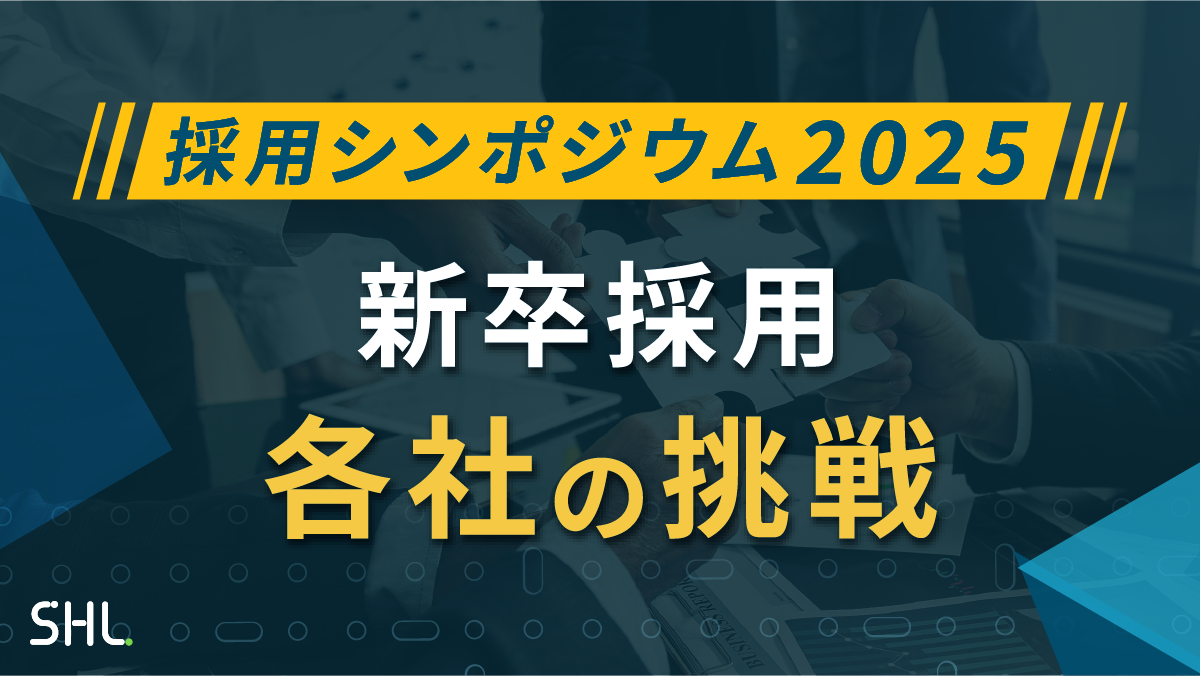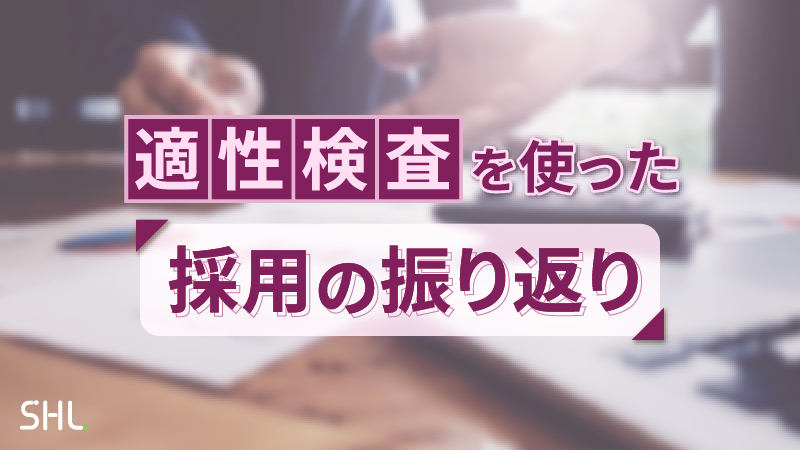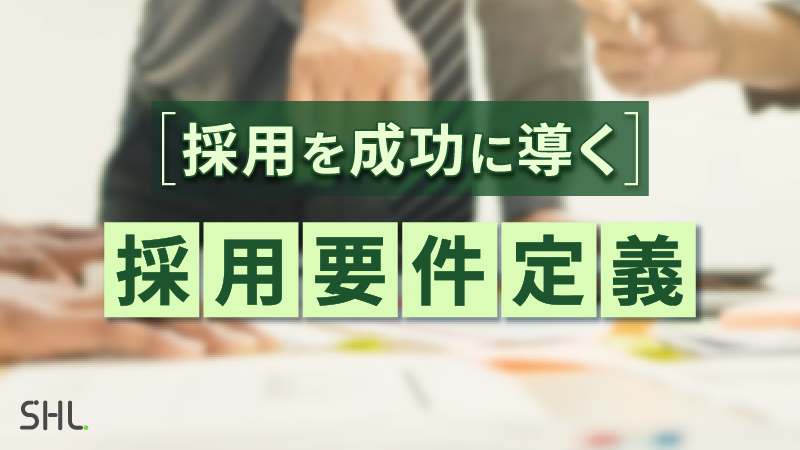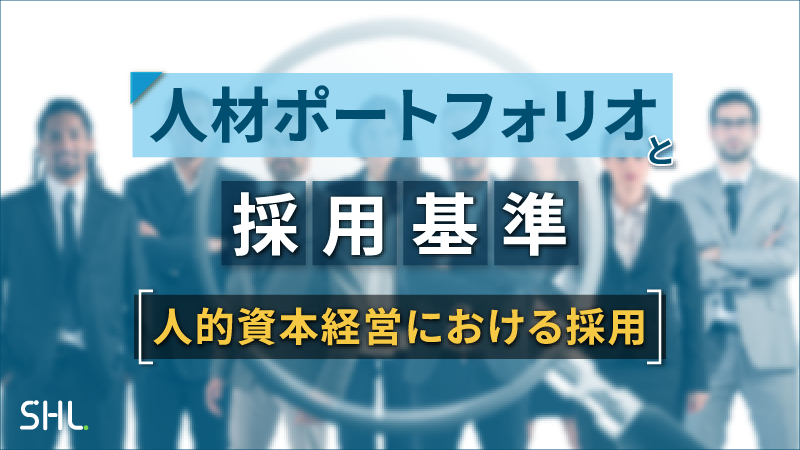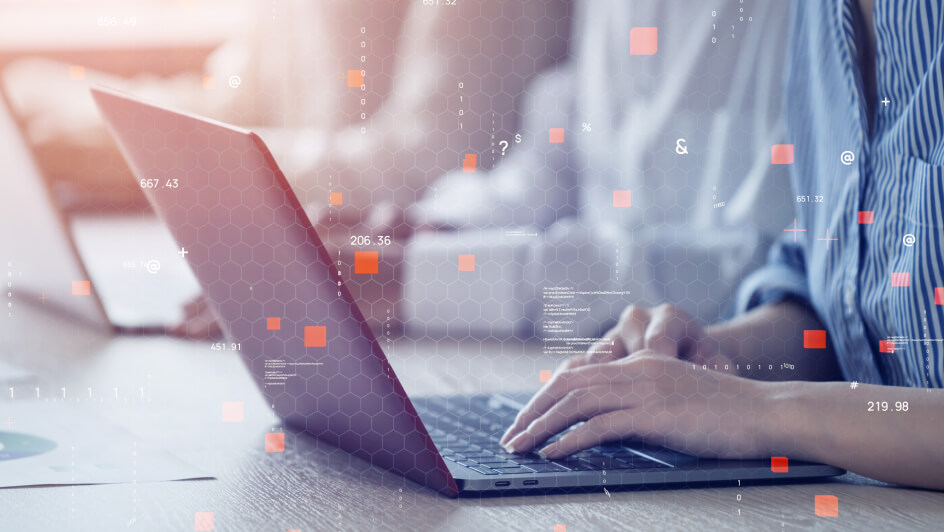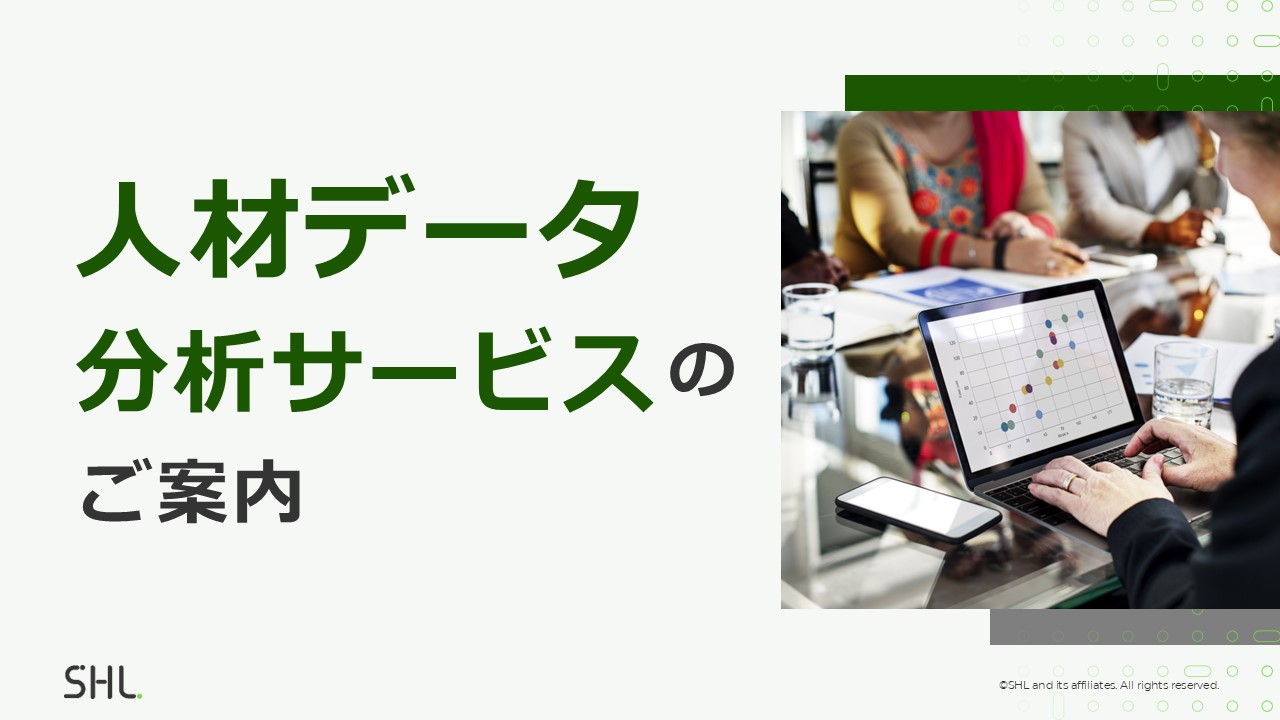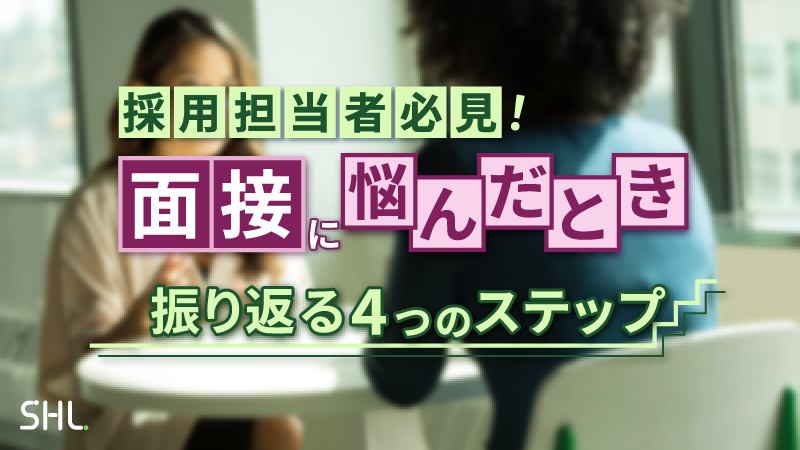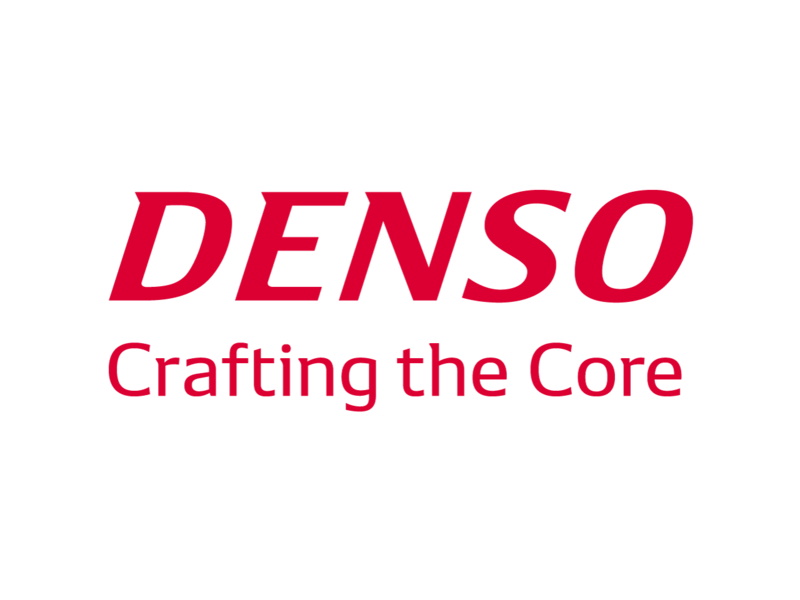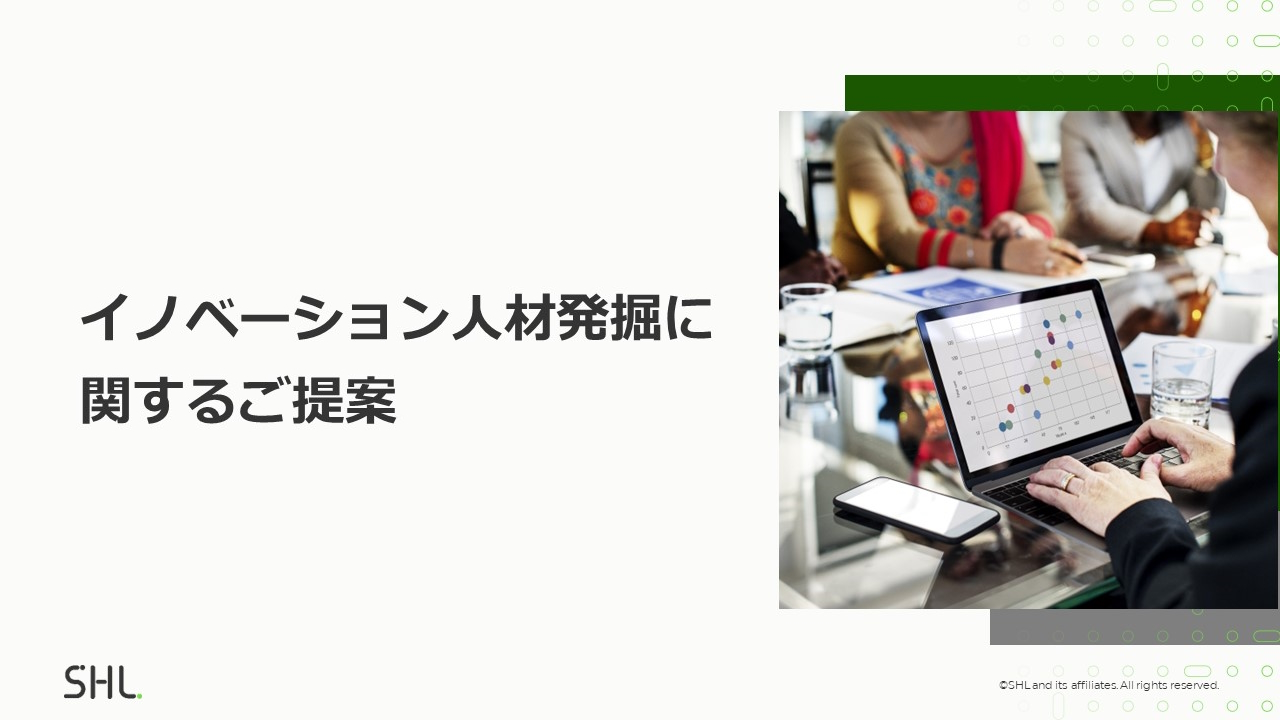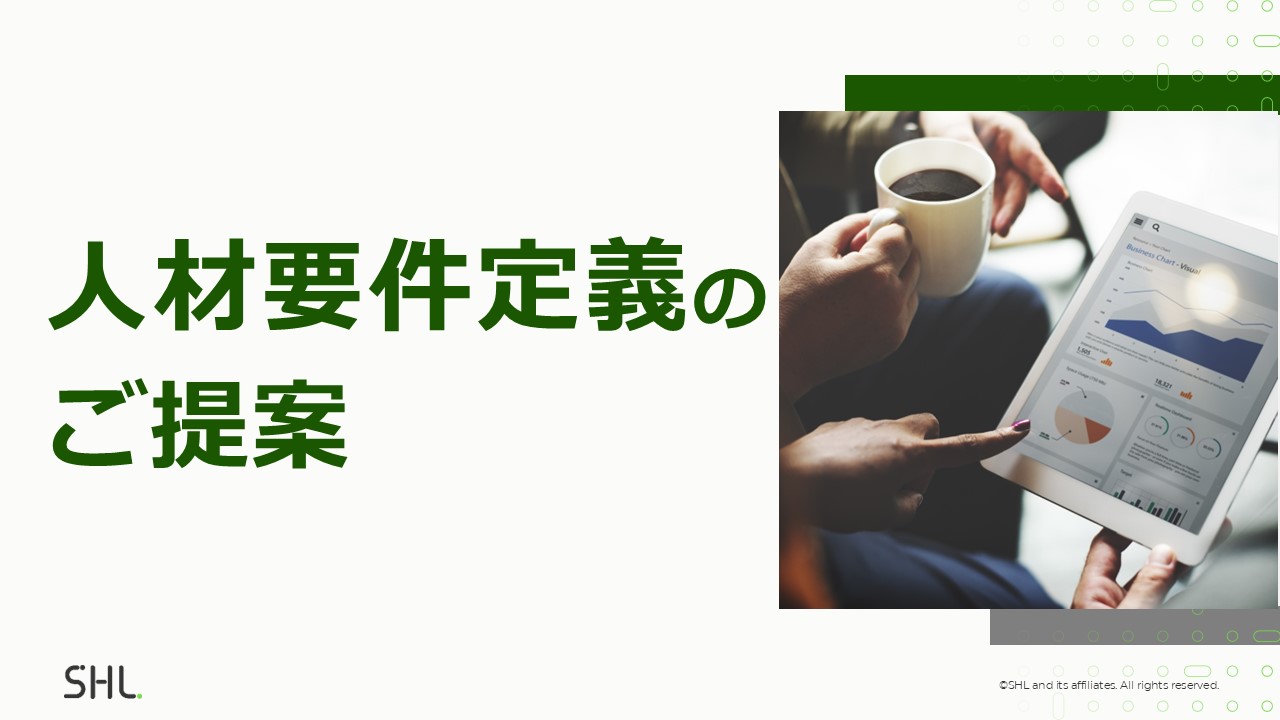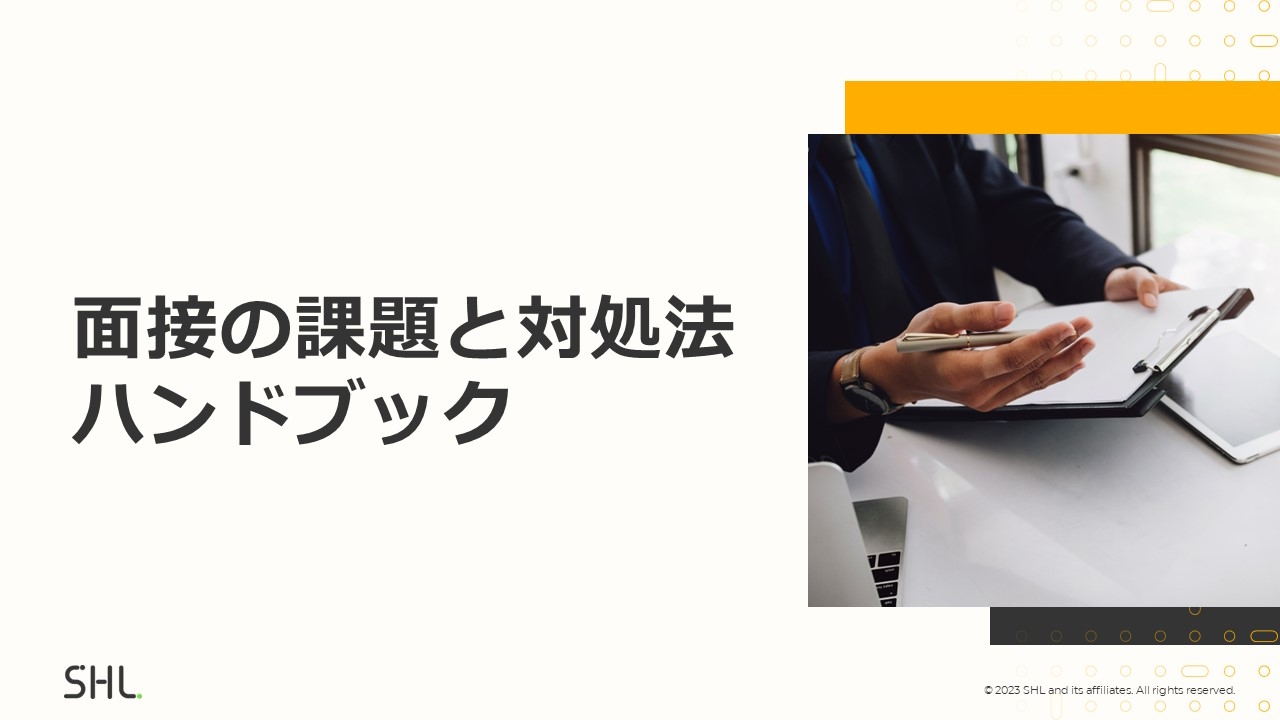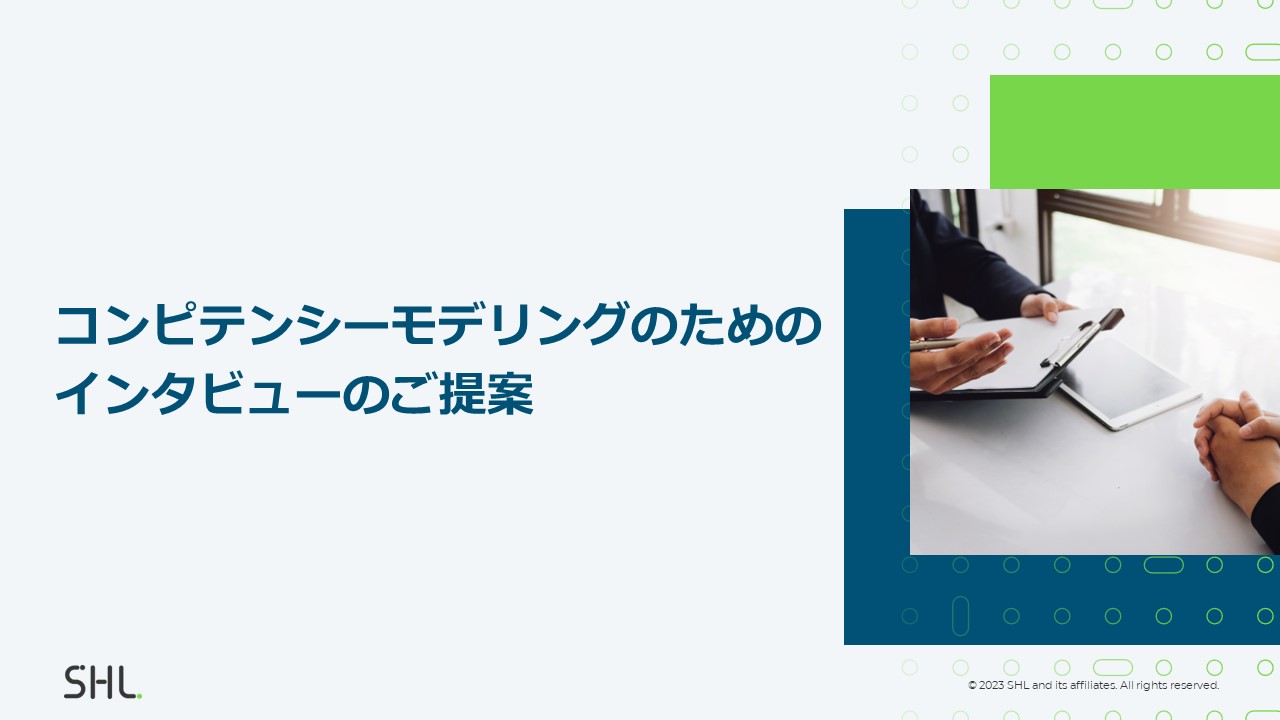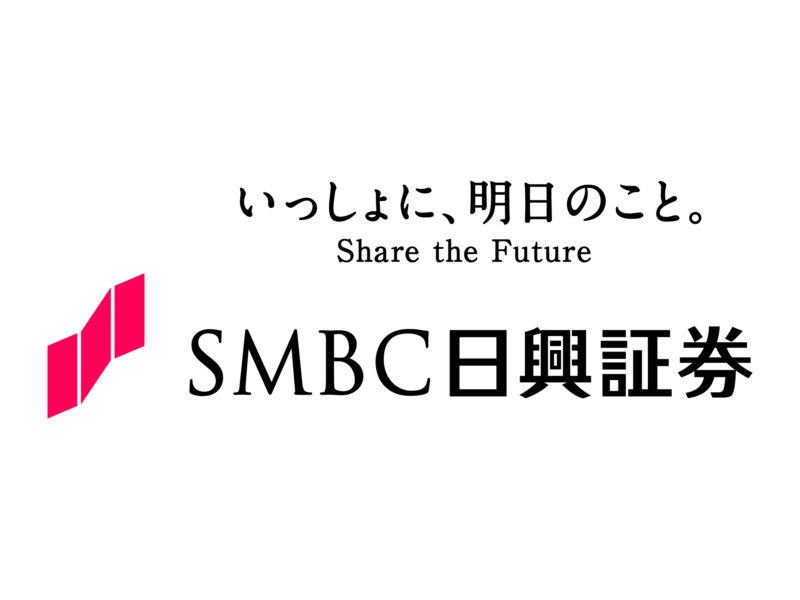安全運航を支える海のプロフェッショナル「海上職」の適性をデータから明らかにする、商船三井の取り組みをご紹介します。
※本取材は2021年6月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社商船三井
ドライバルク船事業、油送船事業、LNG船事業、海洋事業、自動車船事業、コンテナ船事業、港湾ロジスティクス事業、フェリー・内航RORO船事業などを含む総合外航海運業
海運業
1,119名(陸上794名 海上325名):他社への出向者等を除く(2021年3月31日現在)
※SMBC日興証券単体

インタビューを受けていただいた方
小林 裕美 様
株式会社商船三井
人事部 採用チームリーダー
インタビューの要約
明確な言葉で定義しづらかった海上職の適性を、データを使って見える化することに挑戦した。
現有海上職社員にパーソナリティ検査を実施し、協力者には万華鏡30を使って結果をフィードバック。若手から役員までほとんどの社員が協力してくれた。
社員の分析結果をもとに採用要件を決定すべくディスカッションを行った。スキルを重視する海上職において、行動特性の重要性を解釈するのに苦労した。
新しい採用要件について社内でコンセンサスを形成し、コンピテンシーを構造的に見極めるために選考手法を改良した。
今後取り組みたいことは、エンゲージメントの向上や乗り合わせの検討を含めた、海上職に対するタレントマネジメント。
誰も言葉にできない「海上職」の適性。 俗人的な判断ではなく、定量的なKPIを設けたい。
私は入社から約10年で営業部、一度目の人事部での採用・育成業務、シンガポール駐在などを経験しました。その後、自分の専門領域として人事の仕事にもう一度取り組むことを希望し、現在は採用と若手の育成に携わっています。今はHRBPなど、10年前とは違う戦略人事の概念が出てきて、経営に近いコアな部分の業務を担える可能性があるということを魅力に感じています。現場と経営をつなぐような立場が担えたらと思います。
採用と育成に加え、今取り組みたいのはタレントマネジメントです。当社はタレントマネジメントシステムを導入しており、配置における運用などは他のチームで検討していますが、私はタレマネシステムで管理されている評価・パフォーマンスデータと採用の人材要件をつなげることに着目しました。採用の人材要件を俗人的な判断ではなく「見える化」して、定量的なKPIを設けたい。これが今回の人材要件設計プロジェクトの始まりです。

最も課題だと感じたのは、事務系の人材要件を海上職にも適用していたこと。海上職は、6カ月間船に乗りっぱなしの非常に特殊な環境で職務を遂行します。しかし、その適性は誰も明確な言葉で説明できませんでした。職務が変われば、当然人材要件も異なるはずです。採用時点のアセスメントデータを活用しようにも、アセスメントツールをころころ変えていたためデータ蓄積がなく、効果測定ができない状態でした。海上職において、採用時点で見極めるべき指標をきちんとしたアセスメントデータを取得して作るべきではないかと思いました。
海上職社員にパーソナリティ検査を実施し、パフォーマンスとの関連を分析。 結果の解釈に議論を重ねる。
海上職の現有社員にパーソナリティ検査OPQを受検してもらい、そのデータをパフォーマンスと紐づけて統計分析にかけることにしました。「社員の傾向をもとに採用要件を作成するため、受検にご協力をお願いします。協力してくれた方には、ご自身の検査結果をフィードバックします。」と社内告知しました。参加は任意でしたが、若手社員から役員までほぼ受検してくれました。最初は反発を受けるのではないかと心配しましたが、特にネガティブな反応はありませんでした。
収集されたデータを日本エス・エイチ・エルに分析してもらいましたが、この結果を解釈するのが今回一番難しかったところ。なぜこのような結果が出るのか読み解かなければならないのですが、私は海上職ではないので確信がもてず、海上職の社員も日頃アセスメントデータを扱うことはありませんので、結果は受け止めていただいたものの、議論をするとなると難しい。もともと海上職はスキルを持っているということが非常に重要であり、行動特性への着目が進んでおらず、これがディスカッションを困難にした一因であったと思います。人材要件に落とし込むまで、何度も人事部内でディスカッションを重ねました。
結果を一部共有すると、海上職は陸上職に比べて、きちんとプランニングして手抜かりなく職務を遂行するというコンピテンシーがとても大事でした。パフォーマンスを発揮する海上職の方は、危険を予知して事前に準備しリスクを最小化するための努力ができます。これは行動的資質の部分が大きく、採用時点で行動特性としてみないと、安全運航で人命を支えている海上職においてはクリティカルな問題になると感じました。
新しい人材要件を見極められるように、採用選考を構造化。
新しい採用要件について社内でコンセンサスを形成した後、選考プロセスを改良しました。日本エス・エイチ・エルの協力のもと、新しい人材要件をエントリーシートの設問から面接での質問事項まで落とし込み、これをベースに面接官トレーニングを実施し、さらに評価のブレを抑制するため、誰でもセルフチェックができるような面接マニュアルを作成しました。これまでの面接は、業務内容を説明して覚悟を問うような場になっていましたが、より構造的に必要なコンピテンシーを見極める場とすべく努めました。今期の採用活動を終え、優秀な方を採用できたと認識していますが、最終的には実際の職務での活躍を見て、検討を続けていく必要があります。
将来的な目標は海上職のタレントマネジメントを行うことです。海上職は就労環境の特殊性から、安定した人材定着に繋がりにくい側面があります。上司のマネジメントによって左右される部分も大きいので、管理職の人材育成・能力開発をする必要があると思っています。また現在、継続的なエンゲージメント調査を行っており、誰が不調を抱えている可能性があるかを人事部がモニタリングしています。このエンゲージメントとパーソナリティの関連を今年検証する予定です。もしかしたら、コンピテンシーに関連する部分で、エンゲージメント低下の原因が見えるかもしれません。また、船での乗り合わせ(メンバーの組み合わせ)も大事です。メンバーが変われば、同じ仕事でもエンゲージメントが回復する場合もあるのです。タレントマネジメントにおける適正配置という概念になると思いますが、乗り合わせの検討にも適性検査が使えるといいですね。
日本エス・エイチ・エルの良いところは、適性検査の信頼性・妥当性の高さ。今回、海上職の採用テストとしていくつかのベンダーの適性検査を比較しました。採用で使用する適性検査には必ず社会的望ましさ(回答者が自分をよく見せようとするために回答がゆがむ効果)の問題が生じますが、自己相対化をさせるアセスメント形式が用途に合っていると感じます。また、担当コンサルタントによるサポートが手厚く、問題を整理する際の議論相手になってくれるため、感謝しています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング2課 課長
横山 武史
小林さんが陸上総合職(事務系)の採用のみならず、海上職の採用も担当することになり、このプロジェクトはスタートしました。陸上総合職(事務系)では採用選考におけるデータ活用が進んでおりましたが、海上職では人材要件が明文化されておらず、採用選考が体系化されていないことに、小林さんは問題意識を持たれていらっしゃいました。
海上職の適性を説明できる人がいないというお話しを伺い、OPQの社員受検とハイパフォーマー分析をご提案申し上げました。ハイパフォーマー分析の結果、陸上総合職とは異なる特徴を見つけ出すことができ、海上職の人材要件定義に貢献することができました。当プロジェクトでは要件定義を行ったうえで、採用選考へ落とし込むところまでサービス提供を行いました。
ここからは効果検証に入ります。当プロジェクトを通して海上職採用の改善が見られたという証明ができるまで責任をもって取り組みます。また、今後は商船三井の採用戦略の立案と遂行だけでなく、広くタレントマネジメントのお力になれるよう全力でサポートしてまいります。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

顧客や社会へ価値を提供するために、事業部主導で採用や育成を進めてきたメディアフォース。ビジネスの拡大に伴って生じた管理職不足などの人事課題に、全社的に取り組む人材開発プロジェクトが発足しました。本インタビューでは管理職の要件定義についてご紹介します。
※本取材は2023年3月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社メディアフォース
システムインテグレーションサービス、Webシステム構築、汎用系システム構築、インフラ構築
情報処理サービス
208名(2023年4月1日現在)

インタビューを受けていただいた方
家喜 章平 様 / 上村 潤 様
株式会社メディアフォース
取締役 執行役員 (写真左)
業務管理本部 総務人事グループ 課長 (写真右)
インタビューの要約
業界未経験者に自社の価値観を伝えプロとして育成する人材戦略であったが、ビジネスの拡大により管理職が不足。他の人事課題への対処も含め、全社横断の人材開発プロジェクトが発足。
現在活躍している管理職の特徴をデータ分析から導き、さらに今後のビジネスの変化に対応すべく社長や事業部門責任者へのインタビューを行って、管理職要件を定義。
管理職の要件を採用基準に反映して運用している。今後本格的に開始する経験者採用でも活用する予定。
管理職候補生の識別と抜擢、部門間の異動の要否など、今後タレントマネジメント施策を検討していく上で今回作成した要件や分析結果を活用していく。
事業の成長によって人材育成のスピードアップが喫緊の課題に。
当社が業界の未経験者を採用してきた理由は、顧客や社会に貢献する手段としてシステムを開発するという自社の価値観を体現できる人材を自らの手で育成したいからです。しかし、ビジネスが従来の受託開発からソリューション型へ変容する中で、人材育成をさらに加速し、事業成長のスピードに合わせる必要が出てきました。 人材育成を強化したくても管理職の数が足りず、管理職不足を補うことが喫緊の課題となりました。
当社は人事権が事業部にあり、基本的に配属や異動、キャリア形成は事業部の権限で行っています。そのため部門の垣根を超えた情報共有が不足していたり、育成の状況が十分に把握できないといった、人事制度の運用について全社を横断的に統制することが不十分な状態でした。これらの問題を解決するため、育成に限らず、採用や人事制度に関しても改善のスピードを高めるべく、責任者をおいてしっかり取り組んでいく全社的な人材開発プロジェクトをスタートさせました。

手始めに感覚で行っていることを定量化していこうと考えました。定量化しないと、言葉1つをとってもみんな捉え方が少し違います。例えば、「エネルギッシュな人が欲しい」など。人材に関する言葉を皆が同じ意味で用いることができるようにすることが必要だと考えました。そこで定量データを使用した管理職の人物像の明確化に取り組みました。投資に見合う価値があるのかという批判的な意見もありましたが、投資に見合う効果を得るためにやるべきだとの想いを伝え、納得してもらうことができました。
インタビューとデータ分析を用いて管理職の要件を定義。
ビジネスの変化にうまく適応し、活躍している管理職の特徴を、パーソナリティ検査OPQの結果を使用して分析しました。受検していただいたすべての管理職の方々には、自己理解を深めるために、結果をお返ししています。この分析の結果、大きな2つの事業領域において、管理職のタイプが明確に異なっていることが分かりました。感覚的なものが数値化され、客観的なデータで示されることで、納得感のある結果となりました。
ただ、この分析はあくまで現在の管理職を分析しているものであり、今後の事業戦略によって必要となる管理職像を見出すためのものではありません。そこで社長と事業責任者が今後の事業をどのように考えているかを尋ねるインタビューも実施しました。このインタビューから導き出された人材要件は、自分のこれまで持っていた感覚やイメージと全体的に合致していましたが、コンピテンシーとして適切に表現できていなかったと気付きました。特に「元気づけ」や「対人感受性」といった対人面のコンピテンシーが重要であることが明確になりました。これらのコンピテンシーが選ばれたのは、チームで働く際にはもちろん、顧客に接する際にも対人能力が重要だからです。システムを作ることは、どこまでいっても手段であり、本質は顧客との信頼関係にあるということがわかりました。
これら2つの手法から得られた結果を統合し、最終的に6つの要件に絞り込みました。
管理職の要件を採用活動に反映。経験者採用も開始予定。
定義された管理職の人材要件から採用基準を作り、採用選考に使用しています。採用ではWebCABを使用して、結果帳票から採用基準に照らして本人の強み弱みを把握し、面接で掘り下げて確認しています。悩ましいのは、基準を満たす人が限られてしまうことです。パーソナリティ検査と知的能力検査の結果を総合的に見ていますが、それぞれの検査結果において、どの水準をボーダーラインとすべきかについては、入社した社員の検査結果と業績の関係を調査したうえで慎重に検討しています。 また、部門によってシステムエンジニアの特性は異なり、求める人材も変わります。しかし、部門別ではなく一括に採用しているので、各部門の求める人材の平均値を採用することになり、焦点がぼやけてしまいます。もちろん会社に共通の部分もありますが、今回行った分析でも、2つの大きな事業部には異なるタイプの人が多いことがわかりましたので、どう採用し、どう配属するかについては今も試行錯誤しています。
今後は、これまで行っていなかったエンジニアの経験者採用も行います。今までの人材よりも早くコア人材に成長するので、管理職としての人材要件も採用時に確認していくことになります。

タレントマネジメント施策としては、今回作成した人材要件を基にポテンシャル情報を活用し、管理職候補として適任な人材を特定し、抜擢することを人材開発プロジェクトで進めていきます。これが実現すれば、部門間の異動の判断にも役立てることができます。
人事データの収集と可視化による投資効果は即効性があるものではありません。人事としては客観データを共通言語にディスカッションできることが大事だと考えています。月に1度、幹部の集まる会議で人事データを提示してディスカッションをしています。この取り組みが部門の垣根を超えたコミュニケーションを促進し、全社的な人事課題の解決につながることを期待しています。
日本エス・エイチ・エルは、データを収集し分析するだけでなく、その結果をどう解釈し、活用するかに対して積極的にコンサルティングを提供してくれます。その結果、私たちが抱えている問題について有用なアドバイスをもらえることがあります。また、私たちの気づかなかった視点やアイデアを提供してくれるので、重要なパートナーとして位置付けています。ディスカッションの機会をたくさん持ってくれる一方で、過剰にサービスを勧められることはありません。「なぜこんなに親身になってサポートしてくれるんだろうか」と話し合うほどです。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング1課
深津 寛
本プロジェクトが人材要件定義の事例の中で一段目を引くのは、以下の3つの要素を網羅している点にあります。
① 活躍者の人物像を、現在と未来とに分けて分析したこと。
② 活躍者のタイプは複数存在すると仮定したこと。
③ 定量的手法であるアセスメントデータ分析と、定性的手法であるインタビューとを組み合わせたこと。
活躍者を分析する上での、①「現在と未来」②「複数タイプ」という鋭い仮説は、当初からメディアフォースさまにお示し頂いていたものです。ここにアセスメントを専業とする日本エス・エイチ・エルの得意領域がクロスオーバーしたことで、非常に有意義な分析結果を得ることができました。
始動まで1年弱に渡って打ち合わせと検討を重ねましたが、いま改めて振りかえってみても、根底にある価値観は常に一致していたと感じます。
今回のプロジェクトに微力ながらも貢献できたことは大変光栄です。引き続き日本エス・エイチ・エルの専門性を活かして、メディアフォースさまの今後の課題に最善のサポートを提供してまいります。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例

新たな業態に挑戦する松屋フーズホールディングス。その立ち上げを担う人材をアセスメントを用いて選抜し、成功確率の高い人材配置の実現を目指す取り組みをご紹介します。
※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社 松屋フーズホールディングス
飲食事業を中心とするグループ会社の経営管理
小売業
1,613名 2020年(令和2年)3月期・連結

インタビューを受けていただいた方
別役 建治 様 / 一坂 正博 様
株式会社 松屋フーズホールディングス
人事部 人事グループ グループマネジャー(写真左)
人事部 人事グループ チーフマネジャー(写真右)
インタビューの要約
事業規模のさらなる拡大のために、牛めし・とんかつ事業に続く新業態の立ち上げに適性のある人材を社内で特定し、登用・育成する必要があった。
日本エス・エイチ・エルのアセスメントを用いて、これまで新業態を担ってきた少数の人材の特徴を特定。類似した人材を新業態に抜擢するなど、適材適所を効率的に行えるようになった。
今後のミッションは、新業態を担える人材の育成と、部分最適を乗り越えて適材適所を遂行していくこと。
牛めしととんかつに続く、新業態を担う人材を社内から探したい。
当社のようなチェーンストアビジネスは、ある勝ちパターンを作って脈々と回していくことが成功につながるという構造があります。その一方で、中期経営計画ではさらに大きく事業拡大させようという方針があり、牛めし事業ととんかつ事業だけではなく、新業態を展開できる人材を育てるという、いわゆる戦略人事の課題が降ってきました。従来の事業は、同じタイプの人材を採用して育成すればうまくいきました。しかし、新業態を担える人材を社内で探すと、毎回同じ数名の人にしか白羽の矢が立ちません。この人たちの予備軍を作らなければ、中期経営計画に示された大きな事業の拡大は実現できないと考えました。
この人たちはどんな人なのか?社内に予備軍はどれだけいるのだろうか?と考えたときに、実は人材に関するデータがないことに気づきました。昇格試験などで会った時の印象しかない。どこかに隠れた人材がいるのか、いないのかもわからない。それで、新業態に適した人材を、タレントアセスメントを使って探すことにしました。

当社の店長については、本部が決めたことを正確に行えるかどうかが評価基準でしたし、サービスの均一化や徹底力が当社の強みでもありました。一方、新事業は試行錯誤の連続であり、常に臨機応変な対応が求められます。これまでは新事業に適した人材を発掘し、育成しようという発想はあまりありませんでした。しかし今後は、戦略人事として新事業人材の発掘と育成を積極的に行わなくてはならないと経営に提案しました。
OPQを用いて、新業態やその他ポジションへの適性を把握。
アセスメントツールとして、なるべく回答時間が短いもの、コストを抑えられるもので、精度が高いものを探しました。他社の商品もいくつか検討しましたが、やはりコストや所要時間の関係で難しく、結果的にSHLのOPQにたどり着き、これなら採用時にも使っているし汎用性もある、一石二鳥じゃないかということで導入を決めました。
アセスメント結果データを分析すると、新業態を担ってきた社員はロジカルな人たちであることがわかりました。分析結果を見るまでは、感覚派の人たちだと思っていましたので予想外の結果でした。今では、彼らと似たアセスメントの結果を示す社員を、新業態の担当に選んでいます。
新業態以外にも、今は10か所くらいのポジションで、良い人いないかというオファーを貰ったら、成功する人材モデルをもとに、類似した人材を推薦しています。今後は、さらにアセスメント結果を分析して成功確率を上げていくというのが、我々のミッションです。

請負型の人事ではなく「攻めの人事」へ。
ジョブローテーションにおける人材を提案する際も、日本エス・エイチ・エルのアセスメントの結果は納得性の高い情報となってます。本人を知っている場合、結果を見て「ああ確かにな」と、よく思うんですよね。客観的な数字をもって候補者を提案することで説得力を高めています。
従来は、知っている人しか推薦できませんでした。このやり方では知らない人にはチャンスがありません。アセスメントを使うことで、チャンスが公平に行き渡るようになりましたし、異動の成功確率も上がり、適材適所がやりやすくなりました。しかも客観的であり、恣意的でない。これは重要です。人事異動を客観的に行うことが、他の人事施策についても客観的に行うというメッセージにもなります。
特定のポストに対する候補者を見出すときにもアセスメントは重要です。アセスメント結果があることで人事が積極的にしかけていくことができます。新業態の人材選抜は「攻めの人事」だと思います。

日本エス・エイチ・エルのいいところは、担当者が熱心に、細かく要望を聞いてくれるところ。考えがまとまらなくてモヤモヤしていても整理してくれます。提案内容にしても、クライアントの話をよく聞き、クライアントのことを考えて作っているのが伝わります。こちらはストレスなく進められます。
今後のミッションは、新業態を早く立ち上げられる人材を育てていくこととマネジメントのレベルアップ。加えて部分最適になっている組織をどう全体最適にしていくかが課題です。部門は優秀な人を抱え込みたがります。5年後のために今は我慢してくださいと部長を説得します。
個人的なミッションは、社員個人のモチベーションを引き上げて幸せを感じてもらうこと。個人個人のモチベーションリソース(意欲源)は色々あると思うので、それを気づかせて、実現の力になりたいです。本人もうれしいしお客さんもうれしい、結果として会社もうれしい、そういう環境を作りたいですね。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
太田 啓
別役さんから「新業態に適性のある人材を発掘したい」とご相談をいただいてから、何度も意見交換を重ね今回のプロジェクトに至りました。お打合せの間、常に意識していたのは別役さんのビジョンを正しく理解することでした。
松屋フーズホールディングスは長年弊社のアセスメントをご利用いただいており、過去にも優秀店長の傾向分析を実施しておりましたが、これほど大規模なアセスメントデータの分析は初めての取り組みでした。松屋フーズホールディングスの成長戦略に影響をおよぼす本プロジェクトに携わることができて大変光栄です。
今後は、選抜された新業態人材の育成、全社適正配置の実現、本プロジェクトの効果検証でお役に立てるよう微力を尽くす所存でございます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

日本市場で急速な成長をとげた、ホットヨガスタジオ事業のLAVA International。
組織の急拡大に伴う人事課題にどのように取り組んだのか、そのタレントマネジメント事例を紹介します。
※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社LAVA International
ヨガスタジオの運営、ヨガインストラクター養成スクール等の運営、ヨガウェアブランドの展開、ヨガイベントの運営
サービス業
グループ全体 5,877人(正社員4,256名、アルバイト1,621名)※2019年8月末現在
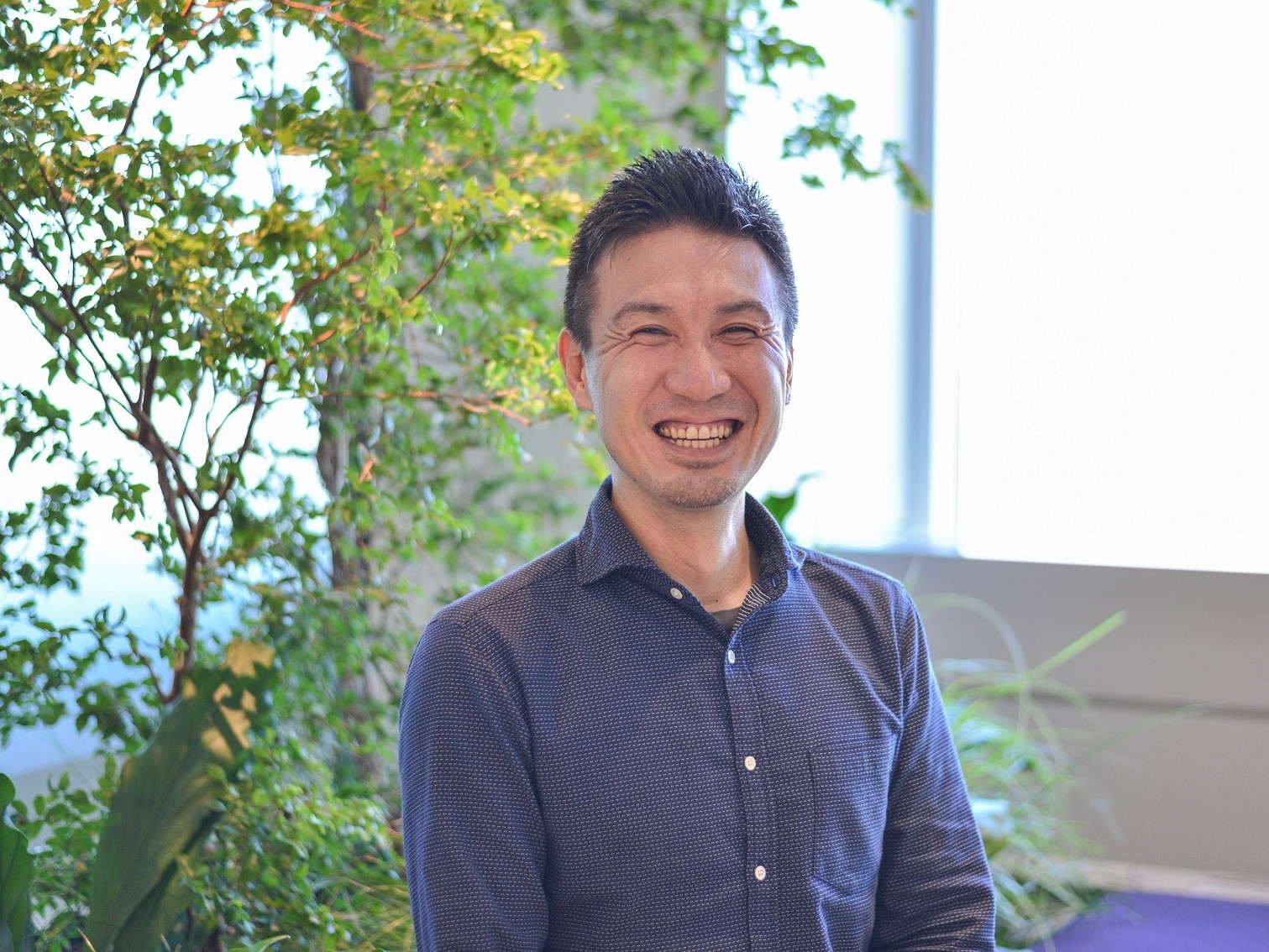
インタビューを受けていただいた方
的場 勝己 様
株式会社LAVA International
運営部 部長
インタビューの要約
急拡大に伴う大量採用が求められる中、採用数よりも採用の質を担保する必要性を感じ、入社後のパフォーマンスを予測できるアセスメントを探し始めた。
部長以下の全社員に日本エス・エイチ・エルの適性検査を実施し、データ分析を行った。インストラクター、店長職、SV職、本部系企画職の適性がそれぞれ明らかになった。
採用のフローにアセスメントを組み込み、質の高い採用活動が可能となった。また、インストラクターから本部系企画職へのキャリアチェンジにもアセスメントを導入し、適性に沿った異動が可能となった。また、社内にアセスメントの用語が徐々に浸透し、人材の能力や特徴を表現するための共通言語ができた。
ギリギリ合格した人材の中に、光る逸材がいる。 それがパフォーマンス分析に目を付けたきっかけ。
今の立場は、店舗運営の責任者ですが、日本エス・エイチ・エルのアセスメントを導入した当時は、人材開発部の採用グループのグループ長でした。大量採用のさなか、私の問題意識は、採用数を確保することも大事なのですが、今の採用は成功しているのか否かを、入社後のパフォーマンスで示すべきではないか、ということでした。
このような問題意識を持ったきっかけは、いくつかあります。私自身のキャリアは営業畑が多く、結果がすべて数字でわかる世界です。採用の結果は採用数はもちろんわかりますが、もっと違う形で採用の成果を表したかったというのがまず一つ。もう一つは、採用と教育、現場の立場の相違です。採用と育成は、育成がうまくいかないケースに対し、「なぜこの学生を採用したんですか」と葛藤が起こります。教育と現場は、現場でスムーズに業務が行えなかった場合に、「なぜこの状態で送り出したんですか」と、また葛藤が起こります。このような構造を解消するために、現場でのパフォーマンスをベースとして、こういう理由で採用したのだという根拠を出発点に持ちたかったのです。そのために、採用の視点と現場でのパフォーマンスに相関があることを示す必要がありました。

もう一つ加えて言うと、大量採用で採用数を確保する必要があったので、ギリギリで受からせた人たちがその後どうなったのかを知りたくて、最終面接評価C-で合格した人材を、自分で追跡調査してみました。その結果、C-で合格した人材は、早期離職はたしかに多かった。でも、入社後パフォーマンスが高い人材の出現率も、C-が多かったのです。このような興味深い結果が表れたことも、パフォーマンス分析に踏み出したきっかけになりました。
選んだポイントはわかりやすさと汎用性、そして「当たっている」ということ。
「採用時のアセスメント結果と入社後のパフォーマンスとの相関をはっきりさせて、より質の高い採用をしたいので、そのための提案をください」と、6,7社くらいにお声がけしました。日本エス・エイチ・エルを選んだのは、最終アウトプットを自分たちがどう使っていくのかイメージしたときに、一番わかりやすかったから。あとは、「今回は入社後のパフォーマンスとの相関を分析するつもりだが、いずれは役職への登用や、本部系の企画職へのキャリアチェンジなどにも使っていきたい。その分析も可能か?」と聞いたら、ことごとくできると言っていただいたので。社員のアセスメントは何かを知りたいというたびに実施するものではないと思うので、一度の実施で色々な活用ができることは大きなメリットでした。
最後の理由は、導入前にモニターとして社員が受検した結果が、本人の特徴を正しく説明していて、役員が感動したからです。「本当だね、この子そうだよね」と。最初はインストラクター採用のためとしか考えていなかったのが、この最終決定に至る過程で上層部に見てもらった時に、これは面白いねとなって、部長以下全員に受検してもらう流れとなりました。
見えてきた各職種への適性をもとに、効率的な採用・異動を実現。
社員のアセスメントデータを分析した結果、インストラクターに必要な特徴に加え、店長職やSV職に求められる特徴、そして本部企画職に求められる特徴がわかりました。店長職やSV職には、インストラクターの資質に加えて求められる資質があり、また本部企画職の適性は、インストラクターの適性とは一部相反することなどがわかりました。
その結果を受けて、採用ではかならずアセスメントを実施して、面接官と見方を共有して評価に使いました。また、インストラクターから本部系職種へのキャリアチェンジの際も、実施して見極めに使うようにしました。インストラクターと本部系職種は、業務内容がまったく異なりますので、アセスメントをして面接してみると、現場よりも本部に適性のある方もいたりします。そういう方を発見できる喜びもあります。
さらに、社内で実施している360度評価の結果を、さらに詳細に解釈する際にも、このアセスメントを組み合わせて使っています。360度評価は、あくまである人の視点なので、時期やペアリングの影響も受けますし、完全に鵜呑みにすべきではないと思っています。本人のアセスメントの結果も併せて参照し、なぜこのような360度評価の結果になったのか、というのを深く理解しようとしています。人には多かれ少なかれ多面性があって、何かきっかけがあれば誰でも異なる側面が出てくるものなので、なるべく客観的な視点をもつよう努力しています。

社内の人材を表す共通言語ができた。
採用や異動を効率的に行えるようになったということのほかに、アセスメントを入れてよかったことは、社員の特徴を的確に表す共通言語ができたことです。実際にアセスメントの結果を目の前にするのは人事系の役職者だけですが、彼らが各部門に対してもアセスメントに使われている用語を使って、採用や育成について話します。アセスメントに使われている表現が社内に浸透すると、他の社員のことを評価するときにその表現で話すので、社内にいる人のコンピテンシーを表すのに共通言語ができます。たとえば、プレッシャーへの耐力がある、というのが正確な表現だとして、それを単に「メンタルが強い」などと表現してしまうと、少し意味があいまいになってしまう。そういう共通言語ができることも、いい人材マネジメントにつながるのかなと思います。
今後の人事施策については二つあります。まず新しく着任した人材開発部長の言葉を借りると、「採用に際して、インストラクターを採るのではなく、全体を対象に利益創出ができる人材をとる」。インストラクターがゴールと見えないような入社後の広がりを感じる採用活動をすることで、良い店長が排出されるようにしたいです。女性が多い会社ですので、妊娠・出産・復帰のサイクルがあることを考えると、もっと役職者を輩出するペースを上げるべきですし、入社当時から自然とキャリアアップを目指したくなる採用をしたいというのは、まさにその通りだなと思います。
もう一つ、私の現在の役割である運営部の目線で言うと、採用を担当していたときから実施したかった、アセスメントを用いた配置や昇進は、まだまだ活用できる余地があると思いますので、今後は運営部でさらに力を入れていきたいと思います。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
下越 千尋
社員の方々のアセスメントデータ分析結果を報告した際、その結果を裏付ける具体的なエピソードや意見が的場さんや役員の方から出てきて、活発なディスカッションとなったのが印象的でした。お客様の持つ仮説がデータによって検証され、それが具体的な言葉や数字となって共通認識された瞬間でした。分析結果を深く理解されようと、実際の現場で起きていることや既存の情報などを組み合わせて多角的に判断しようとされている点は、私自身勉強をさせていただいたことも多かったです。また、私どもが提供するアセスメントツールが現在も社内のコミュニケーションの道具となって活用されていることも、お客様の組織の発展に寄与できているという私たちの自信と誇りにつながっています。お客様がこのツールから得られる知見がより価値の高いものになるよう、引き続き支援させていただきたいと思っています。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例

「くもんの先生」の特徴を、アセスメントデータで分析。学力を計る採用テストから、くもんの先生としての活躍の可能性を見極める採用へと舵を切った、公文教育研究会の取り組みをご紹介します。
※本取材は2021年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社公文教育研究会
算数・数学、英語、国語(母国語)、フランス語、ドイツ語、日本語、書写、学習療法などのフランチャイザーとしての教材の研究開発、制作、指導法の研究、ならびに教室の設置・運営管理。児童書、絵本などの出版および教具、知育玩具など教育関連商品の開発ならびに販売。
教育業
KUMONグループ全体 4,091人(2021年3月現在)

インタビューを受けていただいた方
清原 久嗣 様 / 出口 恵子 様
株式会社公文教育研究会
教室ネットワーク推進部 リクルート・育成サポートチーム(写真左)
教室ネットワーク推進部 リクルート・育成サポートチーム(写真右)
インタビューの要約
コロナ禍で「くもんの先生」の採用活動をオンライン化することをきっかけに、「くもんの先生」としての活躍の可能性をより明確に把握できるよう、従来の採用テストの内容を見直した。
活躍するくもんの先生の人物像について社内のヒアリングを実施。実際の業務と紐づけてイメージできるよう面接サポートツールを整えた。
これまで利用していたテストを変更することに現場(以後、事務局)の担当者は戸惑いも少なくなかった。事務局へフィードバックするため、まずはモニターとして一部事務局で先行実施。「使ってみたら良かった」の声を各事務局に広げていった。
実施の結果、面接が行いやすくなった、教室開設後のサポートまでイメージできるようになった等、前向きな声を得ることができた。今後の展望は、運用面の継続的な改善と、先生の開設後のサポートに活用すること。
コロナ禍で「くもんの先生」採用をオンライン化。
これをきっかけに、現行の採用テストを見直す。
私たちの業務は、「くもんの先生」の募集、採用サポートです。面接は全国にある事務局で行いますが、私たちは募集の施策立案や、説明会に使うパンフレットや動画の作成、面接に用いるツールの案内等、採用業務のサポートをしています。
コロナ禍をきっかけに、これまで紙で実施していた「くもんの先生」の採用テストをオンライン化することを検討しました。従来のテストは来社が難しい方への利便性が低く、また面接後同日に実施するためテストの結果を面接に活用できないという点がありました。
また、学力を中心に測るものでしたが、テストのオンライン化をきっかけに、より応募者の強みや業務遂行能力を把握し、教室開設後のサポートにも、よりつなげていきたいと考えました。
「くもんの先生」としての活躍の可能性は学力だけでは測れない。
くもんの先生の特徴をアセスメントデータで分析するとともに、 社内ヒアリングを実施。
私たちはまず、すでに教室を開設している「くもんの先生」へのモニターテスト受検を実施し、それと同時に、社内のヒアリングによりくもんの先生としての活躍のイメージを改めて明文化し、これをパーソナリティ検査の結果と紐づけていきました。
データ分析によって見出された結果を、「活躍のイメージ」と結びつけ、先生の実際の業務内容に結びつけていくのに時間がかかったのですが、ここがイメージしづらくては実際のサポートに活用できないと考え、丁寧に検討をしました。
その後は、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントに協力いただき、この適性テストを面接の中でどのように活かすか、というツールを作成したり、仕組みを整えていきました。

採用のテストの変更には戸惑いの声も。
本格実施の前にモニター運用し、 「使ってみたら良かった」の声を集めていった。
一方で、数十年にわたり使用してきた従来の採用テストを変えることに事務局の担当者からは戸惑いの声がありました。私たちは、そのような戸惑いの声に対して、より「くもんの先生としての活躍の可能性」を見極め、開設後のサポートにもつなげていくためにも、学力を測るテストから今回の適性テストに変えることにした理由を伝え続けてきました。
テストの運用について事務局からのフィードバックを受けるため、全国リリースの前に、一部の事務局で実際の応募者に対しモニター実施を行いました。すると、事務局の担当者から良い反応がたくさん得られたのです。モニターの事務局の担当者から、「実施してみたらよかったですよ!」と、これから使用する事務局にも伝えてもらいました。私たちが伝えるだけでなく、実際に応募者に使用した声を伝えていくことで、これから使う方にも具体的なイメージを持ってもらえることを実感しました。
まだ全国展開したばかりなので、全体での効果検証はこれからですが、先行実施を進めてきた事務局の担当者からは、事前のwebテストの実施で、より応募者の強みを深堀りできるようになったという声を多くもらっています。また、質問内容が明確になったという声、開設後のサポートをよりイメージしやすくなったという声もありました。さらにオンライン化したことで、応募者の方が参加しやすくなった、という効果もありました。
今後実施したいことは、webテスト運用状況の把握と改善、テスト結果を開設後のサポートに活用するための情報提供、採用時に把握した応募者の強みを教室開設のマッチングに生かすことです。今後の分析次第でより強みを生かし、より可能性を発揮できると思っています。
日本エス・エイチ・エルの良いところは、当社のこだわりや大事にしている部分を理解しようと努力してくださるところです。価値観を共有しながらプロジェクトを進められたので、本当にありがたいと思っています。また、これまで感覚でしか描けなかった人材像をデータで表せるということに手ごたえを感じました。これからの分析もお付き合いいただければと思います。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
仲家 可帆
今回のプロジェクトは、くもんの先生採用テストのオンライン化に伴い、くもんの先生としてのパフォーマンスを予測することのできるテストに変更したいというご相談をいただいたことからはじまりました。当初はテストのみのご提案でしたが、データ分析結果を基に採用基準や選考内容全体の見直しについてもご支援させていただき、私自身もやりがいを感じるプロジェクトでした。
「これまで長くやってきた方法だから」「この方法に慣れているから」という理由でやり方を変えない選択をされる方も多い中で、今回数十年やってきた採用テストや選考内容を変えることは相当大変なことであったかと存じます。ですが、今回のプロジェクトを実施したことによってくもんの先生として適性のある人材が今までよりも多く採用され、より多くの子ども達の学力向上につながると思っております。
くもん教室の発展や先生方のやりがいへの貢献のため、引き続きご支援させていただきます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例

職種別採用への移行をきっかけに、職種ごとの採用基準を策定。
コロナ禍で効率的にオンライン選考を行う日立ビルシステムの取り組みを紹介します。
※本取材は2021年1月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社日立ビルシステム
1.エレベーター、エスカレーター、空調装置、電気設備、 その他ビル設備に必要な機器の製造、販売、据付、保守、改造修理、更新及び設計
2.各種ビル設備の監視、制御並びにビル管理
3.冷凍空調装置並びにそれらの運転制御盤、遠隔監視装置、冷媒回収装置の製造 など
建設業
約8,500名(2020年3月時点)

インタビューを受けていただいた方
北上誉之 様
株式会社日立ビルシステム
人事総務本部 人事企画部 採用・教育グループ 部長代理
インタビューの要約
職種別採用への移行をきっかけに、採用基準の明確化が課題に。社員受検データの分析と、管理職層へのアンケート調査によって、職種ごとの採用基準を策定した。
くしくもコロナ禍でオンライン選考へと全面移行。採用基準を策定しておいたことで有効なスクリーニングが可能に。またオンライン面接での情報不足をアセスメント結果の解釈によって補えた。
今後はチーム編成や、価値観をもとにした配属・任命によるエンゲージメント向上、またテレワークによる協働を円滑にするために、人材データを活用したい。
完全職種別採用に移行したことで、採用基準の策定をスタート。
私は2019年6月から採用業務に携わることになりました。すでに採用活動のピークは過ぎていましたので、次の21卒採用から本格的に参画する覚悟を決めていたところ、新型コロナウイルス感染症が蔓延。さらに未経験の要素が加わり、21卒採用は苦労しました。
日本エス・エイチ・エルには採用基準の設計を手伝ってもらいました。それは20卒採用から完全職種別採用を始めたことからでした。それまでは総合職事務系・技術系をそれぞれ一括で採用し、入社した後に面接で配属先を決定していました。職種別採用に切り替えたことで、どういう人材がその職場・その職種に必要なのかという明確な基準がなく、面接官の主観に頼った判断をしているという問題が浮き彫りになりました。実際に、私が採用業務に携わる中で、初期選考で高い評価を得た学生が最終選考で低い評価となったり、その逆もしかりで、採用プロセスを通して評価に一貫性がないと感じることがありました。会社がさらに成長していくためにはそれぞれの職種に適した人材の確保が大事だというところから、職種別にどういう人材を採用すべきか採用基準を策定することになりました。

また、適性検査は長く利用していますが、面接官がパーソナリティ検査の結果などの事前情報を活かしきれていないという課題もありました。私も事業所総務を担当していた頃に面接官として対応したことがありますが、通常業務を行う中でたくさんの事前資料を見る時間が十分に確保できないというのが正直なところで、それを見ることの重要性を理解していませんでした。面接官に事前情報の重要性を訴えるには、内容や職務との関連性を明確に説明する必要がありました。
社員データ分析とアンケート調査の両面で、採用基準を策定。
採用基準の設計は、まず対象職種の社員にアセスメント(パーソナリティ検査OPQ)を受検してもらい、全体的な社員の特徴と、その中でも特に高いパフォーマンスを出している社員の特徴を統計分析で明らかにしました。また、職種ごとに求める人材像を明らかにするためのアンケート調査を、別途経営幹部や管理職や要職者に実施しました。一般的に、高いパフォーマンスを示す人の割合は多くはないので、少ない対象者で特徴が見いだせるのか不安はありました。
事前にしっかりと主旨をご理解いただいたため、取り組みには社内の協力を得ることができました。アセスメントに協力いただいた社員には、フィードバック用の帳票を返却しました。また面接官には、日本エス・エイチ・エルの担当者に結果解釈のための説明会をしてもらったところ、皆さんご自身の結果に関心を持ってご覧いただけたと感じました。年齢を重ねるとアセスメントを受ける機会も少なくなるので、あらためて自己分析結果を目にすることの新鮮さをお話しされていましたね。
職種ごとの要件と、全社共通の人材要件が見えてきた。
社員分析の結果について、職種ごとにハイパフォーマーの特徴もみられましたが、一番納得したのは、社員の全体傾向として「問題解決力」と「オーガナイズ能力」が高いということ。これは社風の影響です。基幹事業の一つであるエレベーター・エスカレーターのメンテナンス事業では、様々な情報を組み合わせて問題の原因を特定し、お客様の納期に合わせて限られた時間で計画的に作業を進めることが重要になります。この認識が社員に浸透していたため、このような特徴が現れたのだと思いました。面接官からは別の要素も重要だというコメントもありましたが、客観的に社員の共通性を示せたことは、面接官の間での評価差を解消するのに役立ちました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、オンライン面接へ全面移行。
スクリーニング基準が整備されていたことが功を奏した。
21卒採用から一次の集団面接をやめて、書類選考に切り替え、エントリーシートと適性検査の結果で応募者の絞り込み、一次面接と最終面接を経て、合否判定を行うプロセスへと改定を計画していたところ、くしくも、新型コロナウイルス感染症の影響で、選考方法(オンライン面接)や時期への大幅な修正が必要になり、採用基準を策定しておいたことが功を奏しました。採用基準のおかげで、書類の合否判定と次の選考への参加順を客観的に決めることができました。共通要件がボーダーライン上のグループから、各職種要件を持つ人を優先に面接へと進めるなどの細かい調整ができてよかったです。また、今まで検査結果を活用しきれていなかった面接官のために、面接官教育に検査結果の解釈を含めたところ、検査結果から仮説を持ち、事前に質問を準備できるようになったという声が面接官から聞こえるようになりました。
21卒採用の面接はすべてオンラインに切り替えましたので、今までの対面面接では見えていた人となりや雰囲気といった情報は全く得られなくなりました。その観点では、パーソナリティ検査の解釈スキルを強化しておけたのは不幸中の幸いでした。もちろん、実際にお会いして雰囲気を感じ取ることは大事ですので、対面とオンラインの選考をどのように組み合わせていくかは、コロナウイルスが落ち着いた際に検討します。
日本の労働人口が減少していく中で、従業員のパフォーマンスを引き出すためにタレントマネジメントは重要です。ほとんどの従業員が組織で活動をしていることを考えると、良いパフォーマンスを引き出すための従業員同士の関係性や人材の組み合わせを体系化できれば役立ちます。我々は、安全性の観点からメンテナンスを行う際、主に二人以上で作業計画を組むので、その組み合わせもアセスメントで個人の特性を見ながら配置ができればとよいと思っています。
また、私が使いやすいと思ったのは、価値観のアセスメント(V@W)の結果です。本人が職務上で重視している価値観をマネジャーが把握することで、より適したフィールドで活躍してもらうことができます。仕事のアサイメントの渡し方やフォローアップなど、従来なら各人に適したやり方を把握するのに一定期間が必要だったものが、配置してすぐに把握することができるといったことにもつながると思います。
コロナ禍で急速に普及したテレワークが、コロナ終息後も完全に元の状態に戻ることはないと思います。上司と部下が離れて仕事をすることが多くなれば、社員の特徴を把握することはより重要になります。社員ひとりひとりの特徴に配慮したコミュニケーションの取り方や育成担当者の割り当て方などにアセスメントを活用できたらいいですね。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
武田 幸祐
今回の採用基準明確化のプロジェクトは、職種別採用の導入と面接評価の課題の解決という内的要因と、コロナ禍による採用環境の変化という外的要因がある中で、結果的に非常にいいタイミングで実施できました。変化が求められる難しい環境下でプロジェクトに携われたこと、非常に有難く思っています。
今回の取り組みから、主観と経験に頼るのではなく客観的なデータを用いて細かく分析することで、人材評価時の焦点を合わせることができ、より良い採用活動ができると改めて認識することができました。
とは言え、「採用」という人事に関するテーマの入り口が整理できた段階であり、今後、企業としてのさらなる生産性向上と社員の皆様の働きやすさのためには、人同士のマッチングやサービス領域ごとの適性人材など、様々な観点でのより深い分析や継続的なデータ蓄積が必要と考えています。
これからもお力になれるよう引き続き尽力したいと思います。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例

ゲオからセカンドストリートへの事業ポートフォリオの転換を推進するゲオホールディングス。リユース事業であるセカンドストリート800店舗体制に向けて、人数を確保することに加え、質を担保すべく、活躍する店長の要件定義を行いました。
※本取材は2023年3月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社ゲオホールディングス
メディア、リユース、モバイル、オンラインサービス事業
小売業
従業員数:5,314名(グループ全体)

インタビューを受けていただいた方
高橋 知寿 様
株式会社ゲオホールディングス
組織開発室 組織開発課 マネジャー
インタビューの要約
成熟したレンタル事業から成長しているリユース事業へと事業ポートフォリオの転換を行うために、リユース事業のセカンドストリートを800店舗まで増やすことを目指していた。
活躍する店長の特徴を明らかにするため、人事データ分析を行った。全社員のパーソナリティ検査結果から10タイプに分類し、そこに評価データを組み合わせて、最終的に3つのタイプを事業部と協議の上、採用ターゲットとして決定した。
人員要望書を作成し、異動・登用プロセスの標準化に着手。
今後の課題はターゲット人財を確保していくこと。また、変化し続ける事業に適応できる組織であり続けるため、未来を見据えた要員計画にも取り組んでいる。
経営戦略、事業戦略に必要な人財を供給する。
私は、2006年4月にゲオにアルバイトとして入社し、店長やエリアマネジャーを経験した後、2017年10月に人事に異動しました。人事への異動当初は、人事データを分析してほしいと言われていましたが、人事本来の役割とは何なのか疑問を持っていました。自分なりに書籍やセミナー、他社の方々と話していく中で、人事の役割は事業に必要な人財を用意すること、という答えにたどり着きました。この時、人事がどのように事業に貢献できるのかが分かって、モチベーションが高まりました。当時、会社としては、リユース事業であるセカンドストリートの800店舗体制を目標として掲げ、事業ポートフォリオの転換を目指していました。そのため、セカンドストリートで活躍できる人財を増やすことを目的にデータ分析を行うことにしました。

活躍する店長の特徴をデータ分析で明らかにする。
まずは、どのような人が店長として活躍しているのかを明らかにすることが必要と考えました。日本エス・エイチ・エルのコンピテンシーデザインコースで学んだ、カードソートというインタビュー手法を使って、当時のセカンドストリートの責任者にヒアリングをしてコンピテンシーモデルを作成いたしました。また、OPQのデータを活用して、クラスター分析にて10タイプに分類を行い、タイプ別のハイパフォーマーの人数や割合がどのようになっているのか確認したところ、特定のタイプにハイパフォーマーが多く分布している点や、店長・エリアマネジャー・ゾーンマネジャーと役職が高くなるほど、割合が増える傾向が明らかになりました。事業部と作成したコンピテンシーモデルと比較すると共通点が多く、事業部と協議し今後の採用ターゲットに決定いたしました。
当時800店舗体制を目指し、年間50店舗規模の出店を計画、人事主導の採用は「量」が重視されていた中、「質」の視点を示すことができました。
データ分析の経験を異動・登用プロセスに活用。
2020年4月に人事異動の担当となりました。当時は各部門からどのようなオーダーがあったかといった過去の記録があまり残っておらず、異動に関する相談先も担当者だったり、マネジャーだったり、ゼネラルマネジャーとバラバラなことで人財要件が曖昧だったり、追加で確認が発生しながら人事異動が行われている状況でした。そこで、人員要望書(職務記述書のようなもの)を作成し、なるべく要件に合った人財を各部門に配置できるように環境を整えました。
要件がより明確になったことで、データ分析の経験も活かし、より要件に合った候補者の選出が出来るようになったこと、エラーが発生した場合でも何が良くなかったのか振り返りが可能になったこと、追加確認が少なくなったことにより、業務効率を高めることができました。

2023年2月に発表した通り、セカンドストリートは800店舗を達成し、中期的に1000店舗体制を目指しております。正直に申し上げると、当社に応募してくれる方々からターゲット人財に該当する人を量・質ともに継続的に採用し続けることは挑戦的なことで、今までの母集団形成や選考方法の仕組みを変えていく必要があると考えています。
また、未来の要員計画に取り組んでおり、店舗のみならず、間接部門の重点職種においても、将来どのような人財がどれくらい必要なのか、今どのような人財がいるのか、どのようにギャップを埋めていくのか、課題解決に取り組んでおります。日本エス・エイチ・エルは、相談がしやすく伴走してくれる会社だと感じています。我々の課題を解決するために、今後もご支援いただきたいと思っています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング3課 主任
内田 敬己
高橋さんは、「ビジネス」を前提とした人事を考え実行されているすごい方です。ただ、「考えて実行する」ために、様々な知識を獲得し続け、困難な社内外の交渉調整業務を乗り越えられている様子が垣間見え、ご苦労も多かったのではないかと拝察いたします。こちらからの各種ご提案に対して「そうはいっても実際のところ」をご教示いただけたのは何よりの学びになっております。約10年間、担当する中で数々の貴重な経験をさせていただき深く感謝しております。引き続き、有効な関わり方ができるよう当社として気を引き締めて対応させていただきます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例

高度ソフトウェアエンジニア育成のための新人事制度を導入した、デンソークリエイトの企業改革をご紹介します。
※本取材は2021年12月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社デンソークリエイト
車載組込ソフトウェアに関連する研究開発および先行開発、開発支援ソフトウェア(プロジェクトマネジメントツール、レビュー支援ツールなど)の開発、ソフトウェア技術者教育、プロセス改善・品質監査およびソフトウェア構造改革推進
情報・通信業
277名(2022.1.1現在)

インタビューを受けていただいた方
加藤 宏幸 様
株式会社デンソークリエイト
取締役
インタビューの要約
自動車産業におけるソフトウェアへのニーズの急拡大に対応するため、企業改革を実施。「高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループ・業界をリードする会社」を目指し、スペシャリスト育成に振り切った新人事制度を導入。
新制度のポイントは、早期のキャリア複線化、キャリアアップ計画の作成、能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)に基づく絶対評価の人事考課、年功色の薄い処遇など。
コンピテンシー基準は日本エス・エイチ・エルのアセスメントをもとに作成。これに則り毎年の評価者研修を徹底。また、昇格候補者の審査にも同様のコンピテンシーが適用されている。
新人事制度導入以降18名のスペシャリストが誕生し、社員満足度調査の結果も向上。人事考課アンケートや社員満足度調査によるフィードバックを得ながら、現在も制度の改善を続けている。
ソフトウェアニーズの急拡大により会社への期待が増大。高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループと業界をリードする会社を目指し、企業改革を実施。
当社は自動車がソフト化する将来を見据え、優秀なソフトウェア技術者の獲得を主な目的として、名古屋の小さなIT企業として誕生しました。ソフト開発を行うのは人であり、人だけが財産の会社です。親会社とは異なる、当時としては思い切った独自路線で、人事の仕組みを作成しました。コアタイムなしのフレックスタイム制、服装は自由、「アトリエ」という担当業務以外を含む組織でのコミュニケーションと自己研鑽などが特色でした。
設立から四半世紀が過ぎ、会社の規模が拡大するにつれ、トップが全員の能力を把握して処遇するようなことはできなくなりました。人材管理、配置・育成をしくみで行うこと、いわゆるタレントマネジメントが必要になったのです。
ソフトウェアに対するニーズの急拡大により、会社への期待が一気に高まる環境変化に対応し、2016年から企業改革を開始しました。目指したのは「高度ソフトウェアエンジニア集団としてデンソーグループ・業界をリードしていく会社」。親会社からの依頼に対応するだけではなく、ひとり一人が主体性を持って考え、提案し、自身のキャリアを描いて切磋琢磨する組織風土を目指しました。
スペシャリスト育成のための新人事制度をスタート。キャリアの複線化、キャリア計画の作成、コンピテンシーとスキル両面の能力開発、絶対評価などを導入。
改革の目玉として、2017年に新人事制度をスタートしました。それまでのトップの関与が強く、個別に判断して決める傾向があった人事から、仕組みで回す総合的な人事制度を構築して導入。人事の方針は、ソフト技術者は労働市場において流動性が高いことを前提とした考え方から、長期雇用・育成重視へと舵を切りました。
新制度のポイントは、スペシャリスト育成のための早期のキャリアの複線化と、それに付随するキャリアアップ計画の作成。そして能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)の作成、これに基づく絶対評価の人事考課と、年功色の薄い処遇などです。

新人事制度の導入に際しては、日本エス・エイチ・エルの協力のもと、評価・育成の根幹となる人材要件(コンピテンシー)を設計しました。このコンピテンシーに基づき、毎年の評価者研修や、昇格候補者の審査等を行っています。また「万華鏡30」を全社員が継続的に受検し、本人と上司が結果を共有の上、キャリアアップ計画作成や能力開発に活用しています。昇格候補者は別途アセスメントを受検し、その結果について日本エス・エイチ・エルのコンサルタントからフィードバックを受け、上司と本人と人事の三者で共有の上、行動改善に役立てています。 ソフトウェア技術者は科学的なアプローチを好むため、能力開発にも計測・データ解析に基づく根拠を示すことは非常に有効です。言葉だけよりも説得力が高まり、行動改善に繋がる可能性が高いと考えています。
新人事制度の成果は、活躍するスペシャリストの誕生、社員満足度の向上。
複線型人事は、会社ニーズだけでなく社員のニーズにも合致していましたので、歓迎されました。管理職ではなく専門職としてキャリアを積みたい人材も数多くいます。結果として18人のスペシャリストが誕生しました。その認定や昇格は、課題発表やアセスメントデータにより吟味して決定しているため、認定・昇格後はほぼ期待通りに活躍してくれています。会社に対するグループ内の評判も向上してきていると感じています。
また、毎年行っている「社員満足度調査」の結果では、新人事制度導入後、人事制度・育成制度に対する満足度は着実に向上しました。会社全体への満足度を示す「総合満足度」は、約50%から70%まで大幅に向上しており、人事の施策は間違ってはいないと自負しています。
新制度の導入は終わりではなく、始まりだと思っています。特に人事制度の要となる人事考課制度については、毎年評価者研修を実施し、評価の行い方と目線を統一しています。また運用の実態を把握するため、人事考課アンケートや社員満足度調査の結果を検討し、評価者やフィードバック者の変更、業績評価の簡素化など、試行錯誤を繰り返しています。
今後の課題は、実務的には、複線化したスペシャリストコースの拡充と認定方法の改善。先が見通し難い世の中で、キャリア形成の仕方をどう考えるかも課題です。また、どちらかと言えば内向きでモノを言いたがらないソフト技術者の意識を変えて、活発な議論が起きる企業風土へと改革を目指すべく、新たな打ち手を考えています。最終的な目標は、デンソークリエイトを日本のソフトウェア産業を代表する会社にし、社員が誇りを持って笑顔で毎日働けるようにすること。人事制度はそのための手段と考えています。
日本エス・エイチ・エルは、グローバルの膨大なデータと知見を持ちながらも、自社の理論を押し付けずに、常に同じ目線に立って寄り添ってくれる点がありがたいです。企業の信頼度だけでなく、適性検査の正確さ、コンサルタントの方の力量も大きいです。長年実施しているフィードバック面談は非常に好評で、今や欠かせない年中行事になっています。これからも宜しくお願いします。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
改正 晃大
高度なスペシャリストを育成するための先進的な人事制度やタレントマネジメント施策はIT業界のみならず、日本の産業をリードする取り組みです。この様なタレントマネジメント施策の設計と運用に深く関わることができ、大変光栄です。「新制度の導入は終わりではなく、始まり」という言葉の通り、制度は導入することが目的ではなく、制度の運用を通じて人が育ち、組織を発展させることが目的です。これからもデンソークリエイト様が目指す「日本のソフトウェア産業を代表する会社」に向けて、コンサルタントとして共に試行錯誤し、お力になりたく存じます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

様々な応募者の志向に応える部門別採用を採り入れているSMBC日興証券。
経営理念の価値観を体現できる人財を獲得すべく、部門別採用の新たな挑戦と求める人財像の再定義を行いました。
※本取材は2024年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
SMBC日興証券株式会社
金融商品取引業。資産運用コンサルティング業務、投資銀行業務、セールス・トレーディング業務、リサーチ業務など
証券業
9,251人(2024年6月30日現在)
※SMBC日興証券単体

インタビューを受けていただいた方
吉原 淳一郎 様
SMBC日興証券株式会社
人事部 第一人事課 採用担当リーダー
インタビューの要約
経営者から機関投資家まで、幅広い顧客を支援するための様々な職務がある。採用チームのメンバーの多くが新卒採用・中途採用を兼任し、シームレスに事業に必要な人財を確保している。
部門別採用とオープン採用を併用。専門性の高さへの期待から高専卒採用も実施。
経営理念をベースに採用要件を見直し、面接官を増員。
今後はデータ活用を一層進めていくと共に、リクルーター増員で学生の業務理解をより深めていく方針。
経営者から機関投資家まで様々な顧客の支援に必要な人財を確保する
私は2010年に入社し、金融市場マーケティング部で債券を扱う業務や投資銀行部での大手企業向けのフロント業務などを経て、2019年に人事部に異動となりました。その後は人事評価や人事異動、そして人事関連施策の企画に携わり、2023年より新卒・キャリア採用及び採用企画を担当し、今春からは採用担当リーダーとして新卒・キャリア採用を統括しています。
SMBC日興証券の社員数は約9,250名で、100を超える部署があります。大別すると、直接お客さまと関わるフロント部門である「リテール」「投資銀行」「グローバル・マーケッツ」の3つ。投資家や経営者、上場企業から機関投資家までサポートやコンサルティングを行っています。そしてフロントを支えるミドルバック部門である「クオンツ」「システム」「コーポレート」の3つとなります。採用においても、部門別に採用するコースを用意しています。インターンシップやワークショップも部門別に行い、各部門の社員(以下「部門社員)の協力の下でそれぞれの業務内容を体験し理解を深めてもらうイベントを実施しています。

採用人数としては、投資への社会的な関心の高まりもあり、目標人数を確保できています。新卒の割合が多く24年4月には約300名が入社しました。通年採用を行っており、数は多くありませんが10月入社者もおります。中途は従来60-70名でしたが、昨年より積極的に取り組んでおり、約100名を採用しました。新卒は6~8名、中途は4~5名の採用担当者がおりますが、新卒とキャリア採用を兼任しているメンバーが多いという点が当社の特徴です。
オープン採用と部門別採用に加え、高専卒採用を開始
10年以上前に始まった部門別採用は、現在では5つの部門別採用とオープン採用を合わせて全8つの募集コースがあります。最も採用人数の多いオープン採用は、各人が様々なキャリアを構築していくことを前提としており、金融のプロフェッショナルを目指す働き方ができるコースです。初期配属は主にリテール部門となります。オープン採用の中でも特徴的な点は、25卒採用から追加した高専卒採用コースです。入社後は、IT・デジタル等の業務のみならず、幅広い業務に従事していただくことを想定しています。もともと、当社のオープンイノベーションチームが行っているイノベーター人財創出のエコシステムを目指すプログラム「高専インカレチャレンジ」で、高専生と接点があり、高専生の専門性の高さを評価していたため、このプログラムをきっかけに高専卒採用に挑戦しようと考えました。本取り組みは、当社が掲げる「人財ポリシー+1」内の「継続的な人財投資」に基づいており、人事担当役員も含めて全関係者が「やってみよう」と前向きであったため、導入が実現しました。

「経営理念を体現する人財」へ評価項目の見直しと部門社員の動員拡大
選考フローは比較的スタンダードで、エントリーシート提出後にweb適性検査実施、その後複数回の面接を経て内定、となっています。選考に関しては2点工夫しました。1つ目は評価項目の変更です。私自身も選考活動を行う中で評価項目や求める人物像をより明確にしたいという意識があり、採用計画を策定する中で求める人物像を「経営理念を体現できる人財」と再定義しました。経営理念の中に5つの価値観がありますが、日本エス・エイチ・エルの協力のもとで、5つの価値観に近いコンピテンシーは何か、限られた面接時間で確認すべきコンピテンシーは何かの優先順位付けを行いました。
もう1つは部門社員の活用です。コロナ後、部門社員が面接官になるのは部門別採用だけでしたが、オープン採用でも部門社員に面接官を務めてもらうことにしました。入社後、上司になるかもしれない課長や支店長と接することが応募者の動機形成につながるためです。面接経験の有無にかかわらず、面接官をお願いする部門社員に対して、事前の面接官トレーニングを行いました。新たな評価項目の説明も含め、面接実施のポイントを資料にまとめてレクチャーしました。レクチャーにあたっては、事前に人事部メンバーで受講した日本エス・エイチ・エルの面接官トレーニングが大変参考になりました。

今後の採用活動に向けて取り組みたい課題は2点あります。1点目はデータ活用で、よりデータに基づいた採用活動へのシフトです。アセスメント結果だけで合否を決めるのではなく、最後は人が判断するものですが、アセスメントデータを積み重ねて様々な検証を行いたいと考えています。日本エス・エイチ・エルの協力で、これまでに自社社員のアセスメントデータ取得とパーソナリティ傾向の把握はできました。より包括的かつ頻繁に人財データを取得し、採用や育成に活用していきたいです。2点目はリクルーター施策の充実です。部門社員にリクルーターとして協力してもらうことで応募者との接点を増やし、会社と業務の理解促進に努めたいと考えています。当社社員は採用活動に協力的な方が多く、今回面接官をお願いできなかった社員から「面接に協力したかった」という声もありました。今後も会社の未来を創る採用活動の重要性を社内に伝えていきたいと考えています。
日本エス・エイチ・エルは、共感・納得できるアドバイスを的確にしてくれるパートナーだと感じています。担当コンサルタントの関さんはとても頼れる方で、安心してディスカッションをしたり、提案をお聞きしたりすることができました。また、必要な情報を濁すことなく率直に伝えてくれる点も評価させていただいており、多くの学びを得ることができました。今後も当社の採用の形や進め方は変化していくと思いますので、末永くご協力いただきたいと思います。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
関 麻奈美
採用活動の根幹となる求める人財についてご相談いただけたことを大変ありがたく思います。「経営理念」というある種抽象的な概念を採用のコンピテンシーに落とし込むのは一筋縄ではいかず、何度もディスカッションをさせていただきました。結果、価値観が合致している内定者を採用できたことは大変嬉しく、プロジェクトが成功したことに安堵しております。VUCAの時代、採用への考え方はこれからも年々変化することと思いますが、状況に合わせたご提案とサポートを引き続き行ってまいります。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

多様なバックグラウンドを持つ社員の相互理解のために、1on1ミーティングにアセスメントを活用。
マネジャー向けコーチング研修を実施した朝日インテックJセールスの事例をご紹介します。
※本取材は2021年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
朝日インテックJセールス株式会社
医療機器の販売、医療機器関連の研究、開発事業、医療機器に関するコンサルタント事業、医療機器の修理及び賃貸業務
医療機器販売業
従業員数 : 95名 (2021年6月末日現在)

インタビューを受けていただいた方
川又 治 様
朝日インテックJセールス株式会社
営業本部 フィールドマネージメントチーム チームリーダー
インタビューの要約
様々なバックグラウンドを持った社員が相互理解を行うために、客観的に自己をみつめるツールとしてアセスメントを導入。
効果的な1on1ミーティングを実施するため、マネジャーにアセスメント「万華鏡30」とコーチングのトレーニングを実施。離職が減ったほか、マネジャーのコミュニケーションが変わったというフィードバックを得られた。
アセスメントによって見出された社員の全体的特徴を、採用戦略にも活用。新しい個性をもった新入社員をのびのび育成するためにも、コーチングを活用してほしい。
今後の課題は、採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用し、科学的人事を推進することで、変化の激しい医療業界を生き残るための風土改革を行うこと。
様々なバックグラウンドを持つ人材が相互理解をするために、 全社にアセスメントを導入。
私は新卒でリース会社に入社し、外資系医療機器メーカー、日本の医療機器メーカーを経験し、11年前に当社に入社しました。大学を卒業してから営業一筋でしたが、4年前に新設の人事部門で採用・教育を担うことになり、手探りで現在の部署を作り上げました。
2017年にノーベル賞を受賞した行動経済学者、リチャード・セイラーの、人間は必ずしも合理的に意思決定をするわけではないという理論を書籍で読み、心理学的なアプローチに興味を持ちました。営業時代にも、人材育成における個人差を目の当たりにしたり、部下との関わり方がわからず悩んだりすることがありましたので、人事の仕事はこれらのことを学ぶいい機会だと思いました。
日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を導入した目的は、社内のコミュニケーションの円滑化です。当社は、カテーテル治療に使用されるガイドワイヤーでトップシェアである朝日インテックの国内販売部門として2006年に設立されました。売上が10年余りで50倍と急成長した為、内資系企業・外資系企業からの中途入社、新卒入社、また元々当社製品を扱っていた企業からの入社と、様々なバックグラウンドを持った人材が集まっています。一時期離職が続いたこともあり、上下間のコミュニケーションや相互理解が必要だと感じました。特に5年前から始めた新卒採用で入社した社員は、我々キャリア入社組からすると異色の存在。彼らを適切に育成する意味でも、社員の相互理解が必要です。そのため、全社にアセスメントツールを導入して個人に結果をフィードバックし、「自分が何者であるか」というコミュニケーションの土台をまず作りました。万華鏡30の結果については、「当たっている」という声が多かったですね。
1on1ミーティングでアセスメントを活用するコーチング・トレーニングを実施。 離職の減少、上司のコミュニケーション力向上に効果あり。
その後、上司が部下をコーチングするための1on1ミーティングの研修を企画しました。その際に、「万華鏡30を1on1に活用したい」と思い、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントと外部企業のコーチングの講師で打ち合わせをしていただいて、上司が1on1の中で万華鏡30を活用できるように進めました。
1on1ミーティングは月1回、各エリアマネジャーと部下との間で実施されます。万華鏡30を使うことを推奨していますが、使いたくない場合は使わなくてもよいと告知しました。また、1on1で万華鏡30を使う場合は、部下の結果だけを提示すると高圧的に受け止められる可能性もあるため、かならず上司自身の結果も提示して相互理解するようにと強調しました。

万華鏡30を使った1on1およびコーチングのトレーニングを行った効果ですが、まず離職が減りました。もちろん離職はゼロにはできませんし、する必要もないと思いますが、医療業界での重要なリソースであるドクターとの人脈や知識を持つ社員の流出は痛手ですし、すぐに次の人を育てられるわけではありません。今後は、制度面などコミュニケーション以外の部分でもさらにリテンション施策を整えていくことを考えています。
また、一部のエリアでは上司の接し方がガラッと変わったという報告を若手社員から受けています。今まではどちらかいうとトップダウン的なコミュニケーションだったのが、部下の話を聞くようになったということです。コーチングの在り方を学習したことに加え、万華鏡30によって「自分にはこんな要素があったのか」と客観視することで、マネジャーにも学びがあったのかなと思います。
社員の特徴は採用方針にもフィードバック。
採用と育成の両輪の人事施策で、変化の激しい医療業界を生き残る。
また、今回の全社受検の結果をもとに、採用戦略を検討しています。たとえば、当社の営業職社員が強く持つ特徴を採用要件にする、オーソドックスなマネジャー層を補うため創造性を採用要件に入れるなどです。新卒社員には創造性を発揮していただきたいと期待しています。昨今の企業合併やコロナ禍など、医療業界は変化が著しく、環境の変化に適応できる人材がいないと、組織として生き残っていくのは難しいと思います。
その上でコーチングの効果として期待しているのは、マネジャーが新しい発想をもった新入社員の個性を生かし、のびのび育成できるようにすること。せっかく尖った人材を採用しても、マネジメントによってだんだん丸くなってしまうのではもったいない。同時に、私からも若手社員と個別に話をして、「今まで受けた教育で納得いかないことや問題点などあるかもしれないが、自分たちで考えて自分たちで決めていいんだよ」とメッセージを送っています。若い頃から自分で決める経験を積まないと、意思決定のできないマネジャーになってしまいます。せっかく素質のある人材を採用しているので、彼らには早い段階から自分で決めるということ、そして決めたことに責任を持つということを、しっかり教育で身につけさせたいと思っています。
今回、日本エス・エイチ・エルに携わっていただいてプロジェクトを実行し、少なくとも管理職以上の意識は変わりました。頭ではわかっていても感覚的にわかりづらかった「人にはオリジナリティや個性があって一人一人異なる」ということをアセスメントのデータで明示してもらえたことが大きいと思います。担当コンサルタントの方には、社員向けにアセスメントの説明会も開いていただき、社員が理解を深めることに貢献していただきました。
今後の課題は、コーチングと採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用していくこと。変化の大きい医療業界において、人の目による人事のみに頼ってしまうと、オーソドックスな社風が強くなってしまい、組織として生き残ることができません。データや統計など科学的な資料をもって、人の目の限界を補う必要があります。
最後に、個人的な課題は、自分が経験したことを次の世代へ伝えることです。私自身、多くの上司や先輩に育ててもらった恩を感じながら年を重ねましたが、今は私自身が次世代を育て、彼らがまた次世代を支えていくことを実感しています。このような継承の物語が積み重なって歴史となってきたのが、日本企業の強みではないでしょうか。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
藤田 夏乃子
1on1ミーティング実施にあたり、相互理解を行うための材料としてアセスメントを利用したいというお話をいただき、今回の取り組みが始まりました。
きちんとアセスメント「万華鏡30」を理解してほしいという川又様の熱意を受けて、私が「万華鏡30」の説明会を実施させていただきました。説明会当日は参加者の方からたくさんの質問をいただき、皆様積極的にご参加いただいたのを覚えています。
実際に川又様から1on1ミーティングを実施していく中で、上司・部下間でよりよいコミュニケーションに変わっていっているとお聞きしたときはこの取り組みに貢献できてよかったと感じました。
今後も広くアセスメントの活用を考えていらっしゃるとのことで、様々な場面でお力になれるようにしていきたいと思います。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス