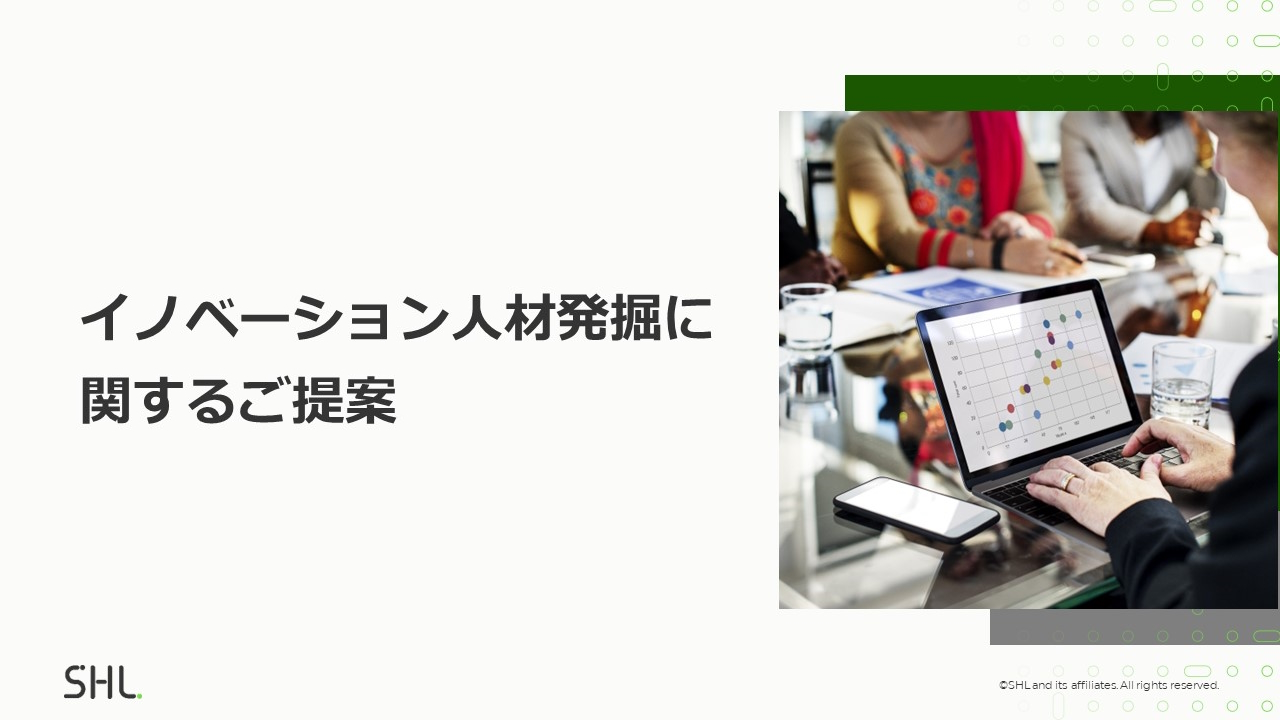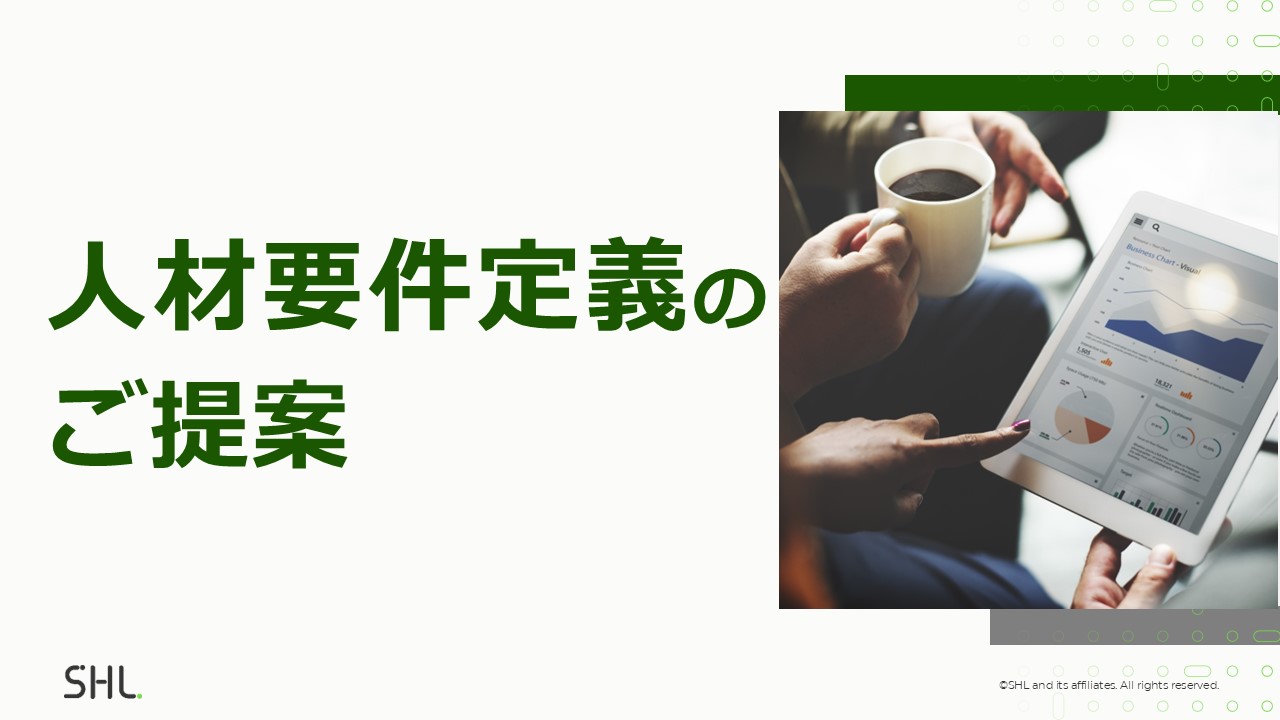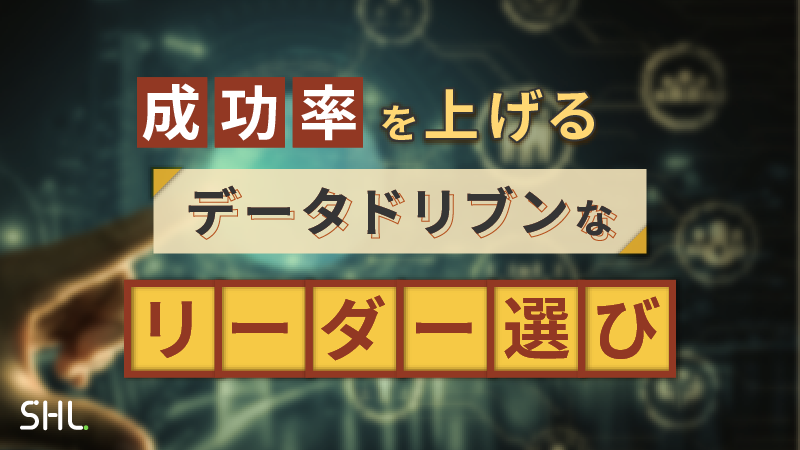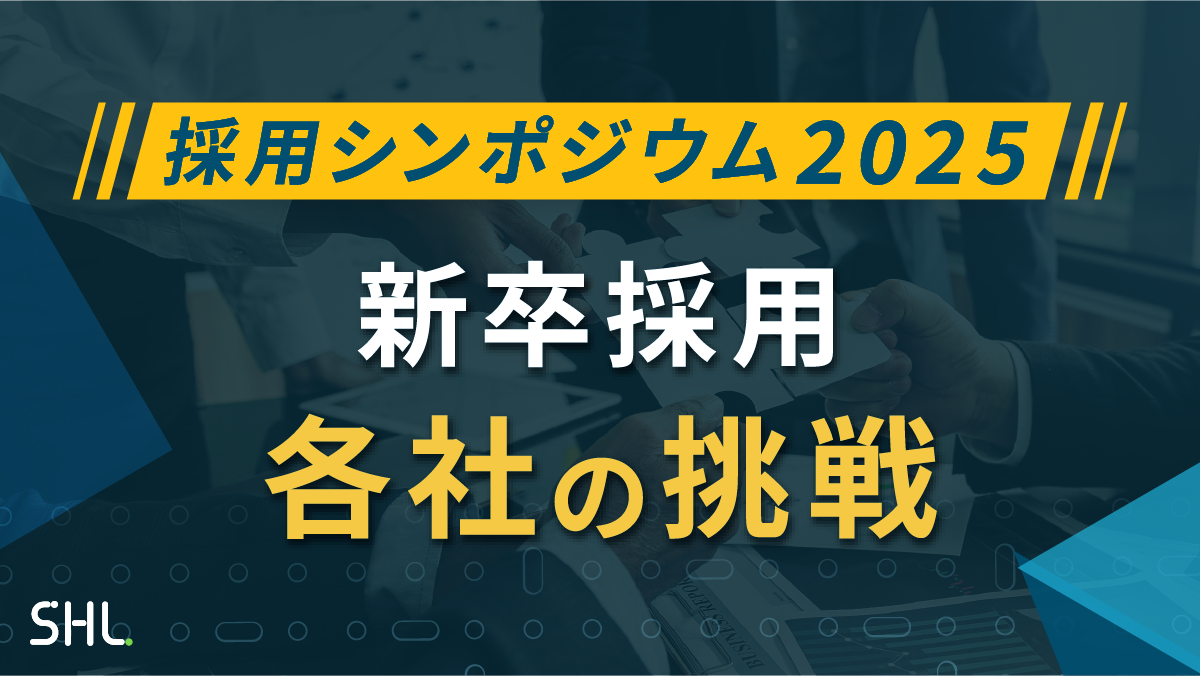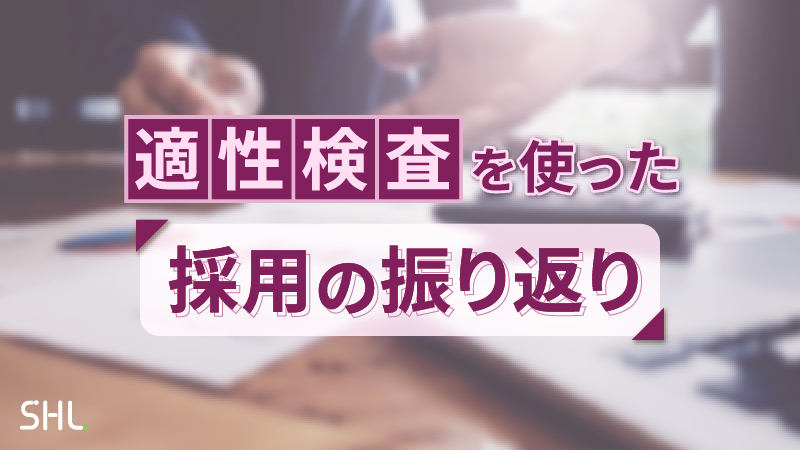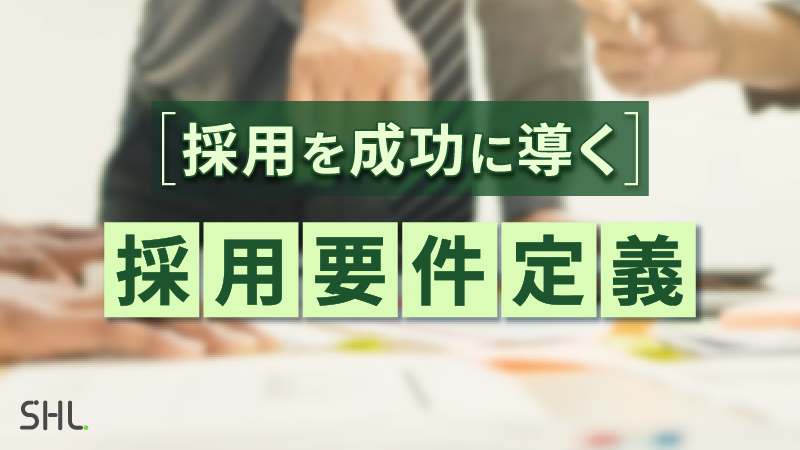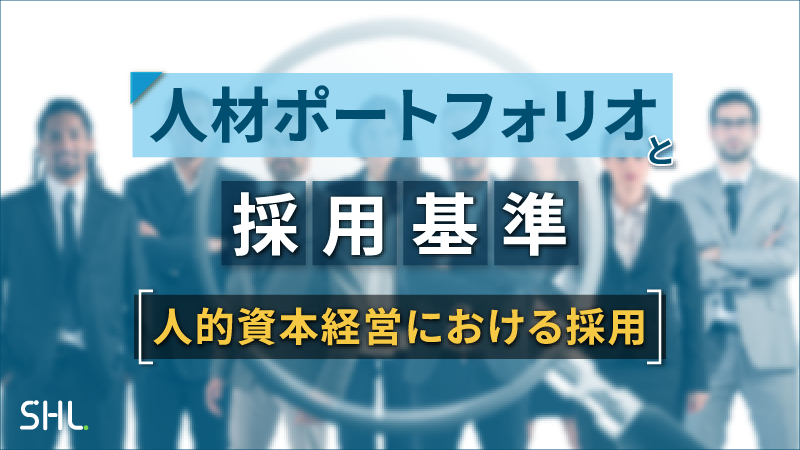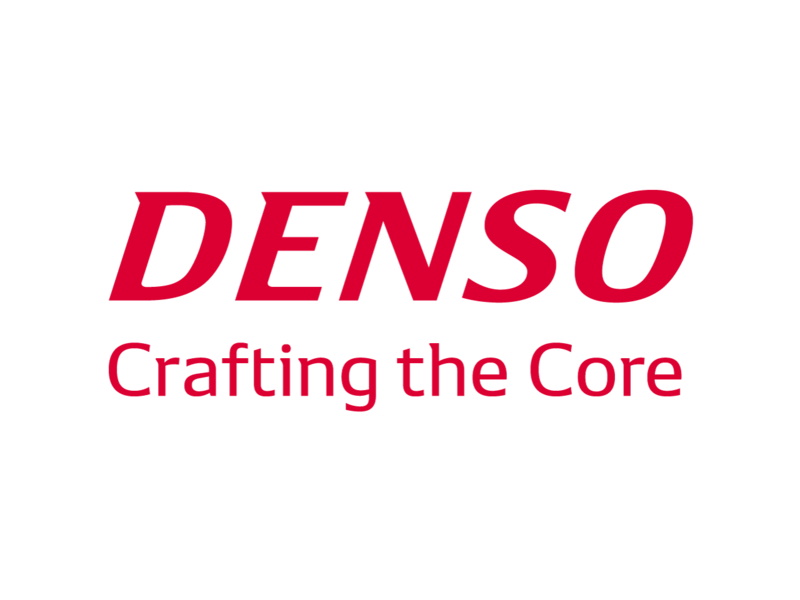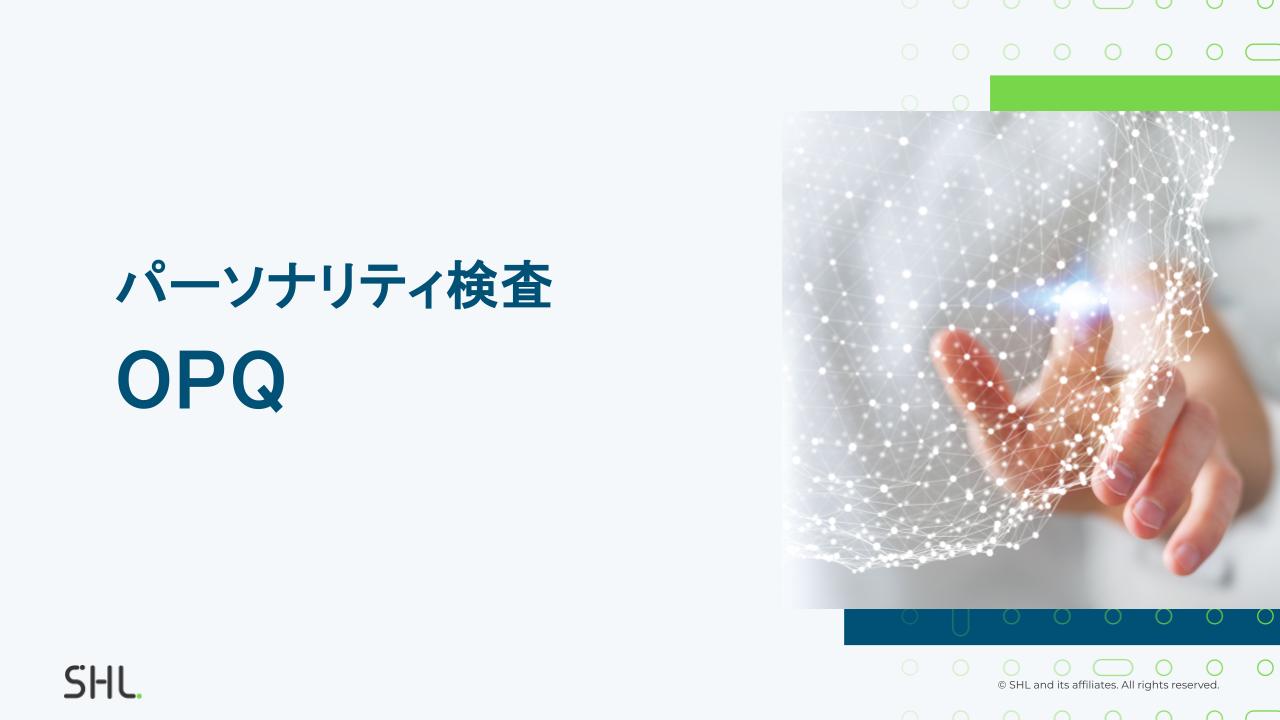新たな業態に挑戦する松屋フーズホールディングス。その立ち上げを担う人材をアセスメントを用いて選抜し、成功確率の高い人材配置の実現を目指す取り組みをご紹介します。
※本取材は2020年9月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社 松屋フーズホールディングス
飲食事業を中心とするグループ会社の経営管理
小売業
1,613名 2020年(令和2年)3月期・連結

インタビューを受けていただいた方
別役 建治 様 / 一坂 正博 様
株式会社 松屋フーズホールディングス
人事部 人事グループ グループマネジャー(写真左)
人事部 人事グループ チーフマネジャー(写真右)
インタビューの要約
事業規模のさらなる拡大のために、牛めし・とんかつ事業に続く新業態の立ち上げに適性のある人材を社内で特定し、登用・育成する必要があった。
日本エス・エイチ・エルのアセスメントを用いて、これまで新業態を担ってきた少数の人材の特徴を特定。類似した人材を新業態に抜擢するなど、適材適所を効率的に行えるようになった。
今後のミッションは、新業態を担える人材の育成と、部分最適を乗り越えて適材適所を遂行していくこと。
牛めしととんかつに続く、新業態を担う人材を社内から探したい。
当社のようなチェーンストアビジネスは、ある勝ちパターンを作って脈々と回していくことが成功につながるという構造があります。その一方で、中期経営計画ではさらに大きく事業拡大させようという方針があり、牛めし事業ととんかつ事業だけではなく、新業態を展開できる人材を育てるという、いわゆる戦略人事の課題が降ってきました。従来の事業は、同じタイプの人材を採用して育成すればうまくいきました。しかし、新業態を担える人材を社内で探すと、毎回同じ数名の人にしか白羽の矢が立ちません。この人たちの予備軍を作らなければ、中期経営計画に示された大きな事業の拡大は実現できないと考えました。
この人たちはどんな人なのか?社内に予備軍はどれだけいるのだろうか?と考えたときに、実は人材に関するデータがないことに気づきました。昇格試験などで会った時の印象しかない。どこかに隠れた人材がいるのか、いないのかもわからない。それで、新業態に適した人材を、タレントアセスメントを使って探すことにしました。

当社の店長については、本部が決めたことを正確に行えるかどうかが評価基準でしたし、サービスの均一化や徹底力が当社の強みでもありました。一方、新事業は試行錯誤の連続であり、常に臨機応変な対応が求められます。これまでは新事業に適した人材を発掘し、育成しようという発想はあまりありませんでした。しかし今後は、戦略人事として新事業人材の発掘と育成を積極的に行わなくてはならないと経営に提案しました。
OPQを用いて、新業態やその他ポジションへの適性を把握。
アセスメントツールとして、なるべく回答時間が短いもの、コストを抑えられるもので、精度が高いものを探しました。他社の商品もいくつか検討しましたが、やはりコストや所要時間の関係で難しく、結果的にSHLのOPQにたどり着き、これなら採用時にも使っているし汎用性もある、一石二鳥じゃないかということで導入を決めました。
アセスメント結果データを分析すると、新業態を担ってきた社員はロジカルな人たちであることがわかりました。分析結果を見るまでは、感覚派の人たちだと思っていましたので予想外の結果でした。今では、彼らと似たアセスメントの結果を示す社員を、新業態の担当に選んでいます。
新業態以外にも、今は10か所くらいのポジションで、良い人いないかというオファーを貰ったら、成功する人材モデルをもとに、類似した人材を推薦しています。今後は、さらにアセスメント結果を分析して成功確率を上げていくというのが、我々のミッションです。

請負型の人事ではなく「攻めの人事」へ。
ジョブローテーションにおける人材を提案する際も、日本エス・エイチ・エルのアセスメントの結果は納得性の高い情報となってます。本人を知っている場合、結果を見て「ああ確かにな」と、よく思うんですよね。客観的な数字をもって候補者を提案することで説得力を高めています。
従来は、知っている人しか推薦できませんでした。このやり方では知らない人にはチャンスがありません。アセスメントを使うことで、チャンスが公平に行き渡るようになりましたし、異動の成功確率も上がり、適材適所がやりやすくなりました。しかも客観的であり、恣意的でない。これは重要です。人事異動を客観的に行うことが、他の人事施策についても客観的に行うというメッセージにもなります。
特定のポストに対する候補者を見出すときにもアセスメントは重要です。アセスメント結果があることで人事が積極的にしかけていくことができます。新業態の人材選抜は「攻めの人事」だと思います。

日本エス・エイチ・エルのいいところは、担当者が熱心に、細かく要望を聞いてくれるところ。考えがまとまらなくてモヤモヤしていても整理してくれます。提案内容にしても、クライアントの話をよく聞き、クライアントのことを考えて作っているのが伝わります。こちらはストレスなく進められます。
今後のミッションは、新業態を早く立ち上げられる人材を育てていくこととマネジメントのレベルアップ。加えて部分最適になっている組織をどう全体最適にしていくかが課題です。部門は優秀な人を抱え込みたがります。5年後のために今は我慢してくださいと部長を説得します。
個人的なミッションは、社員個人のモチベーションを引き上げて幸せを感じてもらうこと。個人個人のモチベーションリソース(意欲源)は色々あると思うので、それを気づかせて、実現の力になりたいです。本人もうれしいしお客さんもうれしい、結果として会社もうれしい、そういう環境を作りたいですね。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
太田 啓
別役さんから「新業態に適性のある人材を発掘したい」とご相談をいただいてから、何度も意見交換を重ね今回のプロジェクトに至りました。お打合せの間、常に意識していたのは別役さんのビジョンを正しく理解することでした。
松屋フーズホールディングスは長年弊社のアセスメントをご利用いただいており、過去にも優秀店長の傾向分析を実施しておりましたが、これほど大規模なアセスメントデータの分析は初めての取り組みでした。松屋フーズホールディングスの成長戦略に影響をおよぼす本プロジェクトに携わることができて大変光栄です。
今後は、選抜された新業態人材の育成、全社適正配置の実現、本プロジェクトの効果検証でお役に立てるよう微力を尽くす所存でございます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

関連する導入事例
関連するコラム
はじめに
DEIとは、Diversity(多様性), Equity(公平性)and Inclusion (包括性)の略語です。ビジネス上で重要な課題とされるDEIですが、SHLのグローバルタレント調査で、取り組みを強化していると回答したのはわずか5社に1社でした。DEIの施策は今や道徳的な義務以上のものと考えられます。従業員のパフォーマンス、定着率、会社の評判、そして長期的な組織の成功にプラスの影響を与える戦略的な意思決定事項です。今回のコラムでは、SHLグループのホワイトペーパーから一部抜粋し、DEIがもたらす組織へのメリットとタレントマネジメントの実践について解説します。
DEIの定義
まず、本コラムでのDEIの定義を確認します。定義は過去の記事から引用します。- Diversity(多様性):その人自身をユニークにする特徴。DEI施策は、組織がサービスを提供する集団の多様性を、職場に反映することを目指しています。
- Equity(公平性):公平性とは、偏りがなく公正であることです。公平性と平等の違いは、平等はすべての人に同じリソースまたは機会を与えることに焦点を当て、公平性はすべての人に同じ結果に到達するために必要なリソースと機会を与えることに焦点を当てていることです。丘に植えられた木から2人がリンゴを収穫しているところを想像してみてください。両方の人に同じ高さのはしごを与えると、上り坂に立っている人はリンゴに手が届きますが、下り坂に立っている人は手が届きません。これは平等です。どちらの人も同じはしごを受け取りました。公平性は、下り坂に立っている人に長いはしごを与え、両方の人がリンゴに手が届くように必要なリソースと機会を与えます。
- Inclusion(包括性):組織の方針や慣行すべてにおいて、組織内の人々が「意見を聞いてもらっている」と感じる職場を作ることです。組織内の人々に「すべての人々を気遣い、耳を傾け、配慮している組織で働いている」と感じさせることが、DEIの施策の最終目標であり、最も難しい部分です。
DEIの施策がどのように組織の成果に貢献するか
- 人材の確保と維持 DEIに取り組む組織は、求職者にとって魅力的な存在となり、企業の評判や優秀な人材への訴求力を高めます。ひいては、従業員の定着率向上や、離職率の低下による雇用コストの削減につながります。インクルーシブな職場環境は、従業員が価値を感じられるようにし、エンゲージメントや仕事満足度、そしてロイヤリティの向上を促進します。
- イノベーション、創造性、意思決定の改善 多様なチームが多様な視点をもたらし、課題解決における創造性とイノベーションを促進します。インクルーシブな環境は、オープンなコミュニケーションと多様な視点への配慮を促し、バランスのとれた意思決定プロセスにつながります。
- 市場と顧客の理解 多様な人材が市場や顧客の理解を深め、その結果、より幅広い消費者層に対応する製品やサービスを生み出します。これらは、最終的に企業の競争力を高めます。
- グローバルな視点 多様な労働力から得られるグローバルな視点は、特に重要です。グローバル市場で事業を展開する企業にとって、文化の違いを乗り越え、多様な市場のニーズを理解するのに役立ちます。
- 企業の評判 ダイバーシティとインクルージョンを優先することは、社会的責任に合致し、企業の評判を高め、社会意識の高いステークホルダーに訴えかけます。
- チームワークとコラボレーションを強化 インクルーシブな組織文化はコラボレーションとチームワークを促進します。社員が自分のアイデアや意見を気軽に共有することで、チームワークが向上し、より効果的なコラボレーションや問題解決につながります。
タレントマネジメントにおけるDEIの実践
DEIを実践する施策をいくつかご紹介します。インクルーシブな採用プロセス
採用の初期段階でブラインド採用プロセスを採択することで、アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)を最小限に抑えることを目指せます。ブラインド採用プロセスとは、採用の過程で応募者の個人的な情報(名前、性別、年齢、出身地、学歴、写真など)を隠して評価する方法です。そのほか、様々なターゲットに向けたジョブフェアに参加したり、多様な人材を惹きつける団体と提携したりするなど、多様なソーシングチャネルを活用することも寄与します。また、求人票で偏見のない言葉を使用すること、特別なニーズがある人々に対応する計画を立てること、多様な面接官をアサインすることも考慮すべきです。リーダーシップ開発とトレーニング
インクルーシブなリーダーシップ文化を育むために、組織はリーダー向けにアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)や異文化への理解など、テーマを絞った研修プログラムの継続的な実施が必要です。また、少数派グループから優秀な人材を発掘し、育成するためのメンターシップ機会をリーダーが提供できるようにすることも必要でしょう。業績評価の透明性
業績評価における透明性の促進は、公正なパフォーマンスマネジメントの実践につながります。明確に定義された客観的な評価基準は、従業員の貢献や成果に基づいて公平に評価される環境作りを支援します。インクルーシブなオンボーディングプログラム
メンターをアサインする、異文化を含む他者理解に関する研修を提供する、重要なリソースにアクセスできるようにするといったオンボーディングプログラムを準備すべきです。新入社員が最初から大切にされている、自分が一員であると感じることができます。従業員同士のコミュニティ(Employee Resource Groups)の設立
従業員リソースグループ(ERGs;Employee Resource Groups)と呼ばれる従業員のコミュニティを設立し、サポートします。つながりや多様な意見を言えるプラットフォームを提供することで、包括性をさらに強化します。コミュニティは、例えば女性やLGBTQ+など、共通の背景や経験を持つ他の従業員とつながることを可能にします。定期的なサーベイ
組織は、従業員の経験や認識に基づいて戦略を適応させ、改善を重ねるため、DEIに関する定期的なサーベイを実施することが望ましいです。おわりに
DEIは理想論や道義的責任といった抽象的な概念ではなく、ビジネス成果を生み出すための具体的なビジネス戦略のひとつです。組織がDEIを重視するカルチャーを創造することは、最終的に従業員の満足度、生産性、イノベーションの向上につながります。冒頭述べたように重要度を認識していても、取り組みに十分着手できている企業は多くありません。完璧を追い求めるのではなく、まずは自社で何ができるか、現実的な一歩から踏み出してみましょう。 近年、新規事業創造人材など従来と異なるクリエイティブな発想を持つ人材に注目が集まっています。しかし、クリエイティブな人材とはどのような考え方を持つ人材なのでしょうか?今回は、今求められる能力として脚光を浴びる「クリエイティビティ」に関して、興味深い研究知見をご紹介します。クリエイティブな人材は不正行為を働きがち
Gino & Ariely (2012)は「クリエイティビティのダークサイド(The dark side of creativity)」というタイトルの論文において、クリエイティビティの高い人材は、成果の誇張や嘘による報酬の割り増しなどの不正行為を行いやすいことを実証しました。さらに、職場をフィールドとした別の研究(Vincent & Kouchaki, 2016)では、本人が自身のクリエイティビティを稀有な才能であると強く自覚しているほど、成果の虚偽報告や会社サービスの私的利用などの不正をする傾向が強まりました。クリエイティビティのポジティブなイメージに逆行する研究結果ですが、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。
クリエイティビティとは、ルールに縛られないこと
Gino & Wiltermuth (2014)は、クリエイティビティと不誠実な行動をつなぐのは「ルールに縛られないこと」であることを示しました。「自分はルールに縛られない」という認知が高まると、人はクリエイティブになり、かつ不誠実な行動も増えるのです。そのため、あえてズルをするような不正行為を行うと、その後の創造性課題の成績が高まるという効果も示されました。つまり、クリエイティブな人材は程度の差はあれルールを破ることへの抵抗が少なく、常識を破ればイノベーションを、規則を破れば不正を起こすという構造が見えてきたのです。このような行動傾向によってクリエイティブな人材が組織の支持を得づらいことが、組織におけるイノベーションの阻害要因にもなっているのではないか、という指摘もあります(古川, 2018)。
感情知能がクリエイティビティの暴走を止める?
一方で、こうした「悪意あるクリエイティビティ」を抑止する要因について、興味深い知見がありました。Harris, et al. (2013) によれば、感情知能の低い人ほど、「悪意あるクリエイティビティ」によって課題を解決しようとする傾向があるそうです。感情知能がどのプロセスで「悪意あるクリエイティビティ」を抑止するのかは不明ですが(思いつかないのか、表現しないだけか)、周囲の人の感情を認識しづらい、もしくは軽視する傾向のある人ほど、クリエイティビティの悪用に注意が必要かもしれません。最後に
古川(2016)の調査によれば、クリエイティブな人材は周囲との間に「壁や溝の認知(自分の考えは周囲に理解されないという思い)」を抱きやすいことが示されています。また、この壁や溝の認知を緩和するのは、「ともに見るもの(共有している大きな目標など)」の存在であるということです。クリエイティブな人材の活躍には、周囲の感情を理解し尊重しようとする姿勢とスキル、また様々な考えを持つ人材を包括する大きな目標が不可欠であるといえそうです。なお、日本エス・エイチ・エルの万華鏡30には、新規事業創造などに適性のある「アントレプレナー適性」のポテンシャルとともに、感情知能の予測値も示されます。イノベーション人材の育成が急務となる中、このような視点で能力開発を考えてみるのもいかがでしょうか。
引用文献
古川久敬 (2016). 創造的アイディアの履行における抑制および促進要因の分析 ー創造革新性パラドックスの克服に向けてー. 日本経済大学大学院紀要, 4, 31.
古川久敬 (2018). 組織行動研究の展望: パラドックスを抱えた組織と個人を意識して. 組織科学, 52, 47.
Gino, F., & Ariely, D. (2012). The dark side of creativity: original thinkers can be more dishonest. Journal of personality and social psychology, 102, 445.
Gino, F., & Wiltermuth, S. S. (2014). Evil genius? How dishonesty can lead to greater creativity. Psychological science, 25, 973.
Harris, D. J., Reiter-Palmon, R., & Kaufman, J. C. (2013). The effect of emotional intelligence and task type on malevolent creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 7, 237.
Vincent, L. C., & Kouchaki, M. (2016). Creative, rare, entitled, and dishonest: How commonality of creativity in one’s group decreases an individual’s entitlement and dishonesty. Academy of Management Journal, 59, 1451. 先日のコラム「今求められる変革型リーダー」で、変革型リーダーについて定義やコンピテンシーをご紹介いたしました。今回は、この困難な時代に変革を起こすリーダーになるためのヒントをご紹介します。

困難な時代におけるリーダーたちのチャレンジ
現在、多くの変化が世界中で起こっています。突如起こった新型コロナウィルスの蔓延、徐々に広がりを見せて世界的な共鳴を生んだBlack Lives Matterの動き、従来から叫ばれていたグローバリゼーションやデジタライゼーションなど。先日のコラムでも記載しましたが、コロナ禍で、リーダーにとって次のようなチャレンジが鮮明になりました。
- リモートワークによって物理的に散らばるチームをうまくリードする
- 曖昧さ、不確実性、混沌であふれる世界で成果を出す
- 目標に向かうべく、従業員に安全と安心を提供する
- 組織を前進させるために新たな戦略を立案し、実行する
- プロダクトやサービス、プロセスが急速に変化する環境で業務を遂行する
- リソースの制約が絶えずつきまとう状況で組織を運営する
- 協力が難しい状況で、協働する価値を最大化できるよう変革すること
- リーダーたちが多様なチームと向き合って、価値を最大化できるようにすること
- 対立が蔓延していた文化を、同じ立場である「1つの組織」として変革すること
困難な時代、多様性がイノベーションの重要な要素になる
アクセンチュアによる「平等な文化」に関する最近のレポートでは、最も平等性が高い文化は最も低い文化と比べて、イノベーションマインドセット(職場でイノベーティブであろうとする個人の意欲と能力)が6倍高いことを示しています。また、女性はより平等な組織で上級管理職につく可能性が4倍高いと述べています。さらに、すべての国がイノベーションマインドセットを10%引き上げた場合、世界のGDPは2028年までに最大8兆ドル増加する可能性があるとのこと。 レポートでは、リーダーの68%が自分たちの組織には平等やインクルーシブの文化・価値観があると感じていたが、従業員で同様に感じているのは36%だけと強調しています。組織がよりインクルーシブな文化を構築するために努力していると感じている従業員の割合は、2018年以降同じであり、50%強です。リーダーにとって、多様性を受け入れるインクルーシブな文化、平等な文化の醸成とメッセージ発信は、イノベーションを生み出し、組織の価値を高めることにつながります。
変革型リーダーになるための3つの方法
これらをふまえ、変革を起こすリーダーになるためのヒントをお伝えします。- 多様性の目標を設定する ―それらを戦略に組み込み、すべての人に本当の帰属意識を持たせます。
- 文脈に合わせる ―文脈をとらえた課題ごとに、最も成功する可能性の高い人材を配置します。隠れた優秀な人材が見つかるかもしれません!
- 経験を共有する ―リーダーを集めて、経験した成功と課題を共有します。お互いから学び、不安を軽減することができます。
新型コロナウィルスの蔓延により、リーダーは多くの予期しない困難に出会いましたが、たくさんの学びもあったはずです。平等や多様性、状況に合わせた対応、そして、互いに耳を傾け、成長し、変化する意欲が重要です。より多くのリーダーが困難を力に変えて、自身や組織の価値をさらに高めることが望まれます。
※本記事はSHLgroupのコラムを参照し、一部抜粋・加筆しています(筆者抄訳)。