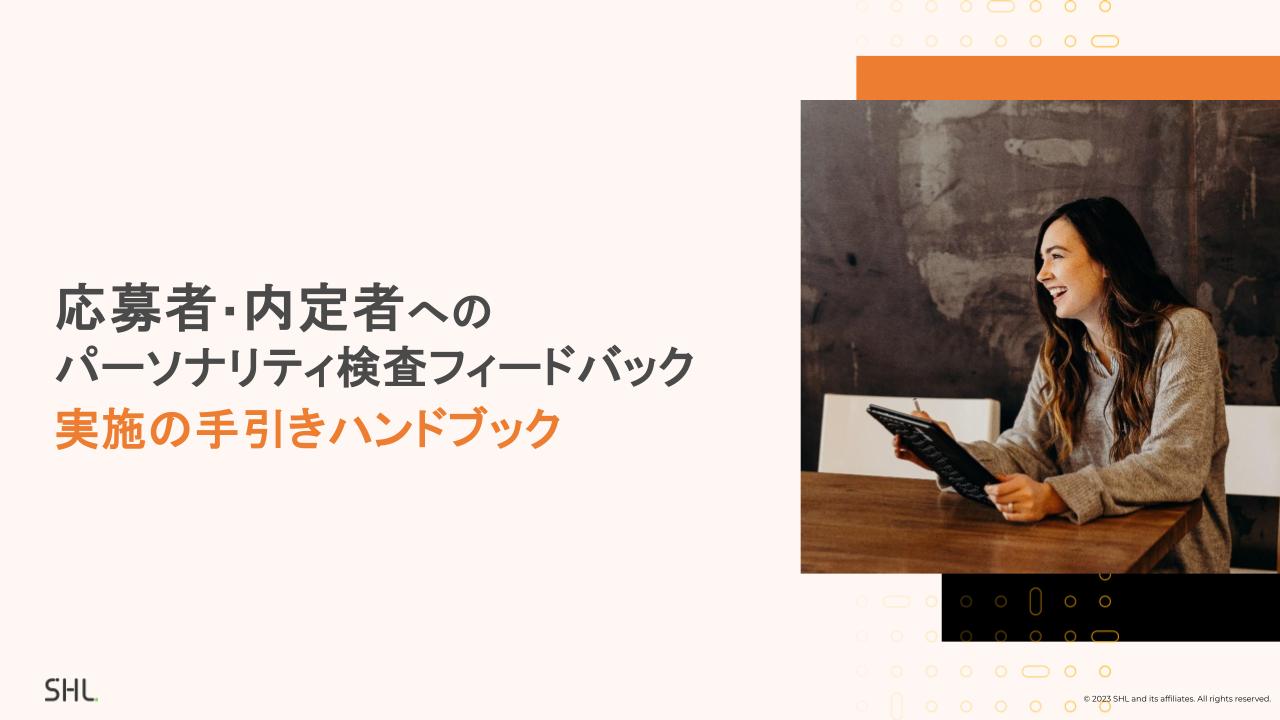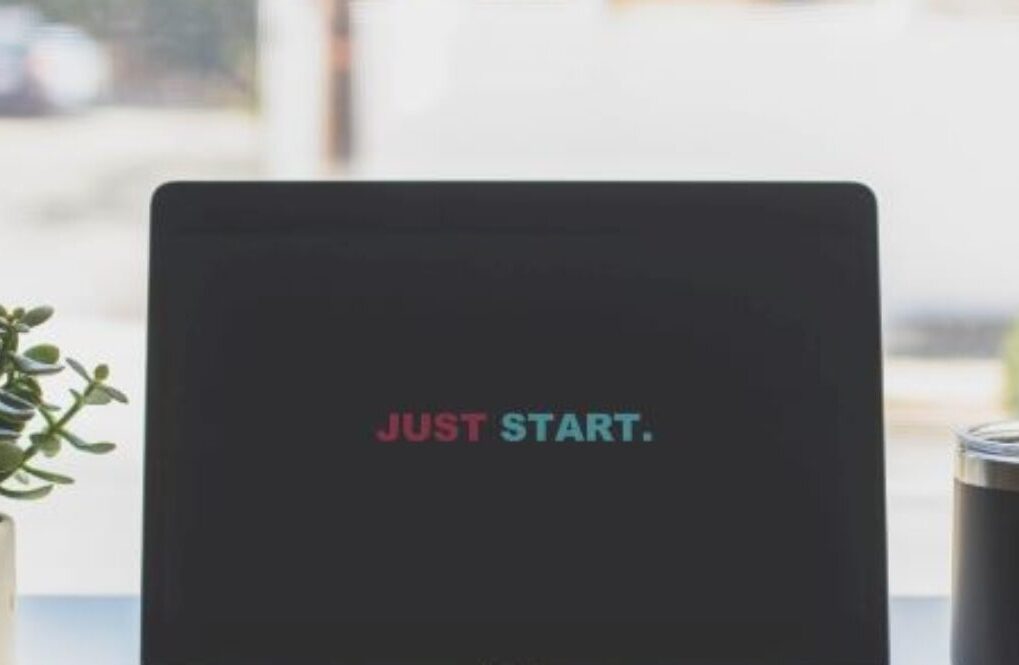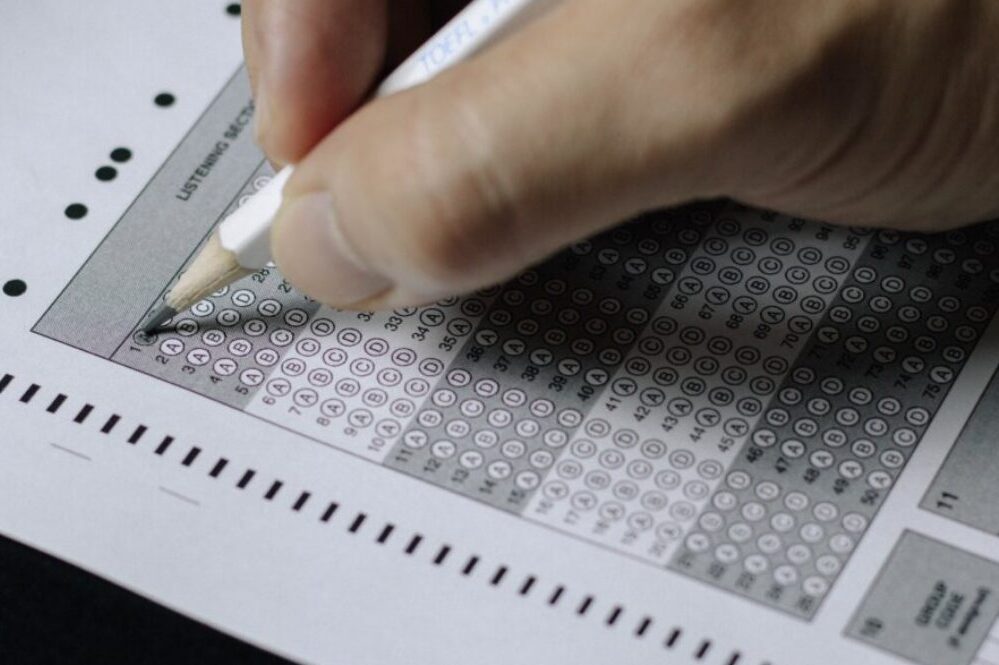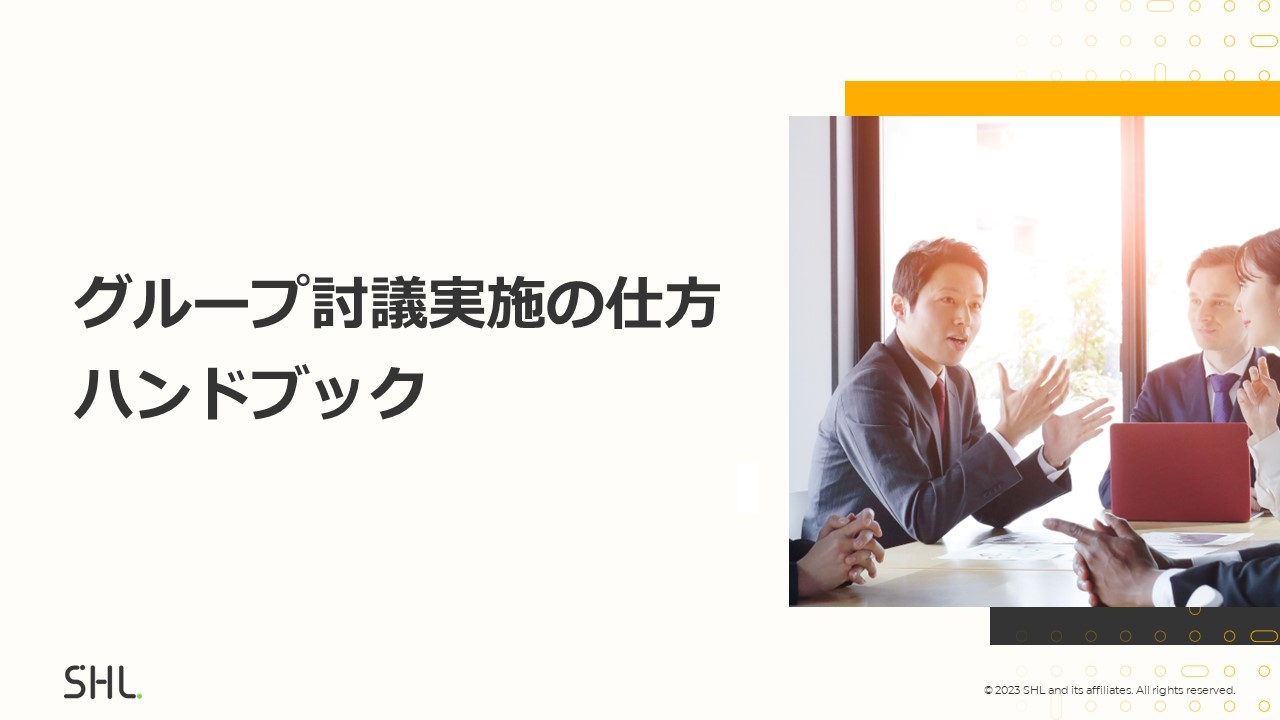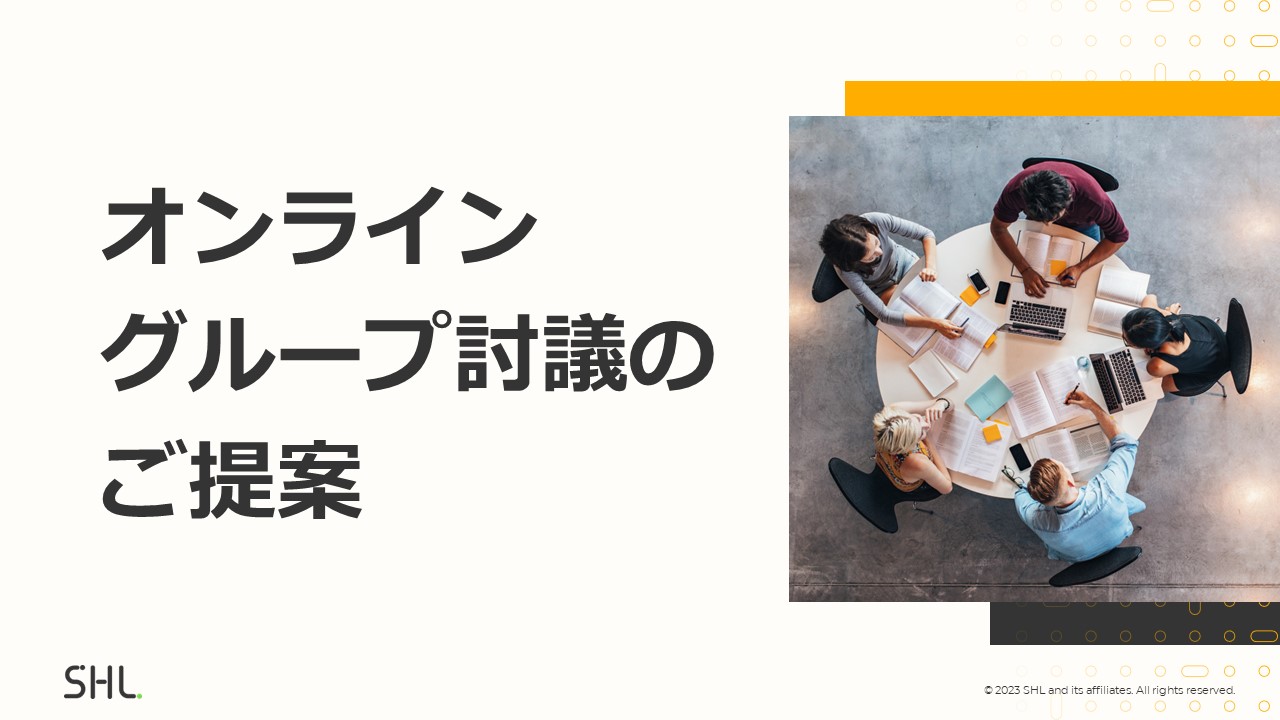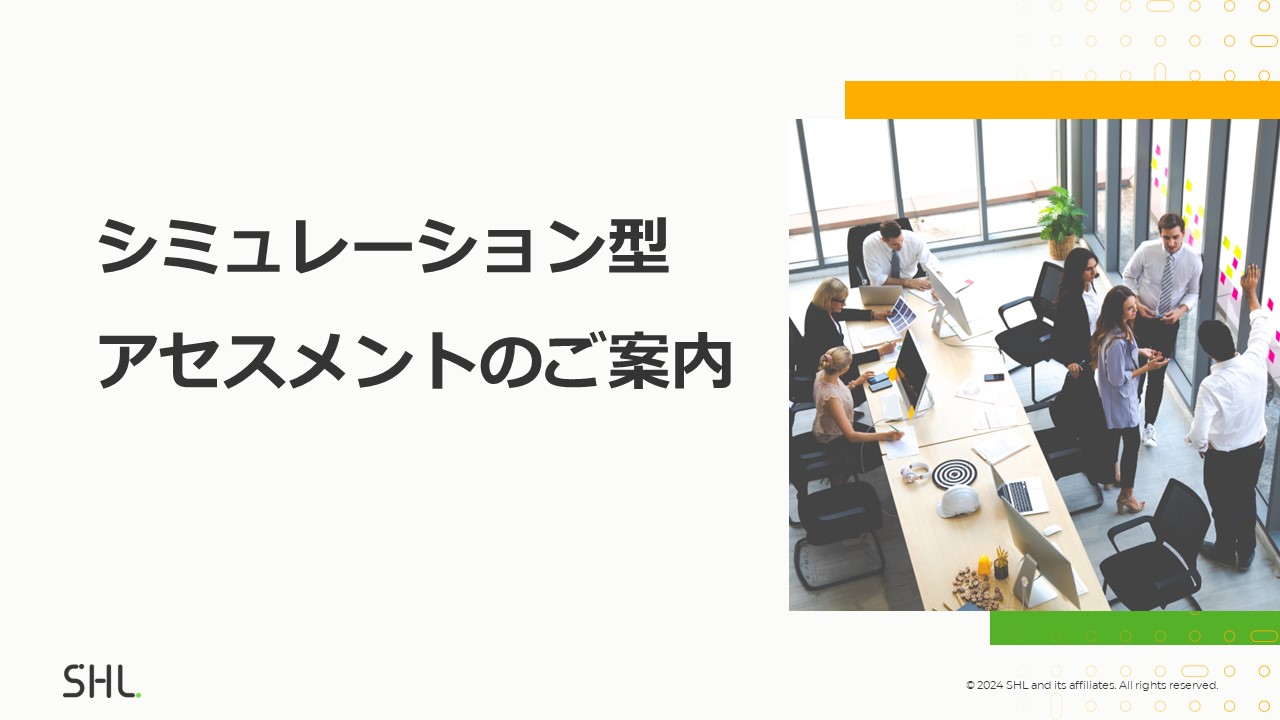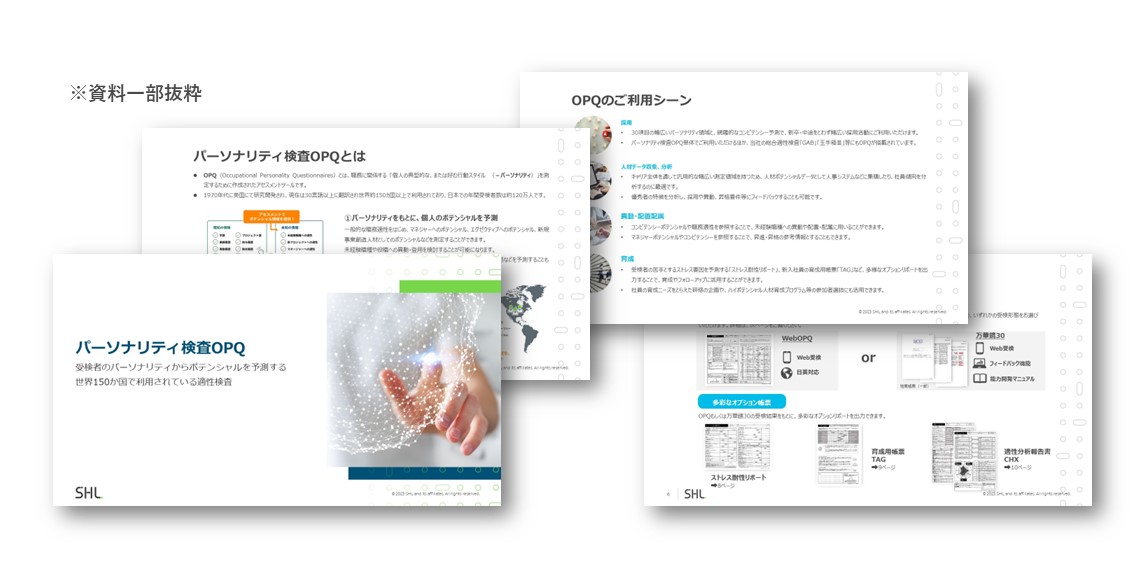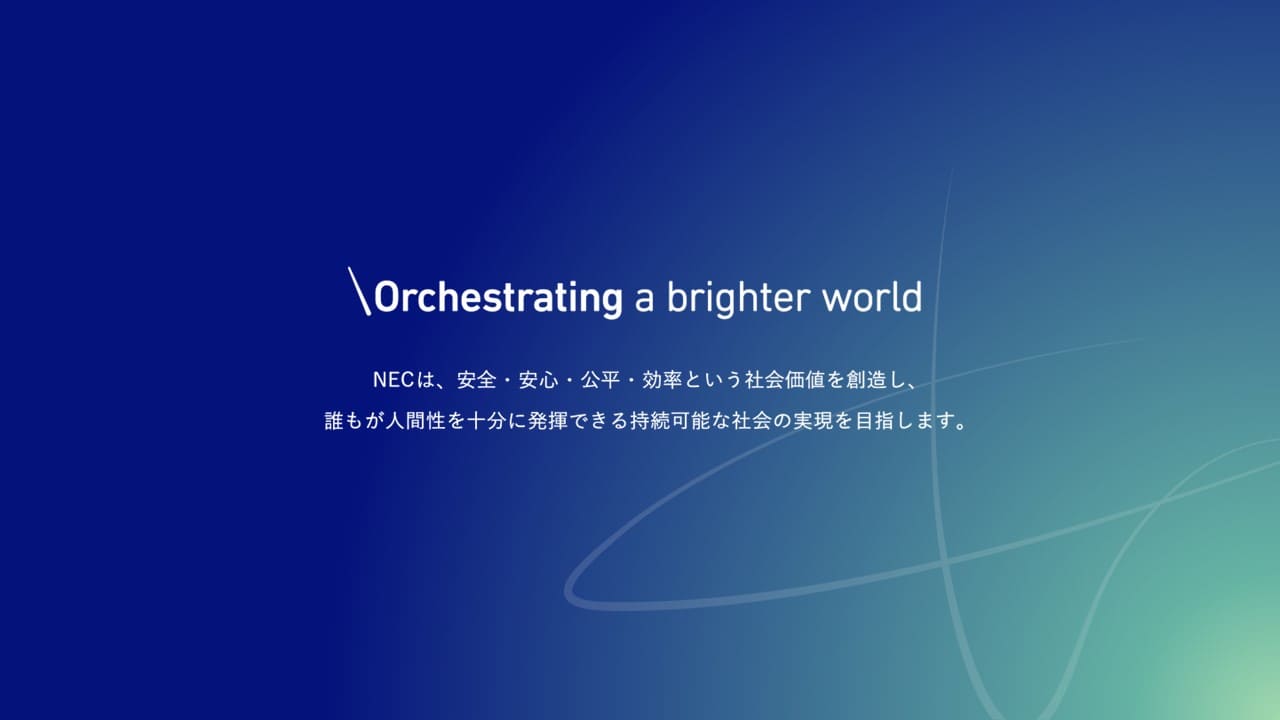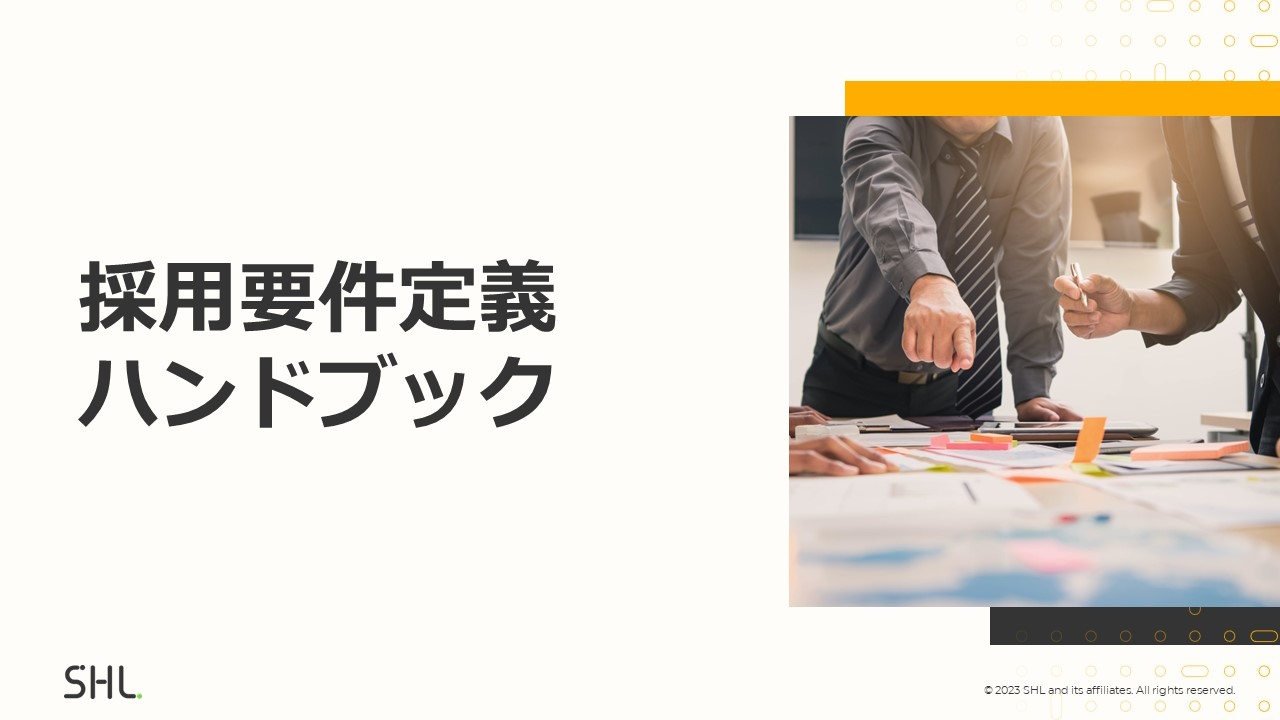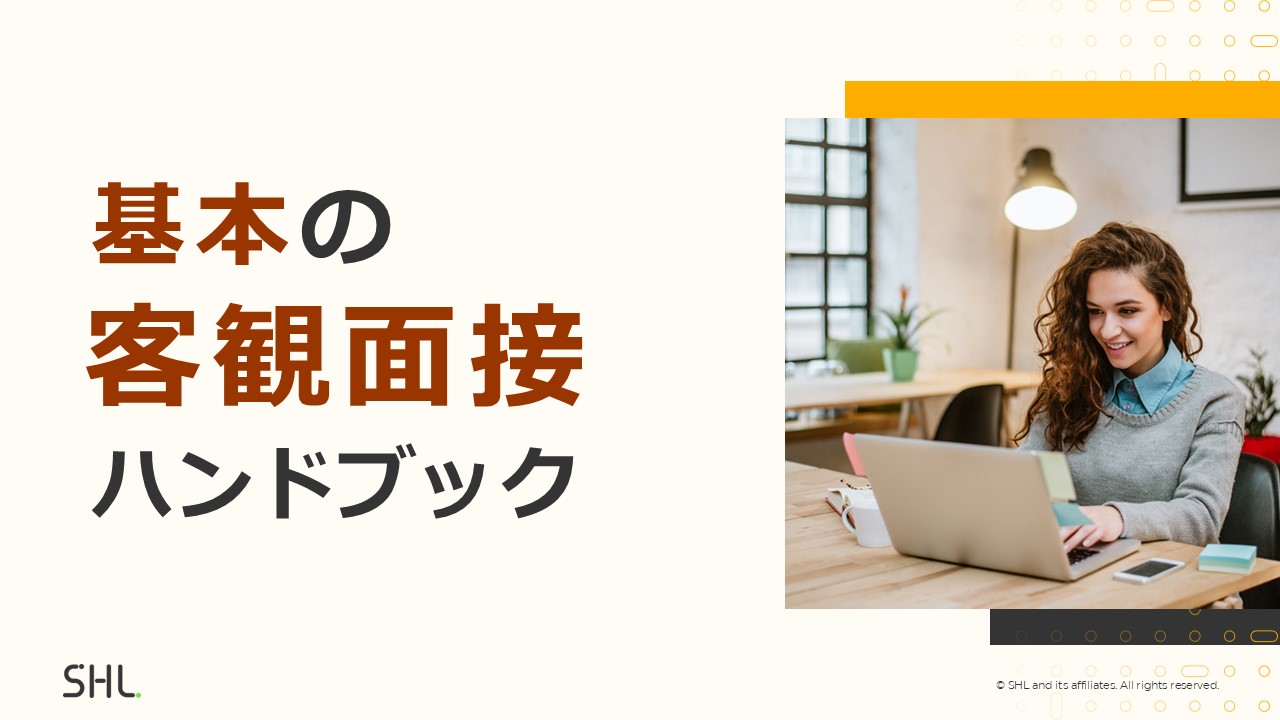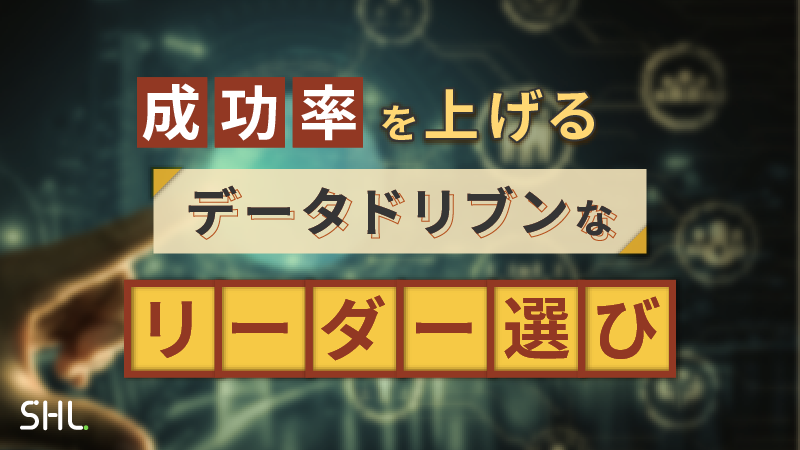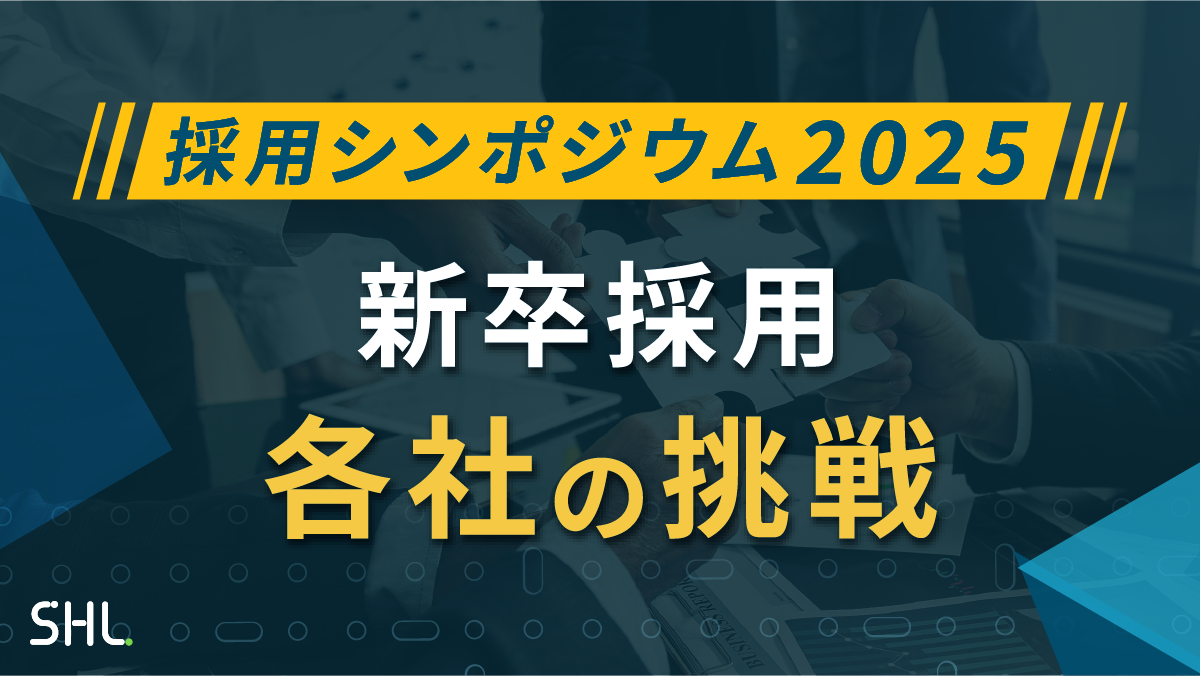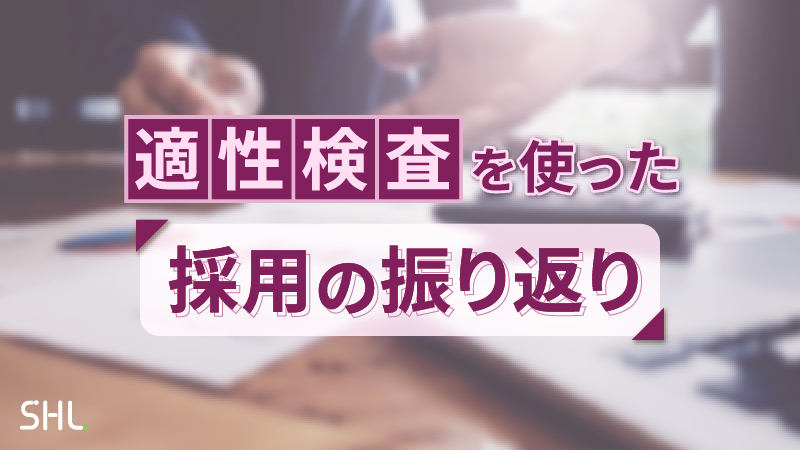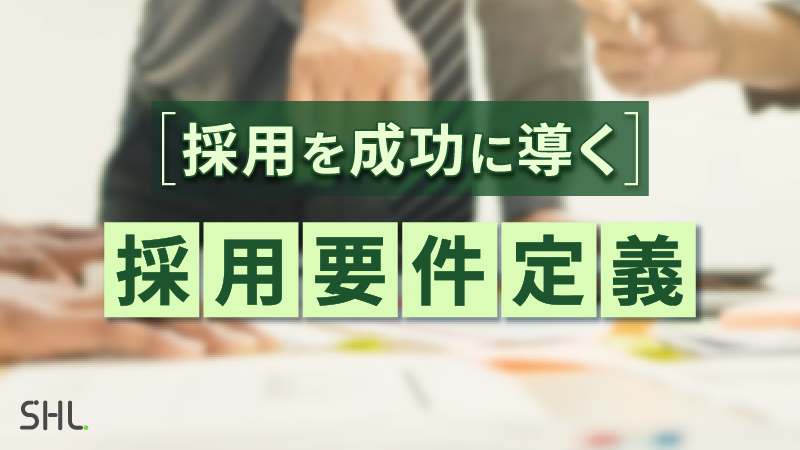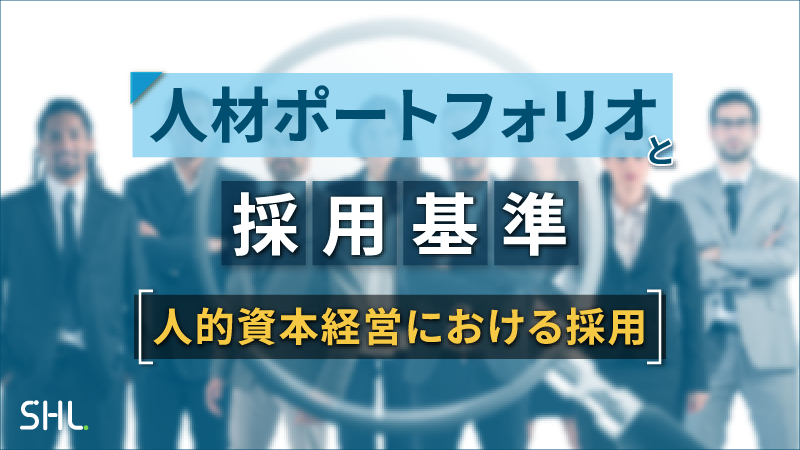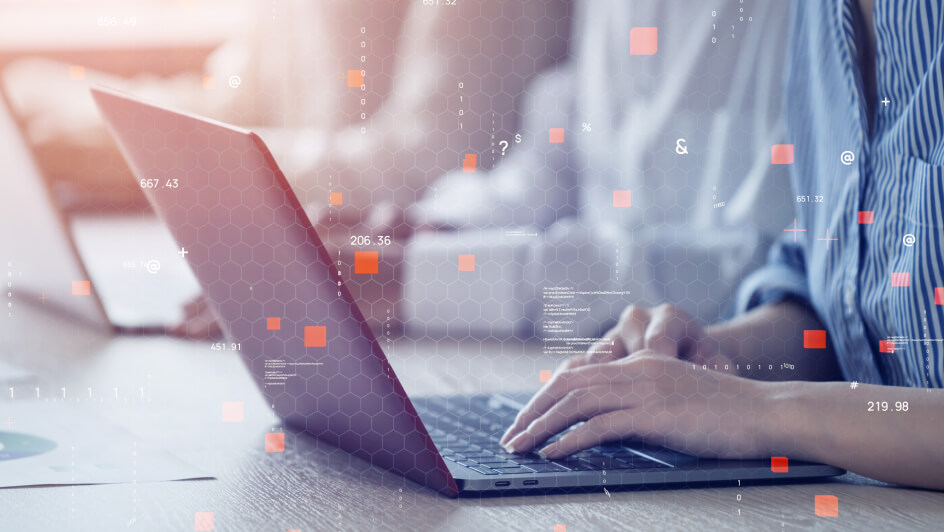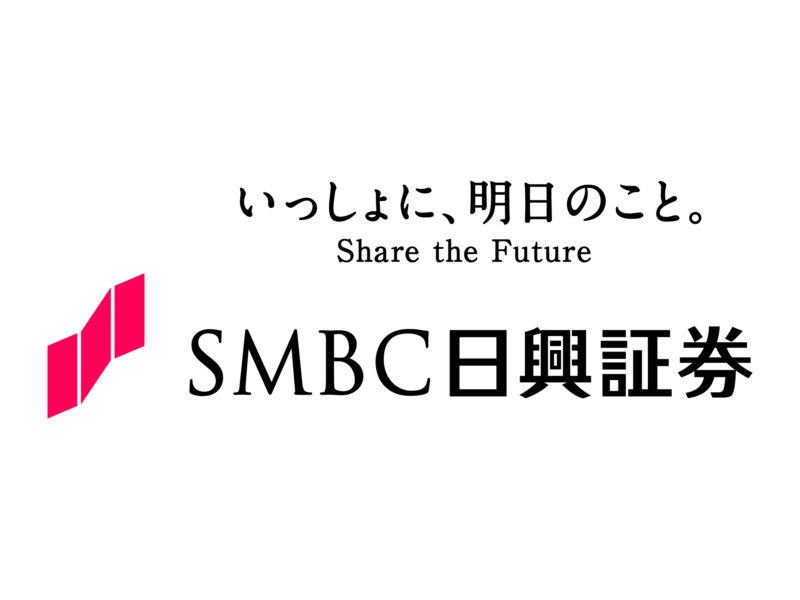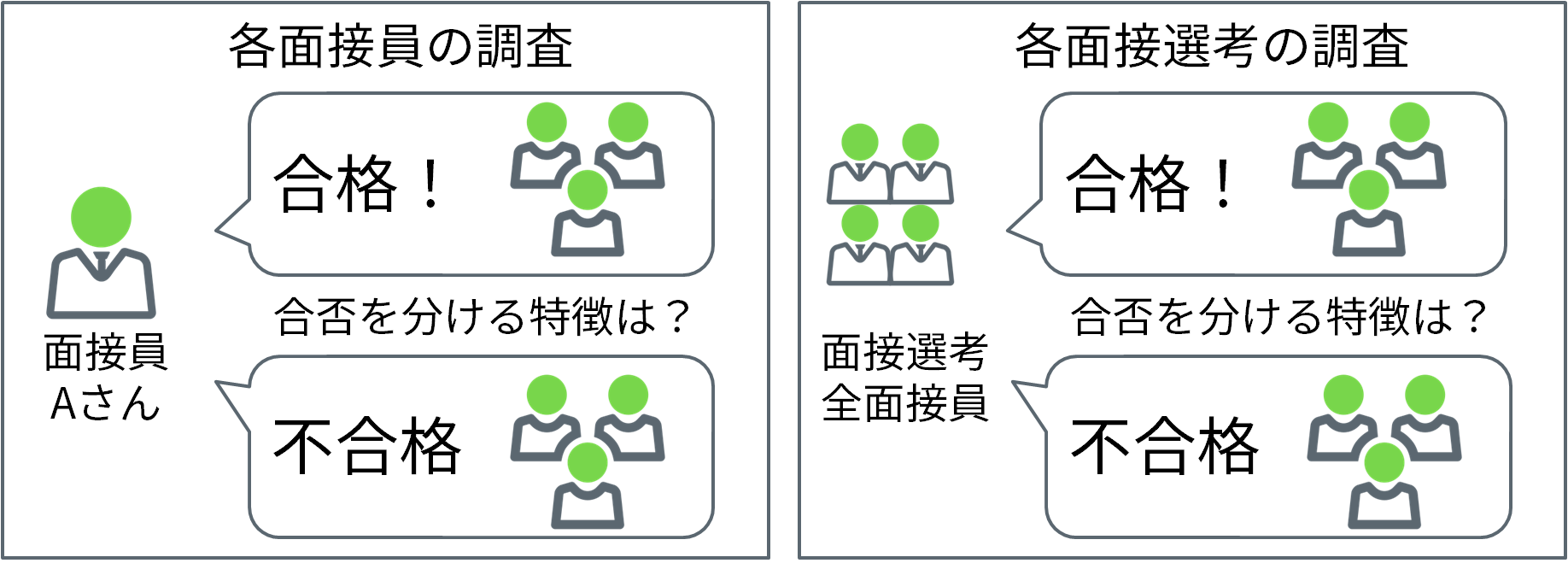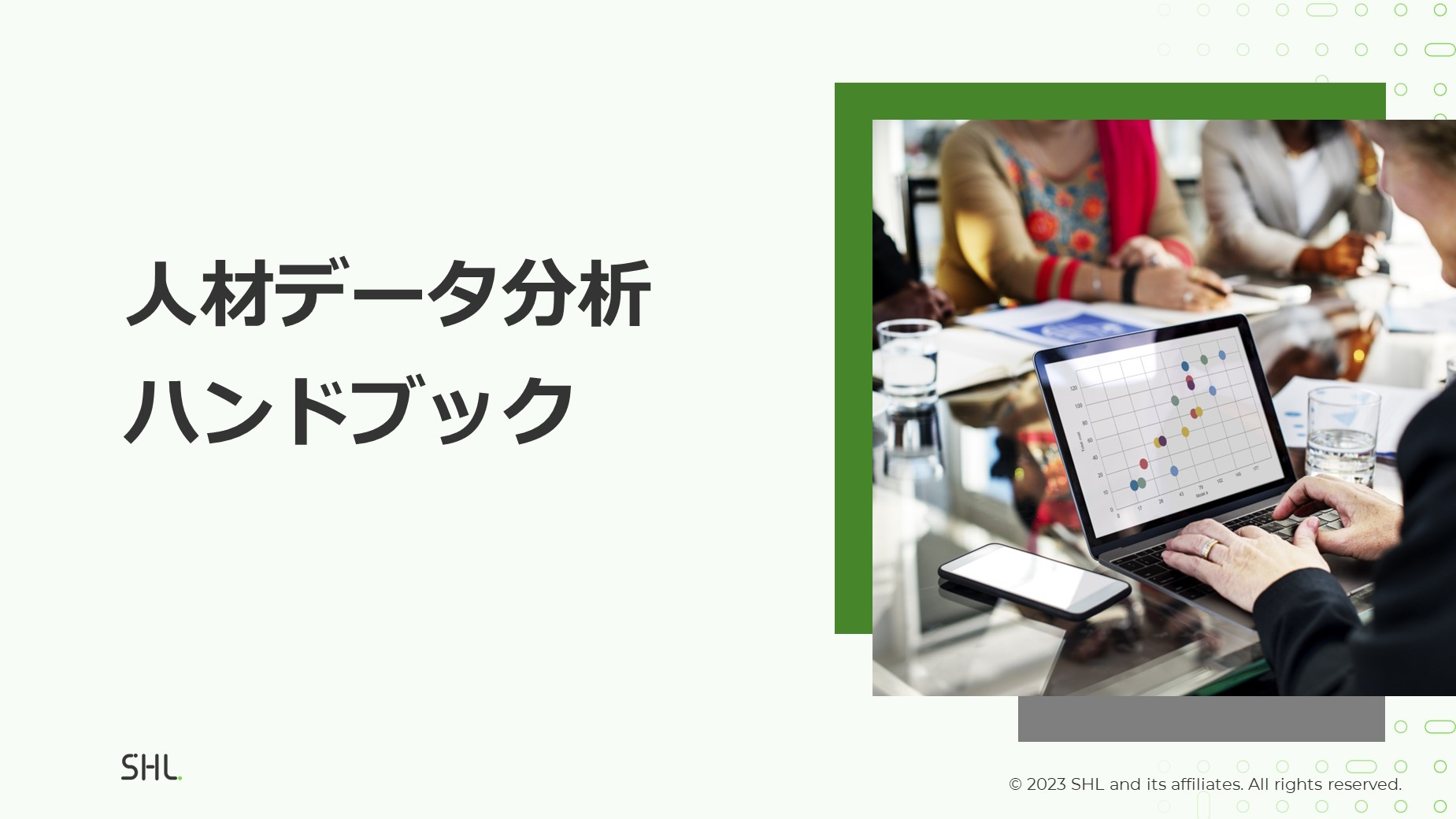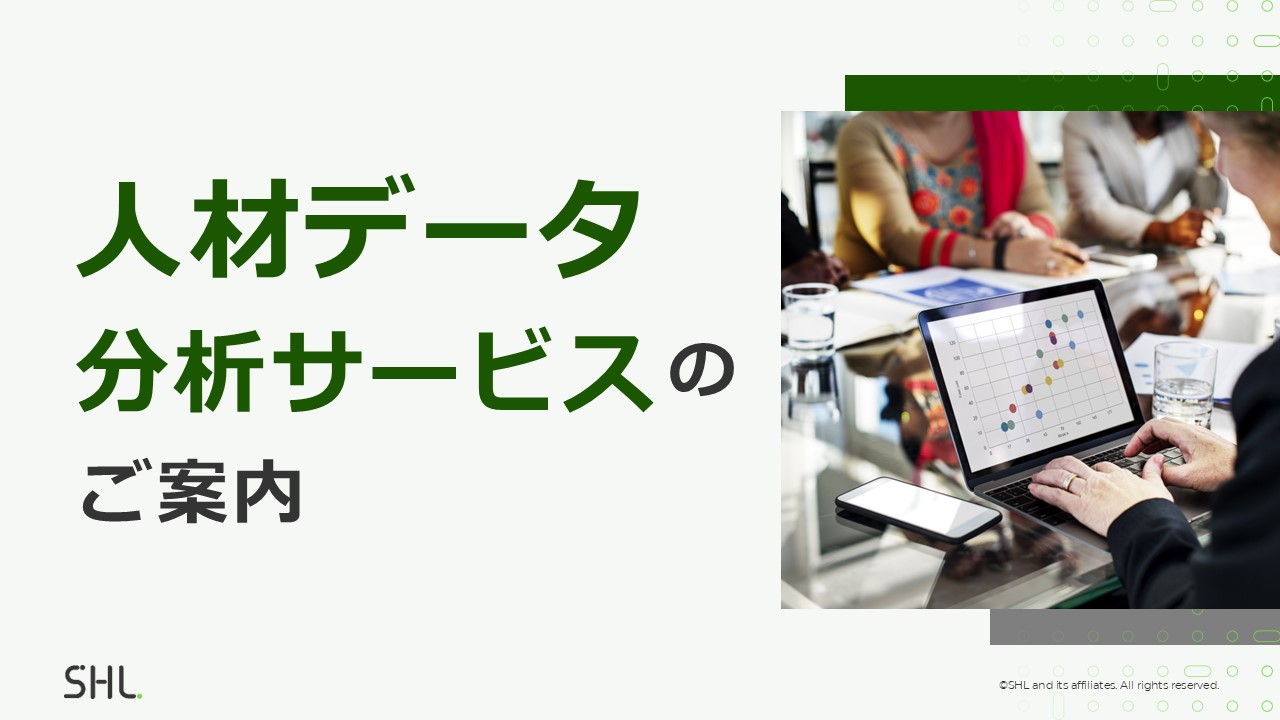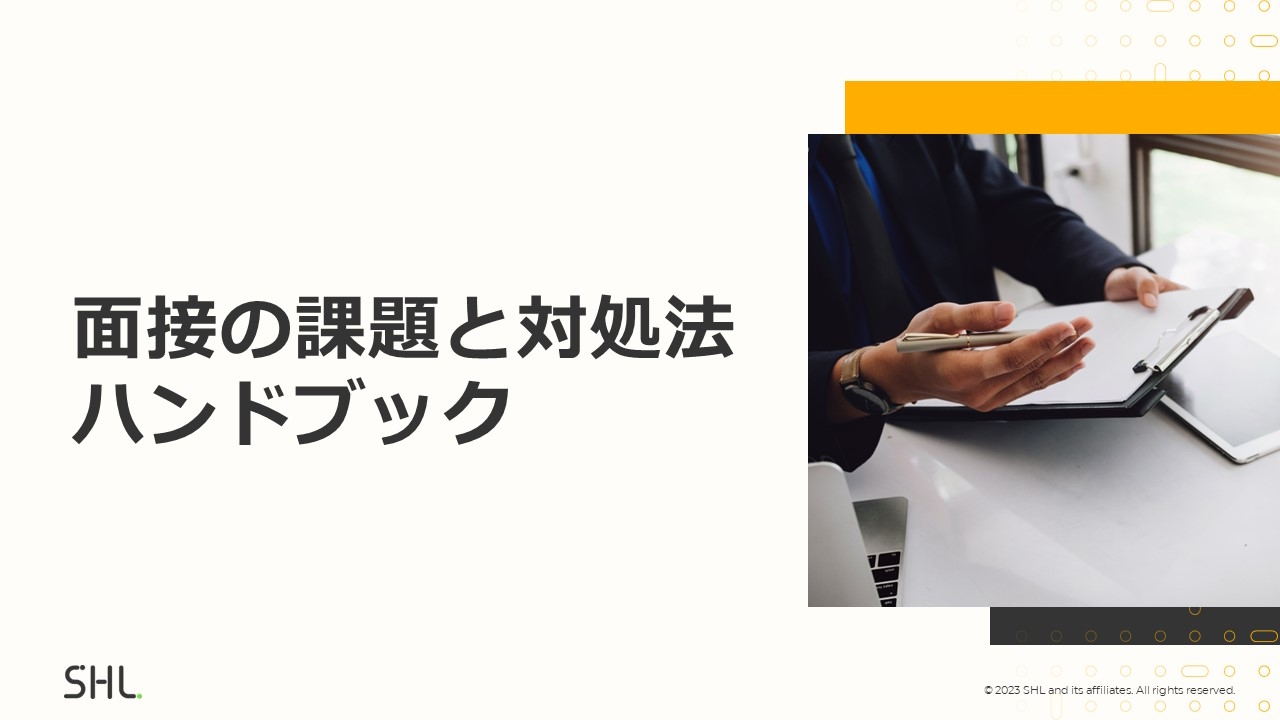インターンシップの位置づけが大きく変化している昨今、効果的なインターンシップの実施及びその後のフォローアップが採用成功のために必要であることは論をまちません。特にキャリアへの意識が全体的に高まっている中で、重要度が増しているのがフィードバックです。本講演では、フィードバックを行う際に押さえておきたい要点をご紹介します。
※本ウェビナーは2024年2月に録画したウェビナーのアーカイブ配信です。
こんな方におすすめ
インターンシップでの動機付けの方法を模索している
学生の意欲形成につながる効果的な面談方法が知りたい
インターンシップでアセスメントを活用してみたい
講師
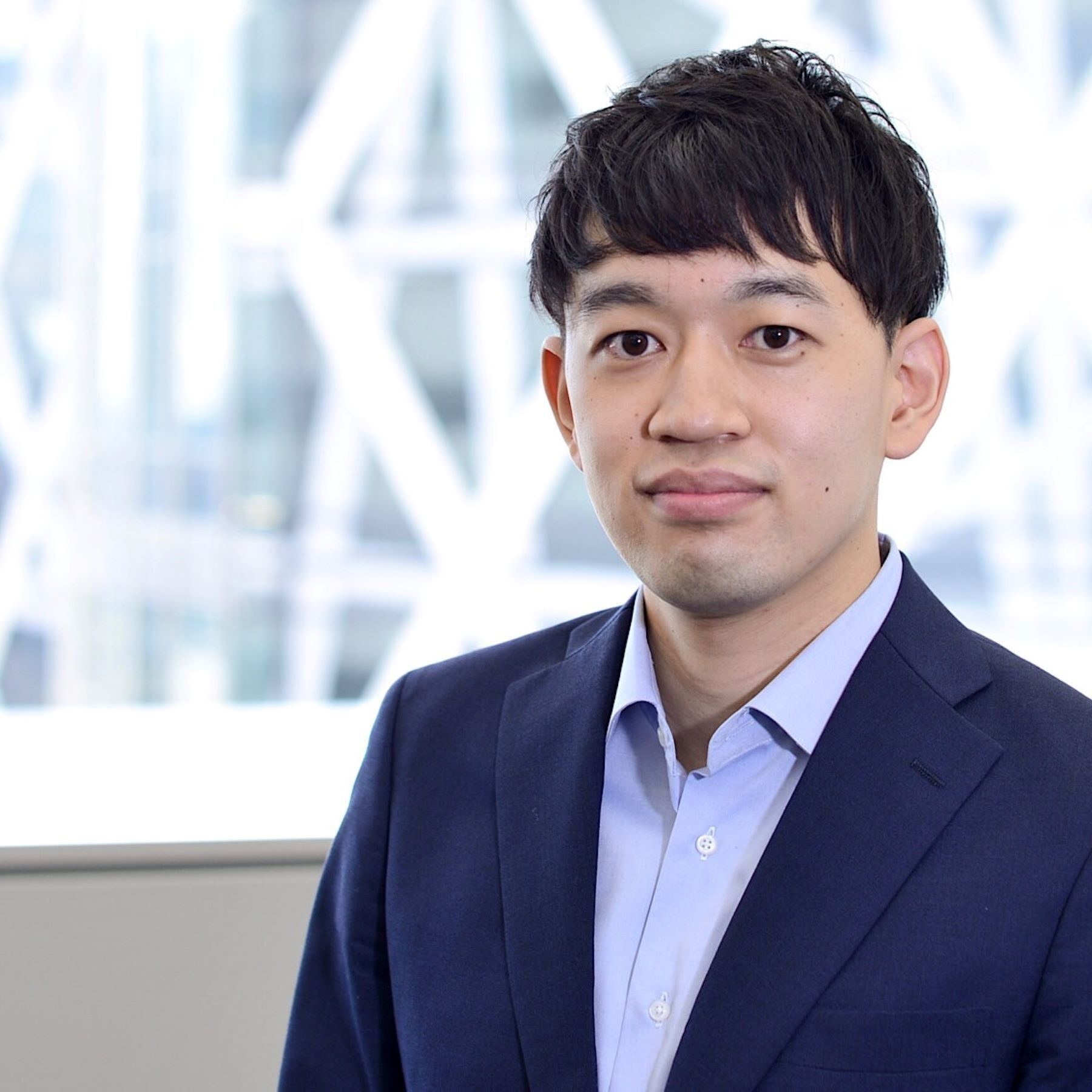
清水 智昭
日本エス・エイチ・エル
HRコンサルティング2課 主任
オンデマンド配信概要
約25分
2025年10月30日(木)まで
Zoomによる録画配信
無料
企業および組織の人事に携わる方
※同業者、学校関係者、個人の方のご参加はご遠慮ください。
日本エス・エイチ・エル株式会社 イベント事務局
TEL:03-5909-7207
Eメール: event@shl.co.jp