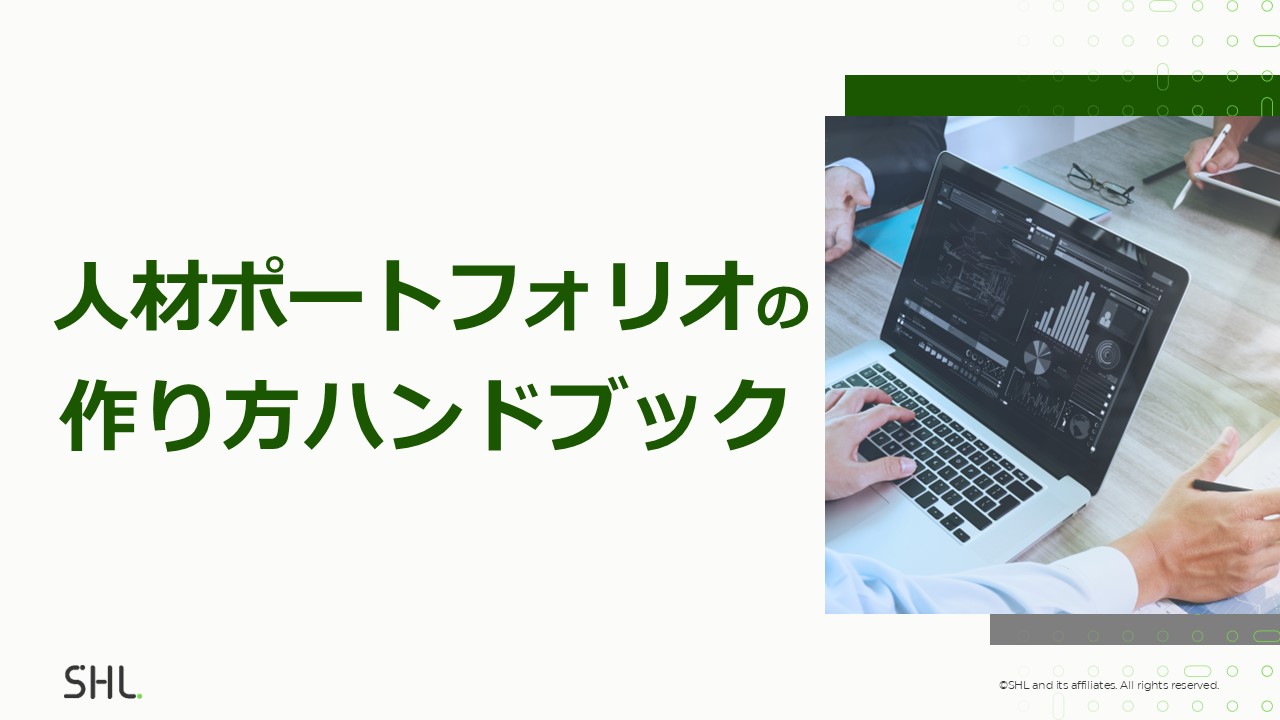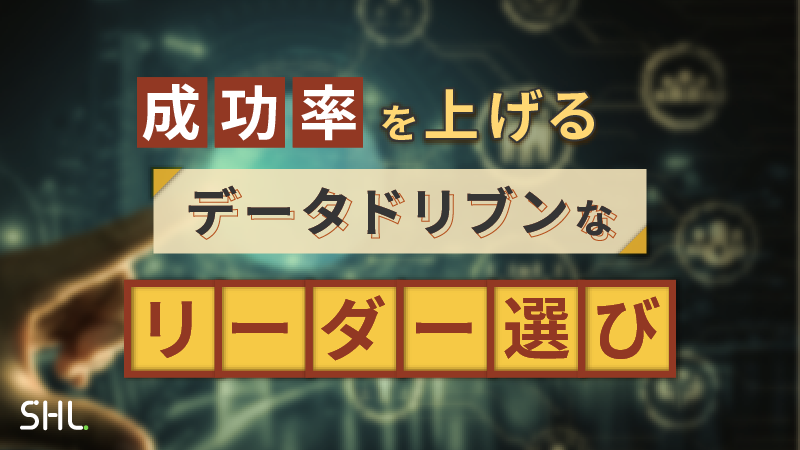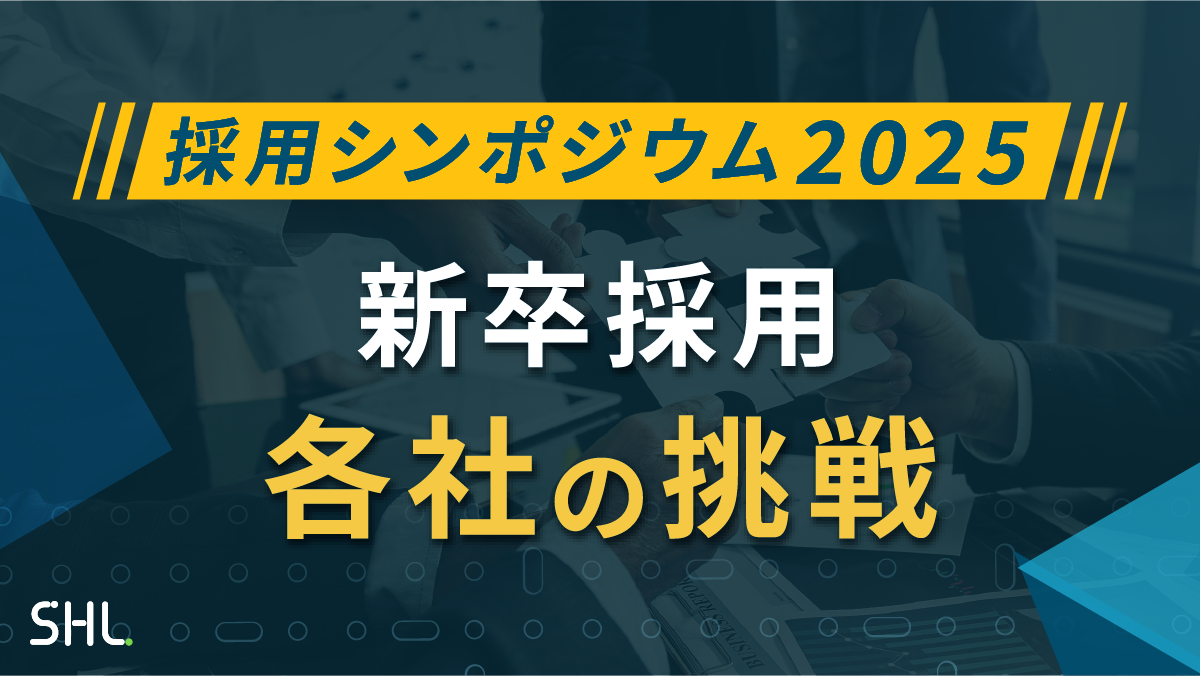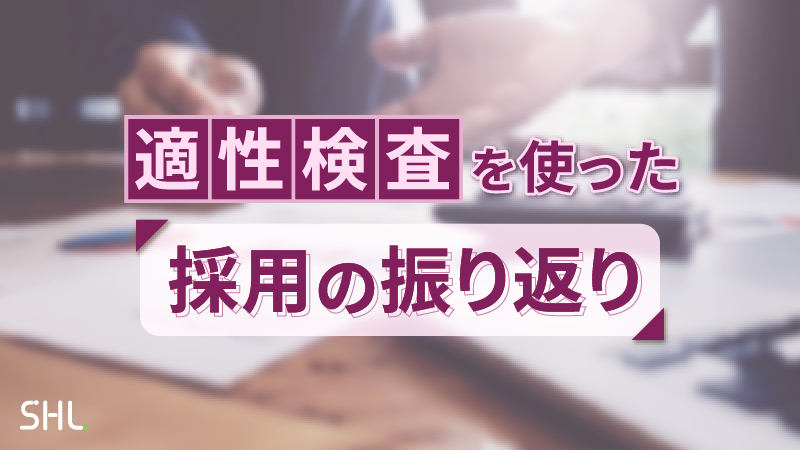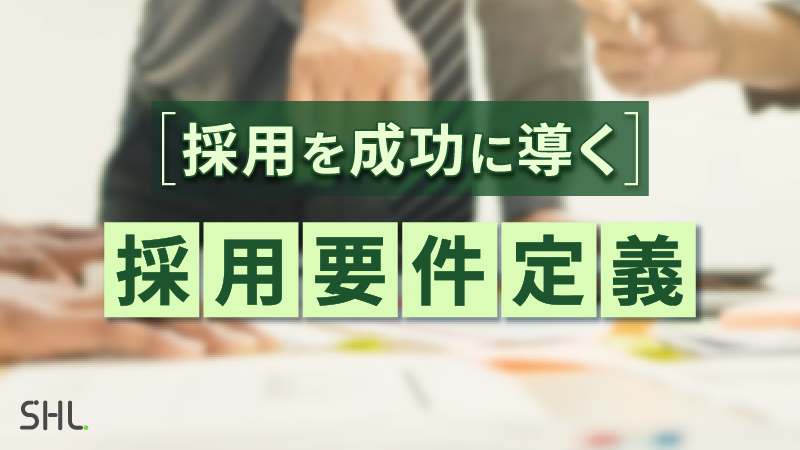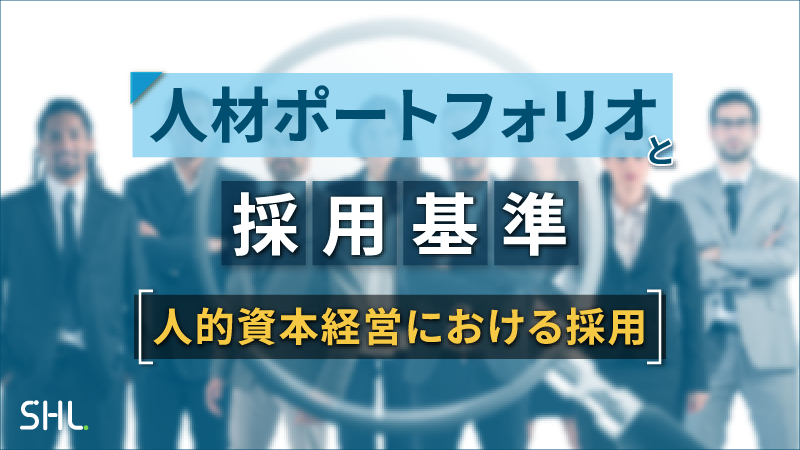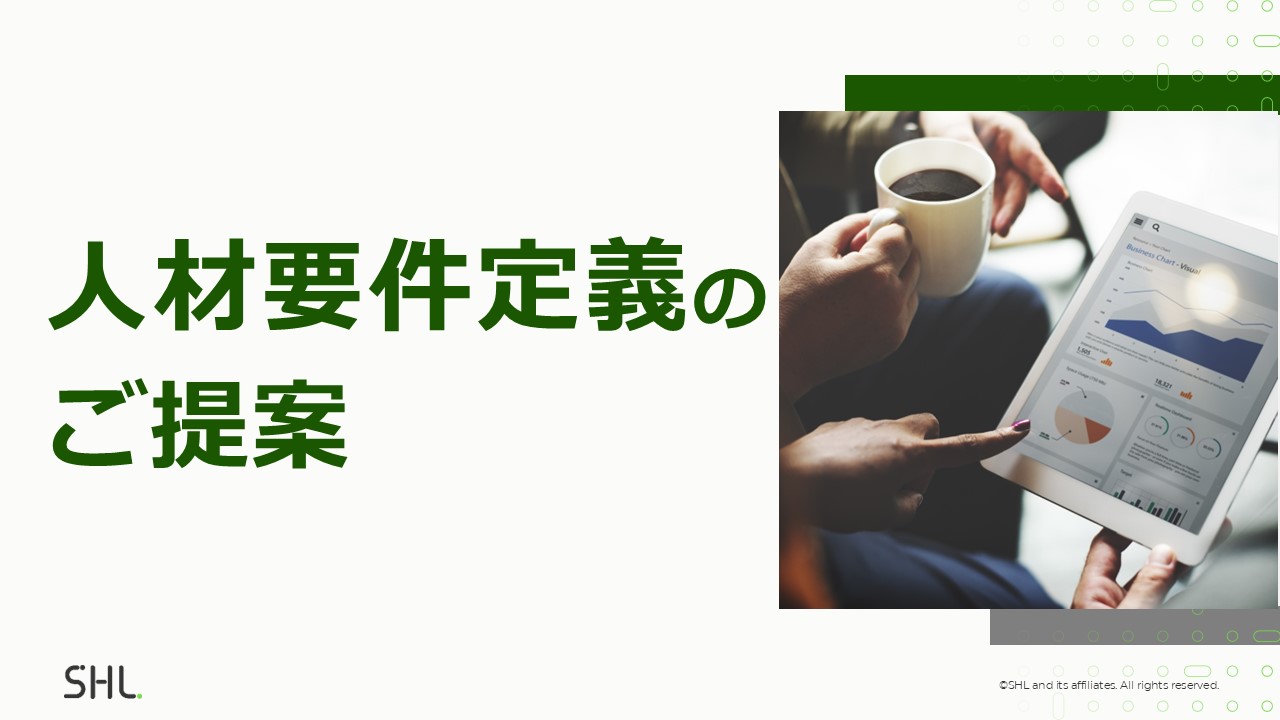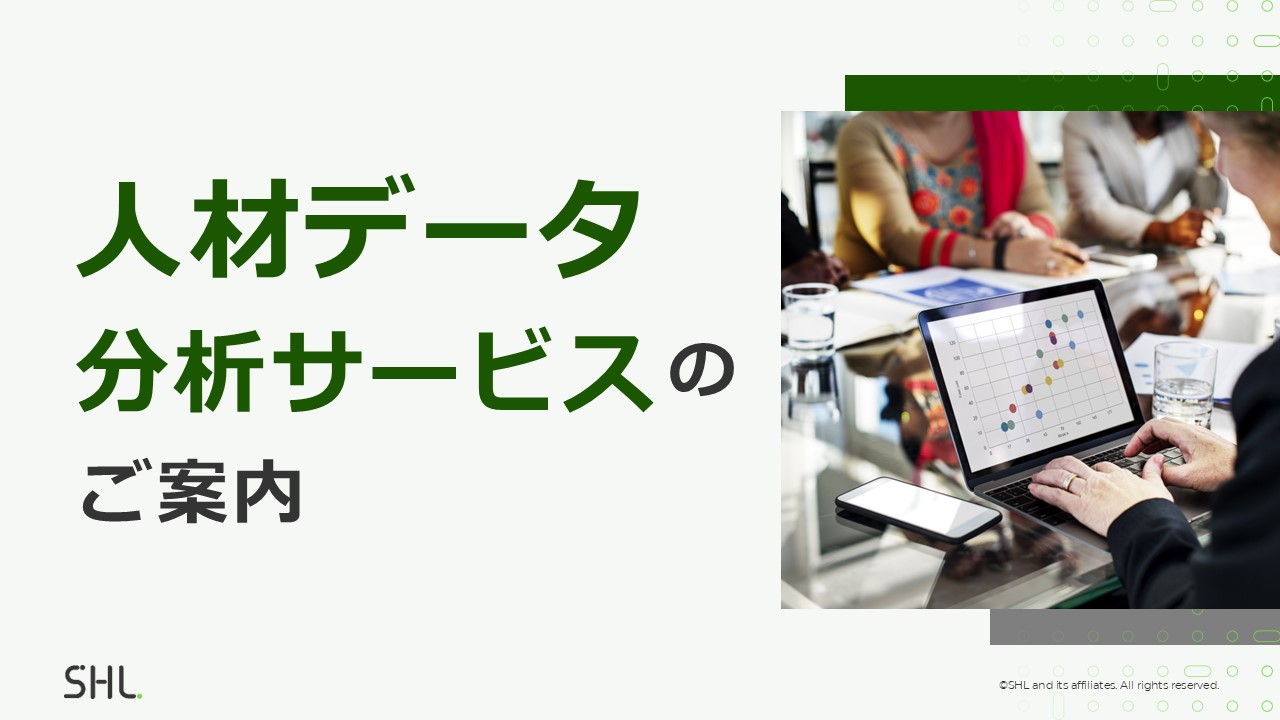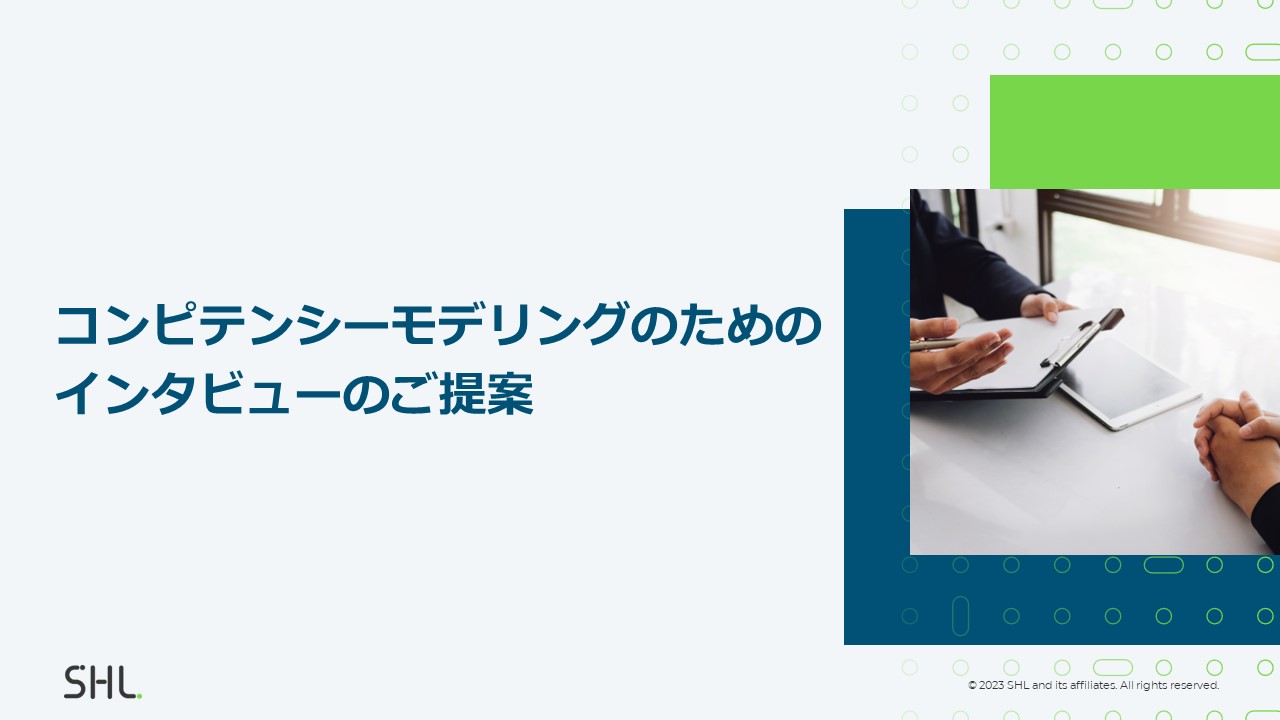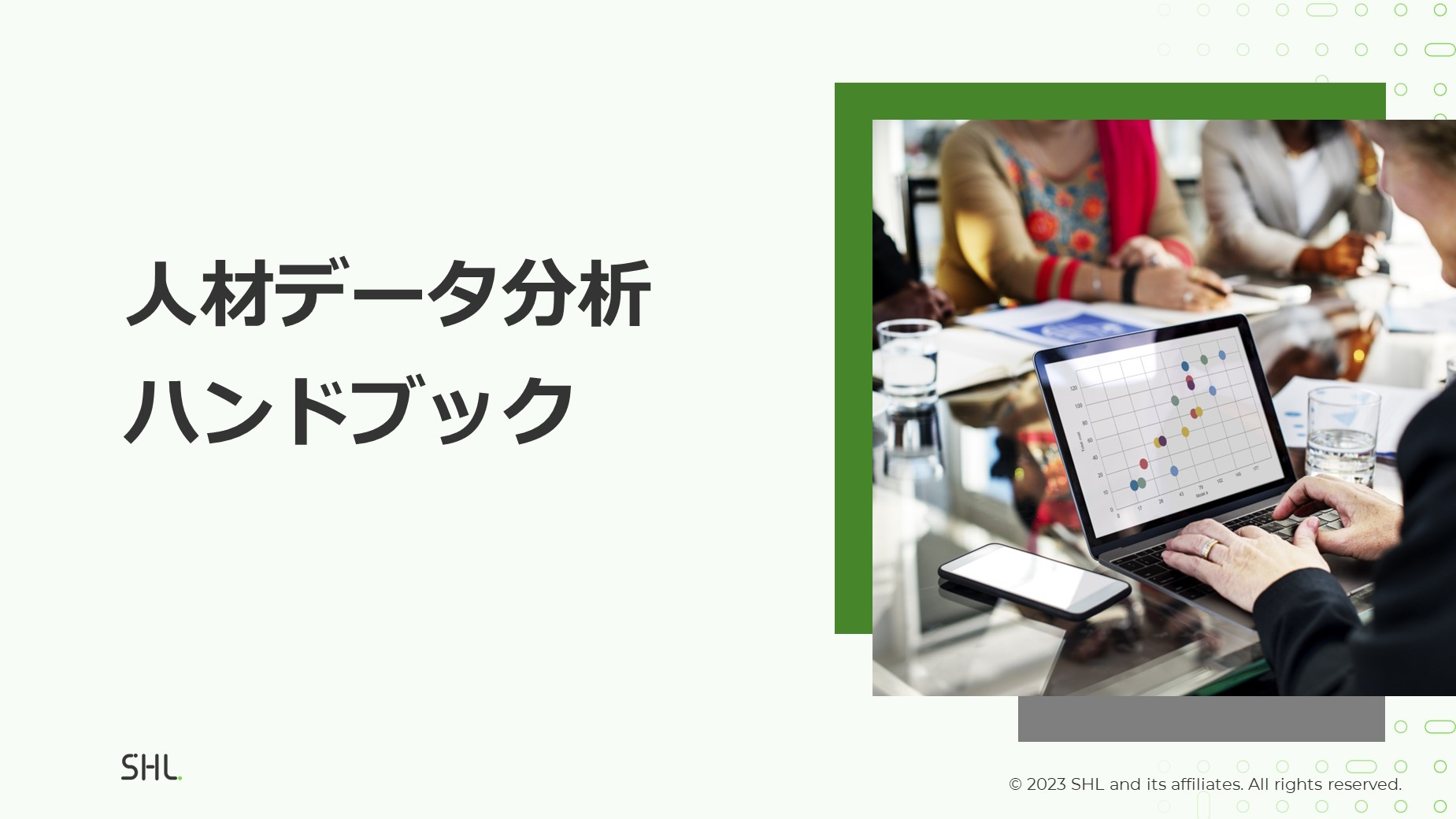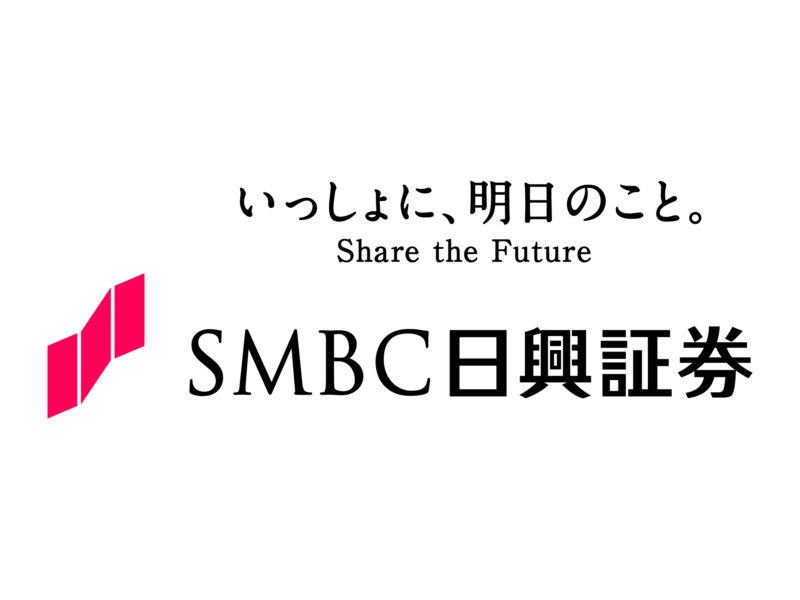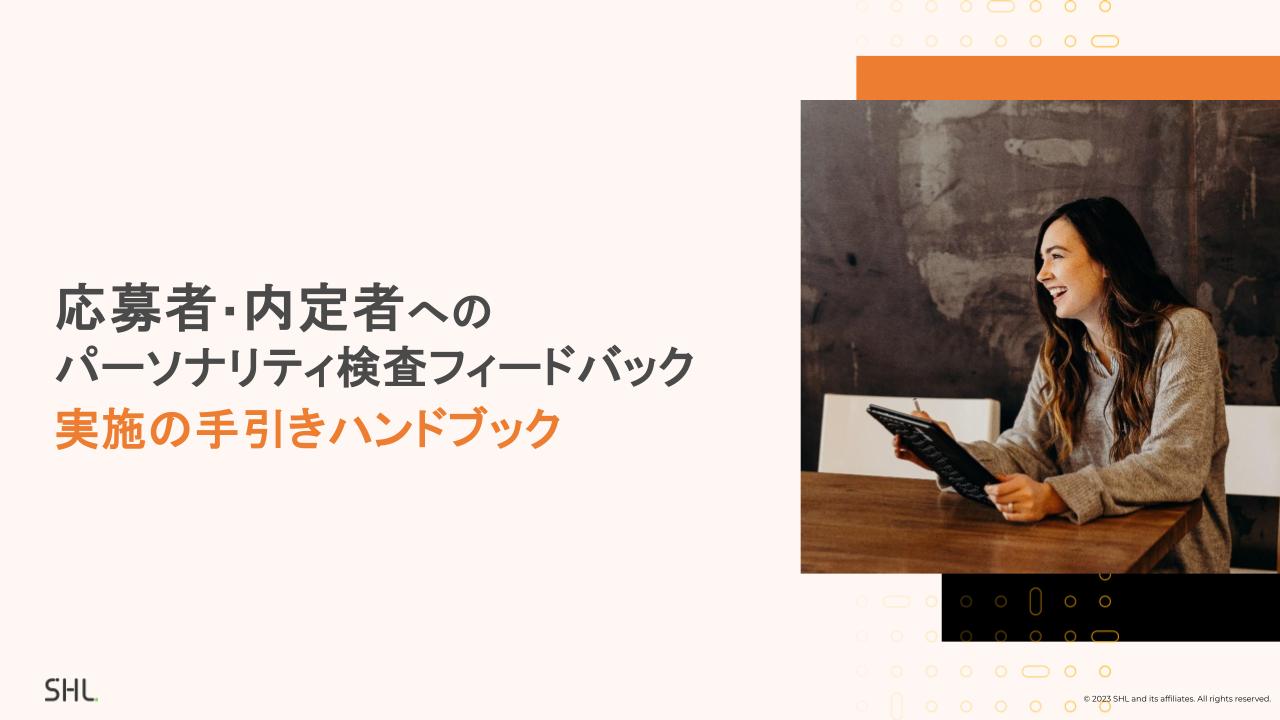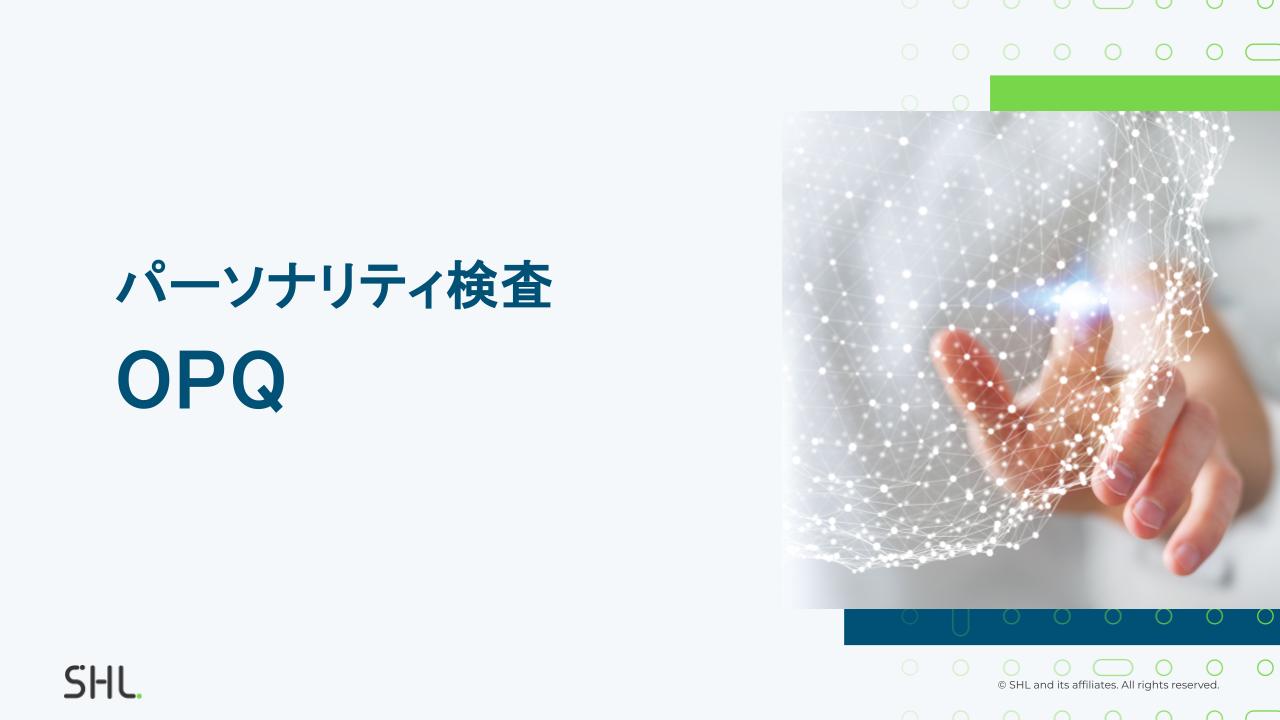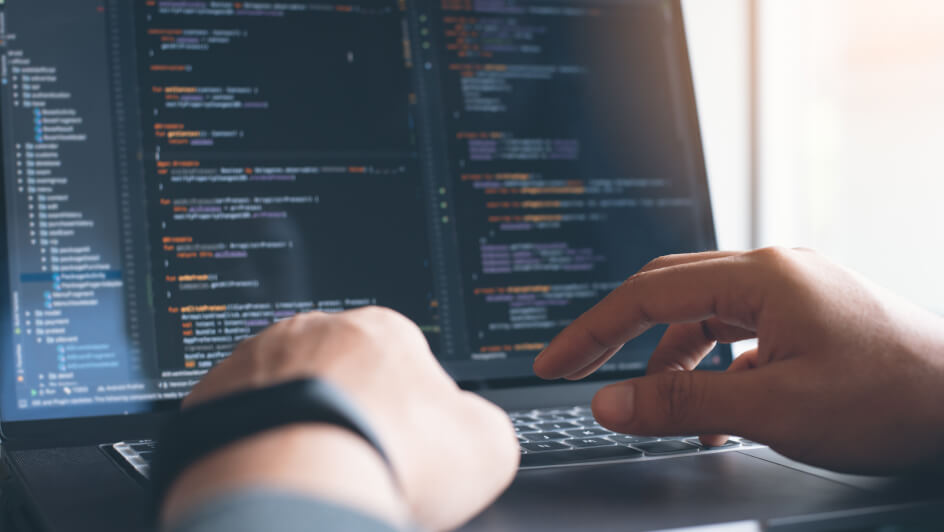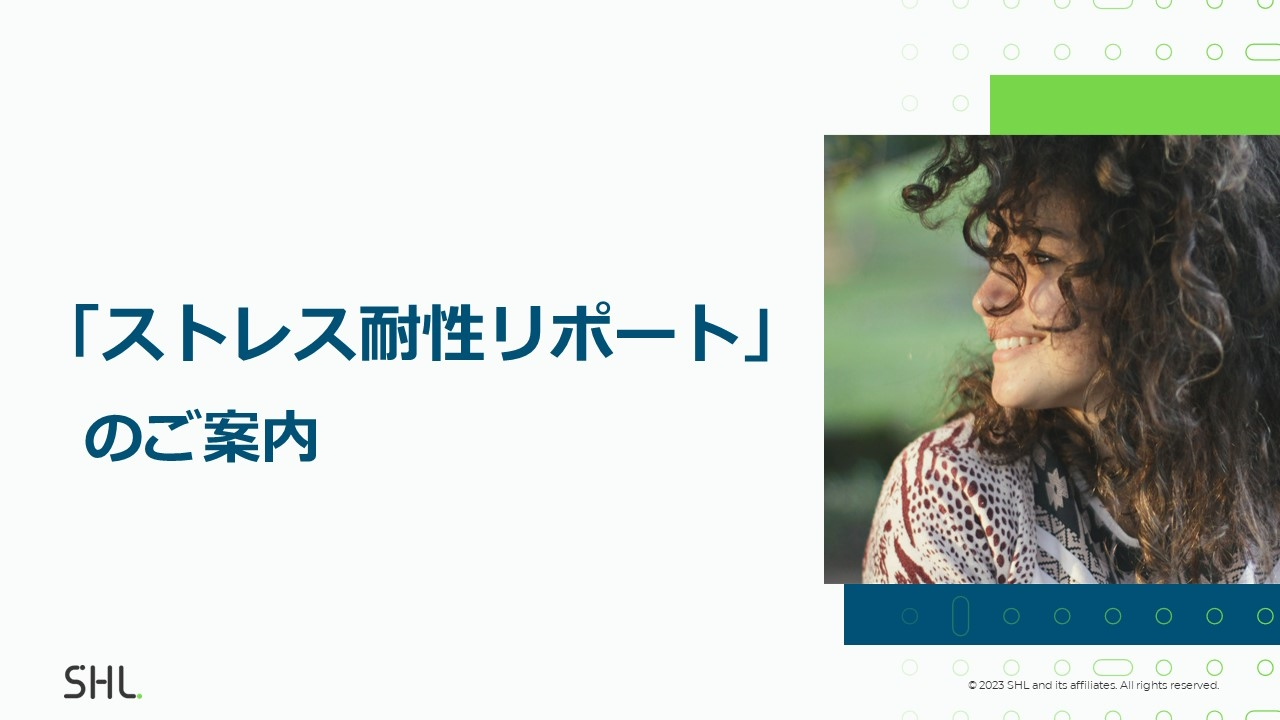通貨処理機等の製造を行うグローリー。昨今の電子決済化など事業環境の変化に対応するため、人材の計画的な発掘・育成・配置の必要性が高まり、タレントマネジメントの基礎として全社員のアセスメントデータを取得し、人材可視化を行いました。
※本取材は2023年5月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
グローリー株式会社
通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション、ロボットSI等の提供
機械
3,498名(グループ連結:10,792名)※2023年3月31日現在

インタビューを受けていただいた方
永瀬 厚司 様
グローリー株式会社
人材開発部 人材教育グループ グループマネージャー
インタビューの要約
コア技術を新たな事業につなげることができる人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。
全従業員共通のアセスメント(OPQ)を実施。説明会や動画にて自己理解の重要性を伝え、受検率100%を達成。
データ分析により全社および部門別の人材の特徴を可視化。
新任管理者研修内にてOPQの説明パートを設け、部下理解およびキャリア面談での活用を促進。
管理職の要件にPMCコンピテンシーを採用し、今後のさらなる人材育成施策を検討する。
未来に必要な人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。
私は、ソフトウェア技術者として国内および海外での製品開発を経験した後、2019年4月に人材開発部へ異動しました。人材開発部のミッションは、効果的に人材の採用・教育・発掘・育成・配置することです。現在は人材教育グループマネージャーとして、各事業部にある教育部門と連携し、全社の教育を進めています。
グローリーは通貨処理機の開発製造からメンテナンスまで一貫して行う機械メーカーですが、培った技術を活かして電子決済サービスや生体認証、メカトロニクスを活かしたサービスなどの事業も行っています。海外では競合と資本提携を進め、この10年間で海外売上比率は半分以上を占めるまでになっています。キャッシュレス化が進み事業環境が大きく変化する中で、新しい事業の柱を作るビジネスリーダー、技術で牽引する開発のリーダー、資本業務提携先とのシナジーを創出できる人材などが必要となってきました。未来に向けて必要な人材要件の定義、その素養を持つ人材を社内で把握し、全社で共有し、計画立てて育成するには至っていませんでした。これらの課題に対処するために、まず現状把握のため人材可視化に取り組むことにしました。

全従業員共通のアセスメントデータを収集。受検率100%。
タレントマネジメントを実施する上で、行動特性を示すアセスメントデータは重要な情報の1つです。しかし、当時社内にあったアセスメントデータは対象層によって異なっていたため、全従業員を共通で見られるものさしが必要だと考えました。また、海外関係会社を含めると、外国人比率も高く、グローバル展開できる日本エス・エイチ・エルのOPQを導入しました。また、従業員への負担を考えたときに、受検にかかる時間なども適切でした。さらに、再受検をせずにより詳細のコンピテンシーが見られる万華鏡リポートを追加出力できることも魅力的でした。
従業員に受検を依頼するにあたっては、全員に受検してもらえるように「キャリア自律のために自己理解を深めよう」というメッセージを発信しました。説明会を10回開催し動画も用意し、受検してもらえるよう促した結果、2カ月かかりましたが、受検率100%を達成しました。
人材の特徴を可視化。キャリア面談でも活用。
受検結果は、人材データベースシステム上で本人と上司が確認できるようにしました。上司には、部下の理解促進のために年1回のキャリア面談でOPQを活用してもらっています。結果の解釈が難しいという声もありましたが、活用度合いに関するアンケートでは、「OPQを活用して部下と対話する」という段階までは60%の方が実施したと回答しており、概ね肯定的に受け入れられたと考えています。しかし、日頃の行動と照らし合わせてフィードバックをしたり、OPQを用いて能力開発計画を立てるなど、さらなる活用段階まで至っておらず、継続したOPQ自体の理解促進や部下とのキャリア面談、1on1のやり方など実践につなげていくための学びの場が必要と考えており、今後の課題です。現場からチームメンバー全員で結果を共有してフィードバックしあい、相互理解が深まったという嬉しい反応もありましたので、こういった活用事例を共有していくことも重要だと思っています。
人材開発部では、結果データを活用し、現状の従業員の全体傾向を可視化しました。具体的には、全体傾向と開発、営業、保守などの部門ごとの傾向を分析しました。結果は従業員の特徴がよく表れており、例えば、顧客と接する職務はOPQの人との関係の領域が高得点の傾向があり、開発は低得点の傾向がありました。また、考え方の領域はその逆でした。

この結果は経営層に報告しましたが、データでの可視化はあくまでも現状把握です。ここから見えてくる仮説と、会社のビジョン達成に向けて、これから必要な人材を計画的に発掘・育成・配置するために会社がすべきアクションにつなげていくことが、次の課題です。
また、会社の経営戦略に基づいて、来年から新たな人事制度の運用が開始します。その中で、管理職の行動評価に万華鏡のPMCの中から当社として重要視する項目をピックアップし、取り入れています。このように、人事戦略、従業員のキャリア形成支援とアセスメントを有機的に機能させることで、人事戦略として掲げている「個人の成長とともに、会社が成長し、一人ひとりがグローリーで働くことに強い魅力を感じ、誇りを持っている」状態を醸成し、会社の持続的成長につなげていきたいと考えています。
日本エス・エイチ・エルは私たちに寄り添い、課題の背景を踏まえて対応策を検討してくれるパートナーです。他社人事の方との情報交換の機会を提供していただけたのも有難いです。今後もタレントマネジメント推進のため様々なご支援をお願いしたいと思っています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
鈴木 悠太
今後の事業展開を踏まえタレントマネジメントの実施に踏み切り、文字通り全社員データを取得、そのデータを様々な人事施策に活用されている本お取組みはタレントマネジメントの好例ではないかと考えております。「アセスメントデータを余すことなく活用したい」、グローリー様が本お取組みに着手され受検率100%を達成し、全社員データを取得した後に永瀬様から改めてご相談いただいたことを今も強く覚えております。次なる人事施策に向けてアセスメントデータをどう活かせるか、都度ご相談を頂戴してお打ち合わせを続け、様々な施策の検討に携われていることは私自身とても大きな経験となっております。グローリー様の「パートナー」と仰っていただいたことに恥じぬよう、今後も微力を尽くして支援させていただきます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

高度ソフトウェアエンジニア育成のための新人事制度を導入した、デンソークリエイトの企業改革をご紹介します。
※本取材は2021年12月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社デンソークリエイト
車載組込ソフトウェアに関連する研究開発および先行開発、開発支援ソフトウェア(プロジェクトマネジメントツール、レビュー支援ツールなど)の開発、ソフトウェア技術者教育、プロセス改善・品質監査およびソフトウェア構造改革推進
情報・通信業
277名(2022.1.1現在)

インタビューを受けていただいた方
加藤 宏幸 様
株式会社デンソークリエイト
取締役
インタビューの要約
自動車産業におけるソフトウェアへのニーズの急拡大に対応するため、企業改革を実施。「高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループ・業界をリードする会社」を目指し、スペシャリスト育成に振り切った新人事制度を導入。
新制度のポイントは、早期のキャリア複線化、キャリアアップ計画の作成、能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)に基づく絶対評価の人事考課、年功色の薄い処遇など。
コンピテンシー基準は日本エス・エイチ・エルのアセスメントをもとに作成。これに則り毎年の評価者研修を徹底。また、昇格候補者の審査にも同様のコンピテンシーが適用されている。
新人事制度導入以降18名のスペシャリストが誕生し、社員満足度調査の結果も向上。人事考課アンケートや社員満足度調査によるフィードバックを得ながら、現在も制度の改善を続けている。
ソフトウェアニーズの急拡大により会社への期待が増大。高度ソフトウェアエンジニア集団としてグループと業界をリードする会社を目指し、企業改革を実施。
当社は自動車がソフト化する将来を見据え、優秀なソフトウェア技術者の獲得を主な目的として、名古屋の小さなIT企業として誕生しました。ソフト開発を行うのは人であり、人だけが財産の会社です。親会社とは異なる、当時としては思い切った独自路線で、人事の仕組みを作成しました。コアタイムなしのフレックスタイム制、服装は自由、「アトリエ」という担当業務以外を含む組織でのコミュニケーションと自己研鑽などが特色でした。
設立から四半世紀が過ぎ、会社の規模が拡大するにつれ、トップが全員の能力を把握して処遇するようなことはできなくなりました。人材管理、配置・育成をしくみで行うこと、いわゆるタレントマネジメントが必要になったのです。
ソフトウェアに対するニーズの急拡大により、会社への期待が一気に高まる環境変化に対応し、2016年から企業改革を開始しました。目指したのは「高度ソフトウェアエンジニア集団としてデンソーグループ・業界をリードしていく会社」。親会社からの依頼に対応するだけではなく、ひとり一人が主体性を持って考え、提案し、自身のキャリアを描いて切磋琢磨する組織風土を目指しました。
スペシャリスト育成のための新人事制度をスタート。キャリアの複線化、キャリア計画の作成、コンピテンシーとスキル両面の能力開発、絶対評価などを導入。
改革の目玉として、2017年に新人事制度をスタートしました。それまでのトップの関与が強く、個別に判断して決める傾向があった人事から、仕組みで回す総合的な人事制度を構築して導入。人事の方針は、ソフト技術者は労働市場において流動性が高いことを前提とした考え方から、長期雇用・育成重視へと舵を切りました。
新制度のポイントは、スペシャリスト育成のための早期のキャリアの複線化と、それに付随するキャリアアップ計画の作成。そして能力基準(コンピテンシー)とスキル基準(ソフトエンジニアとしてのスキル)の作成、これに基づく絶対評価の人事考課と、年功色の薄い処遇などです。

新人事制度の導入に際しては、日本エス・エイチ・エルの協力のもと、評価・育成の根幹となる人材要件(コンピテンシー)を設計しました。このコンピテンシーに基づき、毎年の評価者研修や、昇格候補者の審査等を行っています。また「万華鏡30」を全社員が継続的に受検し、本人と上司が結果を共有の上、キャリアアップ計画作成や能力開発に活用しています。昇格候補者は別途アセスメントを受検し、その結果について日本エス・エイチ・エルのコンサルタントからフィードバックを受け、上司と本人と人事の三者で共有の上、行動改善に役立てています。 ソフトウェア技術者は科学的なアプローチを好むため、能力開発にも計測・データ解析に基づく根拠を示すことは非常に有効です。言葉だけよりも説得力が高まり、行動改善に繋がる可能性が高いと考えています。
新人事制度の成果は、活躍するスペシャリストの誕生、社員満足度の向上。
複線型人事は、会社ニーズだけでなく社員のニーズにも合致していましたので、歓迎されました。管理職ではなく専門職としてキャリアを積みたい人材も数多くいます。結果として18人のスペシャリストが誕生しました。その認定や昇格は、課題発表やアセスメントデータにより吟味して決定しているため、認定・昇格後はほぼ期待通りに活躍してくれています。会社に対するグループ内の評判も向上してきていると感じています。
また、毎年行っている「社員満足度調査」の結果では、新人事制度導入後、人事制度・育成制度に対する満足度は着実に向上しました。会社全体への満足度を示す「総合満足度」は、約50%から70%まで大幅に向上しており、人事の施策は間違ってはいないと自負しています。
新制度の導入は終わりではなく、始まりだと思っています。特に人事制度の要となる人事考課制度については、毎年評価者研修を実施し、評価の行い方と目線を統一しています。また運用の実態を把握するため、人事考課アンケートや社員満足度調査の結果を検討し、評価者やフィードバック者の変更、業績評価の簡素化など、試行錯誤を繰り返しています。
今後の課題は、実務的には、複線化したスペシャリストコースの拡充と認定方法の改善。先が見通し難い世の中で、キャリア形成の仕方をどう考えるかも課題です。また、どちらかと言えば内向きでモノを言いたがらないソフト技術者の意識を変えて、活発な議論が起きる企業風土へと改革を目指すべく、新たな打ち手を考えています。最終的な目標は、デンソークリエイトを日本のソフトウェア産業を代表する会社にし、社員が誇りを持って笑顔で毎日働けるようにすること。人事制度はそのための手段と考えています。
日本エス・エイチ・エルは、グローバルの膨大なデータと知見を持ちながらも、自社の理論を押し付けずに、常に同じ目線に立って寄り添ってくれる点がありがたいです。企業の信頼度だけでなく、適性検査の正確さ、コンサルタントの方の力量も大きいです。長年実施しているフィードバック面談は非常に好評で、今や欠かせない年中行事になっています。これからも宜しくお願いします。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
改正 晃大
高度なスペシャリストを育成するための先進的な人事制度やタレントマネジメント施策はIT業界のみならず、日本の産業をリードする取り組みです。この様なタレントマネジメント施策の設計と運用に深く関わることができ、大変光栄です。「新制度の導入は終わりではなく、始まり」という言葉の通り、制度は導入することが目的ではなく、制度の運用を通じて人が育ち、組織を発展させることが目的です。これからもデンソークリエイト様が目指す「日本のソフトウェア産業を代表する会社」に向けて、コンサルタントとして共に試行錯誤し、お力になりたく存じます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

中部電力グループ唯一のIT企業として、「エネルギーの安定供給」をシステムインテグレーターとして支える中電シーティーアイ。電力自由化等によって事業環境が変化し、DXのさらなる推進のために社員一人ひとりのキャリア形成を支援する人事制度改革を行いました。
※本取材は2023年8月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社中電シーティーアイ
アプリケーション開発保守サービス、インフラセキュリティサービス、解析サービス、大量データ処理サービス、IT運用サービス
情報・通信
1,271名(2023年6月1日現在)

インタビューを受けていただいた方
林 達也 様
正村 宣美 様
株式会社中電シーティーアイ
経営管理本部 人事部 採用・人事企画グループ マネージャー(写真右)
様経営管理本部 人事部 採用・人事企画グループ 専門課長 (写真左)
インタビューの要約
サービスの高度化に合わせて、人材の配置や育成の仕組みを変革すべく、企画から1年で人事制度改革などの様々な施策の運用を開始。
社員のキャリア形成を支援するために、社長・役員も含めてアセスメントを実施。結果の見方研修や説明資料により社内への浸透を促進。
取得データは日々のマネジメントからプロジェクトへのアサイン、全社や部署の特徴の可視化など人事施策の様々な場面で活用。
一気呵成に行った人事施策について、社員の反応や声をしっかりと聞きながら定着させていく。
DX推進のため、人材の流動性を高め、キャリア形成を支援する。
電力自由化により、一層の経営効率や新規サービスに取り組むことが求められるようになりました。その中でITの力は戦略上欠かせません。DXを一層推進する必要があります。これまではどちらかといえば受け身でシステムを作る仕事がほとんどでしたが、より高度な仕事をすることが求められるようになり、仕事の仕方そのものを変えなければいけないという問題意識がありました。組織として人員をなるべく高度領域の仕事にシフトし、保守運用の仕事を海外を含めて外注するという大改革を行うことになり、人の配置育成の仕組みも見直しました。まず、IT技術者としてどのような人を求めるのかを定義し、人事制度と連動する高度IT技術の認定制度を構築しました。次に、個人のキャリア形成支援のために、社員向けにアセスメントを実施しました。さらに、従来は人事異動が硬直的でしたが、流動性を高めるために社内公募制やFA制などを導入しました。また、各職場において年度当初に掲げた業務執行計画を確実に達成させるために、人事評価の運用にクラウドを利用したシステムを導入し、上司と部下のコミュニケーションによる目標管理の手法をより強化しました。
現社長は人事業務の経験も深いため、一体となって変革を進め、21年度に様々な施策を企画して22年度に運用開始することができました。

自己理解促進のため、アセスメントを実施。経営層が積極的に受検。
社員一人ひとりが成長することで会社も成長のチャンスが増えます。しかし、若手社員はキャリア形成の道筋やお手本を求めているものの、お客様の課題解決のために必要となるITスキルの変化が激しく、上司も経験がない仕事をしているために指導が難しい状態でした。そこで、人事アセスメントを活用することを考え、既に採用で使用していた日本エス・エイチ・エルのアセスメント、OPQを社員に実施しました。当初は若手IT人材のみを対象とすることを考えていましたが、社長が「対象者の上司が結果の扱い方をよく理解する必要がある」と、自らも率先して受検し、ほかの役員や管理職も積極的に受検してくれました。合計1,138名が受検し、受検率は約90%でした。受検を依頼する際には、「自身の適性を客観的に把握する」という目的を丁寧に説明するよう心掛けました。公募制、FA制度にチャレンジする際の自己PRに活用できることや、現状社内にあまり存在していないコンサルティングやプロジェクトマネジメントなどの業務に対する適性を知るのに役立つこと、今後も数年に1度、定期的に実施する予定であることを、社員の皆さんに伝えました。
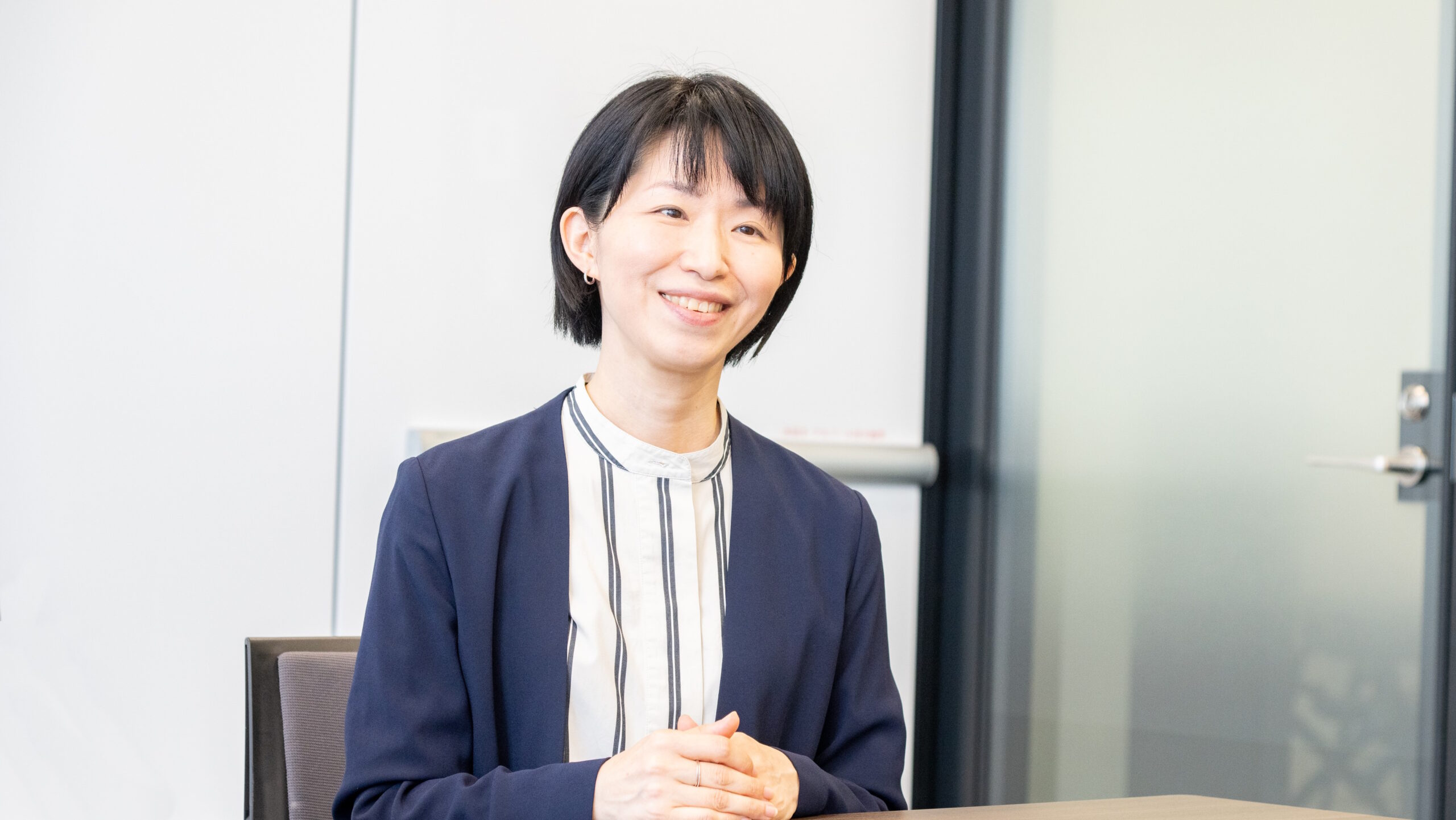
1on1から、アサインプロセス、人材可視化まで広範囲に活用。
取得したデータは目標管理のクラウドシステムに格納し、本人とその上司が結果を見ることができます。上司は部下の職種適性などを見て、キャリア形成のアドバイスや1on1ミーティングの材料などに活用してもらっています。結果の解釈の仕方については、解説動画を社内ポータルに用意しており、70%弱の方が視聴済みです。加えて、上司向け、全体向け、職種適性の能力開発ガイドなどの資料も配布しました。人事主導の施策ゆえ、結果の扱われ方に対する不安を払拭するためにも、なるべく多くの情報を提供しました。
客観的な物差しということもあり、結果はおおむね前向きに受け止められています。また、部署内でお互いに結果を共有することもあります。
人事側では、人事異動やプロジェクトへのアサインを検討する際、1つの参考材料として活用しています。人事内ではかなり浸透してきており、何か判断をする際に「(OPQの)結果はどうなっているの?」という声が聞こえてきます。また、全社あるいは部署ごとの特徴を把握するためにデータ分析も行い、実感を客観的なデータで再確認することができました。
また、これまでは人事異動が少なくずっと同じメンバーと仕事をしてきましたが、今後人材が流動化すると初対面の人々とプロジェクトを進めていくことが増えます。その際OPQという共通言語があれば、コミュニケーションも円滑になるのではないかと思います。
昨年は、盛りだくさんの人事施策を、短期間のうちに今までにないスピードで実施しました。社員にとっても目まぐるしい変化であったのではないかと思います。今後は、社員の反応や声をしっかりと聞き、必要なものを見極めて定着させていくことが大事だと思っています。社員が忖度せずに率直に意見を表明できる風通しの良さの表れなのか、毎年実施している社員の満足度調査では、人事評価結果に対して厳しい意見もありました。社長は常々「社員に何も言ってもらえなくなったら終わり。言ってくれるうちが華」と言っています。改革後の満足度は微増となりましたが、今後もアンケートなどで社員の声に気付くことができるようにしたいです。
日本エス・エイチ・エルは私たちのパートナーだと思っています。「言ってもらえなくなったら終わり」という言葉はどのような関係性にも言えることですので、今後も様々なアドバイスを期待しています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
改正 晃大
「社員一人一人がキャリアについて考えるきっかけを与えたい」という思いの下、細心の注意を払い進めていたことをとても印象深く覚えております。受検結果の開示だけでなく、OPQの解釈方法や活用に関する案内、部門ごとの分析結果の開示など、キャリアについて考えるための情報提供を惜しみなく行っており、皆様の思いがあって初めて実施できた取り組みだと考えております。これからも「パートナー」と言って頂けるよう、微力ながら尽力させて頂きます。
おすすめのセミナー・イベント情報

人事データ・適性データをタレントマネジメントシステムに統合し、キャリア面談、採用基準作成、プロジェクトへの抜擢など様々な活用をするブラザー販売の取り組みをご紹介します。
※本取材は2021年11月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
ブラザー販売株式会社
インクジェット複合機、モバイルプリンター等情報機器、家庭用ミシン等の商品企画・広告宣伝・営業・営業企画・アフターサービス等、ブラザーグループの国内マーケティング事業
卸売業
347名(2021年3月31日現在)

インタビューを受けていただいた方
山内 優 様
渡部 しのぶ 様
舩橋 優太 様
ブラザー販売株式会社
人事総務部 人財戦略グループ シニアマネージャー(写真中央)
人事総務部 人財戦略グループ チームリーダー(写真左)
人事総務部 人財戦略グループ(写真右)
インタビューの要約
ダイバーシティ推進と人事業務効率化のために、タレントマネジメントシステムを導入。いわゆる人事データのみならずポテンシャル適性データも統合して全体最適な人事を行うべく、「万華鏡30」の全社員受検を実施。
適性データをタレントマネジメントシステムで統合し、社員が自身のポテンシャルや似た特徴を持つ社員の分布を把握できるように構築した。またキャリア面談での上司とのトークテーマとし、適性データを見ながら能力開発や能力発揮の支援に活用できるようにした。
勉強会のメンバーの推薦や、採用基準の再設計にも適性検査データを活用。ローテーションや次世代リーダー発掘に生かすため、今後は質的なディスカッションを重ね、各部門で求める人材像を策定する予定。
目指すのは、受け身ではなく主導的な立場で提案できる人事。人事が能動的に動くためのツールとして、今後も人材データを活用していきたい。
ダイバーシティ推進において、大局的視点の必要性を実感。 散在する人事データを統合するため、タレントマネジメントシステムを導入。
もともとダイバーシティ推進において、個人の特性を生かし全社的に最適な人事判断をするための材料が不十分であることに問題意識がありました。当社内の人材を俯瞰することができないと、どうしても局所的な視点から人事異動やリーダーの抜擢が行われてしまう懸念があります。本当のダイバーシティを実現するためにどうすればいいかと考えていたところ、タレントマネジメントシステムが盛り上がりを見せ、興味を持ちました。
様々な人事データが散在しており、業務効率化の観点でも人事データを統合したかったところに改善活動推奨の追い風もあり、タレントマネジメントシステムの導入を決めました。タレントマネジメントシステムをローテーションなどの人事施策に活用するためには、人事データだけではなく、ポテンシャルやモチベーションなど適性データも統合する必要があります。そこで、直接雇用の全社員に対して万華鏡30を実施しました。

最初は新しいシステムの導入にハードルがあるのではないかと思いましたが、社内で反対はまったくありませんでした。折しもコロナ禍でリモートワークが始まり、DXやデータ活用の機運が高まっていたため、とんとん拍子でプロジェクトが進みました。
全社員の適性検査データをタレントマネジメントシステムに統合し、 いつでも自分の情報を見られるように。
コロナ禍で減ったフィードバックの効果も期待。
直接雇用の全社員に対して万華鏡30を案内し、約95%の社員が受検してくれました。受検に際して、「全社的な適材適所を実現するために、個々人の職務に関連する行動スタイルを可視化したい。今後は採用基準やローテーション、育成計画のためにデータを活用する。」という趣旨の案内をしました。 受検結果をタレントマネジメントシステムに取り込み、本人と本人の上司、および事務局のみが結果を見られるようにしました。自分のポテンシャル値が領域ごとにレーダーチャートで表示され、似た波形をもつ社員を把握できるようにしました。加えて、自分の能力開発ニーズに基づいて上司とキャリア面談をできるようにしました。
高い受検率の背景には、コロナ禍の影響もありました。リモートワークが始まり、他者からフィードバックを受ける機会が減りました。その中で、「自分はどのような人間なのだろう」「どのような強み・弱みがあるのだろう」ということを見つめなおしたいというニーズがあったのだと思います。

キャリア面談、特定のプロジェクトへの抜擢、採用基準設計など 広範囲にデータを活用。
今後はディスカッションも併せ、求める人材モデルを作りたい。
タレントマネジメントシステムに集積したデータは、職務を離れて上司と価値観やキャリアなどをディスカッションするキャリア面談に活用されています。本人が自分の結果をもとに、「発揮できている能力」「もっと発揮したい能力」「克服したい能力」「工夫で乗り切りたい能力」などを選び、その情報をもとに上司と面談できるようにしました。キャリアを描く際に、科学的に推測された自分の強み・弱みの情報を活用できることは、社員にとってメリットが大きいと思います。
また、DXに関する自主勉強会の企画が持ち上がった際に、万華鏡30のあるコンピテンシー群の数値をもとに、若手社員の中から推薦者を抽出してみました。浮上したメンバーは事務局のイメージした人材像に近く、前向きな人ばかりでした。人材を探そうとなったときに、特定の条件ですぐに抽出できることの利便性を感じました。

さらに、集積したデータをもとに、採用基準の見直しも実施しました。データを使ってローテーションや次世代リーダーの発掘も行う予定でしたが、これはサンプル数の問題もあり、まだ着手できていません。しかし最近、コンピテンシーの書かれたカードを使ったディスカッションの方法(カードソート法)をご提案いただき、まずは3年目に求める要件、DX人材に求める要件、そしてマネジャーに求める要件とディスカッションを重ねたところ、共通した人材像が見えてきて手ごたえを感じました。今は各部門で求める人物像や次世代リーダーの人物像を明確化し、採用や育成にフィードバックしていこうと思っているところです。
適性検査データの解釈には注意すべき点もあります。たとえば、ある部門に求める人材像を定義しても、すべてを満たす人材はほとんどいません。理想的な人材像を定めた上で、その中での優先順位や、能力開発で伸ばしやすい部分、素養として持っているのが望ましい部分などを細かく選定しておくことが、運用上必要でしょう。また、個々人がデータをどう解釈するかも重要です。若い社員が「このデータが私のすべて」というような解釈をしてしまうと、自己認識を必要以上に固定化するリスクもあります。結果はあくまで現時点のポテンシャルであって、自分に限界を定めないように啓発することも併せて必要だと思います。
上司が部下の適性データを解釈できるようになるためのサポートも必要です。リモートワークで上司が部下を直接見る機会が減ったため、データの重要性は高まっています。また、コンピテンシーに関する理解は、今後求める人材像をディスカッションしてゆく中でも必要な土台になると思われます。
今までの大きな問題は人事が受け身だったこと。今後は情報を出してと言われて開示するのではなく、主導的な立場でデータを提供して判断を仰ぐ、もしくは人事から提案するべきと考えます。人事が能動的に動くためには集積したデータが必要です。タレントマネジメントシステムには、適性データ以外にも様々な人事データが統合されていますので、それを概観してタレントマネジメントの判断材料にしていきたいです。
日本エス・エイチ・エルには適性検査の見方や他社の事例など、今後もご提案をいただけると助かります。打ち合わせで様々なディスカッションができるのを毎回楽しみにしています。これからも良き伴走者になっていただけるとうれしいです。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
松波 里奈
人材可視化から人材データ分析、活用支援までを行う重要なプロジェクトをご依頼頂いた際には、ワクワクすると同時に身の引き締まる思いで毎回の打合せに臨んでいました。 お打合せでの議論においても、当社からのご提案について多様な観点でご質問を頂くなど、社員のポテンシャルを引き出したい、より組織を活性化させたいというお三方の強い思いを感じさせる時間でした。現有社員の特徴を踏まえて、必要とされる人材要件を定義し、採用基準を一新できたことは、皆様と一緒に作り上げた一つの成果だと思っています。一方でタレントマネジメント施策には終わりがなく、よりよい人材配置や人材育成を実現する為に次の議論をスタートさせて頂いていることは、大変光栄に感じております。よき伴走者として頼って頂けるように、私自身も尽力して参ります。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

多様なバックグラウンドを持つ社員の相互理解のために、1on1ミーティングにアセスメントを活用。
マネジャー向けコーチング研修を実施した朝日インテックJセールスの事例をご紹介します。
※本取材は2021年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
朝日インテックJセールス株式会社
医療機器の販売、医療機器関連の研究、開発事業、医療機器に関するコンサルタント事業、医療機器の修理及び賃貸業務
医療機器販売業
従業員数 : 95名 (2021年6月末日現在)

インタビューを受けていただいた方
川又 治 様
朝日インテックJセールス株式会社
営業本部 フィールドマネージメントチーム チームリーダー
インタビューの要約
様々なバックグラウンドを持った社員が相互理解を行うために、客観的に自己をみつめるツールとしてアセスメントを導入。
効果的な1on1ミーティングを実施するため、マネジャーにアセスメント「万華鏡30」とコーチングのトレーニングを実施。離職が減ったほか、マネジャーのコミュニケーションが変わったというフィードバックを得られた。
アセスメントによって見出された社員の全体的特徴を、採用戦略にも活用。新しい個性をもった新入社員をのびのび育成するためにも、コーチングを活用してほしい。
今後の課題は、採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用し、科学的人事を推進することで、変化の激しい医療業界を生き残るための風土改革を行うこと。
様々なバックグラウンドを持つ人材が相互理解をするために、 全社にアセスメントを導入。
私は新卒でリース会社に入社し、外資系医療機器メーカー、日本の医療機器メーカーを経験し、11年前に当社に入社しました。大学を卒業してから営業一筋でしたが、4年前に新設の人事部門で採用・教育を担うことになり、手探りで現在の部署を作り上げました。
2017年にノーベル賞を受賞した行動経済学者、リチャード・セイラーの、人間は必ずしも合理的に意思決定をするわけではないという理論を書籍で読み、心理学的なアプローチに興味を持ちました。営業時代にも、人材育成における個人差を目の当たりにしたり、部下との関わり方がわからず悩んだりすることがありましたので、人事の仕事はこれらのことを学ぶいい機会だと思いました。
日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を導入した目的は、社内のコミュニケーションの円滑化です。当社は、カテーテル治療に使用されるガイドワイヤーでトップシェアである朝日インテックの国内販売部門として2006年に設立されました。売上が10年余りで50倍と急成長した為、内資系企業・外資系企業からの中途入社、新卒入社、また元々当社製品を扱っていた企業からの入社と、様々なバックグラウンドを持った人材が集まっています。一時期離職が続いたこともあり、上下間のコミュニケーションや相互理解が必要だと感じました。特に5年前から始めた新卒採用で入社した社員は、我々キャリア入社組からすると異色の存在。彼らを適切に育成する意味でも、社員の相互理解が必要です。そのため、全社にアセスメントツールを導入して個人に結果をフィードバックし、「自分が何者であるか」というコミュニケーションの土台をまず作りました。万華鏡30の結果については、「当たっている」という声が多かったですね。
1on1ミーティングでアセスメントを活用するコーチング・トレーニングを実施。 離職の減少、上司のコミュニケーション力向上に効果あり。
その後、上司が部下をコーチングするための1on1ミーティングの研修を企画しました。その際に、「万華鏡30を1on1に活用したい」と思い、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントと外部企業のコーチングの講師で打ち合わせをしていただいて、上司が1on1の中で万華鏡30を活用できるように進めました。
1on1ミーティングは月1回、各エリアマネジャーと部下との間で実施されます。万華鏡30を使うことを推奨していますが、使いたくない場合は使わなくてもよいと告知しました。また、1on1で万華鏡30を使う場合は、部下の結果だけを提示すると高圧的に受け止められる可能性もあるため、かならず上司自身の結果も提示して相互理解するようにと強調しました。

万華鏡30を使った1on1およびコーチングのトレーニングを行った効果ですが、まず離職が減りました。もちろん離職はゼロにはできませんし、する必要もないと思いますが、医療業界での重要なリソースであるドクターとの人脈や知識を持つ社員の流出は痛手ですし、すぐに次の人を育てられるわけではありません。今後は、制度面などコミュニケーション以外の部分でもさらにリテンション施策を整えていくことを考えています。
また、一部のエリアでは上司の接し方がガラッと変わったという報告を若手社員から受けています。今まではどちらかいうとトップダウン的なコミュニケーションだったのが、部下の話を聞くようになったということです。コーチングの在り方を学習したことに加え、万華鏡30によって「自分にはこんな要素があったのか」と客観視することで、マネジャーにも学びがあったのかなと思います。
社員の特徴は採用方針にもフィードバック。
採用と育成の両輪の人事施策で、変化の激しい医療業界を生き残る。
また、今回の全社受検の結果をもとに、採用戦略を検討しています。たとえば、当社の営業職社員が強く持つ特徴を採用要件にする、オーソドックスなマネジャー層を補うため創造性を採用要件に入れるなどです。新卒社員には創造性を発揮していただきたいと期待しています。昨今の企業合併やコロナ禍など、医療業界は変化が著しく、環境の変化に適応できる人材がいないと、組織として生き残っていくのは難しいと思います。
その上でコーチングの効果として期待しているのは、マネジャーが新しい発想をもった新入社員の個性を生かし、のびのび育成できるようにすること。せっかく尖った人材を採用しても、マネジメントによってだんだん丸くなってしまうのではもったいない。同時に、私からも若手社員と個別に話をして、「今まで受けた教育で納得いかないことや問題点などあるかもしれないが、自分たちで考えて自分たちで決めていいんだよ」とメッセージを送っています。若い頃から自分で決める経験を積まないと、意思決定のできないマネジャーになってしまいます。せっかく素質のある人材を採用しているので、彼らには早い段階から自分で決めるということ、そして決めたことに責任を持つということを、しっかり教育で身につけさせたいと思っています。
今回、日本エス・エイチ・エルに携わっていただいてプロジェクトを実行し、少なくとも管理職以上の意識は変わりました。頭ではわかっていても感覚的にわかりづらかった「人にはオリジナリティや個性があって一人一人異なる」ということをアセスメントのデータで明示してもらえたことが大きいと思います。担当コンサルタントの方には、社員向けにアセスメントの説明会も開いていただき、社員が理解を深めることに貢献していただきました。
今後の課題は、コーチングと採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用していくこと。変化の大きい医療業界において、人の目による人事のみに頼ってしまうと、オーソドックスな社風が強くなってしまい、組織として生き残ることができません。データや統計など科学的な資料をもって、人の目の限界を補う必要があります。
最後に、個人的な課題は、自分が経験したことを次の世代へ伝えることです。私自身、多くの上司や先輩に育ててもらった恩を感じながら年を重ねましたが、今は私自身が次世代を育て、彼らがまた次世代を支えていくことを実感しています。このような継承の物語が積み重なって歴史となってきたのが、日本企業の強みではないでしょうか。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
藤田 夏乃子
1on1ミーティング実施にあたり、相互理解を行うための材料としてアセスメントを利用したいというお話をいただき、今回の取り組みが始まりました。
きちんとアセスメント「万華鏡30」を理解してほしいという川又様の熱意を受けて、私が「万華鏡30」の説明会を実施させていただきました。説明会当日は参加者の方からたくさんの質問をいただき、皆様積極的にご参加いただいたのを覚えています。
実際に川又様から1on1ミーティングを実施していく中で、上司・部下間でよりよいコミュニケーションに変わっていっているとお聞きしたときはこの取り組みに貢献できてよかったと感じました。
今後も広くアセスメントの活用を考えていらっしゃるとのことで、様々な場面でお力になれるようにしていきたいと思います。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例


能力開発に役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム

関連する導入事例
関連するコラム


配属に役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム


インターンシップに役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム
はて、実際はどうしたらいいのか。評価とは何かを知ることでこの答えを導き出すことができます。今回のテーマは評価です。
評価の目的
評価の本質は意欲形成です。目的は大きく二つに分けることができます。
一つ目は、企業の価値観、戦略、目標に従業員の行動や成果をあわせていくことです。企業は評価を通じて適切な行動をとったり、求めている成果を生み出したりするよう従業員を促していきます。経営者にとって評価は企業戦略を遂行するために人を正しく動かす仕組みです。したがって経営者は企業戦略と評価との関係を従業員にわかりやすく伝える必要があります。
二つ目は、人材開発、人材育成です。評価によって被評価者は今の自分はどれだけ仕事ができているのかを知ることができます。何がどれだけできている(できていない)のかがわからなければ、成長は困難です。評価によって現在の能力や成果を知ることができれば、求められている能力や成果の水準との差を把握できます。そして、評価が処遇や役割との関連でインセンティブとして働けば、従業員はより高い水準を目指して努力します。
何を評価するのか
評価対象として欠かすことができないものは職務成果です。その仕事をすることで得られるアウトプットが成果です。営業職であれば、売上実績、粗利実績、契約件数などが職務成果です。職務成果は企業にとって望ましい結果と言えます。この望ましい結果は、企業の状況や組織の戦略、方針などによって変化します。つまり、何を成果とするかは経営陣が経営戦略、事業戦略を踏まえて決めるべきものなのです。また、企業としての成果を定めたとしても組織や部署の職務内容や具体的な方針、計画などにより、各現場では柔軟に評価基準を設定する必要があります。そして、企業戦略や企業価値観と各メンバーの評価基準を円滑につなぐ工夫こそが評価を効果的に活用するために必要なことなのです。職務成果だけを対象に客観的な評価を行えば、公平性を維持することは可能です。評価は衛生要因である金銭報酬に直結することが多いため、公平性が維持できないと従業員のモチベーションを下げることになるため、公平性は欠かすことができません。しかしながら、職務成果の評価だけでは、なぜその成果を生み出すことができたのか、あるいはできなかったのかがわからないため、もう一つの目的である人材育成には不十分です。
もう一つの重要な評価対象はコンピテンシーです。コンピテンシーは、成果創出のための発揮した行動です。コンピテンシー評価を行うことで、なぜ良い成果が得られたのか(得られなかったのか)が明確になり、さらなるレベルアップのためにどのような行動をより強化すべきか、どのような行動を改善すべきかがはっきりします。
どのように評価するのか
全ての従業員が喜ぶ評価をすることは不可能です。良い評価であっても悪い評価であってもすべての従業員を意欲形成できなければ、評価を行う意味はありません。ではどのように評価を行うべきか。重要なポイントが3つあります。
・評価基準と評価方法をオープンにする
従業員が自分の何を誰がどのように評価し、最終評価がどのように決まるかを知っていることが重要です。従業員が正しく評価基準を理解し、合意していれば、高い評価が得られるように仕事をするでしょう。企業が望む適切な行動を促し、能力開発を促すことができます。・全体の評価結果をオープンにする(個人が特定できる情報は絶対に掲載しない)
組織全体で評価結果がどのように分布しているかをオープンにすることは、二つの効果があります。一つ目は自分の相対的な位置を知ることができること。二つ目は企業のオープンな姿勢をアピールできること。いくらオープンが良いと言っても評価結果は個人のプライバシーです。絶対に個人が特定できる情報を出してはいけません。・評価結果をフィードバックする
フィードバックには三つのポイントがあります。一つ目は速やかにフィードバックすること。評価結果が出たらできるだけ早くフィードバックします。早ければ早いほど効果的です。半期に一度行われる評価では評価結果の根拠となる行動や成果が半年前のものになってしまうかもしれません。おぼろげな記憶ではフィードバックの効果も半減します。すぐにやりましょう。
二つ目は良い点も悪い点も包み隠さず伝えること。良い点を伝えるのは簡単です。お互いに前向きな気持ちになれます。悪い方が難しい。しかし、悪い点をうまくフィードバックできれば効果的な行動変容につながります。フィードバックする上司の力量が問われます。 三つ目は評価根拠を伝えること。なぜ、今回の評価結果となったのかについてわかりやすく伝える必要があります。従業員が評価の根拠をしっかりと理解すれば、評価に対する納得感が高まります。
終わりに
評価のためには、事前に評価基準と評価方法を明示しておくことが必要であることがわかりました。また、業績だけでなく、業績を生み出すプロセス(コンピテンシー)を評価対象にすることで効果的に人材育成ができることもわかりました。
冒頭の人事担当役員も事前に評価基準と評価方法を明示していれば、このような疑問を持つことは無かったでしょう。加えてコンピテンシー評価を加味することで、より人材育成を促す評価制度にすることができると考えます。