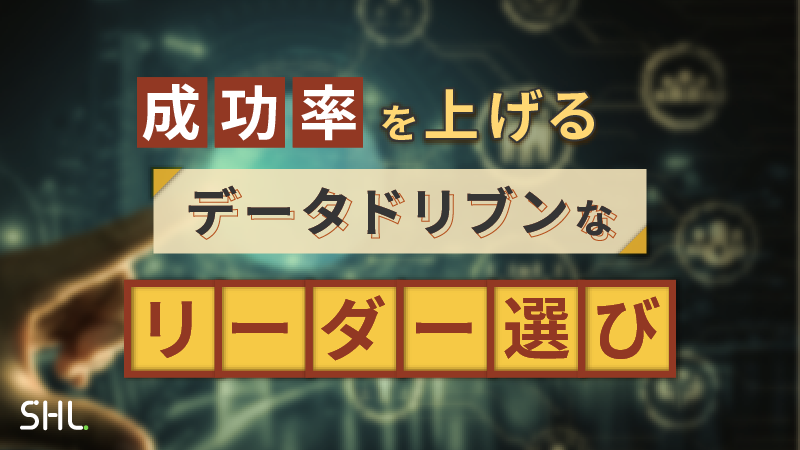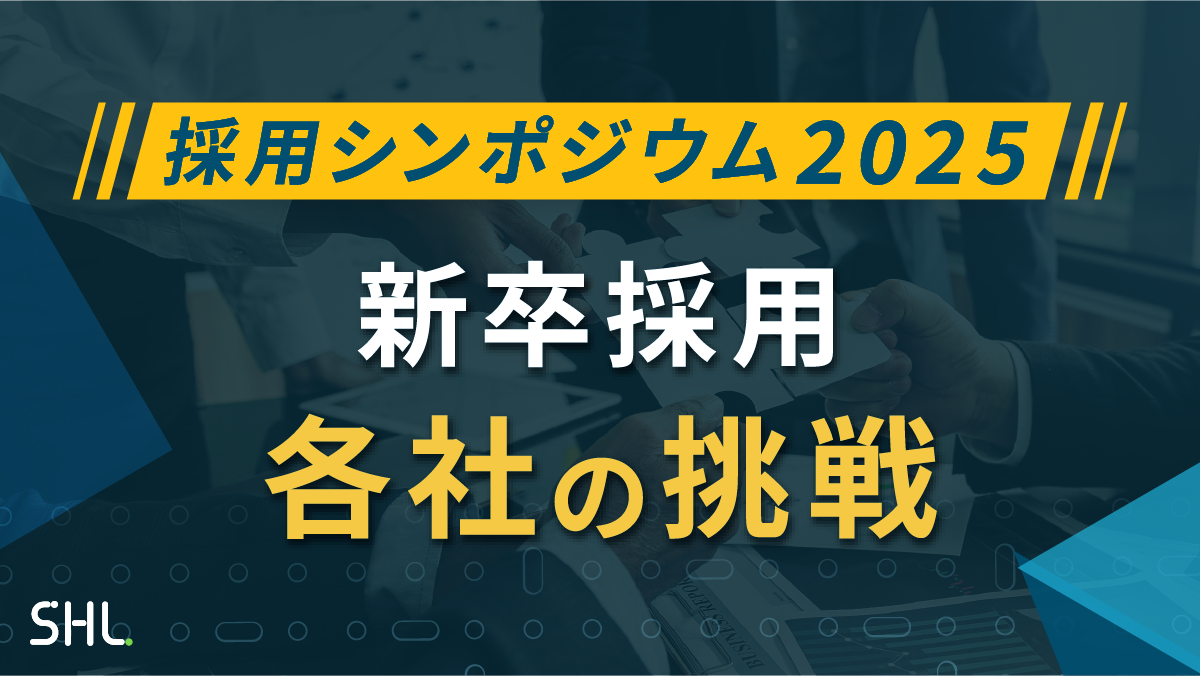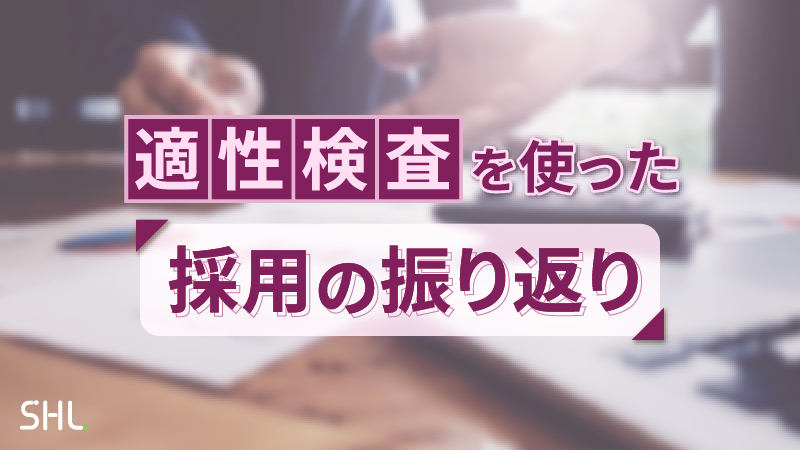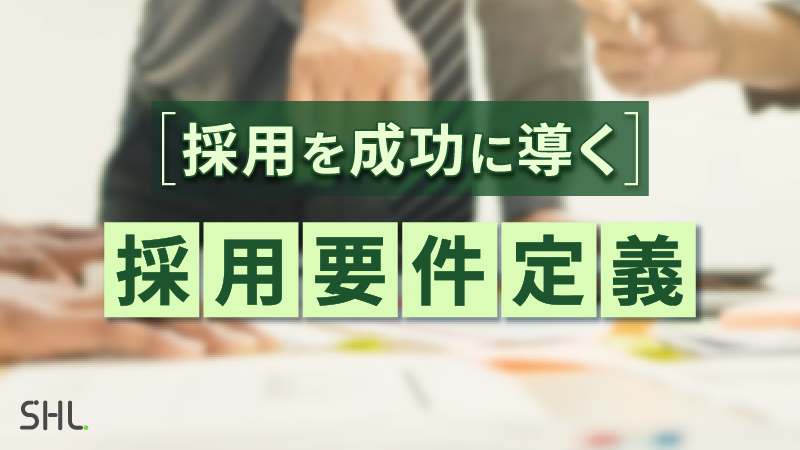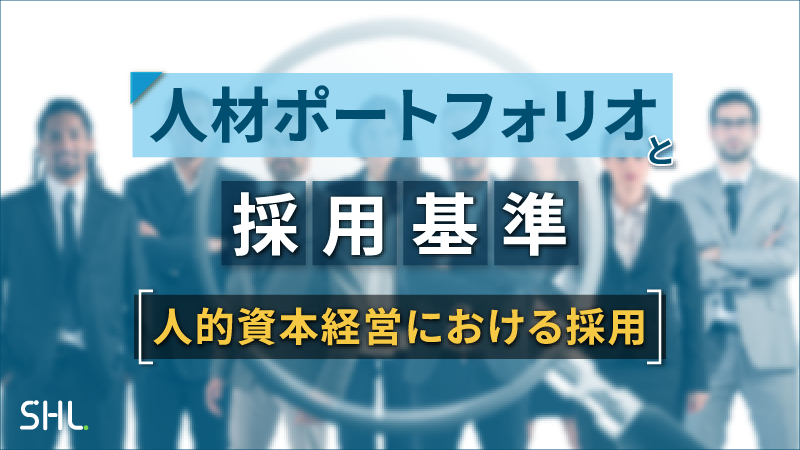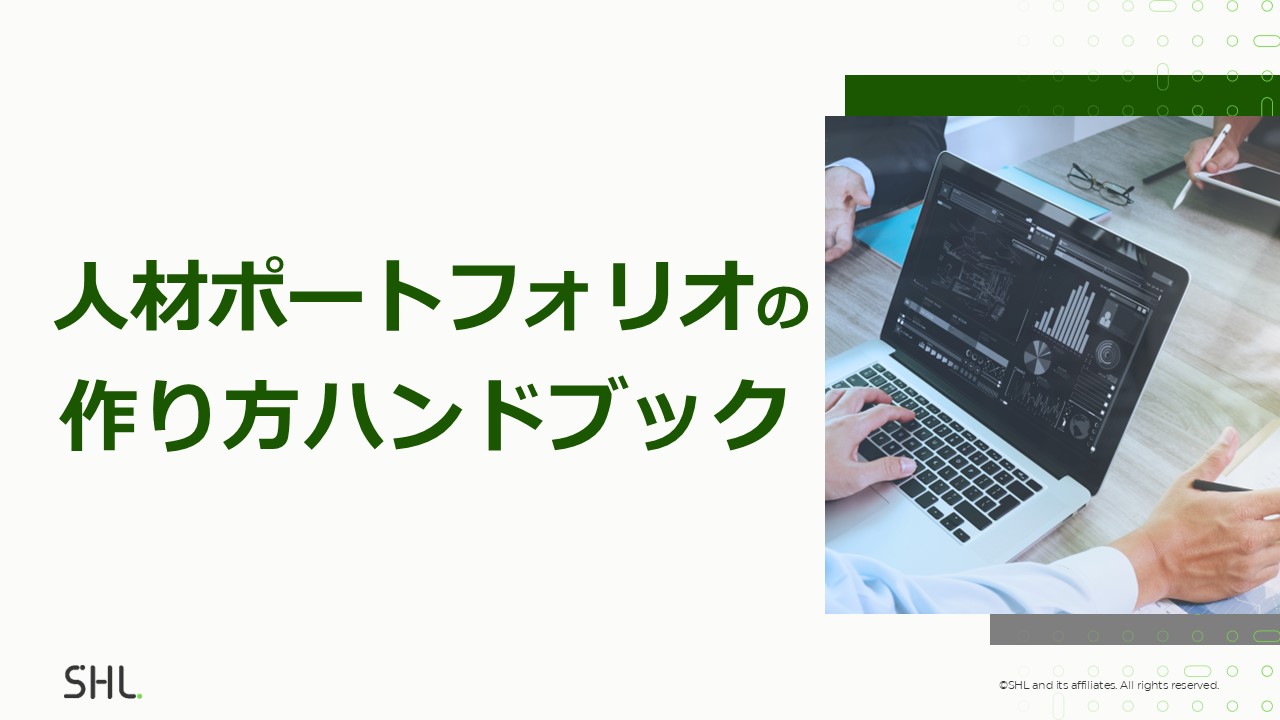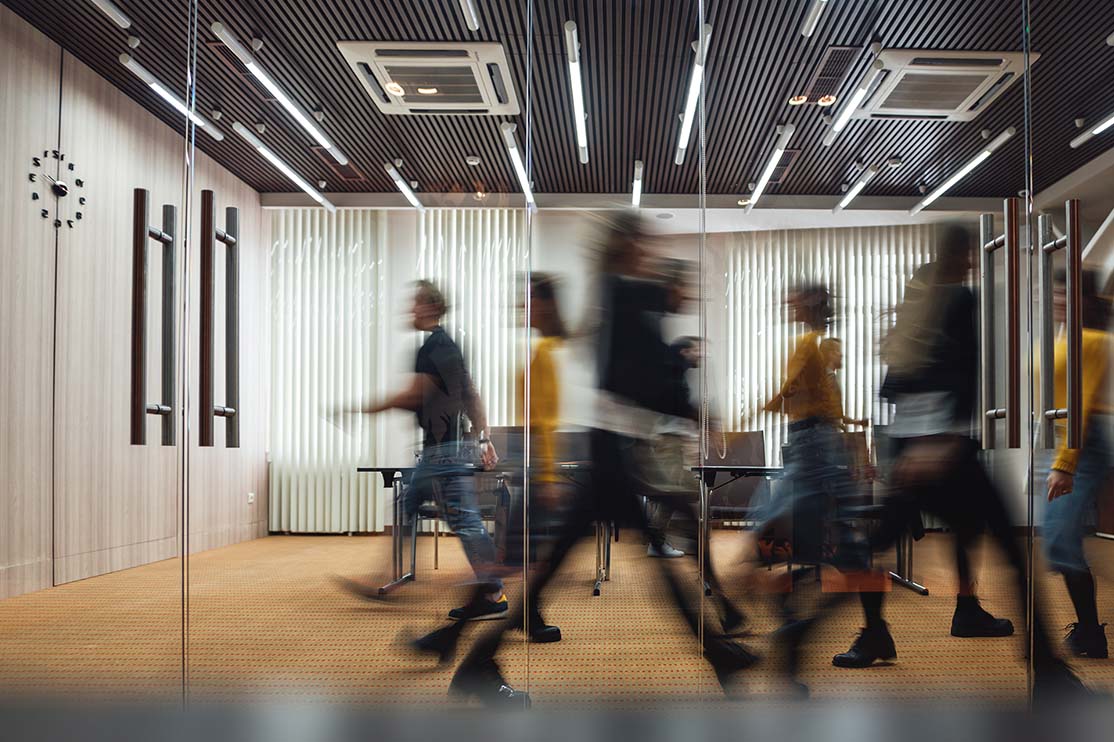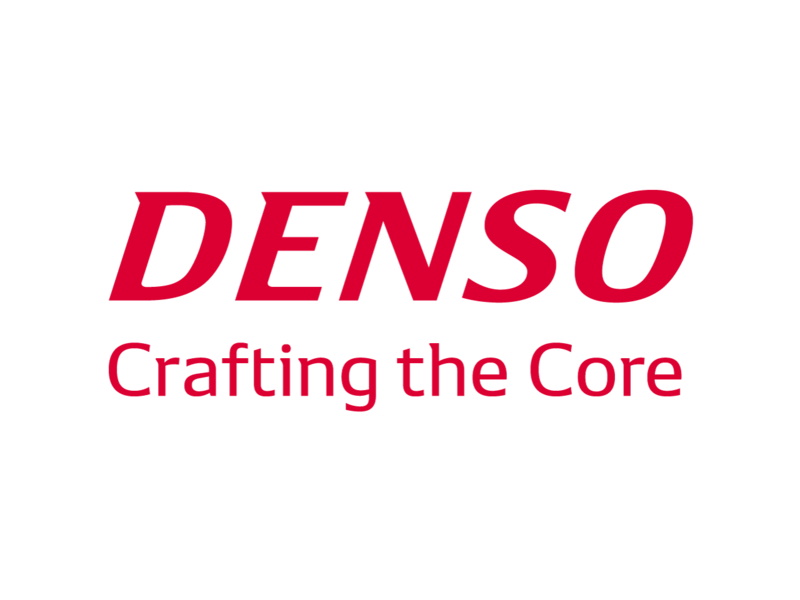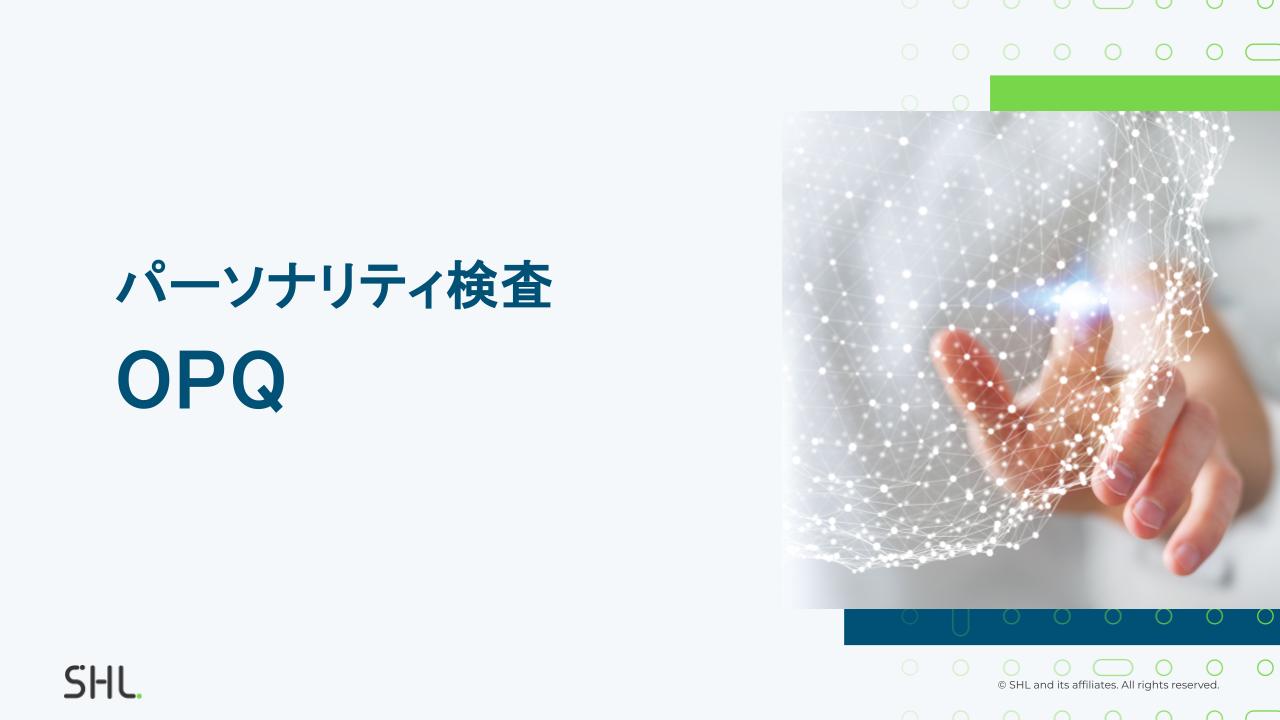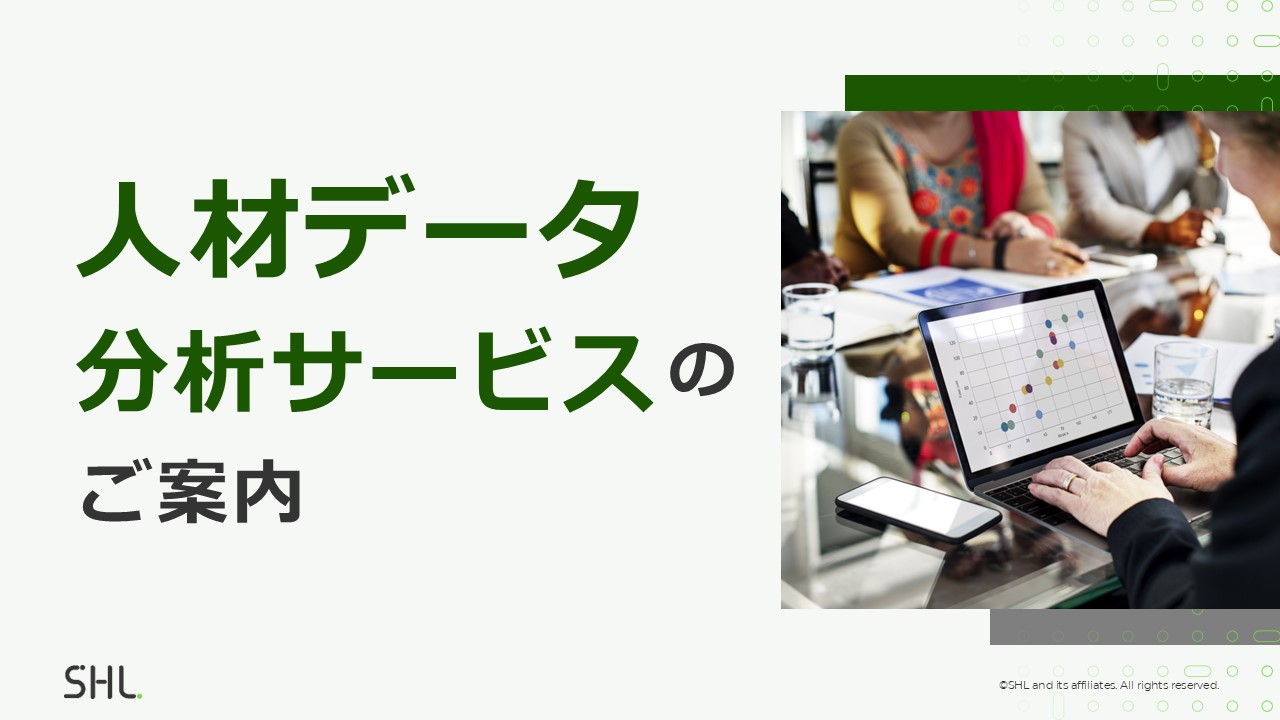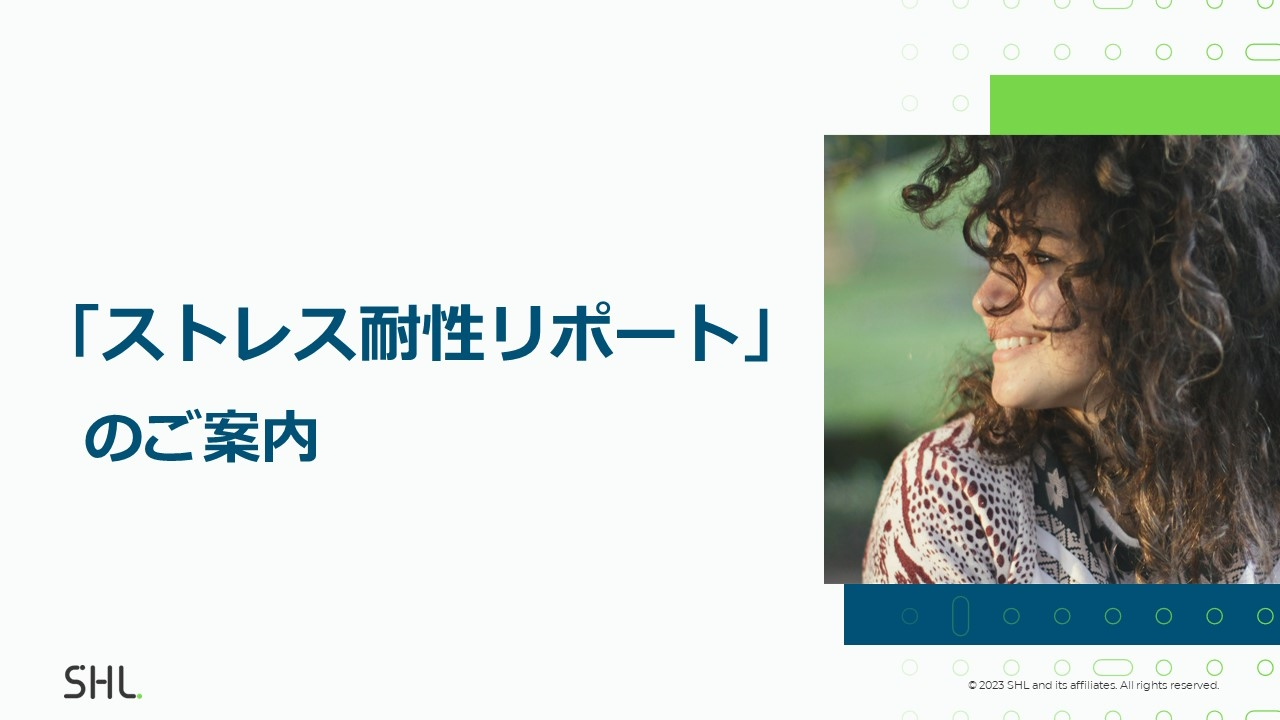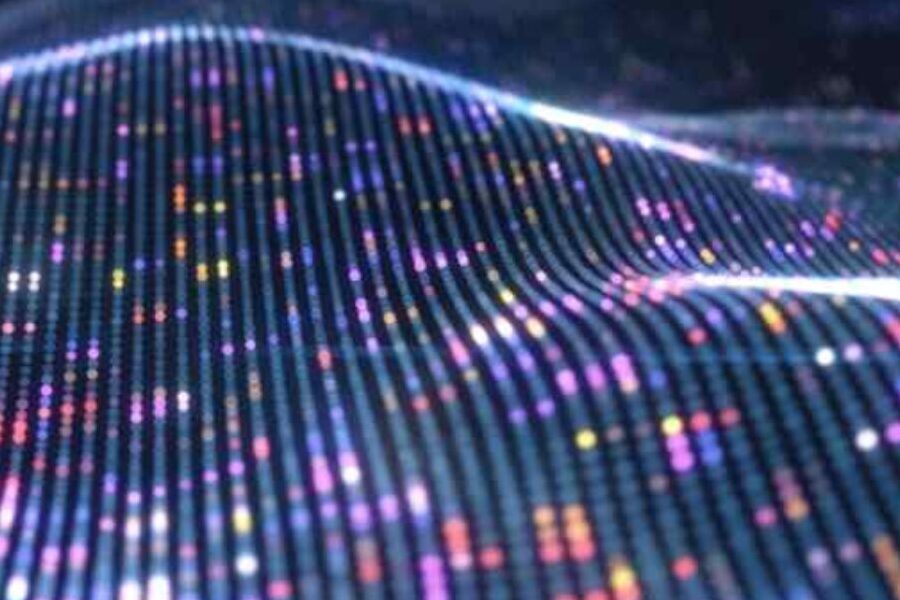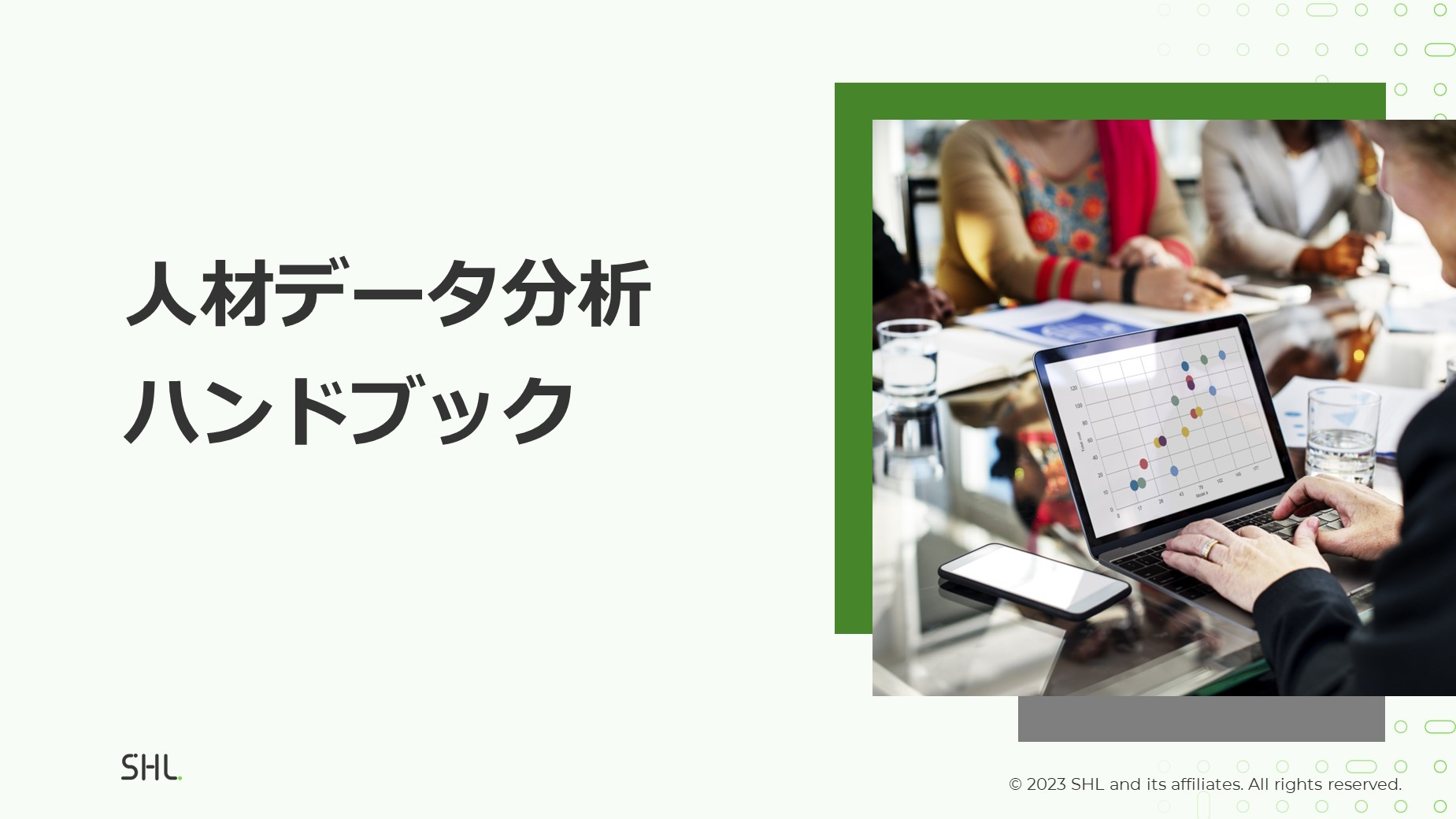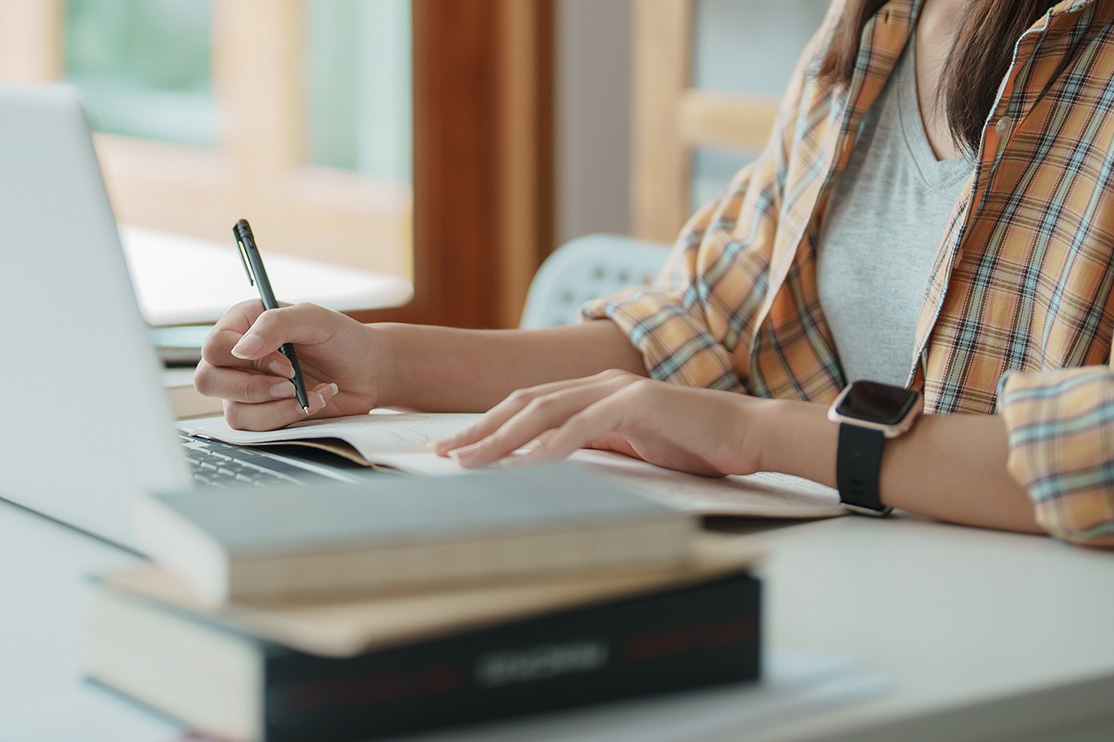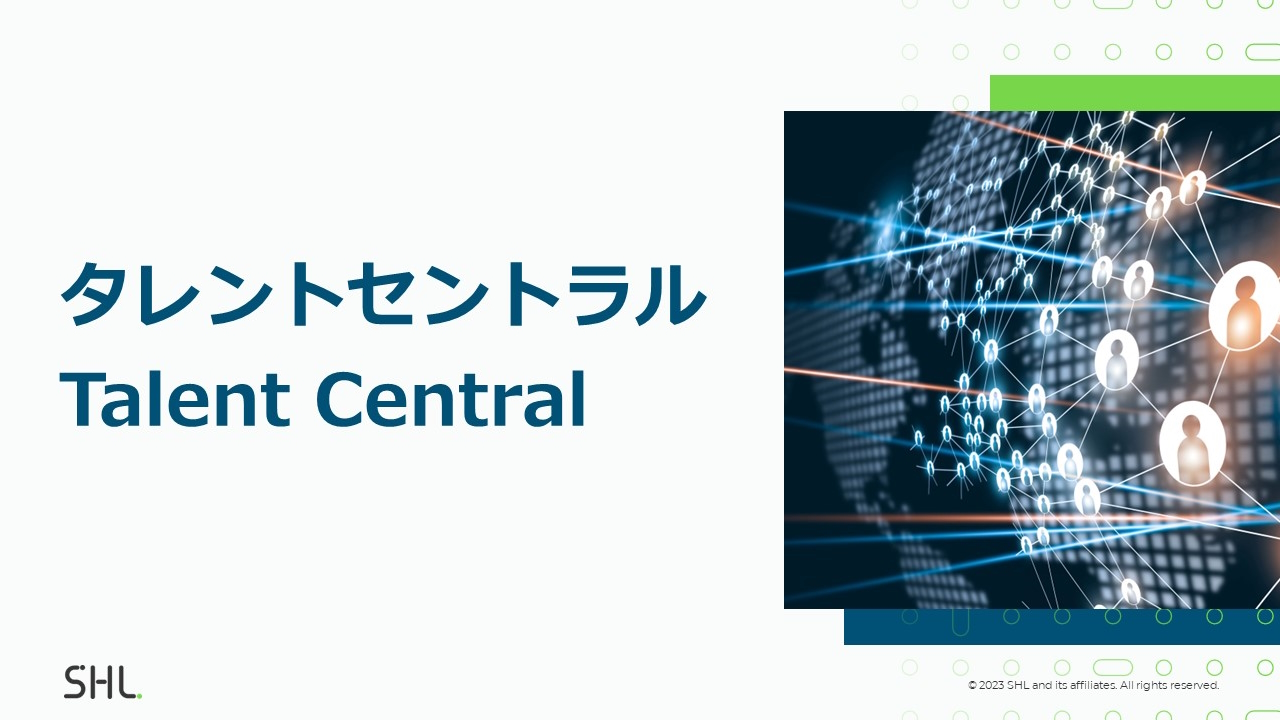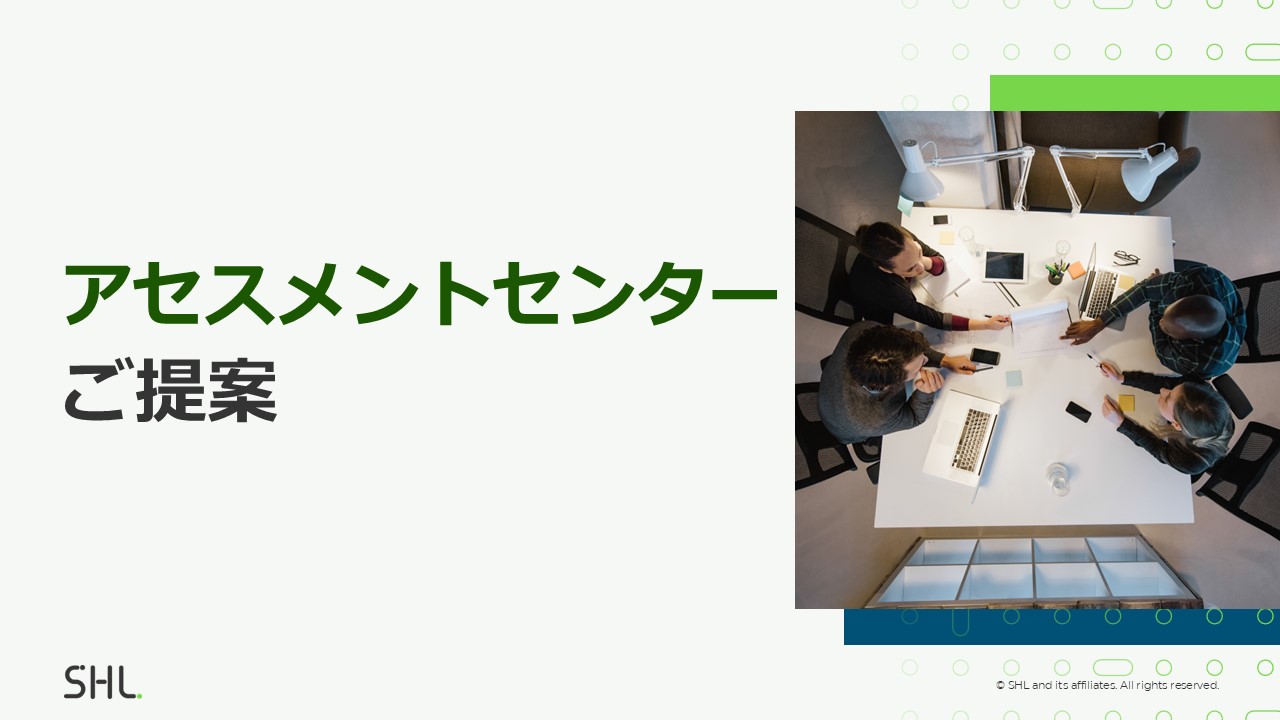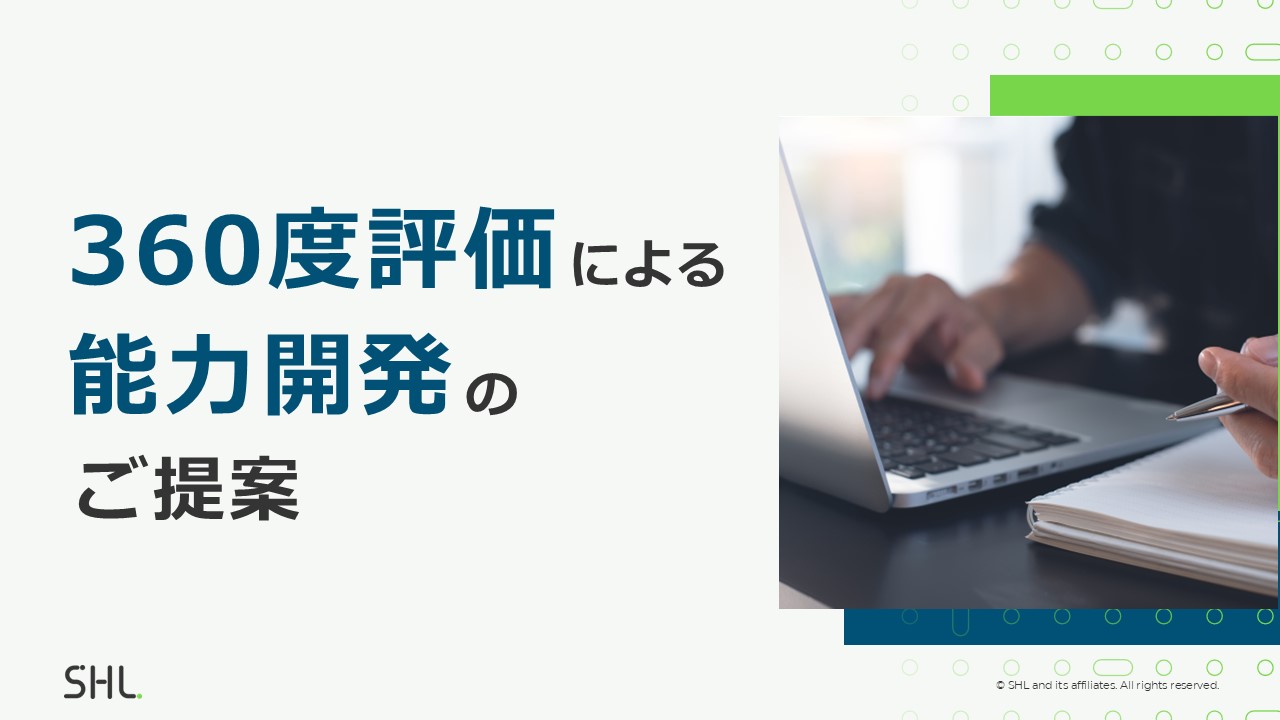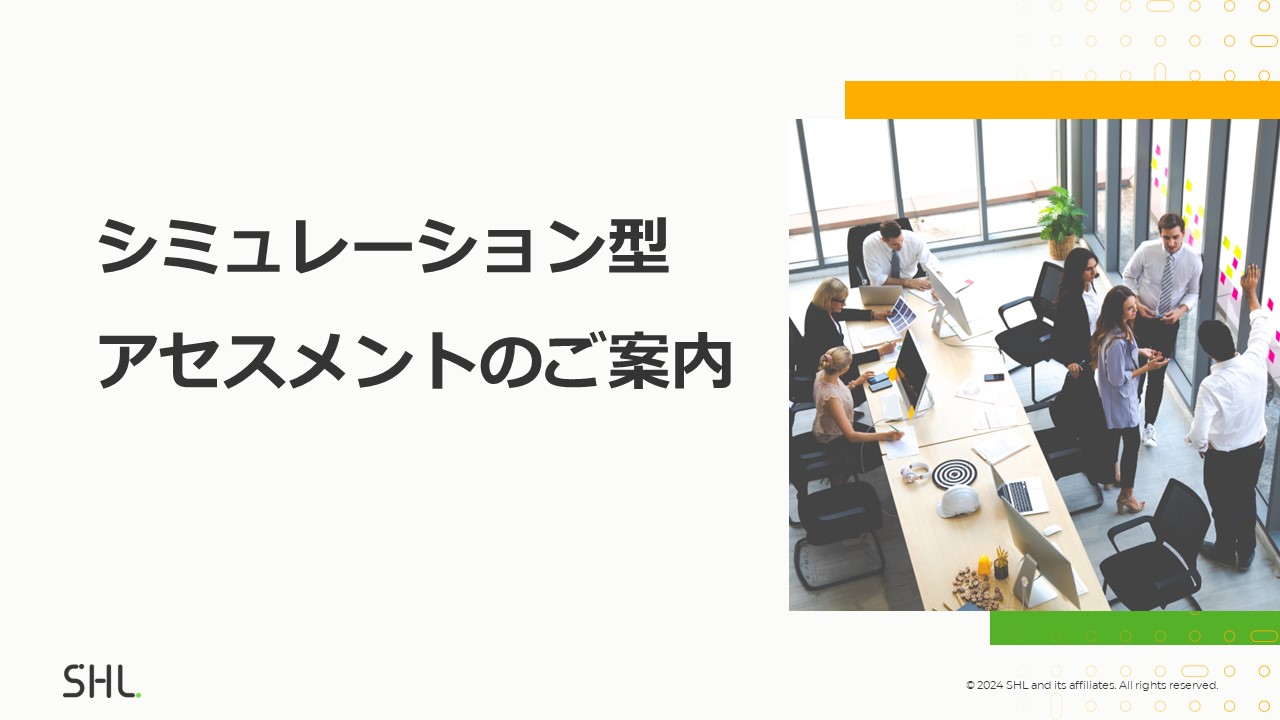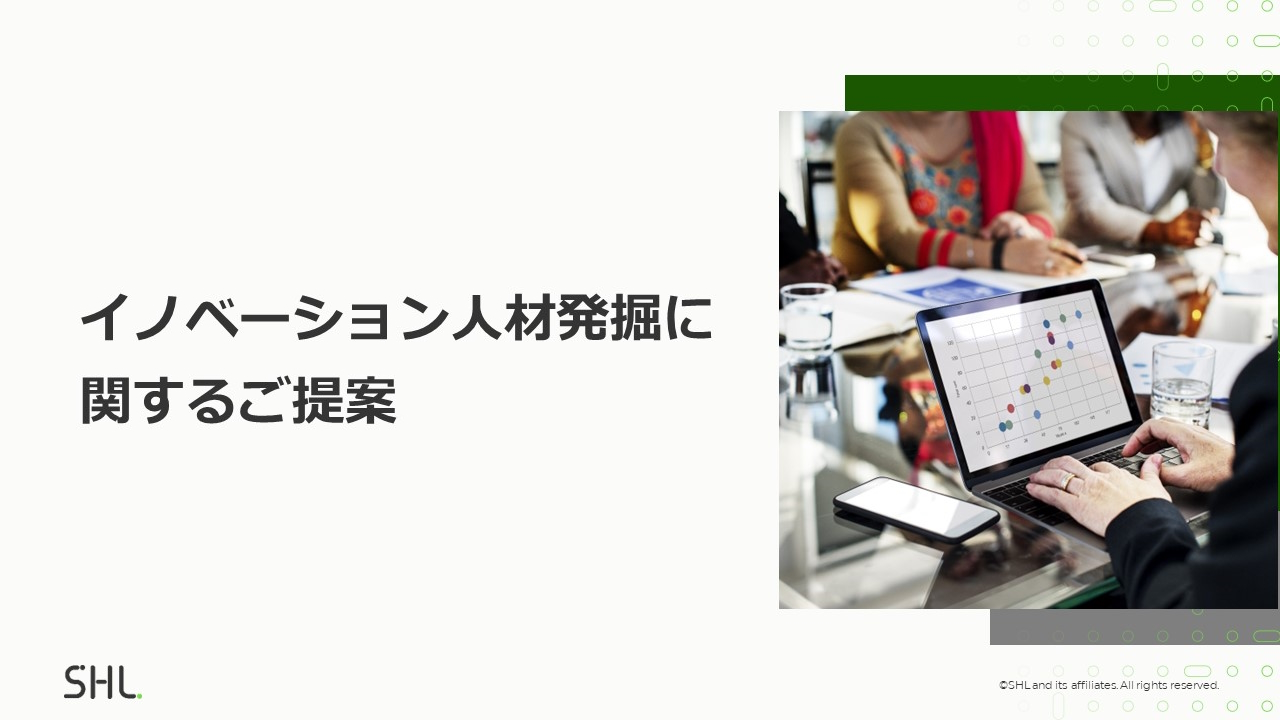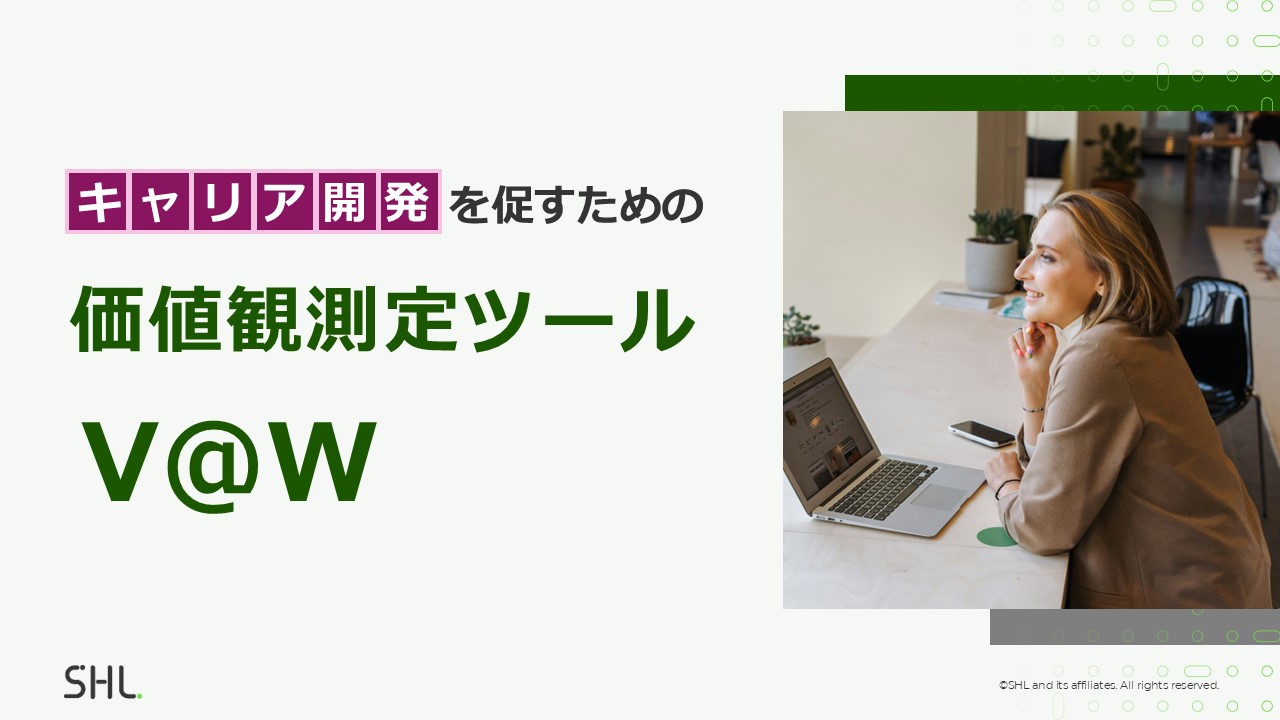創業100周年に向けて、多彩なValue Creatorが共創する組織へ。
社員一人ひとりのビジョンの実現をサポートする「人材成長プログラム」についてご紹介します。
※本取材は2022年6月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社ポーラ
化粧品、健康食品、ビューティーケア、エステサービス
化粧品製造販売業
1,359名(2021年12月末現在

インタビューを受けていただいた方
岸 夏海 様
人事戦略部 ヒューマンバリューチーム
インタビューの要約
化粧品事業の枠に捉われない新たな挑戦や変革のため、多彩な社員一人ひとりのビジョンの実現に向けたキャリアサポートを行う「人材成長プログラム」が発足。
「人材成長プログラム」は4段階。まずは自身の強みを「知る」、次にビジョンや実行計画を「描く」、オンラインスクールやスキル開発プログラムで「学ぶ」、そして実際の業務で能力を「活かす」。
「知る」のフェーズでは、日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を活用。個々人の自己理解が深まっただけでなく、強みを生かした現場でのアサインメントや、社内の人材の可視化が促進される効果も。
社内アンケートの結果、キャリアに対する社員の主体性がアップ。今後も施策全体のPDCAを回していきたい。
既存事業の枠を超えた挑戦のために、多彩な人材のキャリアデザインを支援する「人材成長プログラム」。
弊社は創業100周年の節目に向けて、これまでの化粧品事業の枠に捉われない、新たな挑戦や変革を進めています。組織としてのありたい姿は、多彩な「Value Creator」による共創。社員一人ひとりがValue Creatorとして、最大限能力を発揮し、個人と組織がお互いを高め合う関係の中で、ワクワクするような面白い挑戦により、価値を創出している組織を目指しています。
人事としてValue Creatorの挑戦と成長を引き出すためには、多彩な社員の個の尊重と、チームとしての創発力を最大化しつながりを高めること、そして社員一人ひとりのWillや自らがポーラを通して描いた未来に、自分の意志で向かっていく力強さが必要不可欠だと捉えています。そんな視点をもって打ち出したのが、「人材成長プログラム」という弊社独自のプログラムです。このプログラムは、「知る」、「描く」、「学ぶ」、「活かす」という4つのフェーズに沿って、キャリアを描く機会、成長する機会、そして能力発揮の機会までを提供する様々なコンテンツを実施しています。
「人材成長プログラム」は4段階。自分を知り、ビジョンを描き、 実現に向けて学び、能力を発揮する
「人材成長プログラム」の「知る」というフェーズでは、日本エス・エイチ・エルの「万華鏡30」を用いて、一人一人の個性や強み・弱みを可視化し、自己理解を深めてもらいます。次に「描く」では、今後の自分のキャリアビジョンと実行計画を描きます。具体的にはキャリアデザインのeラーニングや、世代別研修を実施しています。「学ぶ」では、ビジョンの実現に向けて、オンラインスクールや領域限定のスキル開発プログラムを活用しながら、能力開発を行います。最後が「活かす」です。実際に業務に携わる中でさらに成長し、高めた力を最大限発揮していただく。そのために、人事としては適切な異動配置を考えることも課題の一つです。弊社ではタレントマネジメントシステムに社員のスキルやキャリアプランなどを一元管理し、これまでの一律のジョブローテーションを少しずつ個人に合わせたキャリアとすることを目指しています。
これらを体系的に実施しながら、さらに効果を高めるポイントが、上長による定期的な1on1。それぞれのフェーズにおいて上長によるキャリア支援を必須とし、人事と上長は情報連携やフォロー体制を整えながら、人材成長プログラム全体を動かしています。

キャリアデザインの第一歩はアセスメントによる自己理解。 個人の内省だけでなく、適材適所が促進される効果も。
今回、「知る」というフェーズで日本エス・エイチ・エルの「万華鏡30」を活用させていただきました。受検対象は全正社員で、受検後に1時間の「自己理解研修」や上長との1on1での結果の活用を行うことで、さらに自分自身に対する理解や内省を深めています。
導入後の効果は大きく2つあります。一つ目は従業員同士のコミュニケーションです。チームや上司・部下間でお互いのアセスメント結果を見ながら、業務分担を行ったり、個人の強みを生かすようなアサインメントが行われたりするようになりました。二つ目は、人事視点での全社分析が可能になったことです。この万華鏡30の導入により、社員を同一基準で解釈することが可能になりました。
この結果を様々な分析にかけることで、社員の性格傾向がわかりやすく表現され、社内にどのような人材が分布していて、どのような人材が不足しているのかなど、人材分布から育成課題等も可視化されるようになりました。
これらの施策はすべて発展途上ですが、少しずつ変化の兆しが見えてきました。今年の社員アンケートの結果、「自ら主体的にキャリアを描き切り開くマインドが自身に備わっていますか?」という質問に「はい」と答える割合が、昨年と比べ10ポイント以上高まりました。組織として大きな変化が起きるのはこれからと認識しておりますが、今後も情報収集を続け、施策全体のPDCAを回していきたいと思っております。
先般、この取り組みを日本エス・エイチ・エル主催のタレントマネジメントウェビナーでご紹介しました。このウェビナー出演をきっかけに他社の人事担当者と情報交換の機会を得ることができました。お会いした各社さんとも、独自の工夫を凝らしたタレントマネジメント施策を導入されていて大変勉強になりました。今後も情報交換を続けていくつもりです。日本エス・エイチ・エルはアセスメントの専門性が特徴的な会社ですが、人事担当者のネットワークを提供してくれる点も魅力の一つです。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルティング3課 課長
横山武史
多彩なValue Creatorによる挑戦と変革という今回のお取り組みは、当社の「人のポテンシャルを見いだし、登用することで能力の発揮を支援する」という考え方と一致しており、私としても大変共感を覚えます。
このお取り組みは2021年11月、岸さんをはじめとする人事戦略部の方に、トライアルで万華鏡30の1on1フィードバックを実施するところからスタートしました。トライアルから数か月間でここまでの仕組みを作り、施策を動かしておられる実行力に感服しました。
また、岸さんの他社と積極的に交流しオープンに情報交換する姿勢、自ら人材データ分析に取り組まれる熱意は、新しいHRパーソンの在り方を示してくれていると感じます。
これからも当社およびSHLのグローバルな知識と経験でお役に立てるよう全力で努めてまいります。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

通貨処理機等の製造を行うグローリー。昨今の電子決済化など事業環境の変化に対応するため、人材の計画的な発掘・育成・配置の必要性が高まり、タレントマネジメントの基礎として全社員のアセスメントデータを取得し、人材可視化を行いました。
※本取材は2023年5月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
グローリー株式会社
通貨処理機・セルフサービス機器の開発・製造・販売・保守、電子決済サービス、生体認証ソリューション、ロボットSI等の提供
機械
3,498名(グループ連結:10,792名)※2023年3月31日現在

インタビューを受けていただいた方
永瀬 厚司 様
グローリー株式会社
人材開発部 人材教育グループ グループマネージャー
インタビューの要約
コア技術を新たな事業につなげることができる人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。
全従業員共通のアセスメント(OPQ)を実施。説明会や動画にて自己理解の重要性を伝え、受検率100%を達成。
データ分析により全社および部門別の人材の特徴を可視化。
新任管理者研修内にてOPQの説明パートを設け、部下理解およびキャリア面談での活用を促進。
管理職の要件にPMCコンピテンシーを採用し、今後のさらなる人材育成施策を検討する。
未来に必要な人材を計画的に育成すべくタレントマネジメントに着手。
私は、ソフトウェア技術者として国内および海外での製品開発を経験した後、2019年4月に人材開発部へ異動しました。人材開発部のミッションは、効果的に人材の採用・教育・発掘・育成・配置することです。現在は人材教育グループマネージャーとして、各事業部にある教育部門と連携し、全社の教育を進めています。
グローリーは通貨処理機の開発製造からメンテナンスまで一貫して行う機械メーカーですが、培った技術を活かして電子決済サービスや生体認証、メカトロニクスを活かしたサービスなどの事業も行っています。海外では競合と資本提携を進め、この10年間で海外売上比率は半分以上を占めるまでになっています。キャッシュレス化が進み事業環境が大きく変化する中で、新しい事業の柱を作るビジネスリーダー、技術で牽引する開発のリーダー、資本業務提携先とのシナジーを創出できる人材などが必要となってきました。未来に向けて必要な人材要件の定義、その素養を持つ人材を社内で把握し、全社で共有し、計画立てて育成するには至っていませんでした。これらの課題に対処するために、まず現状把握のため人材可視化に取り組むことにしました。

全従業員共通のアセスメントデータを収集。受検率100%。
タレントマネジメントを実施する上で、行動特性を示すアセスメントデータは重要な情報の1つです。しかし、当時社内にあったアセスメントデータは対象層によって異なっていたため、全従業員を共通で見られるものさしが必要だと考えました。また、海外関係会社を含めると、外国人比率も高く、グローバル展開できる日本エス・エイチ・エルのOPQを導入しました。また、従業員への負担を考えたときに、受検にかかる時間なども適切でした。さらに、再受検をせずにより詳細のコンピテンシーが見られる万華鏡リポートを追加出力できることも魅力的でした。
従業員に受検を依頼するにあたっては、全員に受検してもらえるように「キャリア自律のために自己理解を深めよう」というメッセージを発信しました。説明会を10回開催し動画も用意し、受検してもらえるよう促した結果、2カ月かかりましたが、受検率100%を達成しました。
人材の特徴を可視化。キャリア面談でも活用。
受検結果は、人材データベースシステム上で本人と上司が確認できるようにしました。上司には、部下の理解促進のために年1回のキャリア面談でOPQを活用してもらっています。結果の解釈が難しいという声もありましたが、活用度合いに関するアンケートでは、「OPQを活用して部下と対話する」という段階までは60%の方が実施したと回答しており、概ね肯定的に受け入れられたと考えています。しかし、日頃の行動と照らし合わせてフィードバックをしたり、OPQを用いて能力開発計画を立てるなど、さらなる活用段階まで至っておらず、継続したOPQ自体の理解促進や部下とのキャリア面談、1on1のやり方など実践につなげていくための学びの場が必要と考えており、今後の課題です。現場からチームメンバー全員で結果を共有してフィードバックしあい、相互理解が深まったという嬉しい反応もありましたので、こういった活用事例を共有していくことも重要だと思っています。
人材開発部では、結果データを活用し、現状の従業員の全体傾向を可視化しました。具体的には、全体傾向と開発、営業、保守などの部門ごとの傾向を分析しました。結果は従業員の特徴がよく表れており、例えば、顧客と接する職務はOPQの人との関係の領域が高得点の傾向があり、開発は低得点の傾向がありました。また、考え方の領域はその逆でした。

この結果は経営層に報告しましたが、データでの可視化はあくまでも現状把握です。ここから見えてくる仮説と、会社のビジョン達成に向けて、これから必要な人材を計画的に発掘・育成・配置するために会社がすべきアクションにつなげていくことが、次の課題です。
また、会社の経営戦略に基づいて、来年から新たな人事制度の運用が開始します。その中で、管理職の行動評価に万華鏡のPMCの中から当社として重要視する項目をピックアップし、取り入れています。このように、人事戦略、従業員のキャリア形成支援とアセスメントを有機的に機能させることで、人事戦略として掲げている「個人の成長とともに、会社が成長し、一人ひとりがグローリーで働くことに強い魅力を感じ、誇りを持っている」状態を醸成し、会社の持続的成長につなげていきたいと考えています。
日本エス・エイチ・エルは私たちに寄り添い、課題の背景を踏まえて対応策を検討してくれるパートナーです。他社人事の方との情報交換の機会を提供していただけたのも有難いです。今後もタレントマネジメント推進のため様々なご支援をお願いしたいと思っています。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
鈴木 悠太
今後の事業展開を踏まえタレントマネジメントの実施に踏み切り、文字通り全社員データを取得、そのデータを様々な人事施策に活用されている本お取組みはタレントマネジメントの好例ではないかと考えております。「アセスメントデータを余すことなく活用したい」、グローリー様が本お取組みに着手され受検率100%を達成し、全社員データを取得した後に永瀬様から改めてご相談いただいたことを今も強く覚えております。次なる人事施策に向けてアセスメントデータをどう活かせるか、都度ご相談を頂戴してお打ち合わせを続け、様々な施策の検討に携われていることは私自身とても大きな経験となっております。グローリー様の「パートナー」と仰っていただいたことに恥じぬよう、今後も微力を尽くして支援させていただきます。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

ビジネスモデルの大幅な変更を経験し、創薬ベンチャーとして再出発したカイオム・バイオサイエンス。
成果創出に向けて社員の能力開発と協働を促すための取り組みをご紹介します。
※本取材は2021年6月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
株式会社カイオム・バイオサイエンス
独自の創薬基盤技術であるADLib®システムを核とした抗体医薬品の創薬事業および創薬支援事業等
医薬品製造業
58名(2021年6月30日現在)

インタビューを受けていただいた方
弘津 千津子 様
株式会社カイオム・バイオサイエンス
経営管理部長
インタビューの要約
数年前に経営体制の刷新と事業方針の大幅変更を経験。研究員の一部には専門外の分野へのチャレンジが求められたり、成果創出のためにビジネスを意識したプロジェクトマネジメントを初めて任されるなどして、高いハードルが課され、研究者としての探求心と、組織内での貢献をどのようにつなげられるかという葛藤が生じていた。
現在、成長基調にある当社においては、創薬開発のスピードアップや受託研究の拡大に対して、組織的に対応することが急務であり、今後社員には、さらなる役割の変更や拡大を期待する可能性が高い。そこで、自身と組織で働く他者について改めて相互に理解し、協働を促進するためのワークショップを開催した。
管理職以下全社員が「万華鏡30」を受検し、自身の特徴を理解した後、自身の仕事の面白みや悩みを共有するグループワークを行った。他者の仕事への理解と関心が高まると同時に、自身の能力開発への意識が高まる効果を実感した。
今後は、プロジェクトやタスクへの任命にもアセスメントを活用し、成果創出に戦略的人事として貢献していきたい。
組織や人事制度の変更や事業方針の大幅転換の中で 人の心はついてこなかった。
当社は、2005年に国立研究開発法人理化学研究所の太田邦史研究員(現 東京大学副学長・教授)が開発した、ADLib®システム(アドリブシステム)という抗体作製技術を事業化するために設立された会社です。2011年に上場した際の事業計画は、このADLib®システムを、製薬企業に技術導出し、収益を獲得するというものでした。抗体作製の新技術は世の中でも広く話題になり株式市場でも大いに注目を得ましたが、残念ながら当初目指していた技術導出により大きな収益を獲得するという結果には至りませんでした。2017年には経営体制を刷新し、新社長のもと、それまでの技術導出を中心とした戦略から、基盤技術をベースとした創薬開発ベンチャーとして自社で開発した医薬候補品(パイプライン)を製薬企業等に導出するビジネスへと事業転換しました。
この大幅な事業転換を実施する前の2015年には100名を超えていた従業員の数を希望退職の実施により2016年末には約50名まで縮小。機能別だった組織にプロジェクト制を導入するなど、人事制度の変更を進めていた中で、さらに2017年に大きな事業転換を行うことになり、社員の心には期待と不安が入り混じっていました。半数以上の研究員は、専門外の分野におけるチャレンジを求められたり、これまでに経験のないプロジェクトマネジメントの責任を担う状況に初めて直面するなど、とてつもなく高いハードルを課される状況に陥っていました。
事業フェーズの進展に伴い、今後の役割拡大・役割変更に備えて、 自分と組織について知ってほしい。
現在、事業転換から4年が経過し、ひとりひとりの努力が実り創薬事業でも成果が出始め、手ごたえを感じながら研究開発を進める社員が増えてきました。現在、当社には、臨床試験のフェーズに入っているパイプラインが一つと、臨床準備中のものが一つあります。今後、当社が、創薬ビジネスにおいて持続的に成長していくためには、臨床開発フェーズに至るパイプランを継続的に創出すること・外部との取引を拡大していくことが重要であり、社員には事業状況や組織、自分自身、そして一緒に働いている人々について知っていただき、会社の成長とともに起こり得る自身の役割変更・役割拡大に備えていただきたいという思いがありました。
今回、管理職以下全員を対象に、社内の各部門が担っている役割や成果、万が一自分が異動した場合に何が求められるのかをイメージしてもらうための研修を行いました。研究者はもともと、探求心を持って一つのことを深く考察するのに長けているが、自らの専門分野から離れたところで周囲の助力を求めながら仕事を進めていくことは苦手な傾向があります。会社としては、この機会に、自分の特徴を振り返り、自分でできること・周囲の協力を得ないとできないことを知ってもらいたい、また同僚の苦しみや組織の課題を知って、ともに解決策を考えてほしいという狙いがありました。実は、数年前にも全社員アセスメントを試みたことがありますが、当時は事業が停滞していた影響もあり、組織や周囲に対する警戒心が強く、なかにはアセスメント自体を受けようとしない社員もいました。今回は特段反対もなく全社員が期日までに受けてくれて、だいぶ受け止め方が変わったと感じました。

研修は数人ずつのグループによるワークショップ形式。「万華鏡30」の結果をもとに、自身の特徴について理解したあと、「自分の仕事を、面白みの観点から説明する」、「自分の職場での悩みを話す」、この2点の課題に取り組んでいただきました。組織の中で自己アピールをするとともに、他者に共感してもらうのが狙いです。それぞれの行動特性を認識しているので、どのような行動をとるべきかという現実的なディスカッションもできました。
研究者がビジネスをするために、客観的な自己理解と他者への関心が必要。
日頃自然科学研究に従事している研究者が相手ですので、日本エス・エイチ・エルのような外部業者が長年の研究に基づいて作成した、大規模データに基づく評定であるというアプローチが、とても適していました。今回、リーダー候補者層を対象にしたリーダー研修も別途実施しており、そこではコンピテンシーのポテンシャルに基づく説明を強化しました。自分の強みと弱みを認識した上でオンラインの研修を受けてもらうのですが、能力開発の必要性を実感してもらう良い流れができました。
研究者がビジネスをするのには、高いハードルがありますが、会社の成長を支える経験をとおして、現在では、すべての研究員が、研究をプロジェクトとしてマネージして成果に導かなくてはならないことを自覚しており、多かれ少なかれ「このままではいけない」という意識があるように見受けられていました。そのタイミングでアセスメントの結果を見ると、「やっぱり、こういうところが足りないのか」と、実感する部分があったのではないでしょうか。また、もともと研究者や技術者は、みずから腹を割って共感しあう傾向はあまりありませんが、それを解消するために今回の研修は効果的でした。ワークショップでは、皆さんが一緒に働く仲間に興味を持ち始めたな、というのを実感しましたし、体験の共有や共感から得られる学びの存在にも気づいてもらえたように思います。
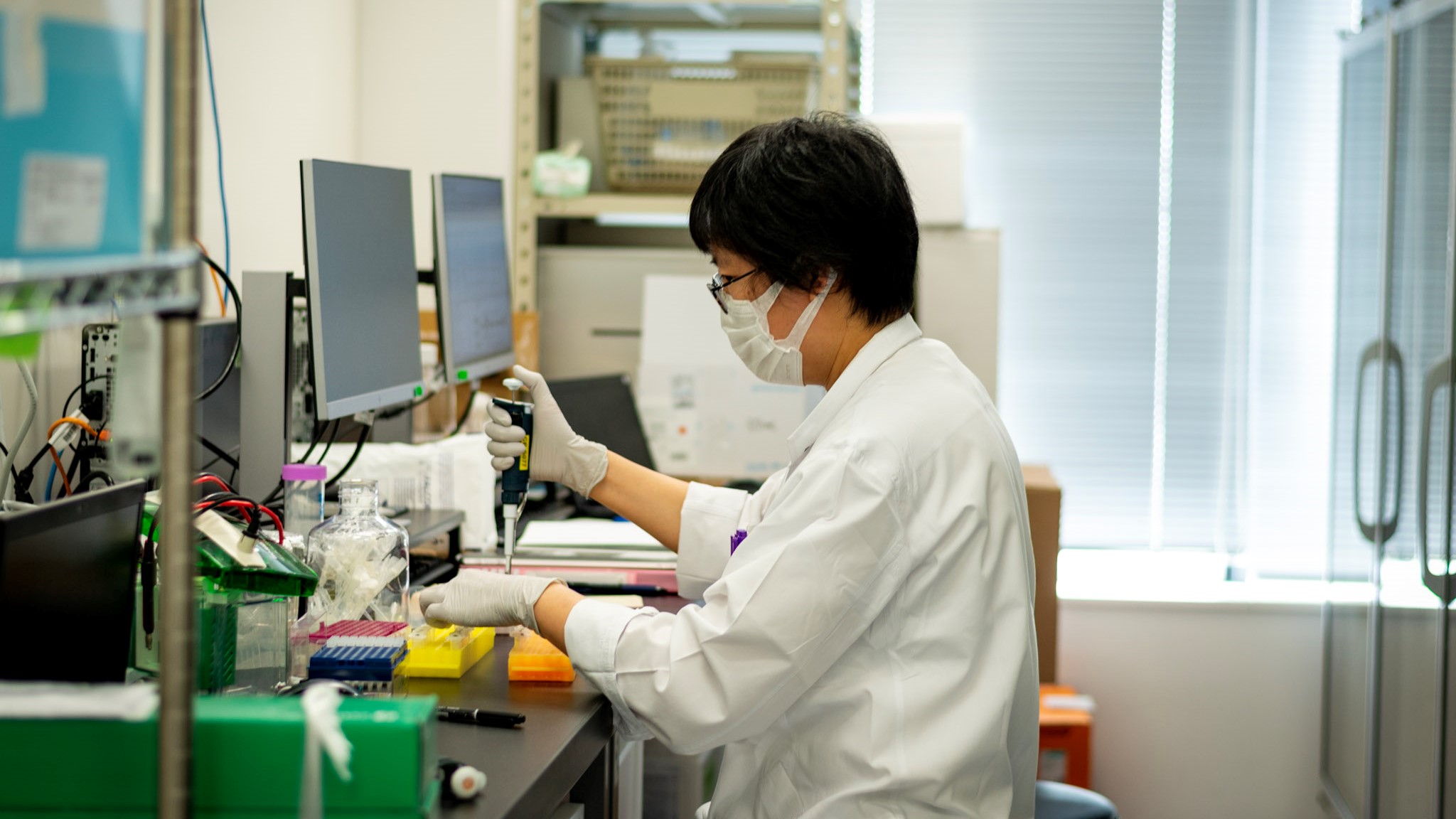
今回、「万華鏡30」を組織開発ワークショップとリーダー研修のために活用しましたが、今後はプロジェクトチームの編成にも活用していけるのではないかと考えています。たとえば、各研究員はプロジェクト提案が通るとプロジェクトリーダーとなって研究を推進しますが、プロジェクトになる前のタスクにおいては、上長からタスクリーダーを任せる研究員をアサインすることが多いので、パーソナリティ傾向をもとに人事から可能性を提案するというのも有効だと思います。マネジメントコンピテンシーの高い人材や、イノベーションのポテンシャルの高い行動傾向を持つ人材を早めに起用するなど、戦略的な人事を展開することで、成果の創出に貢献できるのではないかと考えています。
日本エス・エイチ・エルのコンサルタントに共通しているのは、分析することを楽しみ、結果が役立つのを喜びに感じておられる方が多いことだと思います。万華鏡30の活用方法も、専門家の観点からいろいろと提案してくださるので、「いい会社だな」と感じています。これからも他社の興味深い取り組みなどを共有いただきながら、組織・人材開発について広く意見交換させてもらいたいと思います。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
霞 紫帆
「自分と組織についてもっと関心を持ってほしい。知ってほしい。」弘津様のこの思いが本プロジェクトの推進力となりました。
「研究者の方々に、他人に関心を向けてもらうよう働きかけるには、どんな手法が最も効果的か」を検討し導き出したOPQの学術的背景から伝える方針は、本プロジェクトの一助となったのではないかと考えております。弘津様の思いを皆様と共有できればという気持ちでワークショップの講師も務めさせていただきました。少数精鋭の組織だからこそ、パーソナリティをコミュニケーション活性や能力開発に役立てるやり方が効果的であったと思います。
引き続き、探求心を忘れず多角的に組織発展のお力になれれば幸いです。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

多様なバックグラウンドを持つ社員の相互理解のために、1on1ミーティングにアセスメントを活用。
マネジャー向けコーチング研修を実施した朝日インテックJセールスの事例をご紹介します。
※本取材は2021年7月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
朝日インテックJセールス株式会社
医療機器の販売、医療機器関連の研究、開発事業、医療機器に関するコンサルタント事業、医療機器の修理及び賃貸業務
医療機器販売業
従業員数 : 95名 (2021年6月末日現在)

インタビューを受けていただいた方
川又 治 様
朝日インテックJセールス株式会社
営業本部 フィールドマネージメントチーム チームリーダー
インタビューの要約
様々なバックグラウンドを持った社員が相互理解を行うために、客観的に自己をみつめるツールとしてアセスメントを導入。
効果的な1on1ミーティングを実施するため、マネジャーにアセスメント「万華鏡30」とコーチングのトレーニングを実施。離職が減ったほか、マネジャーのコミュニケーションが変わったというフィードバックを得られた。
アセスメントによって見出された社員の全体的特徴を、採用戦略にも活用。新しい個性をもった新入社員をのびのび育成するためにも、コーチングを活用してほしい。
今後の課題は、採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用し、科学的人事を推進することで、変化の激しい医療業界を生き残るための風土改革を行うこと。
様々なバックグラウンドを持つ人材が相互理解をするために、 全社にアセスメントを導入。
私は新卒でリース会社に入社し、外資系医療機器メーカー、日本の医療機器メーカーを経験し、11年前に当社に入社しました。大学を卒業してから営業一筋でしたが、4年前に新設の人事部門で採用・教育を担うことになり、手探りで現在の部署を作り上げました。
2017年にノーベル賞を受賞した行動経済学者、リチャード・セイラーの、人間は必ずしも合理的に意思決定をするわけではないという理論を書籍で読み、心理学的なアプローチに興味を持ちました。営業時代にも、人材育成における個人差を目の当たりにしたり、部下との関わり方がわからず悩んだりすることがありましたので、人事の仕事はこれらのことを学ぶいい機会だと思いました。
日本エス・エイチ・エルの万華鏡30を導入した目的は、社内のコミュニケーションの円滑化です。当社は、カテーテル治療に使用されるガイドワイヤーでトップシェアである朝日インテックの国内販売部門として2006年に設立されました。売上が10年余りで50倍と急成長した為、内資系企業・外資系企業からの中途入社、新卒入社、また元々当社製品を扱っていた企業からの入社と、様々なバックグラウンドを持った人材が集まっています。一時期離職が続いたこともあり、上下間のコミュニケーションや相互理解が必要だと感じました。特に5年前から始めた新卒採用で入社した社員は、我々キャリア入社組からすると異色の存在。彼らを適切に育成する意味でも、社員の相互理解が必要です。そのため、全社にアセスメントツールを導入して個人に結果をフィードバックし、「自分が何者であるか」というコミュニケーションの土台をまず作りました。万華鏡30の結果については、「当たっている」という声が多かったですね。
1on1ミーティングでアセスメントを活用するコーチング・トレーニングを実施。 離職の減少、上司のコミュニケーション力向上に効果あり。
その後、上司が部下をコーチングするための1on1ミーティングの研修を企画しました。その際に、「万華鏡30を1on1に活用したい」と思い、日本エス・エイチ・エルのコンサルタントと外部企業のコーチングの講師で打ち合わせをしていただいて、上司が1on1の中で万華鏡30を活用できるように進めました。
1on1ミーティングは月1回、各エリアマネジャーと部下との間で実施されます。万華鏡30を使うことを推奨していますが、使いたくない場合は使わなくてもよいと告知しました。また、1on1で万華鏡30を使う場合は、部下の結果だけを提示すると高圧的に受け止められる可能性もあるため、かならず上司自身の結果も提示して相互理解するようにと強調しました。

万華鏡30を使った1on1およびコーチングのトレーニングを行った効果ですが、まず離職が減りました。もちろん離職はゼロにはできませんし、する必要もないと思いますが、医療業界での重要なリソースであるドクターとの人脈や知識を持つ社員の流出は痛手ですし、すぐに次の人を育てられるわけではありません。今後は、制度面などコミュニケーション以外の部分でもさらにリテンション施策を整えていくことを考えています。
また、一部のエリアでは上司の接し方がガラッと変わったという報告を若手社員から受けています。今まではどちらかいうとトップダウン的なコミュニケーションだったのが、部下の話を聞くようになったということです。コーチングの在り方を学習したことに加え、万華鏡30によって「自分にはこんな要素があったのか」と客観視することで、マネジャーにも学びがあったのかなと思います。
社員の特徴は採用方針にもフィードバック。
採用と育成の両輪の人事施策で、変化の激しい医療業界を生き残る。
また、今回の全社受検の結果をもとに、採用戦略を検討しています。たとえば、当社の営業職社員が強く持つ特徴を採用要件にする、オーソドックスなマネジャー層を補うため創造性を採用要件に入れるなどです。新卒社員には創造性を発揮していただきたいと期待しています。昨今の企業合併やコロナ禍など、医療業界は変化が著しく、環境の変化に適応できる人材がいないと、組織として生き残っていくのは難しいと思います。
その上でコーチングの効果として期待しているのは、マネジャーが新しい発想をもった新入社員の個性を生かし、のびのび育成できるようにすること。せっかく尖った人材を採用しても、マネジメントによってだんだん丸くなってしまうのではもったいない。同時に、私からも若手社員と個別に話をして、「今まで受けた教育で納得いかないことや問題点などあるかもしれないが、自分たちで考えて自分たちで決めていいんだよ」とメッセージを送っています。若い頃から自分で決める経験を積まないと、意思決定のできないマネジャーになってしまいます。せっかく素質のある人材を採用しているので、彼らには早い段階から自分で決めるということ、そして決めたことに責任を持つということを、しっかり教育で身につけさせたいと思っています。
今回、日本エス・エイチ・エルに携わっていただいてプロジェクトを実行し、少なくとも管理職以上の意識は変わりました。頭ではわかっていても感覚的にわかりづらかった「人にはオリジナリティや個性があって一人一人異なる」ということをアセスメントのデータで明示してもらえたことが大きいと思います。担当コンサルタントの方には、社員向けにアセスメントの説明会も開いていただき、社員が理解を深めることに貢献していただきました。
今後の課題は、コーチングと採用だけでなく昇進昇格、登用にもアセスメントを積極活用していくこと。変化の大きい医療業界において、人の目による人事のみに頼ってしまうと、オーソドックスな社風が強くなってしまい、組織として生き残ることができません。データや統計など科学的な資料をもって、人の目の限界を補う必要があります。
最後に、個人的な課題は、自分が経験したことを次の世代へ伝えることです。私自身、多くの上司や先輩に育ててもらった恩を感じながら年を重ねましたが、今は私自身が次世代を育て、彼らがまた次世代を支えていくことを実感しています。このような継承の物語が積み重なって歴史となってきたのが、日本企業の強みではないでしょうか。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
藤田 夏乃子
1on1ミーティング実施にあたり、相互理解を行うための材料としてアセスメントを利用したいというお話をいただき、今回の取り組みが始まりました。
きちんとアセスメント「万華鏡30」を理解してほしいという川又様の熱意を受けて、私が「万華鏡30」の説明会を実施させていただきました。説明会当日は参加者の方からたくさんの質問をいただき、皆様積極的にご参加いただいたのを覚えています。
実際に川又様から1on1ミーティングを実施していく中で、上司・部下間でよりよいコミュニケーションに変わっていっているとお聞きしたときはこの取り組みに貢献できてよかったと感じました。
今後も広くアセスメントの活用を考えていらっしゃるとのことで、様々な場面でお力になれるようにしていきたいと思います。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連するおすすめのサービス
関連する導入事例


能力開発に役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム


配置・登用に役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム

関連する導入事例
関連するコラム

関連する導入事例
関連するコラム

関連する導入事例
関連するコラム


オンボーディングに役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム