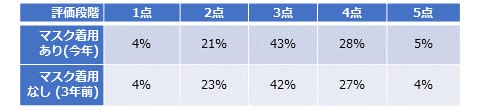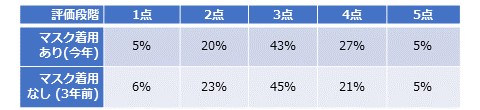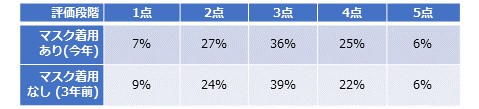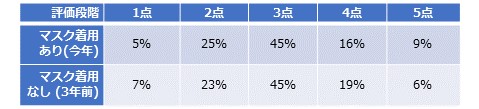シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。本資料では、新卒採用でも利用できる日本エス・エイチ・エルのシミュレーション型アセスメントをご紹介します(全10ページ)。
こんな方におすすめ
選考手法がマンネリ化している
面接以外の効果的な選考手法を知りたい
採用選考の予測精度を高めたい
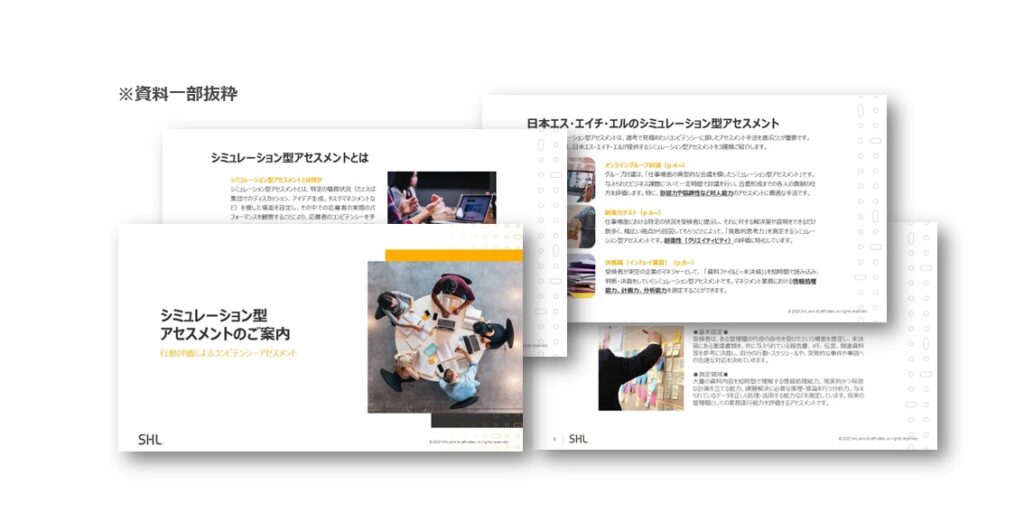


このような方にオススメ
※「グループ討議」は「オンライン」ではなく、「対面」での実施を想定した内容です

3つの特徴
グループ討議を選考で実施するメリット、測定しやすい能力、テーマ設定の方法、運営上の留意点など、当社の実際の題材や評価シートを使いながら、グループ討議という評価手法を詳しく解説します。
学生が実際にグループ討議をしている映像を観ながら評価演習を行い、その後評価のポイント等について具体的に解説いたします。評価対象となる言動を正しく理解するとともに、ご自身の評価の癖や甘辛も見直すことができます。
※当社で提供しているグループ討議題材を使い、評価演習を行います
単元ごとに細かく分かれているため、すきま時間を有効活用できます。パソコン、タブレット、スマートフォンでの視聴に対応しており、受講期間中はいつでも、何度でも視聴が可能です。

(受講時間の目安:120分)
1.はじめに
・動画の概要
2.グループ討議とは
サンプル視聴
・グループ討議とは
・グループ討議の類型、問題例
・グループ討議の類型、それぞれの違い
3.評価者の役割
サンプル視聴
・評価者の役割
・評価者がとってはいけない行動
4.グループ討議題材(課題設定型)
・今回使用するグループ討議題材の説明
・グループ討議題材の資料1~3
5.評価の仕方
・グループ討議の評価指標
・「評価シート」の記入の仕方
6.「分析力」の評価
・「分析力」の評価
7.「影響力」の評価
・「影響力」の評価
8.「チームワーク」の評価
・「チームワーク」の評価
9.能力別評価、総合評価の目安
・能力別評価の目安
・総合評価の目安
10.映像評価演習(練習)
・学生の討議場面をピックアップしながら評価の練習を行う
11.映像評価演習(討議映像)
・学生の討議映像を観ながら実際に評価を行う
12.映像評価演習(解説映像)
・映像を振り返りつつ、評価のポイントや評価につながる言動等を解説
13.グループ討議テーマの作成
・グループ討議テーマ作成のポイント
・グループ討議テーマ作成のプロセス
・課題設定型テーマ例
・自由討議型テーマ例
14.その他の検討事項
・実施時間、人数、環境等について
15.おわりに
・おわりに

主催
日本エス・エイチ・エル株式会社
対象者
企業の人事・採用・育成業務に従事されている方(同業者、学校法人、個人の方はお申込できません)
受講費
受講者1名様につき5,000円(消費税等別)
※「受講人数無制限」の年間契約プランもございます。詳しくは、担当コンサルタントまでお問い合わせください。
受講期間
受講用URLメールの到着日から3週間
お申し込み方法
フォームよりお申込みください。お申し込み受付後、原則2営業日以内に受講用URLとログインID、及びログインパスワードの設定方法を記載したメールをお送りします。
※届かない場合は、事務局までお問い合わせください。
お支払い方法
受講用URL等を記載したメール送信後、当社他サービスの利用料金と併せて請求させていただきます。
※振込手数料は貴社ご負担にてお願いいたします。
動作環境
Windows
OS
Windows 10、11
ブラウザ
Microsoft Edge(最新版)、 FireFox(最新版)、Google Chrome(最新版)
Mac
OS
MacOS High Sierra 10.13 以降
ブラウザ
Safari(最新版)
iPhone/iPad
OS
iOS 14.0 以降 / iPadOS 14.0 以降
ブラウザ
Safari(最新版)
Android
OS
Android 8.0 以降
ブラウザ
Google Chrome(最新版)
注意事項
・1つのログインIDで、同時に複数の端末で視聴することはできません。
・ログインIDやパスワードの共有、第三者への譲渡を禁止します。また、セミナーの録画・録音、転載、第三者への公開等は固くお断りいたします。
・利用可能期間中にコンテンツの受講が完結しなかった場合や、サービスの利用が無かった場合にも、利用期間の延長や返金は行いません。
お問い合わせ
日本エス・エイチ・エル株式会社 セミナー事務局
Eメール training@shl.co.jp
関連する導入事例
関連するコラム


このような方にオススメ

3つの特徴
「採用基準の必要性」とともに「各選考手法の特徴」を理解していただくことで、自社の求める人材像や採用基準に応じた、最適な選考プロセスを組み立てることができるようになります。
知的能力テスト、パーソナリティ検査、面接、グループ討議等、様々な選考手法の特徴を解説します。講義だけではなく、知的能力テストや面接映像の評価演習など、選考手法の一部を実際に体験していただけますので、各選考手法の違いを体感しながら理解することができます。
単元ごとに細かく分かれているため、すきま時間を有効活用できます。パソコン、タブレット、スマートフォンでの視聴に対応しており、受講期間中はいつでも、何度でも視聴が可能です。

(受講時間の目安:90分)
1.はじめに
サンプル視聴
・動画の概要
2.採用基準の必要性
サンプル視聴
・なぜ採用基準が必要か
・採用基準の作り方
3.選考プロセスの設計
サンプル視聴
・採用プロセスの4ステップ
・主な選考手法について
・よい選考手法とは
4.知的能力テスト
・学力テストと知的能力テスト
・テストを選ぶ基準
・妥当性について
・受検形式
5.パーソナリティ検査
・パーソナリティとは
・回答形式の違い(インプット)
・結果出力の違い(アウトプット)
・測定方法
6.面接
・面接の2つの役割
・面接の全体像
・面接における留意点
7.映像評価演習 (面接映像)
・新卒採用応募者の短時間の面接映像を観ながら評価を体験
8.映像評価演習 (解説映像)
・新卒採用応募者の面接映像を振り返りつつ、「評価のポイント」や「質問の意図」等を解説
9.グループ型の選考手法
・グループ型の各手法の特徴
・グループ討議の2つの形式
10.その他の選考手法について
・その他の選考手法
11.演習
・自社の「採用基準」と「選考手法」を振り返る
12.おわりに
・おわりに

主催
日本エス・エイチ・エル株式会社
対象者
企業の人事・採用・育成業務に従事されている方(同業者、学校法人、個人の方はお申込できません)
受講費
受講者1名様につき5,000円(消費税等別)
※「受講人数無制限」の年間契約プランもございます。詳しくは、担当コンサルタントまでお問い合わせください。
受講期間
受講用URLメールの到着日から3週間
お申し込み方法
フォームよりお申込みください。お申し込み受付後、原則2営業日以内に受講用URLとログインID、及びログインパスワードの設定方法を記載したメールをお送りします。
※届かない場合は、事務局までお問い合わせください。
お支払い方法
受講用URL等を記載したメール送信後、当社他サービスの利用料金と併せて請求させていただきます。
※振込手数料は貴社ご負担にてお願いいたします。
動作環境
Windows
OS
Windows 10、11
ブラウザ
Microsoft Edge(最新版)、 FireFox(最新版)、Google Chrome(最新版)
Mac
OS
MacOS High Sierra 10.13 以降
ブラウザ
Safari(最新版)
iPhone/iPad
OS
iOS 14.0 以降 / iPadOS 14.0 以降
ブラウザ
Safari(最新版)
Android
OS
Android 8.0 以降
ブラウザ
Google Chrome(最新版)
注意事項
・1つのログインIDで、同時に複数の端末で視聴することはできません。
・ログインIDやパスワードの共有、第三者への譲渡を禁止します。また、セミナーの録画・録音、転載、第三者への公開等は固くお断りいたします。
・利用可能期間中にコンテンツの受講が完結しなかった場合や、サービスの利用が無かった場合にも、利用期間の延長や返金は行いません。
お問い合わせ
日本エス・エイチ・エル株式会社 セミナー事務局
Eメール training@shl.co.jp
関連する導入事例
関連するコラム
シミュレーション型アセスメントのご案内

シミュレーション型アセスメントとは、特定のビジネス場面を想定した課題を設定し、そこでの意思決定や行動の適切さを観察することで、応募者のコンピテンシーをアセスメントする手法です。本資料では、新卒採用でも利用できる日本エス・エイチ・エルのシミュレーション型アセスメントをご紹介します(全10ページ)。
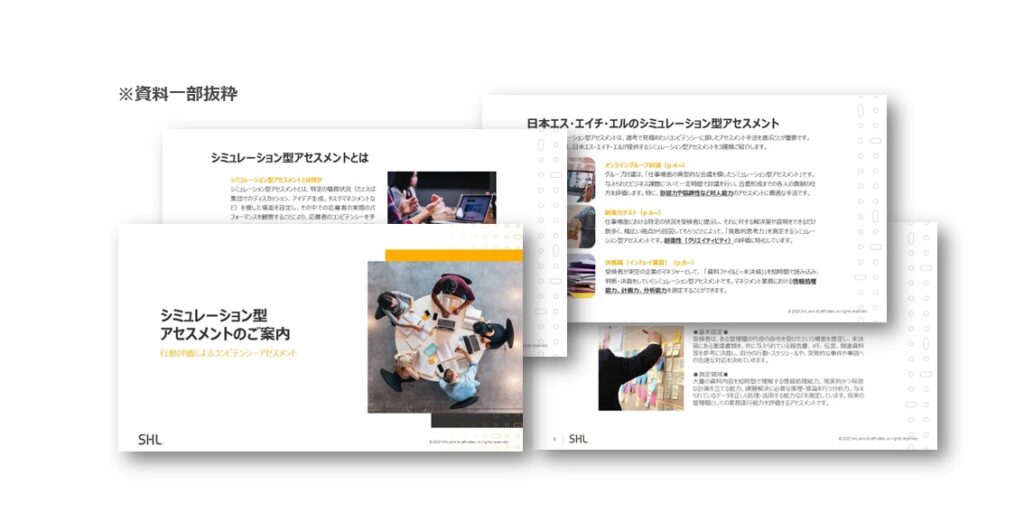
あわせて読みたい

本セミナーでは、行動アセスメントの専門家である講師が「シミュレーション演習」の手法について分かりやすく解説するとともに、実際に選考に取り入れる場合の実施のヒントをお伝えします。

日本エス・エイチ・エル
アセッサーグループ 部長
オンデマンド配信概要
約30分
2025年10月30日(木)まで
Zoomによる録画配信
無料
企業および組織の人事に携わる方
※同業者、学校関係者、個人の方のご参加はご遠慮ください。
日本エス・エイチ・エル株式会社 イベント事務局
TEL:03-5909-7207
Eメール:event@shl.co.jp

コロナ禍によってオンライン化した採用プロセスと応募者に生じた変化に危機感を覚えた川崎汽船。
応募者のチーム行動の特徴を理解するために採用プロセスの改革に取り組みました。
※本取材は2023年11月に行いました。インタビュー内容は取材時のものです。
海上運送業、陸上運送業、航空運送業、海陸空通し運送業、港湾運送業等
海運業
単体:843名 (陸員638名、海員205名) 連結:5,458名

インタビューを受けていただいた方
川崎汽船株式会社
人事グループ 採用育成チーム
私は2018年に入社し、1年間グループ会社に出向して自動車輸送に関するドキュメンテーション業務を担当しました。その後本社に帰任し、極東から北米への自動車輸送に関わるオペレーションと営業を3年間ほど経験し、2022年4月に人事グループへ異動して採用と育成に携わっています。
すでに採用活動が始まっていた中での着任だったため、23卒採用は一人の面接官として関わりました。その中で、これまでの世代では部活動などチームで何かをするのが当たり前でしたが、コロナ禍で学生生活を過ごした23卒採用の学生はそうではなく、中には大学に友人がいないと聞くこともありました。また最終面接以外は全てオンライン選考でしたが、最終面接で初めて対面した際に応募者の印象が大きく異なるケースもありました。24卒採用においても同様の状況が生じる可能性があると考え、採用プロセスの改革に取り組みました。

1次選考は、多くの人が参加できるようオンライン面接を維持し、2次選考を変更しました。1対1だけでなくグループの中でどのように他者と接し、チームに貢献するのかが分かるように、対面のグループディスカッションを実施しました。さらに、同日中に1対1の面談も行いました。グループディスカッションと面談を同日に実施することで、グループでは目立たなかったけれども、1対1で魅力が出てくる人(相手に良い印象を与えながら論理立てて話ができる人など)を見つけることができ、応募者の特徴を多面的に捉えることができました。
オペレーションの負荷は大きくなりますが、今日のような状況下では応募者を惹きつけたり理解したりすることに十分な時間をかけるべきだと考えています。これからはさらに労働人口は減少するので、人材確保はより重要な課題となります。
評価を担当する現場の管理職の方々には事前の評価者トレーニングや選考当日の終日拘束などで大きな負担をお願いすることになってしまったのですが、昨今の学生の事情を説明し、コミュニケーション能力を確認したいという思いをしっかりと伝えることで賛意を示していただくことが出来ました。

応募者の所要時間が長くなる点がこの選考プロセスの不安要素でした。しかし、参加者からは「他社のグループディスカッションでは一体何を見られていたのか分からなかったが、(川崎汽船では)面談もあったので自分のことをよく見てくれていると感じた」と肯定的な反応が多くありました。当社としては、所要時間が長い分、入社意欲の高い方が参加してくれること、休憩時間に応募者の自然な様子を知ることができてその後のサポートがしやすくなることがメリットです。

内定後も途切れることなく人事がコミュニケーションを取ります。当社では配属を決める際に、本人の希望を提出してもらい、日本エス・エイチ・エルのアセスメント結果も参考にしながら向いている部署を検討します。入社後も階層別研修を実施し、一貫して社員の成長をサポートしています。
今後の採用施策では、身近な社員の「生の声」を聞きたいという応募者の要望に応えていく取り組みを行います。社員との対話セッションを毎月行って社員と直に接する機会を増やしていきます。
私自身の今後の展望として、広範な人事業務に携わり、その後は現場で人事としての知見を活かしたいと思っています。
日本エス・エイチ・エルは私たちの課題によく耳を傾けて、目的にかなった最適なサービスを必死に考えてくれます。また、アイデア段階で今回の取り組みを伝えた際に「人にコミットしていますね」とコメントをもらいました。この言葉が後押しとなり自信を持って進めることができました。今後も引き続き宜しくお願いします。
担当コンサルタント

日本エス・エイチ・エル株式会社 HRコンサルタント
橋本様をはじめとする、採用担当の皆様のお考えがとにかく素敵です。採用担当は様々な業務をこなす必要があり、工数削減に目を向けるのは当然のことだと思います。しかし、川崎汽船様は工数がかかったとしても、応募者をしっかりと理解することに労力を惜しみません。この姿勢、魅力的です。
私は母集団形成や選考辞退のお悩みを持つお客様からご相談をいただくことが多くあります。採用選考自体が学生にとって有意義であること、学生を意欲形成するための仕掛けが含まれていることがこのお悩みを解決するための大事なポイントだとこのプロジェクトを通じて気づかされました。
より良い採用選考が行えるよう気を引き締めてご支援いたします。今後とも宜しくお願いいたします。
おすすめのセミナー・イベント情報
関連する導入事例

関連する導入事例
関連するコラム

関連する導入事例
関連するコラム



お客様のご要望に合わせた プログラム
お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。
内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ



一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。


サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)
| 時間 | テーマ | 主な内容 |
|---|---|---|
| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |
| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |
| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |
| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |
関連する導入事例
関連するコラム