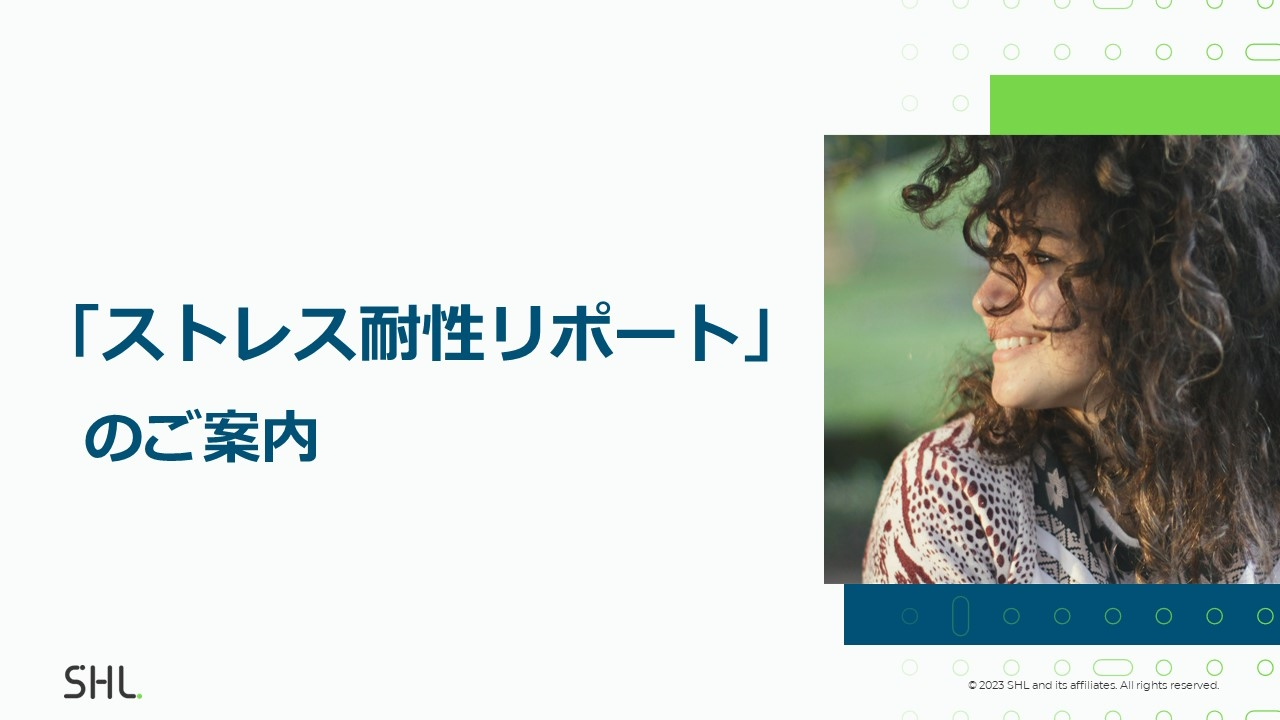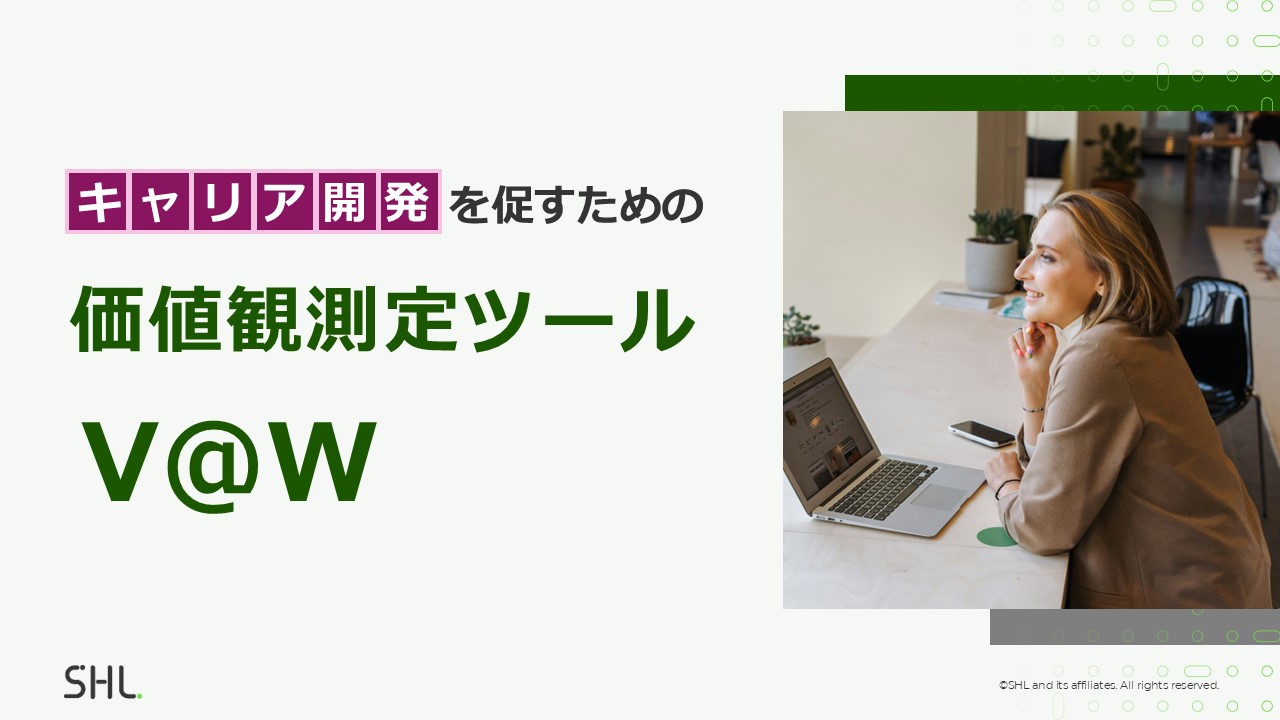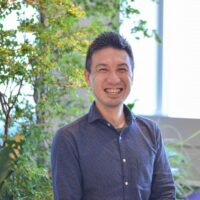能力開発に役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム


オンボーディングに役立つサービス
関連する導入事例
関連するコラム



お客様のご要望に合わせた プログラム
お客様のご要望に合わせたプログラムで実施できるトレーニングです。
内容はお客様のニーズや業界に合わせて調整でき、実際の環境でのデモンストレーションや実践的な演習を行うことで、効率よくスキルを身につけることができます。

こんな時におすすめ
【面接】「自社の採用基準」をもとに、面接官の目線を揃える
一人一人の面接官のスキルを高めるとともに、「自社の採用基準」に基づいて判断基準のバラつきを改善し、評価の目線を整えるためのトレーニングです。

【その他選抜手法】グループ討議評価者の評価のバラつきを改善する
「行動」を評価する手法としてニーズが高まる「グループ討議」アセスメントについて、講義、演習を通じてグループ討議への理解を深めつつ、評価者としての目線を整えるためのトレーニングです。

【能力開発】自社社員の能力開発を効果的に行う
「パーソナリティ検査」結果の解釈理解を深めつつ、講義、演習を通じて、効果的な自己理解や部下育成を支援します。


サンプルプログラム:面接官トレーニング(半日開催)
| 時間 | テーマ | 主な内容 |
|---|---|---|
| 13:00~14:05 | 基礎講義 | ・面接の目的、面接官の役割について ・面接に向けた準備、面接の流れ ・有効な質問、避けるべき質問 ・面接官の留意すべき点 |
| 14:05~15:05 | 演習(1) | ・面接映像を使用した評価演習 |
| 15:05~16:50 | 演習(2) | ・面接ロールプレイ演習「面接を体験する」 (複数回実施) |
| 16:50~17:00 | 総括 | ・まとめ、質疑応答 |
関連する導入事例
関連するコラム

キャリア自律への7つのヒント
具体的なキャリア・ビジョンのあるなしにかかわらず、自分の将来を考えるにあたり、キャリア・マネジメントを成功させた人たちのヒントをご紹介します。- 内省と評価 : 自分を見つめなおす時間を取り、何が自分を本当に突き動かすのかを理解しましょう。自分のスキル、強み、興味、価値観を評価してください。これまでの成果を振り返り、キャリアの中で充実感や満足感をもたらす要素を考えてみましょう。
- 専門家のアドバイスを求める : キャリアコーチやメンター、キャリアカウンセラーからの客観的な意見をもらうことを考えてみましょう。彼らはこの移行期を乗り越えるためのサポートを提供してくれます。
- ネットワーキングと人間関係の構築 : 業界イベントへの参加や専門団体へ加入して人脈を広げ、アドバイスをくれたり、キャリアの機会を提供してくれる可能性のある人たちとつながりましょう。
- 現実的な目標を設定する : 自分の情熱や価値観に沿った、達成可能な短期・長期のキャリア目標を立てましょう。これらの目標は、現在の状況に柔軟に対応できるようにしてください。
- スキルと教育を向上させる : キャリア目標に沿った新たなスキルの習得やさらなる教育を受けることを検討してみましょう。自分のスキルの理解やスキル開発のリソース、成長プランを活用できると、キャリア目標達成のための最も効果的な時間の使い方が理解できます。
- 適応力とレジリエンス(回復力) : 適応力とレジリエンスを重要な特性として受け入れましょう。変化は人生の自然な一部であり、新しい状況やキャリアの変化に適応することで成長や新たな機会につながる可能性があります。
- 前向きで忍耐強くあること : キャリアの転換には時間がかかることを理解しましょう。正しい道を見つけるには時間がかかるかもしれないので、プロセスを通じて前向きで忍耐強く、レジリエンスを持ち続けましょう。
組織として、人事としてできること
これら主体的にキャリアを築くヒントを元に、次のような施策が組織や人事として考えられます。まず、従業員自身が自分を振り返る機会、自己理解を促す機会を提供することです。アセスメントは簡便かつ網羅的に自分の特性を可視化することができるため、おススメです。当社では、パーソナリティ、価値観、モチベーションリソースなど、様々な観点のアセスメントツールがあり、自分をより良く理解する手助けを行います。結果を解釈する際、適切な知識を持った第三者(人事、上司でも可能です)がフィードバックすると更に理解が深まります。最も効果的な方法は1on1のフィードバックですが、難しい場合は集合研修での実施も可能です。また、自分の能力を成長させる教育プランやリソースを提供します。すでに多くの企業は実施していると思いますが、自身の気づきと教育や能力開発がセットとして体系的に行えると理想的です。
部下を持つ管理職層へのインプットも重要です。キャリア自律の考え方を伝え、理解を促します。単なる業務支援ではなく、部下のキャリア支援を行うという視点を持つと、個々人の特性や特徴に合わせて中長期的な視点で業務のアドバイスができるでしょう。キャリア支援の手助けは本人の成長を促し、結果的にパフォーマンスやエンゲージメント向上につながります。
また、組織の仕組みとして、キャリアコーチ、キャリアカウンセラーなどの専門職を配置することも一案です。専門家にアクセスできる環境は実際に従業員のキャリア形成に役に立つだけでなく、組織が主体的キャリア形成を支援するという明確なメッセージにつながります。

おわりに
日々の業務で自分のキャリアを俯瞰する機会のない人もいるかもしれませんが、キャリアの旅は選択したら終わりではなく、常に進行中です。私たちは絶えず進化し、成長し、自己改革を続けています。本コラムが、自分自身のキャリアを主体的に描き、またそれを後押しする組織作りのヒントになれば幸いです。
本コラムでは、社内公募制度でのアセスメント活用についてお伝えします。
求人・選抜
通常の人事異動とは異なり、社内公募制度は人材が必要な部署が社内で求人を出し、他部署の従業員が応募する制度です。募集対象が組織内の従業員であるだけで、社外での採用と似たプロセスを経ます。よって、通常の外部からの採用選考と同様に、各ポストの要件定義や求められるスキルの言語化にアセスメントが活用できます。各ポストの要件定義の手法は、こちらをご参照ください。選抜場面では、応募者は在籍する従業員のため、これまでの経歴・実績、保有資格やスキル、上司の評価など、参照できる情報が多くあります。これに加え、アセスメントでポテンシャルを測定すると、応募する未経験業務のパフォーマンス予測の精度が向上します。

従業員の自己理解とキャリア形成の促進
アセスメントは求人側だけのツールではありません。従業員一人ひとりが定期的にアセスメントを受検し結果をフィードバックすることで、自分自身の強みや弱みを可視化し自己理解を促すことが可能です。自分自身の特徴を含めたこれまでのキャリアを棚卸しして気づきの機会を提供することで、主体的に自分のキャリアを描く支援ができます。これは、近年推進されているセルフ・キャリアドッグ施策にもつながります。主体的なキャリア形成の促進は、社内公募制度の肝である、「従業員自らが応募する」ことの促進にもつながるでしょう。アセスメントは、オンラインで簡単に従業員が結果を見られる万華鏡30がお勧めです。上司との1on1での活用など様々な利用が可能です。

アセスメントが制度活性化の鍵に
冒頭紹介した調査では、多くの企業が社内公募制度を導入していることが分かりましたが、制度が効果的に機能しているかは企業によってまちまちでしょう。求人に際して、応募者がよく理解できるジョブディスクリプションやポストの説明を行うこと、また応募する従業員自身が自分のことをよく理解する機会を定期的に提供することは、ともすると形骸化してしまう社内公募制度の活性化につながります。いずれもアセスメントが補完できる部分ですので、ぜひご活用ください。
はじめに
タレントマネジメントの文脈で退職というと主に退職防止(リテンションプログラム)が話題になります。しかし、企業による退職、解雇がタレントマネジメントの文脈で話題に上がることはほとんどありません。タレントマネジメントは経営事業戦略を遂行するための人に関するあらゆる取り組みのこと。そしてタレントマネジメントの本質は適材適所です。適していない人を外し、適した人を置くことが適材適所だとすると外された人はどうなるのか。もちろん、その人に適した場所に行くのです。タレントマネジメントが生まれた米国ではその適した場所は主に他社です。つまりここで解雇が行われます。ジョブ型雇用では異なるジョブへの異動は原則ありません。
一方、日本では従業員を安易に解雇できません。また、日本においても人材の退出を無視したままタレントマネジメントを進めていくことは困難です。5年ほど前、日本の大手自動車メーカーが行っているハイポテンシャル人材プログラムの事例を当社主催の勉強会で、当事者である人事担当者に発表してもらったことがあります。その際に多くの参加者から次のような質問が出ました。「当社では重要なポストの空きが出ないためハイポテンシャル人材に修羅場経験を積ませる環境を与えることができない。どのようにハイポ人材のための重要ポストを確保しているのですか?」この質問に対する発表者の回答はコラムの最後にお伝えします。
本コラムでは、日本における解雇を概観し、タレントマネジメントのための人材退出をどのように進めるべきかについて述べます。

日本における解雇
解雇とは使用者による一方的な労働契約の終了です。理論上、法律と解雇権濫用法理に抵触しない解雇は可能なのですが、厳格なルールに基づく手続きが必要であり、極めて困難と言わざるを得ません。企業の戦略変更に伴う解雇や低業績者の解雇はできないと考えておくのが現実的です。
日本の解雇は整理解雇、懲戒解雇、普通解雇の3つがあります。それぞれがどのようなものかは以下、東京労働局労働基準部のパンフレットからの引用をご覧ください。(注1)
・整理解雇
会社の経営悪化による、人員整理を行うための解雇
次の4点をいずれも満たすことが必要です。
① 整理解雇することに客観的な必要があること
② 解雇を回避するために最大限の努力を行ったこと
③ 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的に行われていること
④ 労使間で十分に協議を行ったこと
・懲戒解雇
従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として行うための解雇
就業規則や労働契約書にその要件を具体的に明示しておくことが必要です。
・普通解雇
整理解雇、懲戒解雇以外の解雇
労働契約の継続が困難な事情があるときに限られます。
これら3つに加えて会社が退職を促す退職勧奨があります。以下、厚生労働省のWebサイトから引用します。
・退職勧奨
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し「辞めてほしい」「辞めてくれないか」などと言って、退職を勧めることをいいます。これは、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を通告する解雇予告とは異なります。(注2)
日本では解雇された従業員が裁判をおこせば解雇無効と判断されるケースが多く、企業は解決金によって和解することになります。企業は裁判コストと解決金の支払い、加えて企業イメージの棄損という負担を強いられるため解雇しにくい状況が生まれているのです。

どのように行うか
キャリア自律支援を制度として行う場合、キャリア研修、キャリア面談、自己申告制度、社内公募制、人事異動、副業許可、キャリアカウンセリング、社内ポストの提示などの施策があります。これらの制度を整えつつ、人事や上司と従業員との対話機会を作ります。フィードバック面談、1on1ミーティングなどの定期的な対話の機会にオープンな話し合いをしてください。業務に関する頻繁で適切なフィードバックは、従業員に強み弱みの認識と能力開発を促し、将来のキャリアを考える機会を与えます。職務に影響を及ぼすプライベートを知れば、職務上の制限や条件がわかり、業務の工夫や担当変更、部署異動を検討できます。キャリア意向を知れば現職がキャリア実現のためにどう役立つか、どのようなポストを社内で用意できるか、社外にはどんな仕事があるかを検討できます。
キャリア自律支援を退職マネジメントと明示している企業はほとんどありません。また、退職マネジメントを意識していない企業ほど社員の退職に対して、敏感に否定的な反応をするでしょう。しかし、会社が退職をうまくマネジメントすることは、タレントマネジメントを進める上で避けて通ることができないものであり、実は従業員のキャリア形成に貢献することなのです。
おわりに
従業員の退職をうまくマネジメントすべきという私の考え方に違和感を持たれる考え方もいるかもしれません。しかし、雇用システムの変化、働く人の価値観の変化、人口減少に対応し、企業の競争力を強化する上で必要不可欠なものであると考えています。はじめに述べた自動車メーカーの人事担当者様の回答は以下の通りです。
「当社はハイポテンシャル人材に選抜された人が一定の割合で退職します。他社から引き抜きに合うのです。常に人材不足なのでポスト不足で悩んだことはありません。」
キャリア自律支援が機能している証拠ではないかと思います。
●引用
注1 東京労働局. 「しっかりマスター 労働基準法 解雇編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/library/tokyo-roudoukyoku/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/kaiko.pdf, (参照2023-07-23)
注2 厚生労働省. 「労働契約の終了に関するルール」.
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html, (参照2023-07-23)
はじめに
日本企業の賃上げがはじまりました。円安とエネルギー高を背景とした物価の高騰により、社会全体としての賃上げのニーズが高まり、政府による税制支援もそれに拍車をかけています。報酬はタレントマネジメントにおける重要な要素です。本コラムでは、タレントマネジメントにおける報酬の重要性について述べます。
タレントマネジメントにおける報酬
従業員に対して労働の対償として賃金を支払うことは法律で義務づけられています。賃金を支払わなければ人を雇うことができませんので、金銭的報酬はタレントマネジメントの前提となります。しかし、単に労働の対償として賃金を支払うだけではタレントマネジメントになりません。重要なのは報酬を通じて、企業が従業員に対して、期待する行動をとるよう誘導していくこと。報酬をインセンティブとしてとらえる考え方です。インセンティブを使って従業員に組織が期待する行動をとってもらい、各組織での良い成果を生み出し、企業の業績向上や成長につなげていくのです。
企業におけるインセンティブ
インセンティブとは、人の行動や意思決定を促すために提供する報酬や利益のことです。企業が使えるインセンティブにはお金、休暇、職務、地位など様々なものがありますが、大きくお金と仕事に分類できます。お金によるインセンティブは、賃金や賞与、褒賞金などです。お金は誰にとっても魅力的であること、企業にとって量を調整しやすいことがこのインセンティブを導入するメリットです。一方、お金はそれが直接仕事のやりがいにつながるわけではなく、不満を解消することでモチベーションを維持するものです。これを衛生要因と呼びます。お金が不十分であったり、不公平であったりした場合、従業員はモチベーションを下げ、インセンティブの逆効果として働きます。お金によるインセンティブは、動機付け要因としてではなく、衛生要因として扱うことが重要です。
仕事によるインセンティブは、やりたい仕事、重要な仕事、面白い仕事を与えることです。昇進は日本企業にとって重要なインセンティブでした。もちろん地位の向上にはお金の向上も伴いますが、権限と承認が魅力の本質です。しかし、昇進はかつての魅力を失いつつあります。価値観や働き方の多様化に伴い、昇進を求める人が減っているからです。そして、昇進によるインセンティブにとってかわりつつあるものがキャリア自律支援です。働く人の幸せのためにライフステージに合った仕事内容や多様な働き方を会社が支援することがインセンティブとなっています。
このコラムではお金によるインセンティブ、金銭的な報酬をテーマに話を進めます。

なぜ賃上げが必要なのか
金銭的報酬が衛生要因であるために、現在の多くの会社が賃上げを検討せざるを得ない状況になっています。他社が賃上げを行っている中で、賃金を変えなければ相対的な報酬は低下します。お金に対する不満は、自分の経験や社内との比較だけでなく、社外や社会との比較によっても発生するのです。企業の立場から現在賃上げが必要な理由を整理しておきましょう。
賃上げが必要な理由は人材獲得競争に勝つためです。賃上げをしないことで二つの大きな問題が発生します。
一つ目の問題は採用です。競合他社との採用競争において優秀な人材を確保するためには、適正な賃金水準を設定することが重要です。キャリア採用の場合、人材の実績や経験、過去のポストや職務内容から緩やかに賃金相場が形成されますので、相場に比べて賃金が低ければ人材採用は著しく困難になります。新卒採用の場合、初任給による比較は容易ですが、求職者は初任給よりも平均年収やモデル年収に注目しますので、初任給だけでなく全体の賃金水準を適正にする必要があります。
次の問題は従業員の離職です。賃金が適正でない場合、優秀な人材が他社に流れてしまいます。優秀な人材は他社から高い年収で内定が得られるため、転職活動を通じて自分の賃金相場を知り、やがて転職してゆくことになります。賃金に対する不満が転職活動を活性化し、これが従業員のエンプロイヤビリティを顕在化させ、エンプロイヤビリティの高い人材、つまり優秀な人材から順に会社を去っていくのです。
もちろん、仕事によるインセンティブやその他の様々な魅力が動機付け要因となり人材獲得競争における競争優位をもたらすこともあるでしょう。しかし、賃金に対する欲求が満たされなければ、内発的な動機付けは困難であることは、マズローの欲求段階説を見ても明らかです。
多くの企業が賃上げに動いている現在の日本において、賃上げしないことは相対的に報酬水準を下げる行為です。賃上げによって報酬を適正な水準にし続けることは、優秀人材の獲得と維持のために必要不可欠です。

納得できる制度を作る
インセンティブとして賃金体系を作る際に考慮すべきは、成果や求める行動と処遇がつながっていることだけでなく、従業員が納得できる金額であるということです。人は自分の賃金が納得いくものかどうかを確認するために一般的に三つの方法を用います。
一つ目は社内での比較です。自分の上司、同僚、先輩、後輩、他部署の人などと比較して、納得できるかどうかです。給与制度や賃金テーブルを開示することは納得感を高める有効な方法です。
二つ目は自分の経験による比較です。極めて主観的な比較なので制度的に解決するのは困難ですが、本人が納得できれば特別な対応を必要としません。従業員の気持ちを受け止める企業側の姿勢が重要です。
三つ目は社外との比較です。自分の適正な賃金を知るために最も簡便な方法は転職活動を行うことです。他社が自分の職務経験、実績、能力やポテンシャルに対していくら出してくれるかを確認すれば、自分の賃金相場がわかります。ネットフリックスは優秀な人材にどこよりも高い報酬を提示することで有名な会社ですが、社員に対して定期的に他社と面接することを推奨しています。これが自社の賃金が他社と遜色のない水準であることを知る効率的な方法だからです。
納得性の重要さ
タレントマネジメントにおける報酬には納得性が重要です。あまりに当たり前過ぎてお叱りを受けそうですが、納得性が重要な理由は以下2点に要約できると考えます。一つ目はモチベーションを高めるから。タレントマネジメントにおけるあらゆる活動は人材の動機付けにつながっています。人は能力やスキルがあってもやる気にならなければ動きません。ここが機械や人工知能と生身のヒトとの大きな違いです。
二つ目はエンゲージメントを高めるからです。納得性は従業員と会社の信頼関係の基礎です。信頼があるから自分の将来を会社に託すことができるのです。このことをエンゲージメントといいます。
終わりに
今回はタレントマネジメントにおける報酬、特に賃金の重要性について述べました。今までも金銭的報酬はタレントマネジメントの重要なテーマでしたが、すべての日本企業がすぐに取り組まなければならない緊急性はありませんでした。長期に及ぶデフレが日本全体の賃金の上昇を止めていたからです。しかし、物価上昇と賃上げが進む現在の日本において、報酬マネジメントは緊急性を伴う最重要課題になっています。 年末の大掃除でたまたま手にした古い講演録に面白い記述がありました。ITバブルがピークを過ぎた2000年12月5日、当社は招待講演会「IT革命が変える人事インフラの未来」を開催しました。当時の日本企業は年功序列で運用されていた職能資格制度の制度疲労を背景に客観的な成果やコンピテンシーに基づく人事制度の導入を模索していました。
講演会の講師は当時代表取締役社長を務めていた清水佑三氏です。清水氏は講演の中で近い将来に起こる人事の変化について3つの予言をしました。
以下「」内の記述は2000年12月5日清水氏の講演内容抜粋です。
第一の予言:フリーエージェントが活躍する社会になる
「フリーエージェント型の社会が来るとみています。企業の正社員が社会の構成員の半分以上を占める時代が終わり、自由契約選手が社会の大半を占める時代が来るという予言です。(中略)正社員と自由契約選手の違いはどこにあるか、忠誠を尽くす相手が違っています。つまり会社に対して忠誠心を持つ人たちが正社員です。自分に対して忠誠を尽くす人が自由契約選手です。今は正社員が多いが、将来は自由契約選手の方が多くなるだろう。」
働く人の価値観の変化について述べています。会社と社員の絆が忠誠心(ロイヤリティ)からエンゲージメントへ変わっていくと捉えています。現在のスカウト、リファラル採用の普及、兼業副業の推進などは自由契約の増加を示す事象のように感じます。
「変化の激しい時代に固定的な雇用関係に縛られるくらい辛いことはない。(中略)それぞれの企業が自由なキャスティングをして勝負をしないと生き残れない。(中略)プロジェクトベースで契約して働くプロが中心となる社会がすぐ側まで来ていると考えられる。そのときに時間と空間の障壁をなくすインターネットは追い風として働きます。」
自由なキャスティングが競争力の源泉と言っています。プロジェクトごとに最適な人材を社内外から集め、プロジェクトが終了したら解散するような仕事の仕方が強い会社を作るという指摘です。この点について日本企業はまだまだです。ネットフリックス社はこの採用手法の成功事例です。パティ・マッコード氏(元NETFLIX最高人事責任者)が自身の著書「NETFLIXの最高人事戦略-自由と責任の文化を築く」でその手法について述べています。

第二の予言:アントレプレナーと職人の連合軍が主導権を握る社会になる
「技術オタクだけではIT革命は成就しません。(中略)彼らが役者だとすれば彼らをうまく活用する演出家がいる。それがアントレプレナーと言われる人たちです。(中略)シリコンバレーに人材を輩出している名門大学があります。スタンフォード大学です。ここがベンチャーの育成を熱心にやっています。」
当時と今の時価総額ランキングを比較すると、金融、エネルギーの企業から主導権がシリコンバレーのIT企業に移ったことは明白です。講演はちょうど米国のITベンチャー倒産が急増している時期に行われましたが、その後もIT技術は進歩し、真の価値を創造するIT企業の打ち出す画期的なサービスや商品が私たちの生活を一変させました。スマホ、SNS、ネットショッピング、動画配信、リモートワークの無い生活を思い出すことすら難しくなっています。
「アントレプレナーって何でしょうか。結果にすべてをかける人です。結果オーライで構わない、上がってなんぼの世界、それがアントレプレナーの定義です。(中略)アントレプレナーの資質をいかに早く正確にみつけて社内で戦力にしてゆけるか、それが今後の人事インフラ作りの一つのテーマである。(中略)職人ってどういう人をいうのだろうか。プロ性を社会が認めることができる人が職人です。(中略)そういう人が忠誠を尽くすのは会社でも個人でもない、仕事です。(中略)日本文化は職人文化です。こういう文化はアントレプレナーを生む土壌がない。人のフンドシで相撲をとることを嫌う風潮があるからです。」
2023年1月のユニコーン企業数は1,428社。アメリカには713社、中国には246社ありますが、日本企業はわずか13社※です。日本文化がこの結果をもたらしているとすれば、今後日本企業はどのように対処していけばいいのでしょうか。この課題について次のように述べています。
※参考:Crunchbase「The Crunchbase Unicorn Board」
「以上を総合すると大きな構想が生まれる。アメリカにアントレプレナーを出してもらって日本が職人を出す。その二つが連合して世界制覇をめざすとうまくゆく。これは間違いのない未来構想です。」
この予言は、はずれました。既にシリコンバレーには様々な国籍のアントレプレナーがおりますし、ITエンジニアのスキルレベルについてもアメリカのみならず、インド、中国、インドネシア、ベトナムなどのアジア諸国からも遅れをとっています。清水氏の構想が実現していれば日本はもっと多くのユニコーンを輩出していたに違いありません。
第三の予言:IT革命によって新しい人事インフラが生まれる
「まず、労賃という考え方がなくなり、報酬は仕事価値を基準に個別契約で決められる。そして働く時間と場所を自由に選択できるようになる。さらに仕事の仕組みでは、①マネージャーという職種が消滅する、②アントレプレナーと無限に多様なプレーヤーがその都度プロジェクトを組み仕事をする、③いずれにおいて自己責任の論理が貫かれる。」
前半の報酬と働き方については、日本でもジョブ型雇用システムを導入する企業が出始め、裁量労働制とリモートワークも一般的な人事制度となりましたので予言的中といえます。しかし、後半のマネージャーの消滅、都度のプロジェクト制、自己責任の論理は人事インフラとなっていません。
「『できる、できない』よりも『やりたい、やりたくない』の方が先だし、大事だということを憶えておかれるといい。エス・エイチ・エルのように人間のポテンシャルという問題をやっていると人間は実に多様だということがわかる。(中略)そういう立場から申し上げます。人事インフラはできるだけ固定的でない方がよい。その方が現実対応がしやすいし環境適応もしやすい。個人の違いを吸収できます。(中略)やりたいことをやらせてそのレベルを見ながらグレードアップさせていくべきだ。『好きこそものの上手なれ』と『下手の横好き』と二つありますが、好きこそものの上手なれのほうがよい。」
キャリア自律が重要になることについて述べています。企業主導ではなく社員の意思に基づく配置任用と育成を進めるべきであると。社員一人ひとりの心に寄り添った人事制度を作ることが重要というメッセージは予言ではなく、清水氏の願いであったのだと感じました。
おわりに
22年前の当社の社長が思い描いていた人事の未来についてご紹介しました。全ての予言が的中とはいきませんでしたが、これからも私たちは未来を見据えてタレントマネジメントソリューションをご提供し続けてまいります。 近年、アメリカを始めとして「大量自主退職時代(Great Resignation)」と呼ばれる大規模な離職が発生しています。この背景として推測されているのが、まずコロナ禍後の景気の急回復による転職市場の活性化、もう一つが従業員による働き方の見直し、キャリア観の変化です。日本でも、規模は違えど同様のトレンドが発生する可能性があると予測する声があります。SHLグループのe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core(従業員を維持する方法:人材難を根本から解決するために)」では、この大量自主退職時代について触れ、この人材不足の根本的な解決策は、報酬の引き上げや働き方の改善よりも、キャリア開発の機会であるとしています。本コラムでは、この問題に適性検査がどのように貢献できるのかを考えます。
キャリア開発とエンゲージメント
先述のe-book「How to Retain Your Workforce: Tackling the Talent Crisis at Its Core」では、退職の原因の1位はキャリア開発と昇進の欠如であることを指摘し(※1)、社内公募制の存在を対象者のおよそ半数しか知らないことや(※2)、自分の能力が生かされていないと感じる社員は転職活動をする可能性が10倍以上高いこと(※2)、社内流動性に優れた組織は約2倍の期間従業員を維持できることを挙げ(※3)、一部の社員だけに注目したタレントマネジメントの裏でキャリア開発のサポートが追いつかない社員が退職している可能性を主張しました。この全社員を対象にしたタレントマネジメントという発想は、どちらかというといわゆるメンバーシップ型雇用を特徴とする日本企業においてよく聞かれるものですが、ジョブ型雇用の海外企業においてもこのような議論が生じるところに人材流出の深刻さがうかがえます。社員のキャリア開発のために企業は何ができるか
さて、キャリア自律の機運が高まる日本企業においても、キャリアの行き詰まりによる人材流出は今後増加する可能性があります。終身雇用が崩壊する一方で必要勤労年数はますます長くなる中、常に自身の市場価値を意識し、より育成に投資する企業やより新しい経験を積める企業へと転職する人材は増える可能性があります。人材流出をせき止め、従業員が健全なキャリア展望を持って働けるようになるために、適性検査はどのような貢献ができるでしょうか。e-bookでは、94%の従業員は学習支援に投資する企業であれば長く勤めると回答している(※3)ことを挙げ、自社が能力開発のために最適な場所であることを従業員に示す必要があるとまとめています。そのためには、従業員の適性や関心、専門性を考慮したキャリアプランを提示し、そのためにどのような能力開発が必要かという示唆(及びそれを実行する機会やリソース)を従業員に提供する必要があるのです。
具体的には、以下の3ステップが必要です。
(1)人材の可視化により、あらゆる人材の特徴、スキルなどを把握する タレントマネジメントシステムなどを活用し、企業内のあらゆる人材の特徴、経歴、コンピテンシー、スキルなどを人材データとして管理・分析します。そして、各職種に必要なコンピテンシーやスキル、優秀者の持つ特徴などを把握しておきます。
(2)社員一人一人のキャリアの可能性と、そのために必要な能力開発についてすり合わせる
従業員一人一人のキャリア志向性と組織としての能力開発方針をすり合わせるために、上記のような職種ごとの人材の統計情報をキャリア面談や1on1ミーティングなどに取り入れます。本人のキャリア志向性を確認するとともに、適性検査のフィードバックなどを通じて、経験と適性にマッチした社内での今後のキャリアとそのための能力開発について、長期的な展望を話し合います。
この際のキャリアプランは、必ずしも定型のものである必要はありません。たとえば同じように優秀な営業社員でも、マネジメントに関わるコンピテンシーやマネジメント志向性が高ければ営業のマネジャーを目指すのもよいですし、企画や分析に関わるコンピテンシーや専門領域を広げたいという志向性が強ければ、現場経験を生かしてマーケティング業務に異動するのも良いでしょう。そして、それぞれの場合で今後必要な能力開発についてすり合わせる必要があります。
(3)能力開発およびキャリアチェンジの機会を提供する
もっとも重要なのがこのステップとなります。能力開発に関してはe-learningや各種研修をはじめ、社内勉強会や部署横断プロジェクト、各種の越境学習などを柔軟に取り入れ、企業のサポートのもと学習やスキル習得を進められる体制を整える必要があります。同時に、希望の職種にチャレンジするための制度(たとえば社内公募制度や社内FA制度、一定期間他部署で働く社内インターン制度、他部署での副業を認める社内副業制度など)も必要でしょう(そうでなければ、成長した社員は社外に居場所を求める可能性があります)。

最後に
すべての職種でDXが進む昨今、企業側の要請するリスキリングと従業員のニーズによるキャリア開発をマッチさせることも大きな相互作用を生むでしょう。以前は「能力開発をしてもつけるポストがない」という問題意識もよく聞かれましたが、デジタル化による新規ビジネス創出のチャンスは加速度的に高まっています。キャリアに行き詰まりを感じる社員と、人手不足に悩む企業のニーズをマッチさせる一連の仕組みこそがタレントマネジメントといえます。ぜひ社員の適性情報も、重要なキャリア選択の資料としてご活用ください。※1 McKinsey, 2022, 2022 Great Attrition, Great Attraction 2.0 Global Survey
※2 Gartner, 2022, Gartner Recommends Organizations Confront Three Internal Labor Market Inequities to Retain Talent
※3 LinkedIn, 2022, 2022 Workplace Learning Report 人生100年時代と呼ばれ、終身雇用が事実上崩壊したとされる現代において、社員が自律的に専門性やスキル、キャリアを育んでゆく「キャリア自律」の重要性が叫ばれています。これまで組織依存のキャリア形成に従事してきた従業員にとっては、「これからは自己責任」と突然ハシゴを外されたように感じるかもしれません。また、自由なキャリア形成を従業員が組織外で行うことで、人材の流出が起きることを危惧する組織もあるかもしれません。しかし、キャリア開発の方向性を組織と個人がすり合わせ、相互にメリットを提示することで、一人一人が主体性を持って働けるようになるだけでなく、組織が多様な専門性やスキルのある人材を確保し、ビジネスの発展に繋げることも可能なのです。
社会情勢の急激な変化やテクノロジーの急発展により、数年先の予測も困難である現代においては、個人が現時点での戦略にもとづき単一のキャリアを選択するようなキャリア形成自体が困難になっています。そこで再注目され始めたのが、1976年にアメリカの心理学者ダグラス・ホールが提唱した「プロティアン・キャリア」です。本コラムでは、プロティアン・キャリアの概要と、個人が多様なキャリア形成をするために組織ができることに触れます。

プロティアン・キャリアとは
プロティアン・キャリアとは、個人が社会環境の変化や個人の価値観に合わせて柔軟に適応する「変幻自在なキャリア」のことであり、ギリシア神話に出てくる思いのままに姿を変える神プロテウスに語源があります。プロティアン・キャリアは、組織よりもむしろ個人が主体となって形成するものであり、重要な二つの軸があります。① アイデンティティ:自分の価値や興味に基づいており、それが人生を通じて統合されている程度、つまり「自分らしさ」のこと。社会や組織のニーズに迎合するばかりで一貫した自分らしさを感じられないキャリア形成では、やりがいを感じにくいことは想像に難くありません。
② アダプタビリティ:変化への適応力のこと。自身の興味・関心に沿ってはいるが、社会的ニーズの乏しい職業に就こうとすると、生計を立てることが難しくなります。ホールによれば、アダプタビリティとは、適応コンピタンス(アイデンティティの探索、変化への反応学習、行動とアイデンティティの統合力)と適応モチベーションのかけ合わせであるとされます。
キャリアは急速に発達するものではありません。次のキャリアを見定め、長い年月をかけて転身のために準備をする方法だと、準備が整った時点での社会的ニーズがどのようになっているかわからないというリスクがあります。副業や兼業を解禁する企業が増加してきた現在、二足・三足の草鞋をはくといった多角的なキャリア形成はずいぶん身近になりました。自身の専門性を幅広にとらえ、なるべく広範囲にキャリアの芽を用意しておくことは、VUCAの時代におけるキャリア形成に不可欠な戦略といえるでしょう。
従業員のキャリア開発のために組織ができること
こうした従業員の自発的なキャリア形成に対し、組織が無関心であったり、人材の流出をおそれてネガティブな態度を示すことは、「これからの人生を共にすることのできない会社である」と従業員にみなされる可能性を高めるといえます。反対に、個人のニーズと組織のニーズをすり合わせる機会を積極的に設けたり、キャリア発達を様々な側面で支援したりすることは、今後従業員のエンゲージメントにより大きな役割を果たすのみならず、組織の発展の可能性を高めるといえるでしょう。組織ができるキャリア開発支援は、いわゆるキャリア開発研修といったアダプタビリティを高めるための教育プログラムの提供、社内公募制度や社内FA制度など自身のキャリアを組織内で探索するための制度の導入、副業・兼業の推進、自己研鑽コスト(セミナー参加や教材の費用など)の負担など、多岐にわたります。また、現在多くの企業で実施されている1on1ミーティングも、自律的なキャリア支援策の一つです。ホールによれば、プロティアン・キャリアの形成にはアイデンティティの軸が不可欠となります。ただひたすら多くのスキルや資格を獲得することが柔軟なキャリアに繋がるのではなく、現在従事している職務を超えて、一貫した自身の興味・関心、強みの範囲を把握することが、キャリアの幅を広げるための第一歩となります。したがって、1on1ミーティングでは「何を行っている時が楽しいか」「どのような知見を今後深めたいと思っているか」「興味のある分野はあるか」「どのような働き方が理想的か」など、現在の職務を離れて個人が自身のアイデンティティに気づく手助けを行うことをお勧めします。
なお、個人のアイデンティティの確立には、内省だけではなく他者からのフィードバックも重要な役割を果たします。キャリア支援のための情報提供の一環として、適性検査のフィードバックもお試しください。本人の自認する特徴や適性、上司や監督者の見解、適性検査などのツールから読み取れる特徴や適性などを組み合わせ、多角的に自己理解を行うことで、本人や周囲の気づいていなかったキャリアの道筋が現れることもあります。ご興味のある方は、ぜひ資料をダウンロードしてください。